![üÇE¤Cð²ó]Ìû@êpTCgbçtåwåw@ãw¤@ åAíÈwEçtåwãw®a@ åAíÈ](../images/header.png)
![üÇE¤Cð²ó]Ìû@êpTCgbçtåwåw@ãw¤@ åAíÈwEçtåwãw®a@ åAíÈ](images/top1.jpg)
Top@@åAíÈÊM
åAíÈÊM
³ºÌ±ÆªAÅàæí©éI
³ºàÌCxgâAwï\AÊ^t«ÅÚµÐîµÄ¢Ü·Iå³êéûÍK©Å·B
útÊAJeS[ÊÉ®µÄ¨èÜ·ÌÅA©½¢LðNbNµÄ²¾³¢B
åAíÈÊM@Lê
2025.11.21wïæ34ñú{Rs
[^OÈwïäà x¾N(ãõ)
E2025.9.19wïkKâL\\2025úåAíOÈAIwïæâá(åAíÈw mÛö ¯w¶)
E2025.5.15¤2025/5/15 Young Members' Chemotherapy Academy(YMCA)@yGz[áä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)
E2025.4.17wïæ112ñïÜóÜñ(3NA±óÜI)ઠ®u(ÁC³)
E2025.4.1COð¬JUA-EAUAJf~bNexchangevOQÁñ²Ë qa(fÃy³ö)
E2025.3.10wï2025/3/10-13 EAU2025@Madrid, Spaináä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)
E2024.12.16erJ¬Zçtã©wcA[ `ãwðÚw·álÌ´«ÉGêÄ`cº M¾(ÁC³)
E2024.11.5¤Clinical Fellowship in Chiba University HospitalChin-Li Chen. M.D.
(Tri-Service General Hospital)
E2024.10.30wïæ11ñú{×EO¬Ewïcº M¾(ãÈåwãw¤)
E2024.10.27eræ1ñáèStRy(Vät)áä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)
E2024.10.26wïú{åAíÈîáwïæ10ñwpWï{é ¤ß(ãú¤Cã)
E2024.7.1¤Clinical Observership in Chiba University HospitalPing-Chia Chiang M.D.
(Kaohsiung Chang Kung Memorial Hospital)
E2024.5.29¤Report after visiting Chiba university hospital department of Urology in May 2024Jae Young Park. M.D.
(Professor, Korea University College of Medicine)
E2024.5.10wïAUA2024ÆMt Sainaia@ Tewariæ¶KâL(Newark©ç¬cÖÌUnitedÌ@àÉÄ)â{ Mê(fóö)
E2024.4.23wï2024JUA|AUA Exchange Scholarship report, Dr. Kevin Koo from Mayo Clinic, USAKevin Koo, MD, MPH, MPhil
(Associate Professor of Urology,Mayo Clinic)
E2024.1.15¤çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVj2023â{ Mê(fóö)
E2023.12.22wïçtåAíZ~i[@Chiba Urology Seminarcº M¾(ãÈåwãw¤)
E2023.11.25wïæ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï|R °(ãú¤Cã)
E2023.9.20wïNext Generation Urologist SeminarRº ½(ãú¤Cã)
E2023.9.19wïChiba Tokyo Scrum Meeting with SingaporeRc N²(³)
E2023.8.28¤¤ºïcû¢ ˶(ãõ)
E2023.7.29wïæ48ñ@çtåwåAíȯåïwpWï¡´ Ä÷(ãú¤Cã)
E2023.7.22wïªJt@X2023 in{èâV¡ S½(åw@¶)
E2023.7.16ï¡ßµñ(ÍéA}`
A{öVíéʧåï D)úì ån([JÔ\a@)
E2023.7.4wïæ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï§e åã(ãú¤Cã)
E2023.6.16wïProstatic Night 3(ProNi3)ÉQÁµÄì KêY(êUã)
E2023.6.8wïUrology Today in Chiba2023ºã T÷(ãú¤Cã)
E2023.6.1¤}[VA©çJasmineæ¶@çtåtF[VbvñLIM Jasmine(}[VAE}åwãw)
E2023.5.2wïæ110ñ ú{åAíÈwïïδ å(åw@¶)
E2023.3.10wïEAU2023Milan, Italyáä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)
E2023.1.28wïçtåwåAíȯåïä Yå(ãú¤Cã)
E2022.11.19wïæ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï|{ Wq(ãú¤Cã)
E2022.8.30wïæ46ñçtåAíȯåïwpWïn Çê(ãúÕ°¤Cã)
E2022.8.4wïChiba Young Urologist Seminar with University Malayaáä (éåw¿ÎãÃZ^[ ³)
E2022.7.25wïæ1ñ@ú{åAíÈwïçtnûïwpWïVä T¾Y(ãú¤Cã)
E2022.6.15wïUrology Today in Chiba 2022ª ´i(ãú¤Cã)
E2022.5.20wïNew Generations Prostatic Night vol.2@¬ze~}[âV¡ S½(åw@¶)
E2022.5.17¤a@·\²ÌóÜñ²Ë qa(ut)
E2022.5.10¤åAíÈXNuvæ&tbV
}¯×ïnç² LB(ãú¤Cã)
E2022.4.5¤HoLEPúg[jOÉ¢ÄXì ^ß(ãú¤Cã)
E2022.2.10¤t}ø«p¬c d÷(ãú¤Cã)
E2022.1.29wïæ45ñçtåAíȯåïwpïâä ½(§çtãÃZ^[ãú¤Cã)
E2022.1.20¤æ21ñçtåAí o¾³çvO+áèåAíÈïc¬Ñ a÷(ãú¤Cã)
E2022.1.17¤yà¯wLzãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤åcº M¾(åw@¶)
E2021.11.30¤SGLT-2jQÜÌãå@àäD³ö@çtåqõ³öÉACâ{ Mê(fÃy³ö)
E2021.11.20erçtååAíÈvsbãååAíÈغ Á(ãú¤Cã)
E2021.10.20¤StanfordåwÆçtååAíÈñg@Creating Social Value(CSV)Öü¯Äâ{ Mê(fÃy³ö)
E2021.10.17¤ o¾g[jOfìiJ@`KOTOBUKI Medical`NHK WorldæÞ 2021/10/17D´s§ãÃZ^[èpºä º(D´ãÃZ^[ã·)
E2021.10.13¤2021/10/13 tbV
}¯×ïV[ (ãú¤Cã)
E2021.10.07wïæ2ñ Chiba Young Urologist Seminarä º(D´ãÃZ^[ã·)
E2021.9.28¤DÀK& o¾X[`Og[jO{{ ü(ãú¤Cã)
E2021.7.29¤Urology Today in Chiba 2021AáèåAíÈAïcj ¾(ãú¤Cã)
E2021.7.27¤çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVjâ{ Mê(ut)
E2021.4.13¤yà¯wLzéÊãÈåwQmpãwc C½
E2021.3.29¤åAí o¾vOÔê åM(ãú¤Cã)
E2021.3.29eråAíÈ©UpHP ÒWãLáä (åw@¶)
E2021.3.29eråw@¶É¢ÄÀ¡ hC(åw@¶)
E2021.3.2erãwÐt¯ìÆIOY žY(ãú¤Cã)
E2021.2.15¤AUA ASRMj«sDÇKChCì j
E2021.1.26erÙ}Ôé¾ÄÑ ª(ãú¤Cã)
E2021.1.23¤«åAíÈãÌõÁ¡ q(³)
E2021.1.6¤æ2ñáèåAíÈAïcÛö §j(ãú¤Cã)
E2020.11.18er¡NÌÄÌß²µûnÖ Må(ãú¤Cã)
E2020.8.31ï¡ðæèÍÞ«@`å©R©çEêÜÅ`R¨ åS(ãú¤Cã)
E2020.8.11ï¡2020N7@Surfing with 2019 Japan Long Board Pro Championâ{ Mê(ut)
E2020.5.7¤O§BàAIðÍlHm\(AI)ãw@ìãpÇæ¶óû kî(NÃa@)
E2020.3.5¤YÆpÂ\Èèp®æf[^x[X\zÉü¯½vWFNgyS-accesszn®|º ¨d(åw@¶)
E2020.3.5COð¬ASCOGU2020@ÔOÒcº M¾Aä º
E2020.2.13COð¬ASCOGU2020ä ¹H(åw@¶)
E2020.1.25wïæ42ñçtåAíȯåïwpWïVä ²VAغ Á
E2020.1.11wïæ24ñ¶BàªåwïwpWï·ª _¾Y(ãú¤Cã)
E2020.1.10ï¡ãïj
[X@fÚñ@çt§ÌC `Fisher©çSurferÖ`ä º(®a@)
E2020.1.11¤uæ3ñú{ãäJåÜ@àtåbÜvóÜñâ{ Mê(ut)
2018N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2017N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2016N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2015N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2014N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2013N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2012N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2011N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
2010N¥(NbNÅ\¦^ñ\¦)
åAíÈÊM@L
æ34ñú{Rs [^OÈwï
±ñÉ¿ÍB
åw@2NÌäàx¾NÅ·B
æúAæ34ñú{Rs
[^OÈwïɨ¢ÄJóê½AI ChallengeÉQÁµABasicåEAdvancedåÌñåÅD·é±ÆªÅ«Üµ½B

(E©çOlÚªMÒ)
wïö®Lͱ¿ç
https://www.jscas.org/business/2025/07/7fa2da977a91400092d82b332ab12f5434b1c01d.html
{éæÍAèp®æðèÞƵ½ÛèÉεÄAIfðJµA»Ìf¸xð£¤àÌÅ·B¤Òâw¶AéÆÈǽlȧêÌQÁÒª§í·éæègÝÅ·B
¡ñÌæègÝðʶÄA¸xðüã³¹éßöÅAÕ°ãƵÄÌ_ªðɧÁ½Æ´¶Üµ½Bèp®æÌÇÌV[ªÊÉe¿µâ·¢©AÇÌæ¤ÈëèªâèÆÈèâ·¢©ðÓ¯·é±ÆªAfüPÌêÉÈÁ½Æl¦Ä¢Ü·B
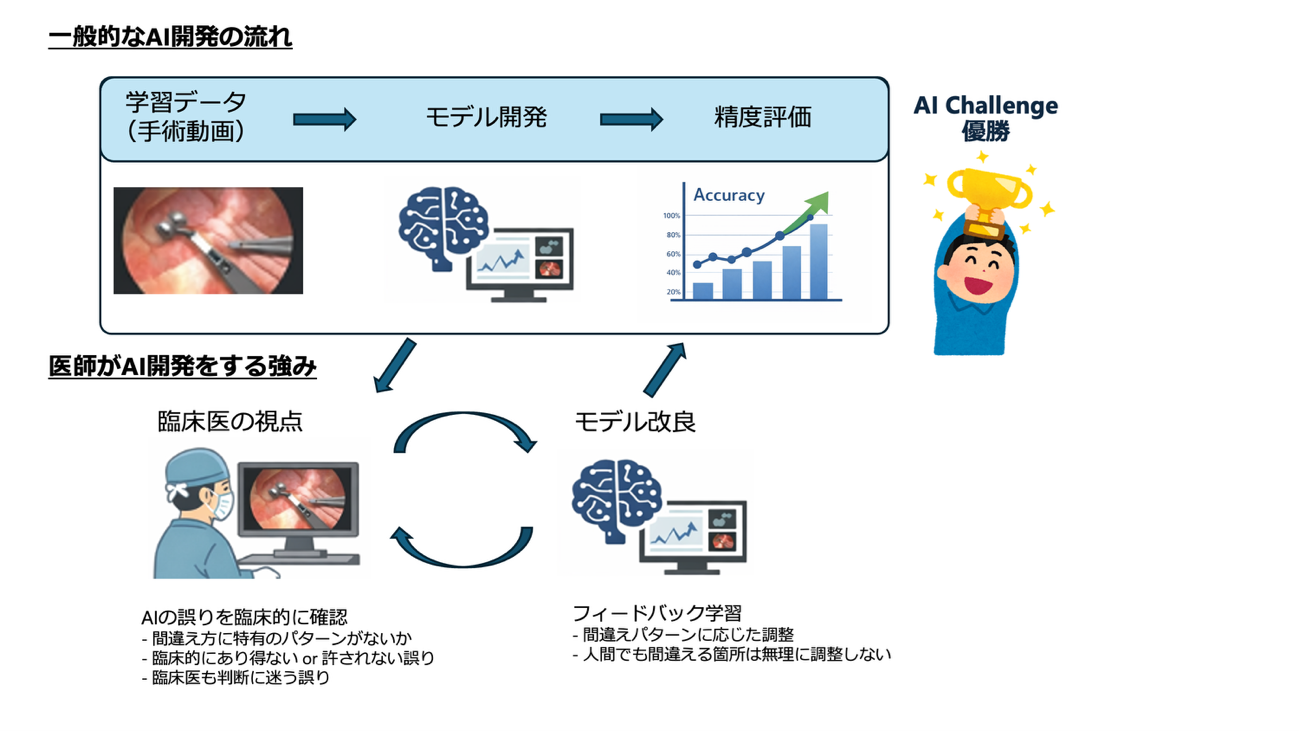
{}ÍAMÒªAI ChallengeÉæègÞÅ´¶½ÂlIÈl¦ðÜÆß½àÌÅ·B
ãÃAI̪ìÅÍAÕ°ÌðªÊÉe¿·éêʪ½X èÜ·BãtªAI¤ÉÖíéÓ`ÍA±¤µ½_ð¿ßé_É éÆ´¶Üµ½B
ÍT2úAåwa@âÖAa@ÅÕ°ð±¯ÈªçAT3úͧªñ¤Z^[a@ÌÉ¡ëºæ¶ÌàÆŤÉgíÁĢܷBܽAçtåwåAíÈÉÍAI¤ÉæègÞæyûª½ÝеĨèAñíÉS¢Â«Å·BÕ°ð±¯ÈªçVµ¢ªìɧíµâ·¢Â«ª®ÁÄ¢é±ÆÍA{³ºÌå«ÈÁ¥¾Æv¢Ü·B
åw@Å̤âAIÖ̧íÍAÁÊÈl¾¯ÌàÌÅÍ èܹñB¡ñÌo±ªAiHðl¦éûÉÆÁÄêÂÌQlÉÈêÎK¢Å·B
¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ(ãõ)@äà x¾N
kKâL\\2025úåAíOÈAIwï
2025N919ú©ç21úÉ©¯ÄAâ{MêfóöƤÉkðKêAúãwÈZð¬¦ïåÃAkåwñ|ã@¤ÃÌu2025úåAíOÈAItH[vɵ©êܵ½B

±ÌwpåïÉÍA¨æÑâ{fóöðͶßÆ·éAWAÌåAíOȪìÌæêüÅô·éêåƪê°ÉïµA
lHm\iAIjÌÅV¤ÆÕ°pÉ¢ÄÈc_ªsíêܵ½B
ßÄÌk\\L[[hÍuåvÆuÃv
kÛó`É
ãAsàSÜÅñ1ÔÌÔÚ®B
kÌðÊÍuÂóüvÆÄÎêé§Ì¹HÔÅ\¬³êA1ü©ç6üÜÅÔª¬³¢ÙÇsSÉßAn¿ªÈèÜ·B
»ÌS±»A¾E´ãÌcsuÖévÅ·B

ÖéÌOɧÂâ{æ¶
wrª§¿ÀÔsåÈssóÔ\\±êªâ{æ¶ÆÌø¢½æêóÛAuåvB
20Kð´¦éItBXrââsAàZ@Öª½©çêܵ½B
µ©µA»ÌÔÉÐÁ»èÆcéÓ¯it[gjâÃzªAà¤êÂÌóÛuÃvðéÉê詯īܷB

ÖéÌ¡ÌHnA´©Ì¤É¯µ½«

VdiÄñ¾ñjÍA15¢I̾ãÉÄçê½ÕâJzÅ èA
ðãcéªVðÕèAÜLõðFé½ßÌêŵ½B
kÍAá¦éÈçuvÆusvðí¹½æ¤ÈXB
VãÆãªðöµA£¢¢A¤¶µÄ¢é\\±ÌssÌpÍADZ©ßãÌúÖWðÛ¥µÄ¢éæ¤Éശܵ½B
Äïµ½ãwÌãJ\\kåwñ|ã@pirQ[V³çZ^[Kâ
tH[JOúA¿å¤Çkåwñ|ã@ÌpirQ[V³çZ^[ÅÍA¼ i`xbgj©ç½áèãtÌg[jOªsíêĢܵ½B

kåwñ|ã@Ìáû³öÆæâqb³öª¼XÉâ{fóöð½}µA{ÝðÄàµÄ¾³¢Üµ½B
â{fóöÍ2NOAÄAUAiAmerican Urological AssociationjïųöEæâ³öÆoï¢A»êð«Á©¯ÉçtåwÆkåwßFQ@m̤¦ÍªnÜèܵ½B

kåwñ|ã@Ìæâqbæ¶Aâ{æ¶
â{fóöÍAɨ¯é{bgxèp¨æÑ o¾ªìÅ̬ÊÉ[¢´Áðó¯AÍÄѱÌãwÌyëÅ̯»Æð¬Å«½±ÆÉS©çÌeµÝðo¦Üµ½B
úÌmÌð·_\\AIªà½ç·åAíOÈÌVã
tH[ÍAúãwÈZð¬wïÌ£¶ï·ÌJï¥AÅðJ¯Üµ½B
åAíÈwÌnnÒÅ è×lÅ és\@mAßFQ@mÍAcOȪçïêÉçêܹñŵ½ªArfIbZ[WðʶÄj«ÆúÒ̾tðñ¹çêܵ½B

s\@mAßFQ@m
wpuÌÅÍAâ{fóöªuO§Bà{bgèpɨ¯éAIÌpvÆèµÄAçtåw`[ÉæéAIèpirQ[V¨æÑp¯ÊVXe̤¬ÊðÐîµÜµ½B
AIfª{bgèpÌìðA^CÉF¯µApÒÌXL]¿ÜÅs¤Æ¢¤\ÍAïêÌå«ÈÚðWßܵ½B
±¢ÄÍAu@BwKÉæéÌOÕgÎjÓpiSWLj³Î¦\ªfvÆèµAAIASYðp¢½SWL¡ÃøÊÌ]¿É¢Ä\µÜµ½B
½{ÝÕ°f[^ðµA¡Ã¬÷¦ðOÉ\ª·é±ÆÅAãtªæèÂÊ»³ê½¡Ãûjð§Äé¯ÆÈé±ÆðÐîµÜµ½B

³çÉAl¯ðúRã@i¢íäé301ã@jÌn?³öÍuAI©®D{bgv̤ð\B
ܾÌOÀ±iKÅÍ èÜ·ªA2áÌÙÚ®àøÈÇá¬Êªñ³êAÌAIJÉηé¢ÆMOA»µÄ¢ÄÉàòçÊÀÍðÀ´³¹çêܵ½B
úÎb\\eNmW[ÌæÉ éãçxÌá¢
3úÔÌØÝA½¿ÍAãwÈOÌe[}É¢ÄàÓ©ððíµÜµ½B
kÌa@ÅÍAÅßAj©çújÜÅúOfÃðs¤Ì§ÉÚsµ½Æ̱ÆB
ãCÅÍ2010NÌȱÌ̧ª±ü³êĢܷB
±±ÉAúÌOE~}ãçxÌå«Èᢪ©¦Ä«Üµ½B
OfÃÅÍAú{ÅÍܸnæÌNjbNðófµAKvɶÄa@âåwa@ÖÐî³êÜ·B
\ñ§ªêÊIÅAÒ¿ÔÍ·Äà¾Á½Ã©È«ªÛ½êĢܷB
êûAÅͳҪ©RÉa@EãtðI×é½ßAå^ÌuOba@iÅa@jvÉlªWµAO³ÒªñíɽÈèÜ·B
ót©çx¥¢AòÌó¯æèÜÅdq»ªiñÅ¢éàÌÌAãtÌJß½ªËRƵÄÛèÅ·B
~}ãÃɨ¢ÄàAú{ÅÍdÇxɶ½¾mÈKw\¢ª èÜ·B
yÇÍnæéÔfÃâxúfêεAdÇÍ119ðʶÄêåa@ÖÀ³êÜ·B
Ì~}OÅÍAyÇ©çdÇÜů¶~}ÉWÜèAéÔÉêʾ³Åóf·élàÈ èܹñB
ÒºÉͽ̳ÒÆÆ°ªlß©¯AfÃÍuæ
vÆudÇDævªÀsµÄ^p³êĢܷB
ú{Ìæ¤Èµ§ÈgA[WæèàA_îÈΪßçêéóÛŵ½B
SÌIÉ©éÆAú{ÌãÃÍuªÆEE\ñvðÁ¥ÆµAÌãÃÍuø¦EWEJú«vÉݪ èÜ·B
»ÌÊƵÄAÌåa@ÌãtÍܳÉuÎ
ØààviúªÎ±újÌæ¤ÈߧÈαóµÉ éÌÅ·B
IÍ
¡ñÌu2025kåAíOÈAItH[vÍAPÈéwpïcÅÍÈA«ðz¦½mÌð¬ÌêÆÈèܵ½B
üßÄAÈwÌÍÍu¤LvÉ èAãwÌ{¿ÍuÂȪèvÉ é±ÆðÀ´µÜµ½BAIZpÍA±ê©çÌúãw¦ÍÌV½È˯´ÆÈèAåAíOÈðæèmIÅlÔ¡Ì é¢Ö±Åµå¤B
»µÄA±ÌnÜèðÛ¥·éçtåwÆkåw̦ÍÍA«ÁÆ¢Éü¯ÄdvÈÓ¡ðÂÆmMµÄ¢Ü·B
kûÊÌL:
https://mp.weixin.qq.com/s/fqeZirL9spek7tqtfUTXwg
https://mp.weixin.qq.com/s/YMAMf3co613yoEIVwUZr8g
¶ÓFåAíÈw mÛö ¯w¶@æâá
2025/5/15 Young Members' Chemotherapy Academy(YMCA)@yGz[
±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B
¡ñÍ5ÉYMCAÆ¢¤×ïðéæµÜµ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B
JÃÌoÜƵÄAVK̪qWIò(TKI)âÆu`FbN|CgjQò(IO)É¢ÄáèÌûo±ªÈ¢Æ¢¤±Æª èܵ½B
©gAtàÉηéIO+TKIâIO+IOAAHãçàÉηéEV+PemÌûo±ªÁʽ¢í¯ÅÍ èܹñB
ǤµÄàe{Ýɨ¢ÄããÉ]ÚÇáâ¢ïÇáªWµAáèÉÍ]ÚÌÈ¢èpÇáªWÜéXüª éÌÅAáèÌÅàÁÊûo±ª½¢XyVXgÌæ¶ûÉ|Cgð³¦Ä¸Æ¢¤ÌªRZvgŵ½B

XyVXgÌæ¶û@¶©çóûæ¶AÄcæ¶A²¡æ¶AVäæ¶
úÍ×35¼Ìæ¶ûɨWÜ袽¾«A·ïÆÈèܵ½B
¡ãà£ÍIÈe[}Ýèªoéæ¤l¦Ä¢«½¢Æv¢Ü·B

¿âɧÂr´æ¶

²¡æ¶©çÍòÜIðÉ¢Ä@@@@@@@@óû涩çÍìpÌ}lWgÉ¢Ä

PáÉÈé\´ÌY|[Y

à¿ëñ[à

§eï
¡ãàAHãçàAO§BàÆe[}ðϦÄAèúIÉJõĢ¯êÎÆl¦Ä¢Ü·B
ܽ»wÃ@ÉÀç¸AæèµÁÄ~µ¢e[}ÈÇ êÎ¥ñ³¦Ä¸¯êÎÆv¢Ü·B
¡ãÆàæ뵨è¢vµÜ·B
¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä
æ112ñïÜóÜñ(3NA±óÜI)
ßÄñe³¹Ä¢½¾«Ü·B
çtåwãw®a@@ÁC³Ìàª@®uÆ\µÜ·B
2025N417ú`19úAæ112ñú{åAíÈwïïªsíêܵ½B
±ÌxAªåw@ÅsÁÄ¢½O§BàÌîb¤É¢Äñ³¹Ä¢½¾«AïÜ𢽾±ÆªÅ«Üµ½B

(ÆÄàå«¢ïêÅA\²¢½¾¢½±ÆÍÆÄࢢv¢oÉÈèܵ½I
ªJÃÆ¢¤±ÆÅATHEª|l@½ØÛEåg³ñàĢܵ½)
åAíÈÌÔ`ÌêÂÆྦéO§BàÌæɨ¢ÄAîb¤ÅÌh_ éóÜ𢽾«AåÏõhÅ·B
O§BàEîbÌÌæÅÍðNÌRcæ¶(n[o[h¯w©çàÇçê½çtåwåAíÈÌCWOX^[)ÉЫÂë2NA±A
³çÉêðNÌInternational session AwardÅÍáäæ¶àAHÎÌæÅAâ{æ¶àO§BªñÌÕ°Ìæɨ¢Äf°çµ¢\ÅóܳêĨèA
í¹éÆ3NA±çtåwåAíÈÌóܪA±µÄ¨èÜ·B
±êàÐƦÉæyûªÂȢž³Á½¤Ìf[^Aܽ}Chª¬XÆÂâĢ騩°©Æv¢Ü·B
̤É¢ĵ¾¯¨b³¹Ä¢½¾ÆAO§BડÃïR«ðl¾µÄŨ±é³Ü´ÜÈϻ̤¿A
Qm(DNAzñ)ÌÏ»ðÆàÈí¸É¨±éGsQmÏ»É
ڵĤðs¢Üµ½B
]Ú«O§Bàɨ¢ÄAGsQmð²ß·é`(NSD2)ª»µÄ¢é±Æð©oµA
³çÉ»êªDNAÌ3³\¢(Üè½½Üêû)Ée¿ð^¦é±ÆÅ¡ÃïR«ÌêöÆÈÁÄ¢é±ÆðßÄ©µAñ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
à¾ð«¢ÄàÈ©È©ª©èÃ碩Æv¢Ü·B
àͶßĤºÉz®³ê½Æ«ÉÍp¸©µÈªçDNAÌ]ÊÌdgÝ·çÜÆàÉà¾Å«È¢óÔŵ½B
½¾ªz®³ê½¤º(çtåwåw@ãw¤@ ªqîáw)ÅÍåAíÈÌæy(Yæ¶A²¡æ¶Aàâæ¶)ª·ÅɤðißĨèA
³Ü´ÜȤf[^AmEnEð~ϵĢ½¾¢Ä¨èܵ½B
ܽ¤ºÌgbvÌàcæ¶ÍGsQm¤Ìú{ÌæêlÒÅ èA¤ÖÌü«¢ûÈÇðê©çJÉw±¢½¾«Üµ½B
æyûÉw±µÄ¢½¾«Èªç©gàè𮩵AÀ±Ì¸sƬ÷ðJèԵĪq¶¨wÖÌðð[ßéÅA¤ÌʳÉvªµÄ¢Á½Ìðo¦Ä¢Ü·B

(¯¶¤ºÌæy Yæ¶(E)Aàâæ¶(¶)Æ)

(ú¤Cã©ç4NÔ¨¢bÉÈÁ½O§Bà¤ÌåÆ Ôqæ¶Æ)
(¤ð¢ÂàµÄ¢½¾¢½Aâ{æ¶Æ)
±ÌLðÝÄ¢éú¤Cãâãú¤CãÌÝȳñA
çtåwåAíȳºÍÕ°ÅèpðÉßéÆ¢¤¹©çîb¤ÅàÌJjYðTéÆ¢¤¹ÜÅALIðª éf°çµ¢Â«¾Æv¢Ü·B

(ïÜÉÆàÉåµ½áäæ¶(¶)Aäàæ¶(¶©çñÔÚ)Æ)
ºÐêÉåAíÈÌæð·èã°éÔÉÈÁÄêé±ÆðASÍŽ}·éõðµÄ¨Ò¿µÄ¨èÜ·B
MÅ·ªA¤ÉWÅ«éæ¤ÉÆAÕ°ÌƱðÙÚt[ɵĢ½¾¢½sìqF³öðͶßÆ·éåAíȳºÌæ¶ûA
îb¤Ì¢ëÍðw±µÄ¢½¾¢½àc¤Ìæ¶ûAܽ\̽ßÌo£ðõ¢½¾«èoµÄ¢½¾¢½NÃa@Ìæ¶ûÉäç\µã°Ü·B
¶ÓFÁC³@ઠ®u
JUA-EAUAJf~bNexchangevOQÁñ
±Ì½ÑÍJUA-EAUAJf~bNexchangevOÉÌð𢽾«fèÌvOÉQÁðµÄÜ¢èܵ½ÌŲñ\µã°Ü·B
COÅ̯wo±ªÈ¢ÉÆÁÄñíÉMdÅåÏhIÈ@ï𢽾«Üµ½B
_ËåwÌAØGlæ¶Æäp©ç̯¶vOÅ¢çµÄ¢é3lÌæ¶Æv5lÅ{vOÉQÁµÜµ½B
ͶßÉ{vOÍñíÉ^tŵ½B
©7߬ÉͶÜèAéÍ12OÜÅfBi[ɨU¢¢½¾«ðUÉÈèÜ·B
°ÔÍ·Ä5ÔöxÅAú{ÅÌdðµæ¤©ÆàvÁĢܵ½ªÅ«Ü¹ñŵ½B
éöxÌÍÉ©MÍ èܵ½ªTàÜßAúÅ·Ìų·ªÉSgÆàɱ½¦Ü·B
òs@Å
ãÉ[}ÌGemelliåwa@ibR«ÅL¼ÈProf.Rocco̳ºjð©wµÜµ½B
2VbgÊ^Íó¨Å·B

Prof. RoccoÆ2VbgÊ^
¬³ºÌ涪··éRARPð©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B
à¿ëñRocco«ð³êĨèܵ½B
EAUÌæ¶Í{ÉeØÅÓfBi[ÉUÁľ³èéxÜŨt«¢µÄ¢½¾«Üµ½B

Gemelliåwa@X^btÆÌ[Hï(¶GÒA¶3ÔÚGProf. Rocco)
úÈ~Íi©gÅ··é@ï̽¢RAPNâRARCð©wµÜµ½B
ïxÌèpðWfgÌæ¶ðèɵÄA¬êéæ¤Éüµ¢èpð³êĢܵ½B
·ãͨ»çƯ¢ãÌæ¶Å èApãÉ¢ë¢ëƨbð³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ïxÌèpð®àøÉI¦½¼ãÉà©©íç¸AªÅamIÉÞÌèpÌMOð³¦Äêܵ½B
TÉÍ5lÅ[}ÌÏõÉs«Üµ½B
T^WFéðÏõãATsGgå¹°io`JsjÜÅà«AgÉÆè[}ÌxúŨȶÝÌXyCLêÜÅs«Üµ½B
»µÄ²Å Á½[bpTbJ[ðÏí·é±Æª«Üµ½B
±Ì Æ}h[hÉ¢í¯Å·ªA»ÌúÔÍã\TÔi¿å¤Çú{ÅÍ[hJbv\IÊߪèjÅ èNuÌÍÈAX^WIEIsRE[}ÅZGAÌAS[}ÎJAÌö®Q[ðÏíµÜµ½B
±±ÅÌ»±à±±ÅLµ½¢Å·ª ÜèÉ·È軤ÈÌÅâßĨ«Ü·B
4úÔÌ[}ØÝãÉ}h[hÉÚ®µÜµ½B
}h[hÅÍProf. Burgosªå÷éRamon y Cajalåwa@åAíÈð©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ܸúÉVersius platformÅs¤RARPð©é±ÆªÅ«Üµ½B
Versius platformÍiªúíIÉgpµÄ¢éDa Vinci XiÆär·éÆââA[ªãµg¢èª«¢óÛÍ èܵ½ªA»±ÍZpÅJo[³êĢܵ½B
ܽK^Éà{bgxtÚApÌRamon y Cajalåwa@1áÚð©w·é±ÆªÅ«Üµ½B
úÍoZi©çGLXp[gÌæ¶ðµãÙµÀSÉI¹µAI¹ãèpºàÅèðµÄìñ¾±ÆªóÛIŵ½B

Ramon y Cajalåwa@ÅÌ{bgxtÚAp1áÚÌ ÆÅ
iOñ¶3lÚªProf. BurgosAE©ç2lÚªÒj
Prof. BrugosÍliÒÅ è©ÂãwÉÆÇÜ縳ܴÜm¯ðàÂæ¶Åµ½B
»Ì¨çÌL³ÅARoyal academy of medicine of SpainâRoyal palace GalleriesâAstronomical¨ÙÉ«êåÆÉÄàðµÄ¢½¾Æ¢¤@ïð¾é±ÆªÅ«Üµ½B
ܽA}h[hÌ{nÅ éBernabeuX^WA~
[WAàprofÌFlÉÄà𢽾«Üµ½B
ÜèÌ´®Å©ªÆ§qÉ2
ö®Q[VcðwüµÄµÜ¢Üµ½BiÍxKÌVcÅ·B©Èè¿Åµ½Bj
¿å¤ÇTbJ[ÌÍ èܹñŵ½ªAXyCÅTbJ[ÌÉW[ÈX|[cÅ éoXPbg{[ÌA}h[hÌðãÇÌæ¶ûÆêÉv20¼ÅÏíµÜµ½B
à¿ëñAªµAåÏ·èãªèêCÉ£ªkÜèܵ½B

Ramon y CajalåwX^btÆÌA}h[hioXPbg{[jÏí
liÒÅ éProf. BrugosÌ·©¢Â«Å3úÔ©wð³¹Ä¢½¾¢½±ÆÍA[}ÅÌo±Æàá¤MdÈo±ÉÈèܵ½B
»Ìã¢æ¢æEAU2025ªnÜèA³|IÈÍÉÁ«ÈªçMÊÌ¢fBXJbVâÅVÌÕ°±ÊÈÇðSÉ׵ܵ½B
·¢½Æ±ëÉæéÆ70¼ß¢JUAo[ªQÁ³ê½Æf¢Üµ½B
JUAÌæ¶ûÌ°XƵ½\Éhð¤¯Üµ½B
éåwçtãÃZ^[Ìáäæ¶Æ¬µwïâÏõàµÜµ½B

EAU2025ÌI[vjOZj[i¶FÒAEFáäæ¶j
ܽvXÌJUAo[ÆÌÄïÉÆÄàÀgµ½±Æðo¦Ä¨èÜ·B
3úÚÌéÉÍthVbvfBi[ɲµÒ¢½¾«A¢EÅô³êÄ¢éåäÌOÅ\²¢½¾«§hÈðàç¢Üµ½B
Ì´®ÍYêçêܹñB
ßÄ^LV[hð
ÄQÁµ½l¶ÅÅÌŵ½B
l¶Ìs[NÉÈçÈ¢æ¤É¡ã¸i¢½µÜ·B

TUAo[ÆêÉEAUth[VbvfBi[Å\²ã(GÒ)
{·MðµÄ¢é»ÝA@ÅÍåÈÔûvà ècÆãk¬Æ¢¤a@©ç̽èðÔÇEÅ éÉÈ°çêĨèÜ·B
^í¸Å è©Èè½ðÄԱƾƪµÄ¢Ü·B
¡ñ©wµ½EAUÅÌåwa@iÁÉèpºjÌOÏ͵ħhÅͲ´¢Ü¹ñŵ½B
æiIÈfoCXðìgµÄAm¯ÆZpÅèpðs¤±ÆÅ¿Ì¢ãÃðñµÄ¢Üµ½B
{MÅÍÆkÈÇÌ_Åïµ¢±Æà èÜ·ªAÝõɽÌðµ·¬é±ÆÍ¢©ªÈàÌ©ÆvÁĵܢܵ½B
ÌâèpºÍDZ©¡ª èA»êÍ»êÅOÈãÉÆÁÄï[¢Å·B
ÅãÉAÍåAíÈãÉÈè¡ÜÅ2TÔèpºÉêààüçÈ¢±Æª èܹñŵ½B
ÌÖèÅà èܵ½B
COÅÆ°Æ£êÜÆÜÁ½úÔðêlÅß²µüßÄ¢ë¢ëȱÆÉ´ÓðµÜµ½B
±±Å±ÆÅÍÈ¢©àµêܹñªAðx¦ÄêÄ¢éÈðͶßÆ°ÌÌå³ðÀ´µÜµ½B
¥µÄ20NêØÌÆðµÈ¢¶ðµÄ¢½±ÆðSêµ´¶Ü·B
º
âCºð°ÔðíÁÄzeÅèô¢µ½o±ÍYêé±ÆÍ èܹñB
Ó¾ñA{ÉK¹È¶ðµÄ¢é©ðÀ´µÜµ½B
»µÄA³ºðÞ¯¼OÅ é^C~OÉà©©íç¸{vOɲE𢽾«õèoµÄ¢½¾¢½sìqF³öA2TÔÌ ¢¾åwa@ÌèpEOEü@ðx¦Äê½Ô½¿ÉüßÄäçð\µã°Ü·B
NxÅÙ®Ì éæ¶à½¢éÈ©Å{ɴӵĢܷB
{vOž½o±A´oA´Óð¡ã¢©ÉÒ³µÄ¢©ð±ê©çl¦Ä¢«Ü·B
±Ì½ÑÍåÏMdÈ@ï𢽾«½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFfÃy³ö@²Ë qa
2025/3/10-13 EAU2025@Madrid, Spain
±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B
µÔªoÁĵÜÁÄ©çÌñÆÈèÜ·ªA3ÉXyCE}h[hÅJóêܵ½¢BåAíÈwï(EAU)ÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B
¡ñÍ¢ÂàêÌâ{æ¶Í¢çÁµáç¸AO¼Íêl·Åµ½B
xúÌÖWÅ1úXyCüè·é±Æªo½ÌÅAúÍ}h[h©çÙÇߢghÉsÁÄQèܵ½B
ghÍXS̪¢EâYÉo^³êĨèAÌȪçÌXÀݪ۶³êÄ¢énæÅ·B

ìÉÍÜêĽXÀݪñíÉüµ¢±ÆÅmçêĢܷ

ä©ç©ºëµ½XÀÝ@iÌlÅ·

êínÜ軤ÈLê@@@@@@@@@@@@@@@zeÌ®©çÌß
úÉÍ}h[hÉßèwïêðKêܵ½B2015NÉâ{æ¶ÆKê½Æ¯¶ïê(Ifema Madrid)ŵ½B
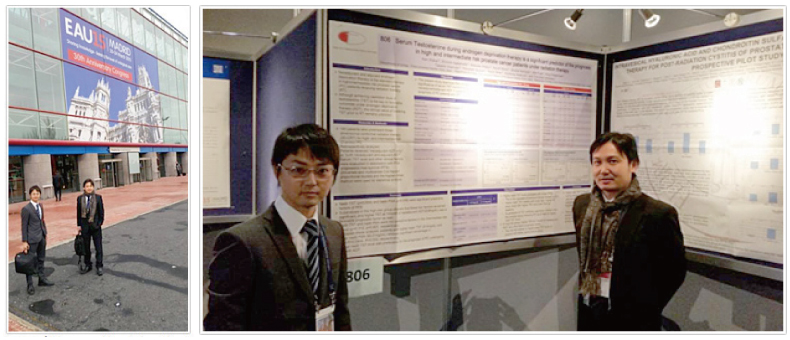
2015NÌEAUÅâ{æ¶Æ
2015NÌEAUßLͱ¿ç

¡ñÌwïêÌlq@W¦u[X
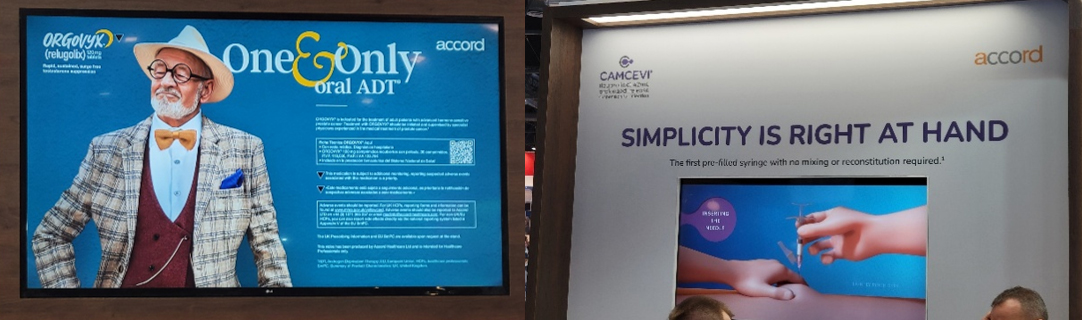
àÂ\ÈADT(AhQÃ@)ò@@@@@¬ºéKvÌÈ¢leuprolide(ADT)Ëò
3ÂÌèp({bgèpAPNLAThuLEP)ª¯isÅsíêĨèA®OÍCzÌ`lðØèÖ¦é±ÆÅ¢¸ê©ÌèpÌÀµð®±Æªoܵ½B


²Ëæ¶Æ¬
wïêÅÍJUAÌExchange programÅ[bpÉ1©ÔØݵĨçêܵ½²Ëæ¶Æ¬·é±Æªoܵ½B
¨Zµ¢AÌvÉSÄí¹Äº³èAñlÅ}h[hÌXðiµÜµ½B

²Ëæ¶ÆXyCr[@@@@@@@@@@@@@@{êÌtRÓÜ
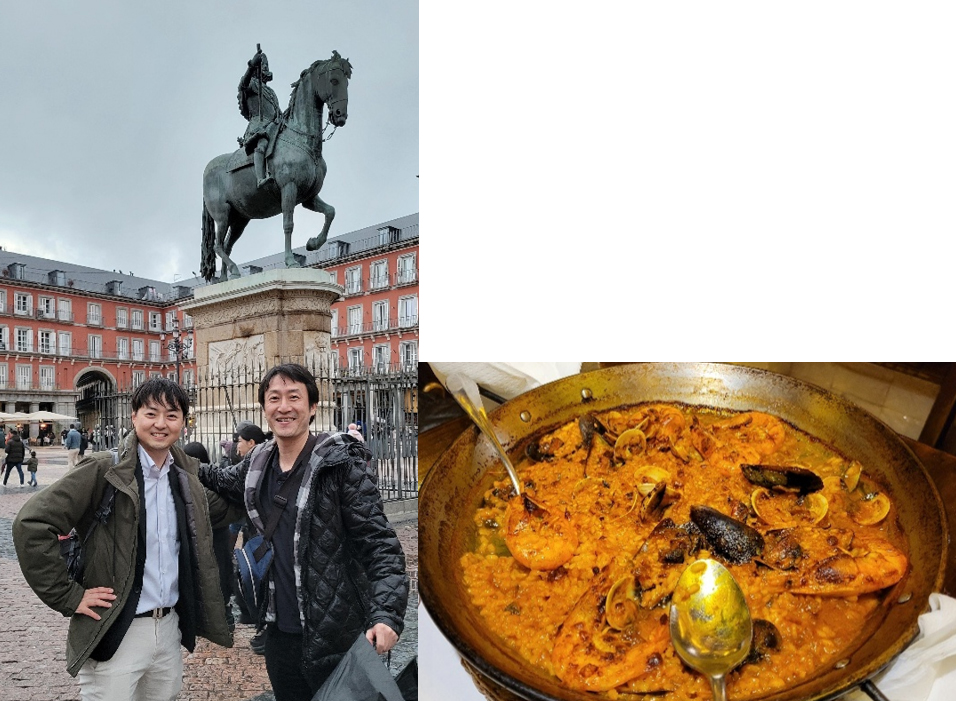
IGeLê@@@@@@@@@@@@@@@@à¿ëñpGAหܵ½
3úÚÌßã©çÍA±êܽ¢EâYÌXZSrAÉKêé±Æɵ½ÌÅ·ªAÌ~XÅoXÌonɽÇè
¯¸A²Ëæ¶Æ1kmÈã_bV
µ½ÉàÖíç¸cA[oXÉæé±Æªoܹñŵ½cB(²Ëæ¶\µó èܹñ¾)
ÈñÆ©úKêé±Æªo½ÌÅ·ªA}h[hæè10xÈã¦áàÏàÁĢܵ½B
±±ÅÍL¼È
¹´âáP̨éÌfÆÈÁ½AJTéÈÇðñé±Æªoܵ½B

ZSrAÌ
¹´@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZSrAÌXÀÝ

AJTé@m©ÉáP̨éÌÊeª èÜ·@@J^[j¿@¹ÌÛÄ«ÆJ^[jX[v
»ÌãAwïêÉßè\ŵ½B
¡ñÍAÇXegª³Ò³ñÌÌàÅÇÌæ¤ÉÂÇ·éÌ©A»ÌJjYÉ¢ÄÌ\ðs¢Üµ½B
îáawÅsÁÄ«½¸dq°÷¾(SEM)ðp¢½¤Ì·ÅA±êÜÅSEMÅðÍoĢȩÁ½XegàoÌÂǨ(fuX)Ìg¬âªzÉ¢ľç©ÉÅ«½ÌÅA¡ãÍÇáðâµA\h@É¢ĤµÄ¢¯êÎÆl¦Ä¢Ü·B
ÅIúÍSÀæ¶AYNɨU¢¸«AïHðµÜµ½B
bÌìN(üÇ1NÚ)Íüǵ½ÄÉàÖíç¸è\ð³êĢİ뵴¶Üµ½B
±¤¢¤¡ÌqªèàåɵĢ«½¢Å·ËB
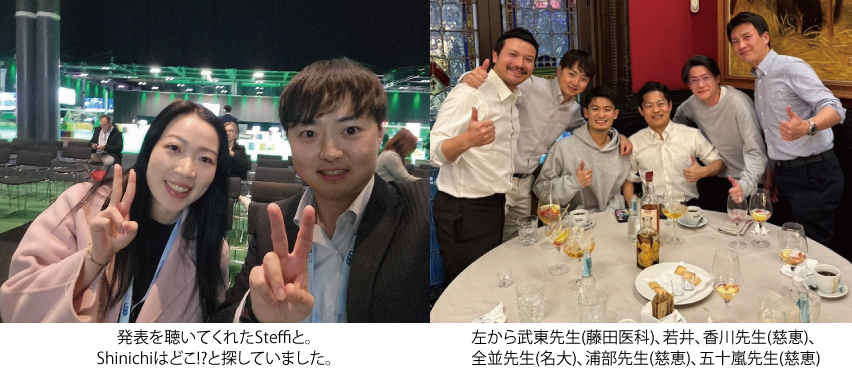
±¤µÄUèÔéÆyµ¢±ÆΩèµÄ½æ¤Éàví껤ŷªcÎ
¡ñÌEAUÅà½ÌwѪ èܵ½B
Xeg̪ìɨ¢ÄàÇñÇñZpvVªiñÅ¢éÌÅA©ªà\ΩèÅÈê¸Â_¶»ðißÄ¢©ËÎÆüßÄ´¶Üµ½B
ܽSÌƵÄÛIÈêÅ\µÄs¯éæ¤ÈyëðìÁÄ¢Kvà éÆ´¶Üµ½B
¢EIÈCtâ~Àà èAÛwïÉsàKIn[hªÇñÇñãªÁÄsÁÄ¢éð¡Å·ªAFXÆHvµÄ¢µ©È¢Ì©ÈÆv¢Ü·B
²Ë涩çÍáèç¬ÉÖ·éAc¢bZ[W਷«·é±Æªoܵ½B
iÍÈ©È©·±ÆÌoÈ¢b𨷫µÄSª±¢§¿A©ªàãiÌç¬Ì½ßÉoé±Æðl¦³¹çêܵ½B
ÅãÆÈèܵ½ªA¡ñ̤\̽ßɲw±¾³Á½â{æ¶AîáawÌr´³öðnßÆ·éæ¶ûA¨xÝðº³Á½éåw¿ÎãÃZ^[ãÇÌÝȳÜÉS©çäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
¡ãÆàæ뵨è¢vµÜ·B
P.S.
²Ëæ¶Í[bpØÝÉRocco stitchÅL¼ÈRoccoæ¶Ìèpð©w·é±ÆªÅ«½»¤Å·B
JUAÌExchange programÍNåWµÄ¢éæ¤ÈÌÅ_ÁÄÝéÌàÇ¢©àµêܹñB
¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä
J¬Zçtã©wcA[ `ãwðÚw·álÌ´«ÉGêÄ`
±ñÉ¿ÍB{N101úæèAà¯wðI¦ÄåwÉßÁĨèÜ·cºM¾Å·B
¡ñÍ10Ì^úÉsíê½AÌêZÉʤ»ðZ¶ðÎÛƵ½çtåwãw©wcA[ÌÍlð|[gµ½¢Æv¢Ü·B
í½µÌêZÅ éJ¬Z©çÍN10¼OãªçtåwãwÉüwµÜ·B
±±NAäXOBªãwó±ðl¦Ä¢é»ðZ¶ðÎÛÉçtåwãwÌ©wcA[ðéæµÄsÁĢܷB
»ðãw·Aa@·Aeȳöw𨵫µA³çÉÍOBÌ»ðãw¶ÉàQÁµÄàçÁÄçtåwãwA»µÄ»Ì²Æ¶ÆµÄÌãtÌAð´¶Äà稤Ƣ¤éæÅ·B
J¬ZÍ̺¬A¼úé¢É é§ZÅ·B
çt§©çʤ¶kàñíɽÈÁĢܷB
ð¡Ìãwó±É¨¢ÄàÌ Æ¯¶æ¤ÉAåwÌïÕxª¢Æ´¶é¶kªãÈÈåwiÅßAÈwåwÉüÌjAçtåwA¡ls§åwÆ¢Á½ñsÉÊu·éö§ãwðó±·éP[Xª½ÈÁÄ¢éæ¤Å·B
åAíÈÉàsì³öðͶßA¡¼Ì¯ZogÒª¨èAà»ÌêlƵÄæyâãyÆÌãJð´¶Ä¨èÜ·B
³ÄúÅ·ªAçtåwªÖéX^[³õwiJ¬OBÆÍÀç¸jÉæéu`{³Cªæè¿ÌáèOBwE»ðãw¶wÉæéãwEa@©wcA[Æ ÁÄA¡NàåD]ŵ½B
í½µÍêðNƯlÉiïisðƵĦͳ¹Ä¢½¾«Üµ½B

³ºªÖéX^[â{y³öÌMu`É·«üéZ¶½¿

¼èÉg[h|[YÅãyÌZ¶½¿ðÎçɷ鳺sì³ö
áNAcA[ÉQÁ·éZ¶©çOEúÉ¿âðó¯éÌÅ·ªA
wȺãtðuµ½Ì©x
wçtåwãwÌÆ©ÌÝEÁFͽ©x
wÔÁ¿á¯Ä^ÍǤÈÌ©x
wAIÉæÁÄ¡ããÃâãtÌÝèûªÇ¤ÏíÁĢ̩x
Æ¢Á½¿âðæó¯Ü·B
ð¡Ag`NrhÆ¢¤¾tð¨É·éæ¤ÉÈèܵ½B
úÕ°¤CðI¦éAàµÍúÕ°¤CðI¦éOɼÚi`NZcjüeirEjÖAÌæÉ¢±Æðw·»¤Å·B
wiÉÍAãÇÉ®µÀ¢^Ååwa@ÌÈ©ÅLAAbvðÚwµÄ¢ãtÌ«ûª ÜèÉgRXphÉíȢƢ¤dåÈóµª èÜ·B
µ©à»Ìæ̸_É é͸̳öÌ|XgÌ^ÍµÄ½Í èܹñB
¼ÚüeÉ¢¯Îì¯oµÌüeOÈãÅàåw³öÌ{ÙÇÌNûð¾çêĵܤÌÅ·©çAüeãÃÉâ誢ð´¶çêêÎR»¿çÉlÞª¬êé±ÆÉÈéŵå¤B
»ñÈóµÍ±ê©çEÆIððµÄ¢á«DGÈZ¶½¿Éà`íÁĢܷB
åw̲ƶª¯»Ì¢EÅÍÈAOnRTÉ¢ÁÄÀÍå`ÅðæèƧðÚw·¬êª éæ¤ÉAá«DGÈãtªú{Ðïðx¦édvÈãêì©ç´©ÁÄ¢éÌÅ·B
æÉ°½Z¶©çÌ¿âÍAgð¡ÌãÃðæèªóµÌÈ©h
wȺãtðu·Ì©x
wûüÍ\ªÈÌ©xA
»µÄwȺçtåwÈÌ©x
wAIªäª·éÈ©ÅãtÆ¢¤d̶ÝÓ`ÍÈñÈÌ©x
Æ¢¤ÉßÄÅdvÈ⢩¯ÆµĄ̈ÉÍ͢ĢܷB
ÂlIÈl¦Å·ªA¹ßĬfÃððÖ·éÈǵÄAåwa@ÉÍfÃàeÌ©Rð^¦AÅæ[ÌãÃZpð¤J·éÓ±ðS¤åwa@®ãtÉüÁÄé¨àðåÉâ³È¢ÀèÍAú{ÌãÃÍÞÌêrðHéŵå¤B
ú{ÌãÃÌMpð¿lƵÄACOxTwÉü¯½ãÃc[Yðñ·éåwª ÁÄࢢ©àµêܹñB
åssÆHcE¬c¼ó`ÖÌANZXA»µÄõ¾ZÈ©RÆAL©ÈH¶»ðàÂçtÉÍå«È|eVª èÜ·B
tÉCOÖÌANZXÌdzðèɵÄAAWAÈÇ¢EeÖÌãÃX^bthÌbJƵÄÌufBOðµÄࢢ̩àµêܹñB
ãtðuµ½©çÉÍAaÉêµÞûXÉó]Ìõðͯég½ª èÜ·B
»ê±»ªãtƵÄ̶«ª¢¾ÆvÁĢܷB
®ÌãAãtÌÝèûͽl»µÄ¢©àµêܹñB
çtåwÌ150Nð´¦é`ðp³µÂÂàAå_ÈüvðÅ¿oµÄ¢Kvª éŵå¤B
ál½¿Ìȱ±ëÉGêA±ê©çãtðu·á¢¢ãªNN·éæ¤ÈA»ñÈåwãÇɵĢ©È¯êÎÈçȢƴ¶Ä¢Ü·B
í½µà÷ÍȪ穪ÉÅ«é±ÆðKÉl¦Ä¢«Ü·B
±ê©çãtðu·FlÖB
çtåwåAíÈÅAÆàÉNNÈVãðnÁÄ¢«Üµå¤I
¶ÓFÁC³@cº M¾
Clinical Fellowship in Chiba University Hospital
I am Dr. Chin-Li Chen, a urologist from the Tri-Service General Hospital in Taiwan.
Chiba University Hospital is an internationally renowned medical center that frequently hosts doctors from various countries for learning and observation.
I am truly grateful to Professor Tomohiko Ichikawa and Professor Shinichi Sakamoto for accepting my application and providing me with this opportunity to train in the Department of Urology at Chiba University Hospital.
During my time here, I have experienced world-class surgical techniques, witnessed the highest standards of patient care,
and observed a collaborative and harmonious medical team in action.


During my time at Chiba University Hospital, I had the opportunity to learn a wide range of surgical techniques (see the figures below),
including retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy under Professor Shinichi Sakamoto,
Robot-Assisted Radical Prostatectomy (RARP) under Dr. Yusuke Imamura and Dr. Kodai Sato,
Saline-assisted fascial exposure (SAFE) technique during RARP performed by Professor Shinichi Sakamoto and Dr. Yasutaka Yamada,
Robot-Assisted Partial Nephrectomy (RAPN) under Dr. Manato Kanesaka, Robot-Assisted Nephroureterectomy (RANU) under Dr. Tomokazu Sazuka,
and microsurgical subinguinal varicocelectomy under Professor Tomohiko Ichikawa and Dr. Hiroki Shibata.
These surgical experiences have been incredibly valuable and have greatly enriched my learning.




During my time here,
I have not only acquired advanced medical knowledge and surgical skills but also had the opportunity to experience the many beautiful aspects of Japan.
The convenient transportation, rich culinary culture, and the admirable civility of the people are all captivating features of Japan.
I am incredibly grateful for the opportunity to train in the Department of Urology at Chiba University Hospital,
and I am confident that the knowledge and experiences I have gained here will serve as invaluable inspiration and guidance for my future medical career.

Chin-Li Chen. M.D.
Division of Urology, Department of Surgery, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan.
æ11ñú{×EO¬Ewï `4N¼Ìåw@¶ðI¦Ä`
²³¹¿µÄ¨èÜ·AcºM¾Å·B
ÈOÌei2022N117újɨ¢ÄAãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤åiJ¤jÉयwðµÄ¢é|ðeµÄ¨èܵ½ªA
¡NÌ9ÉwÊ_¶ð®¬³¹Äåw@ð²ÆµAmiãwjÌwÊðæ¾¢½µÜµ½B
üßIJw±¢½¾¢½æ¶ûÉ´Ó\µã°Ü·B
í½µªSN¼æègñ¾¤ÍAàÌ]ÚÌiWJjYðAîáæiÊɶݷéj×EªY¶·ég×EO¬EhÆ¢¤¨¿ÉÚµÄð¾µæ¤Æ·éÝŵ½B
àÌ]ÚÆ¢¤ÌÍñíÉïîÅ·B
ÉÍ®«ªÈ¢æ¤ÉݦÄÀÍVÂãÓªÉsíêAíÉVµ¢É¶ÜêÏíÁĢܷB
±ÌãÓTCNÌ¢ìÈyëÍà×EÉÆÁÄͤÁįÌB«Åà èAÐƽÑ]ÚðN±µÄµÜ¤Æà×EͱÌL©È«ðàÂàÏÉpµÄÇñÇñiWµÄ¢ÌÅ·B
ÁÉåAíÈàÌÈ©ÅàL¼ÈO§BàÍðñíÉDÞ±ÆÅmçêĨèAisO§BàÌñ7|8ª]Ú𫽷Æà¢íêĢܷB
µÄÀհɨ¢Ä½¿Ü¿]Úð§äÅ«éæ¤Èå©ðµ½í¯Åà èܹñªA é»ÛÌJjYðêèÌØèû©çð¾·é½ßÉ4N¼Æ¢¤Nð©¯ÄA
éúàéúऺŪðYܹAÀ±ðJèÔµ½úXÍAí½µÉÆÁÄå«ÈàYÆÈèܵ½B
K¢Éàåw@Å̤àeÍA¢æú1028úA29úÉsíê½æ11ñú{×EO¬EwïŧãÜi|X^[\jðóÜ·é±ÆªÅ«Üµ½B
±êðãÝɤ}ChðÁÄãtƵÄ̹ðàñÅ¢±¤ÆÓðV½ÉµÄ¢Ü·B

¤vUzeÅsíê½æ11ñú{×EO¬Ewï§eïÉÄ
Ê^¶©ç§äpåwEDr. Li-Chun ChangAVK|[§åwEDr, Minh Le
ܽA±Ìåw@¶ÌÔÉÍACOÅ̤\Ì@ïð½¢½¾±ÆªÅ«Üµ½B
RiЪ¢Eð¢Á½2020`2022NÌÔÍÈ©È©OÉoçêܹñŵ½ªA±ÌÔÉàŤ¬Êð\ªÉ·ßA2023`2024NÉ©¯ÄÍêCÉCOÖòÑoµÄ¢±ÆªÅ«Üµ½B
AJiVAgjA`AI[XgAi{jAVK|[AØi\EjÈÇÅwïÉQÁµA¢E̤ÒÆc_µAð¬·é@ïÉbÜêܵ½B
àÏíç¸pêÍ٢ŷªA°XƤàeÆú{l°ð¦·±Æ±»ª½æèåØÅ é±ÆªgÉõÝÄí©èܵ½B
XÌnqÌ«Á©¯ð^¦Ä¾³Á½³ºÌâ{y³öâAà¯wæÌJ³öÉÍ{ɴӵĢܷB

Û×EO¬EwïÌwïåÃð¬p[eB[
2023N(AJEVAg ¶)A2024N(I[XgAE{ E)
L¼ÈüpÙݵØÁÄNudlɵ½èAsXÌL¼ÈNuðÝØÁ¿áÁ½èB
ÆÉ©COÍð¬ïàêµ³ªÈÄÅÅ·B

L¼Èîb¤Ò¾ÁĨ¨Íµá¬B
ú{©çêÉ«½{o[»Á¿Ì¯Å¢E©çWÜÁ½¤Ò½¿Æ͵á¬Ü·Båa°ÌݹDZëB
Ⱥ©êÉxÁ½èµÄÇÈé¤ÒªwïÜðÆéÆ¢¤äÌWNXÎ

`¶åwÌX[p[G[g̯úÅ èf°çµ¢FlÌSteffiɵ©ê`ÖB
¢E©çWÜéåAÈ㽿ÆwïÅð¬BÕ°¤àâÍèÊ¢B
æl½¿ÌÏÝdË̤¦É³çÉpmðÏÝdËÄ¢¤Æ¢¤cÝÍñíÉüµAܽQÌ éà̾Æv¢Ü·B
ÁÉîb¤É¨¢ÄÍA©gÅß½ÐÆÂÌe[}ɶÁèÆü«¤È©ÅAÇÆÈ©ªÆÎb·éÔª·ÈèÜ·B
lÞªÏÝdËÄ«½¶½ÈwÌðjÉz¢ðy¹ÂÂA©Èð©Âß¼·±ÆÌÅ«½úÔÍãtƵÄÌí½µðÐÆÜí謷³¹Äê½æ¤Év¢Ü·B
UèÔêÎARiÐÅ©mçÊ«Égðu¢ÄnÜÁ½µµ¢åw@¶Åµ½ªA¡ÆÈÁÄÍ©ªÉÆÁÄKvÈÔð^¦Ä¢½¾¢½Æ´ÓµÄ¨èÜ·B

ãÈåwãw¤Å¤É¤·éÅÌo[Æ
çtåwÌåAíÈÉÍ©ªÌ´«É]ÁÄãtƵÄ̹ðfUCµÄ¢¯é«ª èÜ·B
àEOɤ¯w·é±ÆàÅ«Ü·B
à¿ëñOêIÉèpÌrð±ÆàÅ«Ü·B
±êÍçtåwåAíÈÌæy½¿ªÏÝã°Ä«½`̤¦É¬è§ÁÄ¢éàÌÅ·B
æy½¿àãy½¿àDGÅliÉàDê½ûXΩèÅ·B
±ê©çüÇðl¦Ä¢éFlA¥ñçtåwåAíÈÌåð@¢ÄÝܹñ©B
f°çµ¢Â«ðÁ½DGÈæy½¿ªz¢Ä«½ÅÌ«ªMûðÒÁĢܷB
¶ÓFcº M¾
æ1ñáèStRy(Vät)
²³¹¿µÄÜ·Béåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B
¡ñÍ2024N10ÉJóêܵ½æ1ñáèStRy(Vät)É¢IJñvµÜ·B
ÅßÌåAíÈáèÌStMÍ·²¢à̪ èÜ·B
(ãt13NÚ)ðáèƵÄÇ¢©Íc_Ì]nª èÜ·ªAȺ80¼ÌåAíÈáèÌÅAStðâÁÄ¢éÒª30¼Í¢é±ÆðmFµÄ¨èÜ·B
RiOÉ͹¢º¢10¼öx¾Á½Í¸ªARiÐÉæÁÄIɦ½óÛÅ·B
©¢¤àAé¿ÎÉCµ½2022NÉ[J³ǫ̈U¢Éæè{iIÉâènß½ì¯oµSt@[Å·B
¡ñ»ñÈStMɦé×AStRyðJ÷é±ÆÆÈèܵ½B
O[_[Å éVäæ¶Ì¼Oð¥µÄA15NÚȺÌáèɺ|¯ðµ½Æ±ë20¼ªWÜÁÄêܵ½B

ãñ)RA·ªAóûAPA²¡qAVäAáäAºA¼äAä
Oñ)´
AV[AÔêAR¨Anç²Ar´A¬ÑAåºApc(h̪)


´
æ¶ÌeB[VbgB260[h(à240m)òÔ±ÆàI

SõŨB
úÍVCÉàbÜêMµ½åïÆÈèܵ½ªAåï𧵽ÌÍStogÅAãÌÅàNo1vC[¾Á½Æ¢¤¼äæ¶Åµ½B

OX(Å)1Ê̼äæ¶B³·ªÅµ½B
2ÊÉÍqv\õR¾Á½Æ\Ìpc²(äß)æ¶B
xXg70äÅñé¦rÅ·ªA¡ñÍfB[XeB[ÅÍÈêÊeB[©çv[µA©2ÊÆÈèܵ½B
üµß¬éXCOÉSõªBt¯ÆÈÁĢܵ½B

OX2ÊÌpcæ¶B
¡ñÍOXÆnfB¼ûÅÊð¯Aeܪo龯©ÔçÈ¢æ¤ÉJèã°\²µ½ÌŽÌvC[ªüܵܵ½B

nfB1ÊÌ·ªæ¶B@@@@@@@@@@jAsÜÌR¨æ¶Aóûæ¶B

hRÌ·ªæ¶Båºæ¶B
å¬÷ƾÁÄ¢¢·èãªèŵ½ÌÅVäæ¶ÆkµANàJÃÅ«êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
ÂlIÉÍÙRJg[Åêxv[µÄݽ¢ÆvÁÄ¢éÌÅA»Ì ½èðSÉNÌéæðißÄ¢éƱëÅ·B
Ýȳñ\èÌmۨ袵ܷB
ܽAܾStnßĢȢæ¶Í¡©çÅàÔɤÌÅûKµÜµå¤Î

ÙRJg[Nu
ÅãÉA¡ñÌRyJÃÉ۵İåÉ਼Oðݵľ³Á½Väæ¶Éäç\µã°Ü·B
±ê©çàáèê¯yµâÁÄ¢¯êÎÆv¢Ü·B

Väæ¶Æáä@@@@@@@@@@@@@@@@@@[Ì|[Y (¨Üè)
¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä
ú{åAíÈîáwïæ10ñwpWï
ͶßܵÄB2023NxüÇÌ{é¤ßÆ\µÜ·B
ÈPÉ©ÈÐĢ½¾«Ü·B
ogÍ«ê§Å®
åw²ÆãAÖÉioµÜµ½B
àä©èà èܹñªAa@©wÌÛɵÍCÌæ©Á½çtåwåAíÈÉüÇðßA¡ÉèÜ·B
2024N4©ç9ÜÅçtåwãw®a@ÉÎßA10©çÍéåw¿ÎãÃZ^[ÅαµÄ¨èÜ·B
éåw¿ÎãÃZ^[ÅÍ[Jæ¶ðͶßA«L©Èæ¶ûª½aCå\XƵ½µÍCÅ·B
ܾµêȢ«ÅÍ èÜ·ªAæ¶ûâÅìtAX^btÌDµMSÈT|[gÌàÆúXÌƱÉãޱƪūĢܷB
AHÎârAáQiWEATURPjA o¾ºèpÌÇ᪽AܽA2024N7©ç{bgèpànÜèAÜ·Ü·èp̪LªÁĢܷB
¡ãAªñ¾¯ÅÈÇ«¾³ÌèpÌo±à½ÏޱƪūéÆv¤ÌÅyµÝÅ·B

(½}ïðµÄ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½)
³ÄA2024N1026úA27úɪ§ÌJRãBz[ÅJóê½ú{åAíÈîáwïæ10ñwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ÍRcN²æ¶²w±ÌàÆO§BàÉ¢Ä|X^[\ð³¹Ä¢½¾«Açtåw©çÍZhao Xueæ¶Aâ{Mêæ¶à|X^[\ðs¢Üµ½B
ßÄÌ|X^[\ž¢ÔÙ£µÄµÜ¢A3ªÌv[ÅÍ èܵ½ªÔzªªí©çÈÈÁ½èw¦_ð¼èÅÁÄ¢½èƽÈ_ͽX èܵ½B
ªAÆÄàÇ¢o±ÆÈèܵ½B
²w±¢½¾«Üµ½Rcæ¶É´ÓÌC¿Å¢ÁϢŷB
èªÆ¤²´¢Üµ½B

(Ù£·é{éÆ»êð©çéRcæ¶)
ªÆ¢¦Îü¡µ¢²ÑÆ¢¤±ÆÅA[âàÂçA¾¾qÈÇH×é±ÆªÅ«Üµ½B

(Zhaoæ¶A{éARcæ¶A[Jæ¶Aâ{æ¶ @ÆæȪ)
NÌú{åAíÈwïધÅJóêéÌÅF³ñàºÐQÁµAü¡µ¢²ÑðyµñÅ¢«Üµå¤B
¡ñÙ®ÉÈÁ½ ÆÉàÖíç¸A²w±²¦Í¢½¾«Üµ½çtåw®a@Ìæ¶ûAãÇÌX^bt³ñAZt³ñɱÌêðØèĨç\µã°Ü·B
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓF{é ¤ß
Clinical Observership in Chiba University Hospital
Around mid-May, I had a 4-week clinical observership at the Chiba University Hospital.
The Chiba University Hospital is a medical center in which doctors deal with complicated diseases.
During the observership, robotic-assisted surgeries (RARP, RAPN, robotic assisted retroperitoneoscopic adrenalectomy, etc.) were the most I observed.
I was so impressed by the strict hierarchical medical system as well as the Japanese working style that gteamworkh played such an important role.
It was quite different from my country.
I think patients would benefit from the delicate and personalized care, and doctors probably could deserve a healthier work-life balance.



Recalling the period in Chiba, I believe one of the most precious parts is to meet so many interesting people and to build lasting friendships.
Prof. Ichikawa is a humble gentleman who speaks so many languages and is still learning more.
Prof. Sakamoto is an open minded and proactive mentor.
Aside from his love for surfing, I appreciate his willing to learn about different ideas and try new surgical techniques.
I also met Prof. Park from South Korea, who is always energetic and thoughtful.
Sharing his own experience, he taught me how to survive in Japanese Hospital as a foreigner and about Japanese Edo history.
During the observership, I felt happy to hang around with these inspiring gsenpaih from different countries and discussed various topics with them.
The professorsf vivid personalities correspond to the role models for young doctors like me.
Furthermore, we had great times with Dr. Imamura, Dr. Yamada, Dr. Saito, Dr. Shibata, and many of the members in the Chiba University Hospital.


Special thanks to Prof. Sakamoto for facilitating the observership.
I am lucky to have this experience in my first year of attending doctor, and I believe it will somehow make me a better urologist in the future.
Ping-Chia Chiang M.D.
Department of Urology, Kaohsiung Chang Kung Memorial Hospital,
Kaohsiung, Taiwan
Report after visiting Chiba university hospital department of Urology in May 2024
This spring, I had a chance to have 3-month sabbatical leave.
I already decided that Japan is my place for this precious period, because besides the fact that Japan is the closest neighborhood country from my country South Korea, I wanted to get some information regarding my grandfather and great grandfather by my mother side because they all had graduated from Jikei university college of medicine.
In last April after I had successfully achieved their information from Jikei university and made good friendships with Japanese doctors, I moved to my second place for observation, Chiba university hospital department of Urology.
I and Dr. Sakamoto have been in good friendship for several years, and I wanted to observe his operation and research lab with my eyes this time.
Before I visited Chiba university hospital, I already had a chance to meet professor Ichikawa in Uro Fun Run JUA 2024.
I was so surprised to see that he could speak Korean language so fluently, and more surprised to see that he ran so fast, even faster than I!
With big welcomes from professor Ichikawa, Dr. Sakamoto and other doctors, I could start the observation in Chiba university hospital.
In addition, I was so lucky to start it with Dr. Pinga from Kaoshiung, Taiwan.
She is a so smart, active and adorable doctor.
I could know how to read Katagana and Hiragana, and she already knows the meaning of Chinese language, so we together could translate most of signboard or some information letters (Fig 1).

The operations here were impressive to me because all the operations I observed was the ones with retroperitoneal access and they were done very smoothly.
My hospital (Korea university Ansan hospital) has DaVinci Sp system, so I was interested in the operations with retroperitoneal access. Therefore, these observations were so fruitful to me.
And I also had a good time in dinner party with the candidates of new residents next year.
The conversations with young Japanese doctors gave me an inspiration and a deep understanding of similarities and differences between two countries (Fig 2).

Every Tuesday Dr. Sakamoto works in outside clinic. On 21st of May, he guided me and Dr. Pinga to Naritasan shinshoji, Unagi restaurant and old town village after finishing his outpatients clinic.
The Unagi don was so wonderful that we enjoyed it so much. After lunch, we had great time in the temple and garden.
At that time, I thought I did not live in the real world but in another world just like paradise.
The old town village was the hometown of Mr. Ido, who made Japanese map with his bare foot, and I enjoyed it very much because I read his story in my Edo era history book that I brought this time from my country.
There, we drank a cup of beer or Ginger ale, and we had talks about the international situations from Japan, Taiwan, and Koreafs viewpoints.
In our conversation, I strongly felt that these 3 nations exchange program is urgently needed (Fig 3-5).



The discussion regarding not only academic field but also doctors' general life or the present international situation were so meaningful to me, and I believe my friends doctors also feel the same way.
I have to say to professor Ichikawa, Dr. Sakamoto and the other doctors in Chiba university that I appreciate this chance for observation so much.
With this precious opportunity, I came to look back on myself, my hospital, and even my country.
And I believe that it was not the end of my visiting but the starting of real friendship among us.
Thank you for everything and I wish you full of good luck!
29th, May, 2024 in the airplane on my way back to home
Jae Young Park. M.D.
Professor, Korea University College of Medicine
Chief of Department of Urology, Korea University Ansan Hospital
AUA2024ÆMt Sainaia@ Tewariæ¶KâL(Newark©ç¬cÖÌUnitedÌ@àÉÄ)
¡ñÌ·ÌÚIÍ3ÂÅA
@5NÔèÌAJåAíÈwïiSan Antonio TxjÆ
ANYÌMt Sainaia@ÉÄ Tewari³öÌHood Technique https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33067016/ ðwÔ½ßÆA
BÌîbÌt Å éNatasha³öðKâ·é½ßŵ½B
Mt SainaiÌTewari³öÆÍAðNH̹æåwÌ涪å÷éJSER̵Òużh𷳹Ģ½¾AôRA̤t Ìi^[V³öàÝзé±ÆÉCªt«A}ç¯ñl̳öÉ˳¹Ä¢½¾«A¡ñÌKâÉÂȪèܵ½B
AUAÅÍAįw̹æåÌXæ¶ÆôRïêŨÄAµ©àAuñTÔOÉMt SainaiK⵽Ωè¾ævÆÌbÉA¡ñÌ^½Ì±«Ìæ¤ÈàÌð´¶Üµ½B
X涩çÍAOÉîñûW³¹Ä¢½¾ÅAñíÉX[YÉKâ·é±ÆªÂ\ÆÈèܵ½B
êûÅAa@©wªMt Sainai©çúÜÅoȢƢ¤h^o^ÈÇà èAñíÉXìêéóÛ[¢KâÆÈèܵ½B

2023JSERÉÄHood@ðlĵ½Tewariæ¶Æ(¶)
ñTÔOÉMt SainaiðK⵽ΩèÌXæ¶ÆAUAÅôR¨ï¢µÜµ½(E)
1. AUA@2024NÉ¢Ä
¡ñÌAUAÅÍAÈÌÜ涪tÌ\ðARc涪AResearch Show CaseÆ¢¤¢E©çWÜÁ½30¼ÌÅANo.1ðßéZbVÉú{ã\ƵÄQÁ³êܵ½B
»ÌZbVÅAôRAñ©êñÌWebŵ©ïíÈ¢AuInternational Working GroupvÌÓCÒÆàÀÛÉ櫓ƪūܵ½B


AUAÌTCÉÄÜæ¶Æ(ã)
Rcæ¶ÌPosterOÅAú{åAíÈwïÌc³ñÆ¡ls§åw̲®æ¶Æ(¶)
AUA International Research Work GroupÌRAo[ÆRcæ¶Æ²®æ¶Æ(E)
ܽAæTÜÅçtåŤCµÄ¢½AUA-JUA Exchange ScholarÌKevin@Kooæ¶iMayoNjbN@y³öjÆKevin̼eÆ[Hð²ê·éõhÈ@ïà èܵ½B
»ÌÅAKevinªàÈ¢Ag^̧wàÅUndergraduateÌn[o[håwð²ÆÅ«½±Æà èÜ·ªA³äpliYj̼eª@½Éú{Æ¢¤ð¸hµÄ¢é©´¶Üµ½B

AUA-JUA Exchange ScholarƵÄçtåŤCµ½Mayo ClinicÌKevinÌÆ°ÆÌHï
wïSÌƵÄÍAÈOæèAîbâAò¨¡Ãª¸èAèpÖAª¦½æ¤ÈóÛð¿Üµ½B
åAíÈÌò¨Ã@ɨ¯éîáàÈ̶ݪå«ÈÁ½±Æªe¿µÄ¢éÆv¢Ü·B
ܽAîbÍAAJ¯lÉAãtªèpÉW·éA¤ÒÉä¾ËéXüªÈÁ½ÊÆvíêܵ½B
êûAèÉAIªñíɦ½óÛÅ·µAäXƯ¶ðÍðµÄ¢é{Ýð¡ÝÆßÄÁ«Üµ½B
êûAåKÍf[^ðAIð͵ÄàAù¶ÌðÍÆ ÜèÏíçÈ¢óÛà éAUSCiUniversity of South CaliforniajÌèÅAMRIÌæÆTarget¶ÌaÊð·é±ÆÅAMRIæ©ç@½ÉaÊð\ª·éðͪóÛIŵ½B
u»ÝAæÅ©¦È¢StealthàÍAIůèÂ\©HvÆÌÌ¿âÉεÄAÒªAuUSCÅÍA·ÅÉVeXÌMRIªüÁÄ¢éBܾAÄp«ÅÍÈ¢ªAæîñª¦éAStealth¯èÂ\ÆÈéÆvíêévÆ̦ªóÛIŵ½B
{M©çÍAcÌO[vªAO§BSEßöÌNX^OÌf°çµ¢\ð³êĢܵ½B
OúÉÍAeLTXÅÅà¢^[iTower of AmericajÌÅãKÌo[ÅAo[{ùÝúèÆ¢¤CxgÉêÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B

cåw¬âæ¶ðSÆ·éo[ÆTower of America̸ãÉÄ
éÆu[XÅÍADa Vinci5ªóÛIŵ½B
GoÌÝÈç¸AeA[ÌdCXâgNVîñªAvãÅFÂ\ŵ½B
¡ãÌèpßöÌAIðÍÉñíÉLpÈîñÉvíêܵ½B

DavinciÌV@í@Davinci 5
2. Mt SainaiÉ¢Ä
èp©wɨ¢ÄAN`ÈÇÌíÞªñíɵµAÇACtGUN`ÍAúÉó¯È¨µÄAâÁÆÅ©w̪¨èéÈÇÌêJª èܵ½B

Mt SainaiÌåAíÈÌÅÂÌOÅ(¶)
»nÅà·®ÉᦸA豫ɩÈèêJµ½©wobW(E)
»Ìbãà èATewariæ¶ÌHood@Ìèpð4©w³¹Ä¢½¾«Üµ½B
åÉDual ConsoleÌ×ÉÀç¹Ä¢½¾ÅAèZÉ¢Äྡྷ½¾«Üµ½B
ñíÉÙ£µÜµ½ªAàuPricelessvÈo±ÆÈèܵ½B
ÁÉóÛI¾Á½ÌÍAHood@ÌèZÉ¢ÄA£CªGrade 1-4 éA@pOÌMRIAA´´xGR[ABPSMA PET©çAíZÌ\ª¦ðl»µÄA»fµÄ¢é_ŵ½B
ñíÉJÉA©ÂZ¢ÔÅèp³êé̪óÛIŵ½B
iÀÛGrade1|2Ì_o·¶CªHood@ÆÈèÜ·j
Dr. Tewari©çÍAñúÚÉ2ÔÙÇu`𢽾«Üµ½B
»ÌÅAðUðʵÄAO§BüÍÌ_oÌsðwÔ½ßÉAûÌ~VKBÜÅs«A¨@ÈÌðUªIíÁ½ãÉAO§BððU³¹ÄàçÁ½±ÆA¹æåw̳öÆAéÜÅðUµ½bÈǪóÛIŵ½B
Ъá¤A³öð¢©É¸hµÄ¢é©´¶Üµ½B
áèãtÉuO§BàÍA½ªj[N©vÈÇ¿â·éÅAðUÌÝÈç¸AÆuAQmA½l«AÉÍANwIÈbÜÅÉ¢½éñíÉ[¢¿^ɳ|³êܵ½B
ܽA»ÌßöÍArfIBeµÄAêÅà éChÌåwÌu`Égp·éÆ̱Æŵ½B
ܽAÌt Åà éîb¤ÒÌNatashaæ¶Éà¨ï¢µÜµ½B
CovidÌe¿à èA5NÔèŵ½ª³CÈlqÅAMt SainaiàÌZ~i[ÅRcÆêÉuÌ@ï𢽾«Üµ½B
³öâáèàQÁ³êAuEnjoyed your talkvÈǽ³ñÌæ¶ûɾÁÄ¢½¾«Üµ½B
Natasha³öàAºÌRcæ¶ðAêÄ«½±ÆðñíÉìÎêAÅIúÉfGÈt`XgÅHÆMt SainaiÌXqÈÇA¨yY𢽾«Üµ½B


Rcæ¶ÌuÊ^(¶ã)@uãÉX^btÌæ¶ûÆ(Eã)
Mt SainaiÌXqði^[V涩碽¾¢Ä(¶º)@i^[Væ¶ÆAbV
ÆÌÅãÌHï(Eº)
ÅãÉA¡ñÌKâÅêÔóÛÉcÁ½ÌªAÀÍAshŵ½B
AshÍAUC Berkley̨wÈð²Æ·éAêNÔAResearch FellowƵÄAMt SainaiÌåAíÈÅAI¤ÉgíèANAãwÌZ^[±Ìæ¤ÈM-CATðó¯ÄAMt SainaiÌãwÉAvC·éÆ̱Æŵ½B
ÞªAî{AäXÌ{ÝÄàð·éAúËüÈÆåAíÈÌãt¯mÌJt@ðÞªdØèA©ÂAâèÇáÈÇðÞªPick UpµÄv[µÄ¢Üµ½B
½xྡྷܷªA©êÍAãwÉ·çüÁĢȢUndergraduate̶kÅ·B
¼ÉÍAYaleåwãw²ÅAWfgüÇðNÚw·«ÈÇàT[`tF[ŢĢܵ½B
¢EIÈgbvCXeB`
[gÉüé×ÉAíªIÉwÍ·épAܽA]¿·é¤àCVÅ»f·éÌÅÍÈAlÔ«AÐð«AM«ÈÇ çäéÊ©ç½ÊIÈ]¿ðµæ¤Æ·ép¨É³|³êܵ½B
ǤèÅA¢ÄÅÍAuNÌRecommendation Letterðà礩HvªåØÈRªí©èܵ½B

¢ÌX[p[X^[ AshÆ
ÜÆß
¡ñAvµÔèÌAUAÅhðó¯éAÀÛÌMt SainaiÌÕ°ÌêðK⳹Ģ½¾¢½±ÆªñíÉå«ÈwÑÆÈèܵ½B
Dr. TewariÌJX}«ÆlÔ«ÉàGêé±ÆªÅ«Üµ½B
ܽAíZ\ªÌæ¤ÈVXe}`bNȤÊðtp·éAw¶âAWfgóâÒÌliðc¬µæ¤Æ·éÈÇlÔIȤÊðåØÉ·ép¨ð_Ô©é±ÆªÅ«Üµ½B
¡ñÌ·ÍAòs@Ìxà èAHcA¬cAèÅ·ªAçtåÍAñÂÌåvÈÛó`ðpÅ«éACOÆÌÖ«ªnwIHÉàbÜê½êɶݵܷB
T©çAØÆäp©ç¯w¶ªÜ·ªA¢EÆÌÂȪèðåØÉ·éÅA¢E©çwÑAÉA½©ð`¦Ä¢¯êÎÆv¢Üµ½B
u§íµÄ¸sµ½±ÆÍã÷µÈ¢vuOne Teamv
¡ñàAMt SanaiÌHood @̶ÝÌeÅ éATewari³öKâɧíµÄæ©Á½ÆS©ç´¶Üµ½B
áèÌRcæ¶ÉÆÁÄàóÛIÈCxgÈÁ½ÆmMµÜ·B
±ÌñÂ̾tðåØÉA¡ãààñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B
êTÔsÝÌÔAÕ°ðçÁÄ¢½¾¢½cèÌ`[Ìæ¶ûÆCO{ÝÆÌ豫ðsÁÄ¢¢½¾¢½éÌûXÉA±ÌêðØèÄ[äçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{ Mê
2024JUA|AUA Exchange Scholarship report, Dr. Kevin Koo from Mayo Clinic, USA
I was honored to visit the Department of Urology at Chiba University as an American Urological Association/Japanese Urological Association Academic Exchange Scholar, under the generous leadership and hospitality of Professor Tomohiko Ichikawa, MD, PhD. During my three-week observership, I had the privilege of joining the outstanding urology faculty, staff, and trainees to learn about the contemporary practice of urology in Japan and the flourishing academic mission of Chiba University.
The visit encompassed a diverse range of activities, including observing surgical procedures in the operating room, presenting a lecture to the department, and engaging in productive discussions with faculty and residents.
One of the highlights of my experience was observing innovative robotic surgery.
Experiencing the precision and efficiency of minimally invasive robotic radical prostatectomy, partial nephrectomy, adrenalectomy, and cystectomy left a profound impression.
As I learned from skilled Chiba University urologists manipulating the surgical robot with finesse, I gained valuable insights into advanced techniques for treating urological cancers.
The integration of technology and surgical expertise was inspiring.
I also appreciated the team-based approach to perioperative care.
Observing the coordinated efforts of surgeons, anesthesiologists, nurses, and operating room staff gave me powerful ideas about how to optimize procedural efficiency and patient safety.

Interacting with Chiba University residents and medical students provided a comprehensive perspective on medical education in Japan.
I thoroughly enjoyed participating in case discussions, attending rounds, and exchanging ideas about career development with these enthusiastic learners.
I was particularly impressed by the residents' dedication to advancing urological care through clinical innovation and research.
From these interactions, I was delighted not only to share my knowledge about urology training in the U.S. but also to learn from Chiba University trainees' experiences and perspectives.

I would like to express my sincere gratitude and appreciation to my hosts, Professor Ichikawa, Dr. Shinichi Sakamoto, and Dr. Yasutaka Yamada, for this enriching opportunity.
Their kindness and generosity helped to make this once-in-a-lifetime experience successful, productive, and educational.
The collaboration between our departments has transcended borders, fostering a stronger bond between our faculty and medical schools.
As we exchanged best practices, cultural perspectives, and research insights, I realized that urology truly has no physical or geographic boundaries. Finally, I would like to recognize the longstanding partnership between the American Urological Association and the Japanese Urological Association, which continues to be strengthened by this unique program.
The experience of serving as an AUA/JUA Academic Exchange Scholar at Chiba University has reaffirmed my commitment to international collaboration and the pursuit of excellence in urology.

Kevin Koo, MD, MPH, MPhil
Associate Professor of Urology
Mayo Clinic
Rochester, Minnesota, USA
çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVj2023
2021N7AÈÌHome pageÉg10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVjhÆ¢¤^CgÅAÂlIÈ©ððñeµÜµ½B
»Ì±Æð¥Ü¦ÄANÌ2023N12»Ýɨ¢ÄÌÊß_ðUèÔÁÄݽ¢Æv¢Ü·B
2021N©ç2023NÌÏ»H
±Ì2N¼ÌúÔÉ Á½CxgÍARiARemote WorkAChat GPTÈÇAIÌÀp»ÈÇB
2021NÍAViCs¾Á½AcfDNAÈÇÌLiquid BiopsyàA2023NÉÍAÀÛÌÕ°Ép³êĢܷB
YÆEðÝéÆA2019NVRo[ÅÁÄ¢½eXÈÇÌdC©®ÔÍ{MÅà¦éA2023NÌVRo[ÅÍA®S©®^]Ì^NV[ªÀ³êĢܷB
pf~bNÌe¿à èAZoomª®SÉÀ·éÈ©AàÌÝÈç¸ACOÆÌR{às¢â·Èèܵ½B
[gïc©çÌAWAãÃÉ¢Ä
ÈÅÍA2021N`iChinese University of Hong KongjA2022N}[VAiMalaya UniversityjA2023NVK|[iNational University of SingaporejÆ[gÅÌÛïcðs¢Üµ½B
»Ìà èA¡NÍANUSÆäpðKâµÜµ½B
äpÅÍAwïåÃÒ̺³ñÌ¥®ÉàQÁ·é@ïª èܵ½B

Singapore DUKE|NUSÌw·Prof. Thomas Coffmani¶©çñÔÚjÆiE[@¯wÌYæ¶j

Singapore ªñZ^[iNCCNjÌ·Å èA¯wÌYæ¶Ì{X@Prof. Teh Bin Tean
iÈÌqõ³öÉÈÁÄ¢½¾«Üµ½j

VK|[åwåAíÈÌEdmund Chiong³öÆãÇé³ñ½¿Æ

äpiYjAPPSÆ¢¤ÛwïÅ
i¶©ç@â{AäpÌäïiTsaijæ¶Aäæ¶Aäæ¶j

Asian Pacific Prostate Society iAPPS)@2023ðåóê½Po Hui Chiang³öi`OåwåAíÈj̺³ñi³ñjÌ¥®ÉÈÌäæ¶i¶[jÆQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½iY@äpjB
E©çñÔÚÌ·³ñÍA2024N5©çÈÉÄÕ°¤C\èÅ·B
»ÌÅå«´¶½±ÆÍA¢äXÍAKChCàp¶Gà¢Ä𩪿ŷªA·ãàA£IÉàAAWAÌÅ é_ŵ½B
çâÌiàÄ¢éµA éÓ¡Avl·çÄ¢éªà èÜ·B
¢EIÈlû̪zðÝÄàA2020NÌ¢Elûª78lÌAAWAÍ46lƼªÈãðèßA[bpi7ljAkÄi3ljðy©É½®AXÉÁµÄ¢Ü·B
ܽAú{ÍAIntuitiveÌ{bgª500äÈãüÁÄ¢éAiñ20äjA}[VAi5äjAVK|[i5äjÆärµÄàA³|IÈÇáðÂXÌpÒªo±µÄ¢Ü·B
¡ãÍAZpÍ éãtðãÇ©çh·éãªéÌÅÍÆv¢Ü·B@
ܽAAWAðÝéÆA¬fêî{Å èA{bgð󯽢³ÒÍA©ïŨæ»300~x¥¤A100~Í·ãtÉüédgÝÈÇà èܵ½B
ÊAãtÌûüÍAAJf~AÅà6000©çê~ð´¦éûà¢Üµ½B
êûAòÜÉÖµÄÍAQmòâ¿ÈVKòÜÍÀxzÌÝèª èA»êÈãÍA©ïš÷éAÐïÛ¯¿Ìã¸ðh®HvÈǪeÅ èܵ½B
{MÍA¶ÛìANîÈÇÉÖWÈA³§ÀÉÝȽÉ{bgèpðó¯çêéµAIOhbNâQmnò·çANZXªÂ\Å·B
à¿ëñAzIÅ·ªAq»Aî»ÈÇɺ¢AÐïÛ¯¿ÌSÈÇÆ\ZÉÀEª éA@K§ÌÏvªÒ½êéªà é©Ævíêܵ½B
åAíÈÌ[VbgH
åAíÈðÜß½¢ÍǤŵå¤H
àt{Ìz[y[WðÝéÆ[VbgÚWªfÚ³êĢܷB

àt{z[y[W©çøp@https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html
[VbgªÚw·ÐïÌêÔºÉȺ̶ͪ èÜ·B
ylÌ\Íg£ZpÆAI{bgZp̲aÌæê½pÉæèAÊMxÉàÎÅ«élXÈT[rXiFóÔÅÌìÆjªno³êéBz
AI{bgZp̲aÌÆê½pÍAÈÅs¤{bgèpæÌAIF¯VXeiªñZ^[a@Æ̤¯vWFNgjÉàʶéà̪ èÜ·B
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2023/0619/index.html
©ÂÄA1960NãAX^tH[hÅᢤҪ©®^]̤ðs¢Aüèªu¢à è¦È¢vÆnÉ·éA2023NÉÍAÀÛɬðA©®^]Ì^NV[ªÁĢܷB
https://jidounten-lab.com/u_32604
èpàuAI©®»ÈÇA³¾vÆæúÌÛwïÅÀ·ÉÎíêéAAIÌi»ªÁ¬·éA൩µ½ç2030N²ëÉÍA·ÅÉÀ³êÄ¢éÌ©àµêܹñB@
AJf~AÌ¢H
ÅãÉAèÉAJf~AÌ¢ðl¦½¢Æv¢Ü·B
±±NÌå«È¬êÍA©ç̪¸éAƧs@l»©çÌ©§µ½^cÅ·B
P¼üÉ¢¤ÆAåwƵÄà(^cïE¤ï)ðmÛ·é±ÆªK{ÆÈèÜ·B
IMOAJETROÈÇAx`[NÆÌT|[gªåwàÅ·çÝu³êéA¶ÈÈÌÝÈç¸AAMEDðÜß½oÏYÆÈÆàNµ½vWFNgðN±µÄ¢ãÉüÁÄ¢éÆv¢Ü·B

ܽAåwàÅàAYwAgµ½AvJAÂÊ»ãÃATuXNvVT[rXÈÇànÜéæ¤Év¢Ü·B
±êÜÅAåwÆÍA¤ðs¢_¶\ªÛèŵ½çA¡ãÍA³çÉãÌAÁæ¾AYÆ»ÈÇÌÀªßçêéãÉÈéÆv¢Ü·B
x`[NÆ·éãw¶àFßéAåwÌãÇ©ÌàúXÌãÃÌÝÈç¸AJpj[iÔjƵÄANÆðÜß½AÐïÀðÀ»·éãÉüè éæ¤Év¢Ü·B
Z¢ãAAt@¢ãªÐïÉoê·éAºa¢ãÌäXàAíÉAuù¬TOðó·ECÆVµ¢TOðó¯üêé]Tvª³êÄ¢éÌÅÍȢŵ天H
uOne Teamv@u§íµÄ¸sµ½±ÆÍã÷µÈ¢v
±Ìñ¾ðe[}É2024NààñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{ Mê
çtåAíZ~i[@Chiba Urology Seminar
Fl±ñÎñÍAåw@4NAãÈåwãw¤ÉoüÌcºM¾Å·B
2023Nàc·Æ±ë Æí¸©Å·ªA¢©ª¨ß²µÅµå¤©B
1222úÌ~Ìé·ÉA±ÌLð¢Ä¢éÌཀྵÌöÊŵ天B
gúZ«±Æi«íÜjéhÆ¢¤Ó¡Ì~ÍÃͶ½ÌIíèð\µAĶÌƨ¦çêÄ¢½»¤Å·B
úÌüèªÅà¢ÌÍ~Ìñ¼OAúÌoªÅàx¢úÍ~Ìñ¼ãÅ èA»ÌÔ_É ½èAêNÅÅà¾zªoÄ¢éÔªZ¢úª~ɽèÜ·B
®¨àØ஫ðößA¾zÆn
ÌGlM[ª¢EÉ¿ÄéÌð¶ÁÆÒ¿Ü·B
NX}XÉYNïÆQ½¾µ¢GßÅ·ªAí½µ½¿lÔàµÁ©èÆxßðµÄAGlM[É¿ìêÄ¢tÉü¯Ä{¶µÄÜ¢èܵå¤B
³ÄAé1129úAçtåwå@LpXãw{ÙÉÄ¡NÅãÌçtåAíZ~i[ªJóêܵ½B
2023N828úÌû¢ ˶æ¶ÌLÅàGêçêĢܷªA±ÌZ~i[ÍAÉ1ñÌåw@¶âåwαÌX^btÆ̤ºïciÌïcjÌãÉJóêéÙÆígbvi[ÉæéuïÅ·B
åÉy³öÌâ{æ¶Ì¨mè¢ÌÈ©©çAíêíêåAíÈãðCXpCAµÄ¢½¾¯éÙÆíÌûXÉuð¨è¢µÄ¢Ü·B
MÒÅ éí½µàÙÆíÌûXÆÌqªèÍú ©çdµÄ¢éÌÅ·ªA³·ªâ{æ¶A2023N10ÉJtHjAÝZÌ`àÌrbOEF[uT[t@[ìGjY³ñðuɵҵ½ÌÉÍxÌð²©êܵ½B
í½µÍ`Éo£Å èAze©çÌICQÁÉÈÁ½ÌÅ·ªAú{ðw¢Aåa°ð©¯Äågɧ޻̿CìêéuðÔßÅ·¢ÄA®O꯹ðŽê½lqŵ½B
í½µ©gàÙÌnÅú{Év¢ðy¹Èªçuð·«AgÌø«÷Üév¢Åµ½µA²É¶«A½ðRâ·A»ñÈj̶«lÉhÓðø«Üµ½B
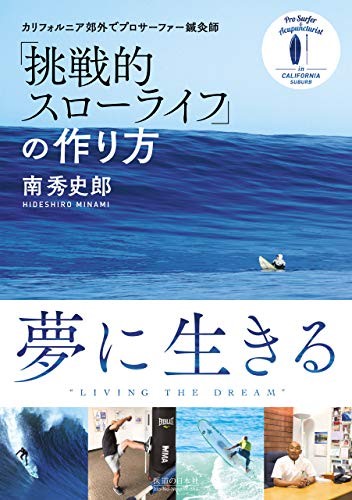
ìGjY³ñÌ
1129úÌuÒÍAA tech Ventures / A Biz Schoolã\Ì|MFæ¶B
|æ¶ÍA²©gÌïÐÅVCix`[Ls^jÆAAhoCU[ÆÉ]·éTçAçtåwHwCmR[XFx`[_ñíÎutƵÄåwųÚðÆçêĨèAåw¶ÌAgvi[Vbv³çÉàÖSª¢ûÅ·B
uàeÍAãÃEwXPAÆSaaS (Software as a Service)AܽãÃɨ¯éCmx[VÉ¢ÄB
¡{Ìæ¤ÉÀñ¾¾tÌÓ¡ª³ÁÏ誩çȢƢ¤»±Ì ȽAºÐçtåwåw@ÉüwµÄA|æ¶ÌöÆðæèܵå¤iÎjB
ÀÍí½µÍHwCmR[XÉÝè³êÄ¢é|æ¶ÌöÆðåÉICÅóuµÄ¢Üµ½B
»Ì²©çãÃÆEÌvVINÆÆÌûXÉàïí¹Ä¢½¾ÈÇåϽðwιĢ½¾¢Ä¨èÜ·B
¨àƳÉdâ¶ðµÄ¢éû͢ȢÆv¢Ü·B
Ðï¶ðÁÄ¢éÈãA¨àª¢ÔÅÇÌæ¤ÉÜíÁÄ¢éÌ©ðmèA¨àð¡ûɯĩªª¬µ°½¢±ÆðÇy·éÌÍf°çµ¢±ÆÅ·B
ÊÉNÆiJÆjµÄ¨àðÒ®±ÆͽçÁÊȱÆÅÍÈ¢¯êÇàA¿åÁƵ½RcÆo±AECÆEϪKvÅ éÆ¢¤±Æð|涩糦Ģ½¾¢½ÆvÁĢܷB
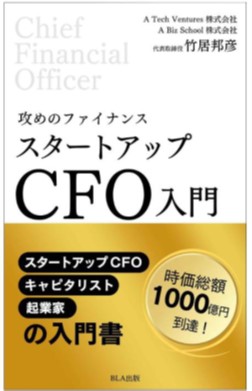
|MF³ñÌ
ãtƵÄåw@ÉüéÆAî{IÉÍåwa@ÈÇÅÕ°ðè`¢ÂÂAz®æ̳ºÅw±³¯ÌàÆɤðs¢Ü·B
í¦ÄA²ÆÉÖíéãwnÌöÆÉoȵA²ÆPÊðC¾A ÆͤðÜÆß½m_¶ðdã°Ä3`4NŲƷéAÆ¢¤ÌªêÊIÅ·B
í½µÍñíÉnR«ÈÌÅA¹Á©¢öÆ¿ð¥¤ÈçAãwÈOÌöÆà«É¶«»¤ÈàÌÍ·¢Ä¨±¤AÆ¢¤±ÆÅRiÐɨ¢ÄIC¹pÉÈÁ½»¡[¢¼wÌöÆðCo^µA¤ÌÔÔÉICÅ®uµÄ¢Üµ½B
FlÌÈ©ÉÍåw@ÖÌiwðÀÁÄ¢éûà¢é©àµêܹñB
åw@ÉüéÓ`ÍA½¾ãwmðæ¾µÄÈñÆÈLAÉðt¯é¾¯ÅÈA¢Á½ñÕ°ð£êÄ«ÌãtƵÄÌÝèûð©ªÈèÉÍõÅ«é_É éæ¤É´¶Ä¢Ü·B
±ê©çÍãtA»µÄãwEãÃÌÝèû©Ìàå«ÏíÁÄ¢«Ü·B
öIàÅ^c³êéÛ¯fÃðSƵ½ãÃàÀEð}¦A¯FÛ¯ðobNOEhɵ½Û¯ãÃVXe©Ìªå«È]·ðçêé©àµêܹñB
êÊIÈαãÌ^ÍÜ·Ü·ºªéûü«ÆÈèAªmÛ·é¤\ZàíçêÄÜ·Ü·£ªµµÈèÜ·B
êûÅAIÌBÉæè¤JÌXs[hÍ¢EÅÁ¬xIÉ㸵AîñÌEÊM̬xàIÉãªÁÄ¢«Ü·B
¤ÌÝÈç¸AÀհɨ¯éffâ¡Ãɨ¢ÄàAIªüè±ñÅ«Ü·B
ãÃÍa@àÌÝÅ{³êéàÌÅÍÈAa@OÅ{³êéãÃÌdv«ªÇñÇñµÄ¢«Ü·B
ãt@ÉççêÄ«½ãtÌÁ Ì¿l͵AÙÆíÌÍð¤ÜØèçêÈ¢ãtÍêJ·éŵå¤B
ÂXÌãtÆ©ÌzâACfAÆAAIÆqg𮩵Ļêðï»»·é\ͪÅàdv³êA®·éa@â¤@Ö̼OÅÍÈAÂXÌÀÑÆ\ͪ]¿³êÄt@i³ÒâoÒjjªÂãÉÈéÆl¦çêÜ·B
â{涪åÉåw@¶Ì½ßÉJõľ³éçtåAíZ~i[ÍA±ê©çÜ·Ü·½l»µÄ¢ãtÌÝèûð©ªÈèÉÍõ·éqgÉÈé±ÆÍÔá¢ÈAåÏMdÈ@ïÅ éƴӵĢܷB
K¹ÉÈéAÆ¢¤l¶ÌÅåÌS[ÌÈ©ÅAÇñÈãtƵÄlÞÌNÉñ^µÄ¢Ì©B
}¬ÉÏíèä±ÌãÉAêx§¿~ÜÁÄãwEãÃÆ¢¤àÌðNwµÄÝÄࢢ̩àµêܹñB
í½µ©gªåw@ÉüÁÄæ©Á½±ÆÍAãwâãÃÌWÆ¢¤àÌðà¤êx©Âß¼µA»¡ÌÎÛðåAíÈâqgÉiÁÄ¢é±Æ©Ìªà¤ÜÌȢƴ¶çêéæ¤ÉÈÁ½±ÆÅ·B
®¨âA¨ÈÇ çä鶨íÉ»¡ðL°é±ÆÅlÞÌNÉñ^·é»Ûð©Å«éÆl¦A»¡ÌÎÛð®A¨ÉÜÅL°ÄsöëðµÄ¢Ü·B
åAíÈwAãwA»ÌæÌ¢EÖB
çtÌãÃAú{ÌãÃA»ÌæÌ¢EÖB
±ê©ç±Ì¹ÖiÜêéF³ñAçtåwåAíÈÅêɪñÎÁÄÜ¢èܵå¤III
ÇL
ñAN¾¯ÌçtåAíZ~i[ÌuÒÍA³TbJ[ú{ã\H¶¼IèI|æ¶ÌqªèÅÀ»µÜµ½B
yµÝÅ·ËI

|æ¶ÌZ~i[Ì ÆÌêB¿^àåÏ·èãªèܵ½B

|æ¶ÆN[YhÈuãÌÈB
|æ¶ÌöÆð»Ýis`Åó¯Ä¢éãw»ðw¶à«Äêܵ½B
¶ÓFcº M¾
æ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï
2023NxüÇÌ|R°Æ\µÜ·B»ÝÍçtåwãw®a@ÅαµÄ¨èÜ·B
eÅ·ÌÅÈPÉ©ÈÐîð³¹Ä¾³¢B
Íú{ãÈåwÅåwãAú¤Cããðß²µAãú¤Cãæèn³ÌçtÉßë¤ÆAçtåwãÇÉüç¹Ä¢½¾«Üµ½B
»ÝåAíÈ1NÚƵÄwÑ̽¢úXðß²³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
NæèØgÉÍÜèA¡ÍJ[vZÆØ÷ð¯é±Æɶ«ª¢ð´¶Ä¢Ü·B
ܾܾ¢nÅLÑãÌ ég̾Æv¢Ü·ÌÅA}b`Èæ¶ûAºÐ²w±ÌÙǨè¢vµÜ·B

bhv_Eð·é
³ÄA¡ñÍ2023N1125úÉsíê½æ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
ïêÍOñƯlAçtåw®a@ÌK[lbgz[Åsíêܵ½B
áNÊèAçtåÖAa@ðͶßAçt§à̽Ì{Ý©ç²QÁ¢½¾«Üµ½B

áè©çxeÌæ¶ÜÅA21àÌè\ª èAÆÄàhÉÈèܵ½B
ïêÍ¿^ªòÑð¢AÆÄà·èãªÁĨèܵ½B
à\³¹Ä¢½¾«Üµ½ªil¶Ìö®ÈêÅÌ\ŵ½cjAܾܾçÊ_ª½AܽñÉÂÈ°Ä¢«½¢Æv¢Ü·B
¬xeÉÍAæ¶ûÌð¬à·ñÅ èAFlyµñÅ¢½¾¯Ä¢éæ¤Åµ½B
ܽÁÊuƵÄA§§ãÈåw̬Ëhæ¶É²uµÄ¢½¾«Üµ½B
ÆÄ໡[¢¨bÅAÅãÉÍÖÌM¢z¢ðêÁľ³¢Üµ½B
XgÌNxÌú{rA@\wïÌv[VrfIÅÍ¢ڪªMÈÁĵܢܵ½B

ܽ¡ñÌnûïÌxXgv[^[ÜÍAçtåw®a@ÌìKêY涪óܳêܵ½B
ú ©çìæ¶Éͨ¢bÉÈÁĨèÜ·ªAvX¸hÌOª[Üèܵ½B
¨ßÅƤ²´¢Ü·B

sì³ö(E)Æìæ¶(¶)
ÅãÉÈèÜ·ªA¡ñÍFl̲¦ÍÌàÆAØèÈïðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
é³ñûàAïêÌ^cש¢Æ±ëÜÅ èªÆ¤²´¢Üµ½B

é³ñûBÎçªfGÅ·B
ÈãAæ4ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÌñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B
Fl̲ÉͨCð¯ÄAÇ¢Nð¨ß²µ¾³¢B
¶ÓFãú¤Cã@|R °
Next Generation Urologist Seminar
ßܵıñÉ¿ÍI
^NVçtåwåAíÈãú¤CãÌRºÆ\µÜ·B
±Ìx920úÉJóêܵ½Next Generation Urologist SeminariÈ~NGUSjÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŻ̲ñÆÈèÜ·I

Æ»ÌOɱÌR[i[Å©ÈÐîð¨ÚÉ©©ç¹é̪ÊáÌæ¤Å·ÌÅáɽªí¸^NVßàâç¹Ä¢½¾«½¶¶Ü·B
^NVRºÍ²zɶðó¯sàÌð²ÆµAZpêÉïª Á½½ßnûÍmÖÆhÉ6NÔs«Üµ½B
m§Í©RL©Å»Ì§¯«Íú{ðÆTJið±æȤ·éfGÈynŵ½B
ÍejXÉ®µAðÆejXÌúXŵ½B
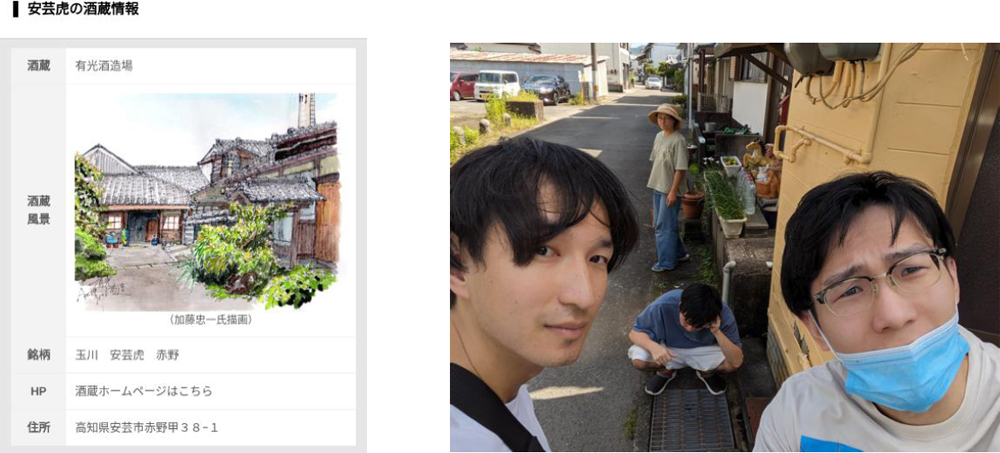
¶j±¿ç^NVêµÌð ÉÈèÜ·B
Ej¯ú̪æ¶ÆiEªMÒj
ÈñÆÈsàÅú¤CðI¦A¢´Ç±ÌåAíÈÉ®µæ¤©ÈƽÌåwð©wµ½Çè
¢½çtåwAAAII
µÍCÌdzÉä©êACªt¢½çüǵĨèܵ½I
ã÷Í èܹñII
úyµß²µÄ¨èÜ·B
ÆÜ ©ÈÐîÍ±Ì ½èÅIíèɵÄNGUSÉ¢ÄêÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·I
NGUSͻ̼ÌÊèCPCPÈáèi+¿jÉæéÏÉIÈ×ïHuïÉÈÁĨèܵÄNGUSÌCCƱëƵܵÄÍcJVC¾tųçÁÆu·éÌÅÍÈáèü¯Éî{©çµÁ©è³¦Ä¢½¾¢Ä¢éƱë¾Æv¢Ü·B

À·ÌRcæ¶iоèjAiïÌáäæ¶ijAÒÅ¢çÁµáÁ½Xæ¶iݬjÅ·B
¨OûÍçtåw̯úÆ̱ÆAAAIIçtåwÆbãåð¤É¡øµÄ¢Ü·III

ÏÉIÈc_ªJèL°çêĨèÜ·II

iïÌáä涩çM¢ÜÈ´µð¢½¾«Üµ½II
^NVÌæ¤ÈáèÌ]¡XÉà·é·éÆüÁÄéí©èâ·³iµÄiÌuïÍ·é·éüÁıȢƢ¤í¯ÅͲ´¢Ü¹ñªjÍÈ©È©É©gÌ»¡ðø«AÆÄàLÓ`ÈïÆÈèܵ½B
ïÌãÍáèÌã©çºÜÅQÁ·éîñð·ïª èA¡ãÌLAvâúXÌfÃÌ¿åÁƵ½MiNÌ£ê½ãiÉÍ·«Ãç¢HHjÈñ©ðÔÁ¿á¯Å·¯éMdÈõàJóêñíÉ[Àµ½êúÆÈèܵ½B
¡ãÌçtåwð¡ø·éDGÈæ¶ûÆÚ·é@ïÅ è`x[VAbvµ[Àµ½ïÅ èܵ½B
ñÌJÃàyµÝɵĢܷIIIII

ÅãÍSõÅçtå|[YðyeahhaaIIII
¶ÓFåAíÈãú¤Cã@Rº ½
2023/9/19 Chiba Tokyo Scrum Meeting with Singapore
½¬23N² Rc N²Æ\µÜ·B
3NÔÌ{Xg¯w©çAµA{N4æèçtåwãw®a@ÉÄα³¹Ä¸¢Ä¨èÜ·B
2023N919ú(Î)ɬze~}[ÉÄ·èsíêܵ½AChiba Tokyo Scrum Meeting with Singapore ÉQÁvµÜµ½ÌÅA±±Éñ³¹Ä¸«Ü·B

{¤ïÍAWAÉL¢lbg[NðÂâ{涪åóêAêðNÌ`EðNÌ}[VAɱ¢ÄJóêܵ½B
¡NÌÁ¥ÆµÄÍAú{ÌçÆྦéåwÉQÁµÄ¸«AAWASÌÌ©ÍðAܳÉScrumðgñÅAßÄ¢«½¢Æ¢¤ï|ªäÀ¢Üµ½B
ܽAVK|[ƾ¦Î»ÝYæ¶(H22N²)ª¯wÆ¢¤à èAäXçtååAíÈƵÄàåÏéõÝ[¢}b`AbvÆÈèܵ½B
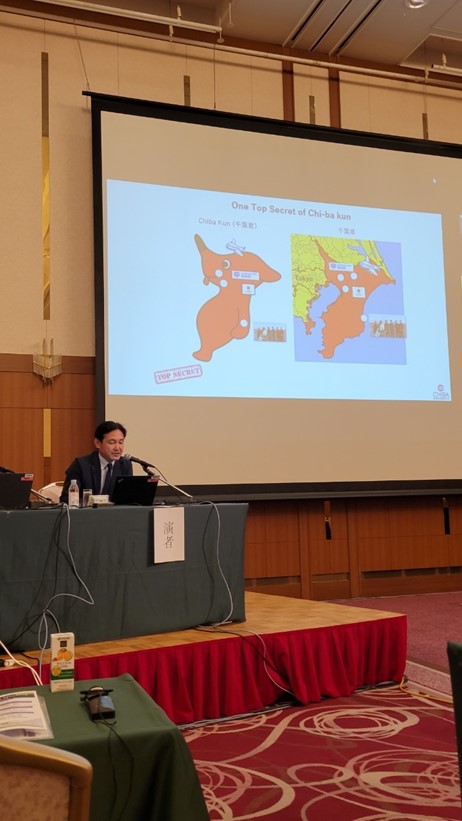
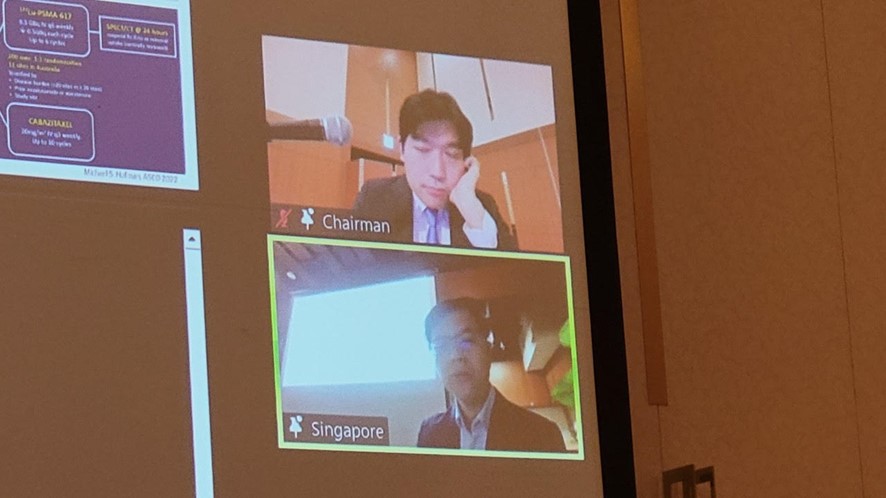
uïÍ3p[g©ç\¬³êAܸéåw ìæ¶À·Ì³Aâ{æ¶EDr. EdmundÉæéisO§Bàɨ¯éò¨¡Ã©çX^[gµÜµ½B
¢ÂàÌ@A¬êéæ¤ÈpêÅu·éâ{æ¶B
`[oNÌXChÅuïªX^[gµÜµ½B
Dr. Edmund©çÍ»ÝÌisO§Bàɨ¯é¡ÃV[NGXÉÖíéÕ°±ðÔ
·éuð¸«Üµ½B
»ÌãÌdiscussion partÉqªéåÏÜÆÜÁ½àe¾Á½Æv¢Ü·B

æ2ƵÄA¡ºæ¶À·Ì³Aú{EVK|[ðã\·éexpert surgeonÅ ébåw OØæ¶EDr. Wuɲu¸«Üµ½B
ÁÉäNã÷z£fÉÖ·éªðÁɲµÄbµÄ¸«A{bgèpðܳÉn߽ƵÄàåÏ×ÉÈèܵ½B

Panel DiscussionÅÍåw Rcæ¶Eéåw¿ÎãÃZ^[ áäæ¶Eªú{TChA»µÄICÅVK|[TChɪ©êAåÉmHSPCÌ¡ÃíªÉ¢Ģ_µÜµ½B
PointƵÄÍ@PSA responseÌdv«AòÜV[NGXÌÛÌ»fÞ¿BTriplet¡ÃÌKÇáÉÖµÄAAWA¡fIÈc_ªo½ÆvÁĢܷB
Ü_pêÅÌdiscussionŵ½ªAÈǪñlͬwZãÌwÇðÄÅß²µ½¶ÌAqÅ èAÍr©ÈèÌââ¾ð©¢Ä¨èܵ½B

ÅãÉ»nQÁÌF³ñÅWÊ^BICÅà½QÁ¸«Üµ½I

uïã̧eï@ì̹ÅÌêR}BçtååAíÈ|[YàI
èpÉÖ·ébèâvCx[gÉéÜÅAÔá¢È©ªÜèܵ½B
¢ÄɯÊ椳ʩ笤àåÅ·ªAAWAÅ©ðßÄ¢àñíÉåØÈÌÅÍÈ¢©Æ´¶Üµ½B
ܽNÈ~à¥ñ±¯Ä¢«½¢Æv¢Ü·B
QÁµÄ¸¢½æ¶ûALï¤äÀ¢Üµ½B
¶ÓFçtåwãw®a@ ³@Rc N²
¤ºïc
µµ¢³ª±«Ü·ªAFl¢©ª¨ß²µÅµå¤©B
üÇ7NÚAåw@3N¶ÌyG TWÆ\µÜ·B
2015Nçtåw²ÆAÝwÍ
jÉ®µÄ¨èܵ½B
²ãÍsà̧ÛãäZ^[Åú¤Cðs¢AçtåwåAíÈÖüdz¹Ä¸«Üµ½B
D«È¾tͨ²ÑÆé²ÑA]ÉÍ·sðæµÄ¢Ü·B
ܽAÅßÍCOVID-19Ìe¿ªÈÈÁÄ«½±Æà èACuâRT[gÉæo©¯Ä¢Ü·B

}EiPAÎRR¸ÅånÆÌÍð¶ªÉ´¶é
åAíÈÊMÉÍe{ÝÅÌyµ¢¶âwïE¯w̲ñÆ¢Á½ñíÉ»¡[¢Lª½³ñ èÜ·ªA¡ñ͵ÚüðϦ½Lðñ¹ÄÝÜ·B
ßNüǵ½æ¶ûÖ̲ÐîàËÄßµâåw@ÅÌ ê±êÉ¢ĨbªÅ«êÎÆvÁĨèÜ·B
ÍüÇãåwa@Açt§ªñZ^[Åãú¤CÌ×ð³¹Ä¢½¾«AüÇ5NÚÅçtåwåw@ÖüwµÜµ½B
p¸©µÈªçAüwÌ®@Íuåw@ÍÆè ¦¸svÆA·¢àÌɪ©êé¸_ŵ½B
±Ì¤ªµ½¢A±¤¢Á½ÌæÉ»¡ª éÆ¢Á½±ÆÍ ÜèÈAåw@ªÇÌæ¤Èê©Æ¢Á½C[WàÁĢȩÁ½Å·B
Ç¿ç©Æ¢¤ÆOAaƱAèpÌÕ°¶ªñíÉyµAúa@És̪yµÝŵ½B
´ïÖÆæíêéåw@üw±ð©ËjµAåAíÈ®ÌàÆòw³ºÖhµÄ¸«¤ðsÁĢܷB
ܽANTTR~
jP[VYÆ̤¯¤àißĢܷB
a@ÅÍo±Å«È¢æ¤ÈlÔÖWÌ\zâl¦ṳ̂LªÅ«A[Àµ½¶ðÁĢܷB
Á¦ÄÖAa@ÅÌfÃαâçt§ºa@Å̼AհƱÉàgíç¹Ä¸«AÈé×´oªÝçÈ¢æ¤É²z¶µÄàçÁĢܷB
ÀÍAÉ1ñåw@¶âåwαÌX^btÌæ¶ûƤºïciÌïcjÈéà̪§©ÉJóêĢܷB
±±ÅÍeX̤àeÌiÂ\ÈÀèÌj¤LAȤïÌgpóµâgrÌmFAÌÌæ⤻ÌàÌÌÏR¸â¯ÓÉÖ·é`FbNðsÁĢܷB
©g±Ìæ¤È±Æªé§ ÉsíêÄ¢éÆÍSmèܹñŵ½B
êQÁÒÅͲ´¢Ü·ªAãÇ^cÆ¢¤àÌÌêpð_Ô©Ä¢éCªÉÈÁĢܷB
ܽïcͬÉæÁ½web¯JÃû®ðÌðµÄ¨èAåwa@OŤðißÄ¢çÁµáéæ¶ûÉà²QÁ¢½¾¢Ä¢Ü·B


XæXƵ½c_ððí·³öÆåAíÈ㽿
»ÌïcÆA±µAÅßÍeÌæÌgbvi[ÌûXɲuðµÄ¸±Æà èÜ·B
IT/Ap/|\v_NVÌNÆÆÅ éìèзɲu𢽾«Üµ½B
NÆANƵ½ãÌïÐ̶±E¬·AgDÌgbvÆÈèl𮩷E笷é±ÆÌ¢ï³âåϳðmé±ÆªÅ«Üµ½B
¯É»¤¢Á½o±ðµÈ¯êξé±ÆÌÅ«È¢¬÷̱⬷೦Ģ½¾«Üµ½B
²uãÍêÈðݯĢ½¾«AXÉ[¢¨bðyµf¦Üµ½B
A]Ìá·µªâ¦é±ÆÈA·²P¢Ä©¦Üµ½B

nTÅC³ÈìèзÆA²uðq®·éåAíÈ㽿
ܽAÊúÉͳ©úV·LÒ¡äkxÇ·A»Ýt[W[iXgÅ èìÆ嶻åwÐïw³öÌìæ¶É²uð¸«Üµ½B
ú{ɨ¯éäpW[iYÌæêlÒÅ èAú{¾¯ÅÈEäpÅàìÆƵĮ³êÄ¢éûÅ·B
»ÝÌEäpªø¦éâèðñíɽÕÅÈɲ³¦¸«AäXÌ¿âÉàtNɦĢ½¾«Üµ½B
COÌå«ÈâèÅ·ªäÖ¹¸ÅÍÏܳêÈ¢AÞµëÂ\ÈÍÍÅÒÓ¯ðÁÄâèðl¦é±ÆªKv¾ÈÆÉ´µÜµ½B
ܽAú{ðã\·éæ¤ÈûÆÖíé±ÆªÅ«Aå«hðó¯Üµ½B


²u¸¢½ìæ¶ÆñíÉ´Áðó¯½åAíÈ㽿
úÍOOåwâHcåwÌæ¶ûà²QÁ¸«Üµ½iIj
Ç¿ç̲uàåwÈçÅÍAТÄÍçtåwåAíȳºÈçÅÍÌõŷB
µ©àåAíÈÆÍê©SÖWªÈ¢ªìÅ·B
µ©µA±±É̪ éÆv¢Ü·B
SÖWÌÈ¢2ÂÌṲ̂Ê_ð©Â¯é±ÆÅVµ³ª¶Ü껤ÅÍȢŵ天B
±Ìæ¤ÉAåw@ÆÍãwðCß龯ÅÈAãÇÆ¢¤àÌÌðâSÙÈéªì̱Æðmé±ÆªÅ«éê¾Æv¢Ü·B
¼Ú³Ò³ñÉÖíéªÅÍÈ¢©àµêܹñªA³Ò³ñÉÖí驪ÉÆÁÄÍ嫬·Å«éêÅ·B
êUãÌFlÍåw@¶Æ·¢Äu½ðâÁÄ¢é©C}C`í©çÈ¢A½ÜÉaâùÝïÉov·éWcvÆC[W·é©àµêܹñB
ÀÛÍuaƱà½ÜÉÅ«ÄAùÝïàåD«ÅA½Åàâè½¢±ÆªÅ«éWcvÅ·B
êxüwµA̱µÄÝÄÍ¢©ªÅµå¤©i2ñÚÌüwÍî{IÉ èܹñÌÅA µ©ç¸jB
ñð·µÄ¨Ò¿µÄ¨èÜ·I
¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ@û¢ ˶iyG TWj
æ48ñ@çtåwåAíȯåïwpWï(2023N729ú)
ßܵÄA2022NxÉüÇðvµÜµ½ãú¤CãÌ¡´Æ\µÜ·B
eÆ¢¤±ÆÅè^ÊèHÈPÈ©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B
¶Üêàç¿àçt§ØXÃsÅAogåwÍk¢åwÅ·B
§a@@\çtãÃZ^[Åú¤C2NEãú¤C1Nð¾ÄA»ÝÍçtåwãw®a@ÉÄαµo±ðÏܹĢ½¾¢Ä¨èÜ·B
ï¡Í
ZSÊÅ·B
¬EwÅì
AZÍd®ejXAܽåwÅÍStÆlXÈX|[cðo±µÄ«Üµ½B
ÅßÅÍåAíÈâ¤Cãã̯úâãyÆejXð·é@諾AܽStàéåw¿ÎãÃZ^[̳öÅ é[Jæ¶â§a@@\çtãÃZ^[Ì·Å éêFæ¶A¼ÉàStD«ÌFlɨU¢¢½¾@ïª èyµv[µÄ¨èÜ·B
oh~gâì
à}CPbgðwü·éÙÇD«ÈÌÅ(ãèÍȢŷª)A@ïª êÎ¥ñ¨U¢¢½¾¯êÎÆv¢Ü·B

ª¨CÉüèÌê
³ÄA{èÖÆÚç¹Ä¢½¾«Ü·ªA2023N729úÉyGz[ÅJóêܵ½æ48ñ çtåAíȯåïwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ªïê(yGz[)@@@@@@@@@@@@@@@@@ªvO
1̯åïÉø«±«A¡ñàyGçt yGz[ÉÄJóêܵ½B
¡ñÍAçtåw¼_³öÅ éè ~æ¶à²oȳêܵ½B³CȨpðq©·é±ÆªÅ«ðµv¢Üµ½B

ªJïOÉèæ¶ÆBeµ½Ê^
áNÊèçtåwåAíȳö sì qFæ¶æèJïÌ«ðèA±¢ÄwïÌ®üEðõï̲ñAܽÝÍÜa@ ³ä îVæ¶æè÷JÜƵÄA
¡NxD´s§ãÃZ^[ð²ÞC³ê5æè³Æ¤åAíÈNjbNðJƳêܵ½²¡ Mvæ¶Ì²ÐîE\²ð¢½¾«Üµ½B

ªsìæ¶@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ª³äæ¶
¡Nxæè~ÌúÉsíêé¯åïƯlè\ÌÔàݯĨèA¡ñÍ6lÌæ¶ûÉ\µÄ¢½¾«Üµ½B
ÇÌèàÆÄàwѪ½AܽáèSÌ\Æ¢¤±Æà 詪à¯çêÈ¢Æhðó¯éÇ¢@ïÆÈèܵ½B

ªãi¶æèVäæ¶Aìæ¶Acæ¶
ºi¶æènç²æ¶AÁ¡(m)æ¶AÁ¡(q)æ¶
±¢Ä¡NÌVüÇõÐîÖB¡Nà7lƽÌûÉüǵĢ½¾«Üµ½B
ÐÆèÐÆè©ÈÐîðµÄ¢½¾«Üµ½ªNêl¨|¶¹¸É¨bµ·éƱëðÝĤ°ªÈ¢Æv¤½ÊÆÄà൴¶Üµ½B
VüÇõÌF³ñA±ê©çXµ¨è¢vµÜ·B

ª¶©çJ{æ¶AÑcæ¶Aغæ¶Añræ¶A{éæ¶
(åvÛæ¶Aɬæ¶ÍsÝ)
ÅãÆÈèܵ½ªAàòåwåw@ãòÛw¤È åAíAwI¡Ãw³ö aã Öæ¶æèwFrom Basic Research to Clinical PracticexÌe[}Ųuðèܵ½B
O§Bªñƻ̡ÃòAtªñÆJ{U`juåÏ×ÉÈèܵ½B
ܽîb¤Ìdv«ðwÑAl¦éÇ¢@ïÆÈèܵ½B
¨Zµ¢AåÏMdȲu èªÆ¤²´¢Üµ½B

ªPáÌ[Ì|[Y
sìæ¶æèÂïÌ«ðèïͳI¹AÅãÍ«ð^ñž³Á½æ¶ûSõÅÊ^ðBèðUÆÈèܵ½B
ÈãAæ48ñ çtåwåAíȯåïwpWï̲ñŵ½B
¯åïÍi¨ï¢Å«È¢æ¶ûÆð¬ð[ßéÇ¢@ïÅ èA~̯åïà¡©çÆÄàyµÝÅ·B
»êÜÅêlOÌzÆ·éåAíÈãɵÅàßïéæ¤úX¸iµÄÜ¢èÜ·B
¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@¡´ Ä÷
ªJt@X2023 in{è
F³ñ±ñÉ¿ÍI
åw@mÛö4NÌâV¡S½Æ\µÜ·B
¡ñ{èÅsíêܵ½æ7ñªJt@XÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¢½¾«Ü·B
çtåwåAíÈ©çÍÈOÉâ{æ¶AD´s§ãÃZ^[Ìä涪QÁ³êܵ½B
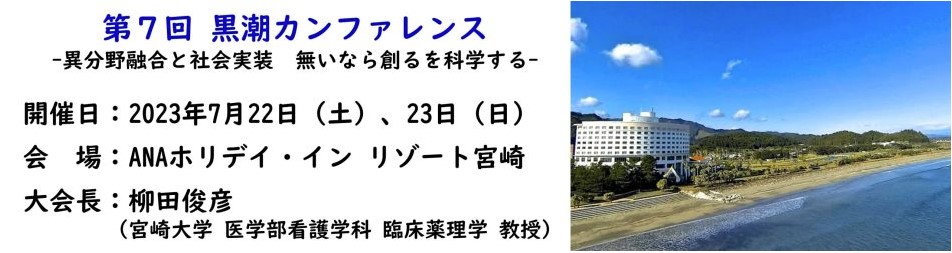
ïêÍêÊI[Vr
[ÌzeÉÄsíêܵ½B
ªJt@XÍAçtåwåw@ãw¤@òw³ºÌÀ¼®F³öªçt§ã\ã¢ÅÌJÃðLO·×«æ1ñƵ½¤ïÅ·B
¼OÌRÍALú{Æ¢Eðq¬¾½mÝðSÉñíɽÌbÝð^¦A¶»Ée¿ðyÚµ½Ü³µuªv»ÌàÌ©çĨèÜ·B
QÁÒÍòwâãwɯÜç¸AwâHwÈÇlXÈÙªì©çlªWÜèð¬ªsíêéêÉÈÁĢܷB
¡ñÌJÃnÍ{è§Æ¢¤±ÆÅAÍ¡ñÌKâªßÄÅà èAÆÄàVNÈ·HÆÈèܵ½B
JÃúOúÌαãÉoµ½½ßA»nÉ
µ½ÌÍ21 ÆÈèܵ½B
¹Á©Ì{èŵ½ªéx̽ßó¢Ä¢é¨XàÈAØÝzeßÌ[®ðKêܵ½B
ÈñÆK^ȱÆÉ{輨Ìn{Ä«ªÌÁ½un{[vÈéà̪ èãÛðſܵ½B
»ÌãÍṳ́ïúÉõ¦ÄzeÅ\ÌC[Wg[jOðs¢Üµ½B

úÍVóÉàbÜêAf°çµ¢iÏÌŤïúð}¦Üµ½B
ïêÍÂÉ éANAzfCEC][g{èÉÄJóêܵ½B
ÚÌOªêʸâ©ÈgªÅ¿ñ¹éI[Vr
[ÌzeÅ èAåï·Å{èåwòwöcæ¶Ì²ñÄà èulN^CµÖIIvÌAN[rY©çAnVcÜÅlXÈX^CÅInyµ°ÈµÍC¾Á½ÌªÆÄàóÛIŵ½B

çtååAíÈRcAçt§àÅα³êÄ¢é¤CãÌæ¶ÆçtåPáÌu[vÌ|[YÅêB
MÒÍÇX[cÅQÁµÄµÜ¢Üµ½BiE©çMÒAäæ¶Aâ{æ¶A¤CãÌåìæ¶ÆäÃæ¶j
åìæ¶ÍçtJÐa@©çAäÃæ¶ÍNÃa@©çQÁµÄêܵ½B
åAíÈàu]ÈÌêÂÉã°ÄêÄ¢éÆ̱ÆÅA«êÉúª¡©çyµÝÅ·B
ïêÅͽÌm©ð¾é±ÆªÅ«Üµ½B
îb¤ânò̪ìÌÝÈç¸A³çâãHwÉéÜŽÌ\ªsíêܵ½B
Åà×ExÌ~NÈÌæÉεĿûòÌøÊð¢·éñÍóÛIŵ½B
¼mãwÆÙÈèAlÔðuCvƵĨ¦Ä¡ÃÉü©¢¤¿ûÌvz©ç·éÆAu×EÉàCª é̾뤩HvÈñıÆðÓÆ^âÉvÁ½èµÜµ½B
ßãÉÍà©g̤É¢Ä\³¹Ä¢½¾«Üµ½B
iwïÈÇÅÍX[cêFÌI[fBGXÅ·ªA¡ñÍOqÌÊèTVcâAnVcÌæ¶ÜÅ¢çÁµáéÆ¢¤ÙFÌóÔÅÌ\ÆÈèA©¦ÁÄ¢ÂàÈãÉÙ£µÜµ½B
ïêÉÍCOÌQÁÒà¨è¼Ú¿^ÈÇÅïb·é@ïÍ èܹñŵ½ªA¡ãpêÍàßÄ¢Kv«ðÀ´µÜµ½B

DG\Üðóܳê½äæ¶I³·ªÅ·IAnVcਢŷI
úÌéÉͧeïªsíêܵ½B
ÍúÌ\èÌÖWÅcOȪçQÁ·é±ÆÍūܹñŵ½ªAQÁ³ê½â{æ¶æèäæ¶ÆÌ\ªDGÜð_uóܵ½±Æð³¦Ä¢½¾«AÆÄàðµ¢C¿ÅAHÉ
±ÆªÅ«Üµ½B
¡ñÍñíÉZ¢ØÝÆÈÁĵÜÁ½½ßA2úṲ́ïÌlqA{è§ÌÏõâOÈÇÌ£ÍðLŲÐîÅ«¸åÏ\µó èܹñB
{èÌf°çµ¢¼Å éuçävâãB̬sÆÄÎêéuúìsEéKìi¨ÑjvÈÇðKêé±ÆÍūܹñŵ½ªA¢Â©Ü½xWµ½¢ÆÓðV½ÉµÜµ½B

çtÉAÁÄ©çòw³ºÀ¼³öÉóÜ̲ñ
ÅãÉÈèÜ·ªA±Ìx\Ì@ïð^¦Ä¾³Á½À¼³öðͶßA¤àeÉֵIJw±¾³Á½sì³öEâ{æ¶AåAíÈãÇEòw³ºÌFlÉ[äç\µã°Ü·B
¡ãÆà²w±²Ú£Ìöæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFåw@mÛö4N@âV¡ S½
ßµñ(ÍéA}` A{öVíéʧåï D)
Fl¢©ª¨ß²µÅµå¤©B
[JÔ\a@ÉαµÄ¨èÜ·AüÇ6NÚÌúìånÆ\µÜ·B
ßµñƵÄMð·ç¹Ä¢½¾«Ü·B
¬Å·ª716úÉsíê½ÍéA}`
A{öVíéʧåïÅD·é±ÆªÅ«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
ðNÍDŵ½ÌÅAxWūĤêµv¢Ü·B
[JÔ\a@·@É¡æ¶àÍéðnÜêé½ßAÊ^ÌƨèåÏìñź³¢Üµ½B826A27úÉsíêéSåïÅÍú{êðÚwµÄæ£è½¢Æv¢Ü·B

[JÔ\a@·@É¡æ¶AåAíÈ·çtæ¶É¨j¢µÄ¢½¾«Üµ½B
ÍéÅÍ»Ì̸_óÔª»ÌÜÜÕãÉ\êÜ·B
SªrñÅ¢éÆéàÈèASª«ê¢¾Æüµ¢éªÅÄÜ·B
Ãæèûm½¿ÍÍéÌZÊðßé½ßÉúX̶ɨ¢Äçßðdñ¶AÈðߧµßīܵ½B

ÎÇÌ
¡ñ©ªÍñíÉ梸_óÔÅÉÕß½Æv¢Ü·B
»Ìå«ÈvöƵÄA©ÌØgÉæé÷Ìü¢ª °çêÜ·B
åAíÈ·ºÉÍ}Vªõ¦çêĨèAâfBbvXÌg[jOª¢ÂÅàÂ\Å·B
·Ìçtæ¶æèuèpɨ¢ÄÅãÉ©ªð¯éÌÍØ÷¾vÆÌà¾ðö©èAw¶ãÈ10NÔèÉØgðÄJ¢½µÜµ½B
©oηéÆAܸÍNà¢È¢·ºÖQèÜ·B
»±Å20ªöóÉ©ªðÇ¢ñ¾Ì¿ÉA¾Îñ¾óÔÅaÖÆü©¢Ü·B

óÉÇ¢Þ
uØ÷ÍØ÷»ê©ÌðÚIƵÄb¦çêËÎÈçÈ¢vÆࢽORIvÉw`ÉÈèÜ·ªA}ç¸àúÌg[jOÌÊƵÄèpZpÌüãA³çɸ_ÊÅÌÀèªà½ç³ê½Æ´¶Ü·B
éAØ÷Í¢ïÈTURÇáɨ¢Äð~¢Üµ½B
ÈOÈç¢ïðÉ߽Šë¤OÇÌå«Èîáà¶èÌÍÈvXªø«®·é±ÆªÅ«Üµ½B
{bgèpS·ÌãÉ ÁÄàåAíÈOÈãÉÆÁÄxÈ÷̪KvÅ é±ÆðÀ´µ½æÅ·B
ÜÆßÜ·ÆA[JÉCµÄ©çèpEØgEÍéªOÊêÌÆÈ謷ūĢéÀ´ª èÜ·B
±êÍÐƦÉúyµ¯é«ðìÁľ³éçtæ¶Í¶ß¯»Ìæ¶ų̂©°Å è´Ó\µã°Ü·B
ÈãAßµñÆÈèÜ·B
Èðß½¢áèÌæ¶ûAºÐ[JÅêɫܵå¤I
¶ÓF[JÔ\a@@úì ån
æ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï
ͶßܵÄAðNxæèçtåwåAíÈÉüdz¹Ä¢½¾«A»ÝÍçtåwãw®a@ÅαµÄ¢é§eåãÆ\µÜ·B

ÈPÅÍ èÜ·ªµ¾¯©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
Måwt®MZð²ÆAªìð²ñÅü±¤¤É é}gåwÉüwµA²ãú¤CÍïéÌJAÆèÅãÃZ^[ÉÄsÁĨèܵ½B
ðNx©çÈñÆ©ªì̱Á¿¤ÉßÁÄé±ÆªÅ«ÜµÄAçt§±Çàa@ŤCµAñíÉMdÈo±ðÏޱƪūܵ½B
ï¡Íd®ejXÅ·B
¯úÉejXo±Òª½AÅßÍTÌæ¤ÉejXµÄ¢Ü·B
ºÐêÉejXµ½¢æ¶ª¨çêܵ½ç²A¾³¢B
³Ä¡ñÍæ3ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉ¢Äñ³¹Ä¢½¾«Ü·B

ïêÍçtåwãw®a@ÌK[lbgz[ÅAOúÉÍäçªÄÂA¡ºæ¶wöºÌàÆAüOÈõÆn[Tªsíêܵ½B

nûïúAçtåãÇõªeXzuÉ«ASÌóÔÅÕޱƪūܵ½B
¡ñÍéÌûXÉà½åȦÍðµÄ¢½¾«Üµ½B
àµé³ñ½¿ª¢È©Á½çtbV
}½¿ÌdÍ10{ç¢ÉÈÁÄ¢½Æv¤ÆªªãªèܹñB
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
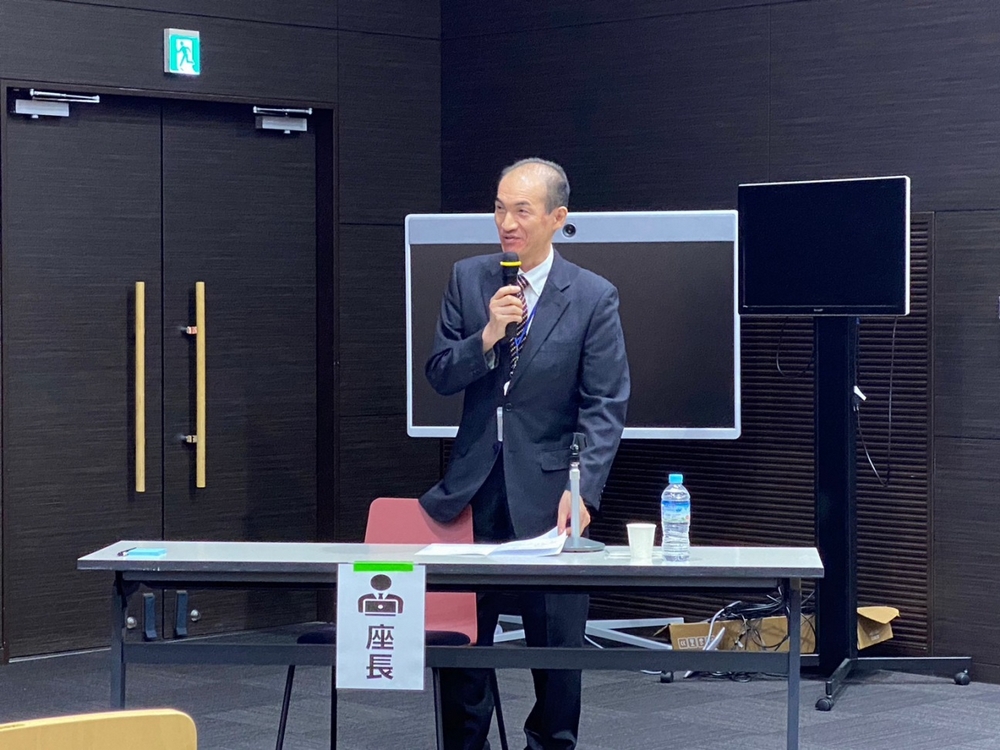
»µÄçtnûïï·Å ésìæ¶ÌJį̈¾tÅØèÈïÍnÜèܵ½B
¡ñàOñOXñÉø«±«Açtåa@âçtåÖAÌsa@ðͶßAbïãÈåwt®a@AÈåwsìa@AMåwãÃZ^[²qa@AV°åwt®YÀa@Aú{ãÈåwçtka@AÛãÃåw¬ca@AqãÈåw®ªçããÃZ^[Aéåw¿ÎãÃZ^[ÈÇñíɽÌ{Ý©çQÁµÄ¢½¾«Üµ½B

\ÌàeÉ«ܵÄÍñíÉcOÅÍ èÜ·ªL̶ÌÖWŤ³¹Ä¢½¾«Ü·B
ê¾¾¯t¯Á¦éÆ·éÆAlÉÆÁÄܾoïÁ½±ÆÌÈ¢Ç᪽A¢ÌÉÍïµ¢aCª½¢ÈÆv¢Üµ½B

¡ñÌnûïÅÍDGÈ\ðµ½æ¶Éü¯ÄxXgv[^[ܪ¡çêܵ½B
çt§àÌáèÌ涪óܵĢéÌð©ÄÆÄàhÉÈèܵ½B
ÈãÅæ3ñçtnûï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B
ÆÄà×ÉÈé\ΩèÅåAíÈÌʳðÀ´·é±ÆªÅ«Üµ½B
làñÍxXgv[^[ÜðóÜÅ«éç¢Ì\ªÅ«é椸iµ½¢Æv¢Ü·B
¡ãÆà²w±ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@§e åã
Prostatic Night 3(ProNi3)ÉQÁµÄ
2022NxÉüdz¹Ä¢½¾«Üµ½ìKêYÆ\µÜ·B
eÅ·ÌÅA©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B
ogÍÌ¢²JÆ¢¤Æ±ëÅ·B
»ÝA¢²Jo
ÌxzºÉ éÆ¢ÁÄàß¾ÅÍ èܹñªA¨¢µ¢XâC é¤XXªÀñŨèÆÄࢢƱëÅ·B
¬Í}gåwt®ÉÊÁĨèܵ½B
»ÌãçtåwÉiwµA²ÆãA¡lJÐa@Åú¤C2NÔÆåAíÈ1NÔðß²³¹Ä¢½¾«Üµ½B
¡NÌ4©ççtåwãw®a@ÅtbV
}ƵĢĨèÜ·B
¬wZ©ç¸ÁÆTbJ[µ©µÄ±È©Á½l¶ÅA¡ÅàTbJ[âtbgTͱ¯Ä¢Ü·ªA»ë»ëVµ¢X|[càâÁÄݽ¢Æ¢¤C¿à èAejXâ
jAÞèiX|[cHjÉàèðoµÄ¢«½¢Æl¦Ä¨èÜ·B

¢²J̵[ÕèÌlq@@@@@@@@@@@@@@@@TbJ[ãÌ©ªÅ·
³ÄAµOÉÈèÜ·ªProstatic Night 3(ProNi3)ÖQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
2023N616úAzetNXÆ¢¤Cl£É éR³µ«zeÉÄsíêܵ½B
TbJ[ÌåæyÅ çêéäæ¶À·ÌàÆA¸h·é±¿çàTbJ[ïà·Î´æ¶ÌuðçØèÉïÍX^[gµÜµ½B

X^[^[Ìδæ¶B
hZ^LZ¡ÃÌÏJÉ¢ÄA²©gÌðjÆÆàɨbµ¢½¾«Üµ½I
æñÒÌOcæ¶ÍçtfBJZ^[ÅÌêÏíÁ½¡Ã@ÈÇÉ¢ÄAæOÒÌÂæ¶ÍÈåwsìa@ÅgpµÄ¢éèpp{bgghinotorihÈÇÌuðµÄ¾³¢Üµ½B
çtåwɢ龯ÅÍmé±ÆªÅ«È¢±ÆΩèÅÆÄà×ÉÈèܵ½B


ïêÉÍOr[pâEGbgX[cÌûà¨èAeíX|[cE©çàuð·«ÉÄ¢éûª¢çÁµáéæ¤Èõiŵ½B
À·Ìºæ¶Aäæ¶Í®¶é±ÆÈisð³êĨèÜ·B
ProNi3ÌùÌ[³ðÀ´¢½µÜ·B

ÈãAæOñProNiÍå·µÅI¹¢½µÜµ½B
uïâð¬ðʶÄáÁ½_©çÌl¦ûðwÑAæ謷·é±ÆªÅ«éÆ´¶Üµ½B
±ê©çÍcÌÝÈ縡ÌÂȪèàåØɵĢ«½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFçtåwãw®a@åAíÈ@ì KêY
Urology Today in Chiba2023
2022NxüÇ̺ãÆ\µÜ·B
ͶßܵÄÅ·ÌÅAy©ÈÐĢ½¾«Ü·B
ú¤C©çONÜżËs§ãÃZ^[ÅαµÄ¨èܵ½B
»±ÅçtååAíÈÌæ¶ûƨçtåwåAíÈãÇÉüç¹Ä¢½¾±ÆÉÈèܵ½B
iͤĤ絢LBÆéçµÄ¨èÜ·B
Åß1CÕ®¢µÄ3Cɦܵ½B
Æ¢¤±ÆÅ©ÈÐîÍ»ñÈƱëɵĨ«A¢EêÂ©í¢¢¤¿ÌÉáñ¸ðÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B
·jÍ4Î̫ȱñÅ·B
Gį́Z³ñB
ºÌq2CªÆÌðo^o^ì¯éÌð¢Âà©çÁÄêĢܷB
ÆÉAéÆêÔÉì¯ñÁÄ«ÄSSµÈªçæīܷªAGè·¬éÆ{èÜ·Î

¨Í·Ì±Þ¬¿áñ(1Î)Å·B
N©ç¤¿É½A©í¢¢©í¢¢}`J¿áñÅ·B
êÔl©mèÅî}Ǫ̈¶³ñªéÆBêĵܢܷ(©í¿¡)iÍæıȢcÅ·ªaÌÔ¾¯CèñÁÄéAc¢ÈªçcÆfðg¢ª¯éÒÅ·Î

ÅãªÅßÔüèµ½¤Éñ(5)Å·B
±Þ¬¿áñƯ¶}`JÅZ¢rªÆÄà©í¿¡B

©N«éÆÚÌOÅQÄ¢½èµÜ·BÅßƪ¢Ì©°É¾çµÈQ»×ÁÄ¢é±Æª½¢Vüè¿áñÅ·B
ÈãA¢Eꤢ¤¿ÌÉáñ¸Åµ½Î
LͳĨ«A68úÉOäK[fzeçtÉÄJóêܵ½Urology Today in ChibaÌlqÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
áNçtååAíÈÖÌüÇðl¦Ä¢éw¶Aú¤CãÌæ¶ü¯ÉJõĢé{ïÅ·ªA¡NxàáNæèàXÉå¨ÌüÇó]Ìæ¶ûɲQÁ¢½¾«Üµ½B

ªöOÉÒÌæ¶ûÅLOBe
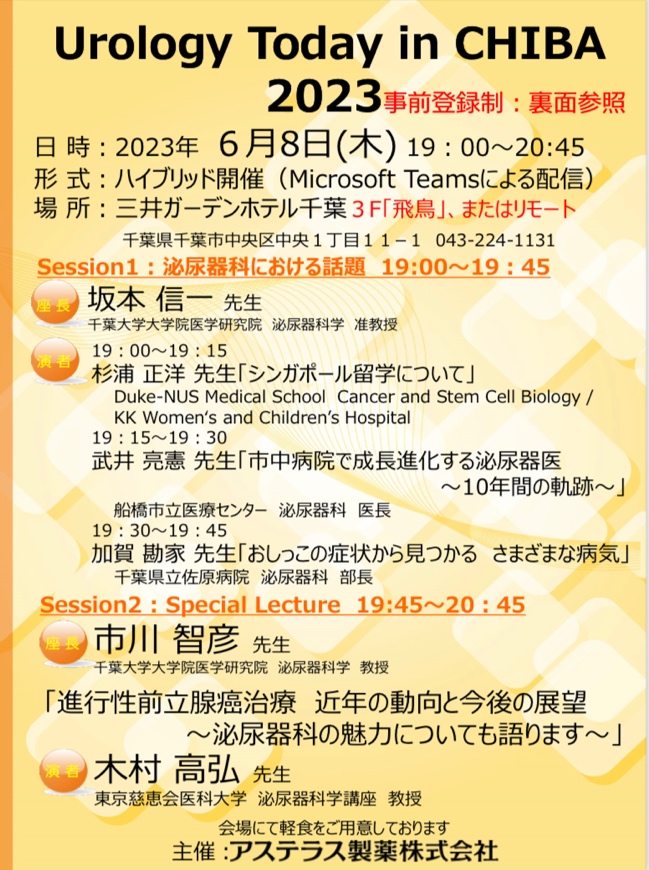
ªöàeÉÈèÜ·B
O¼Í»ÝVK|[ɯwÌYæ¶ÉuVK|[¯wÉ¢ÄvAD´s§ãÃZ^[äæ¶Éusa@Ŭ·i»·éåAíÈã`10NÌOÕ`vAçt§§²´a@ÌÁêæ¶Éu¨µÁ±ÌÇó©çÝ©élXÈaCvÆ¢¤àeŲu¢½¾«Üµ½B
Yæ¶ÍyXVK|[©çweb©ç²u¢½¾«Üµ½B
ú{ÆÍSÙÈ鶻Ŷ³êÄ¢élÅ·B
½ÐÌæ¶ûÆ[Àµ½¯wlifeðçêÄ¢élŵ½B

ªWebãÅÎb·éâ{æ¶ÆYæ¶
äæ¶Í±ê©çåAíÈãðÚw·æ¶ûÖ²©gÌ10NÔÌOÕð²u¢½¾«Üµ½B
x̲Æ[AÉxñ¾àeÅïê©ç½X΢ªN«Ä¢Üµ½ËB

ªÊ¢©Â´®IȲuðµÄ¾³Á½äæ¶
Áê涩çÍåAíÈÉÅརrAáQÉX|bgðĽ²u𢽾«Üµ½B
ïÌIÉÀáð¥Ü¦½²uÅw¶E¤CãÌæ¶ûàC[WªÂ«â·©Á½ÌÅÍȢŵ天B

ªí©èâ·¢¨bðµÄ¾³Á½Áêæ¶
ã¼íÍÀ·ðsì³öɱßÄ¢½¾«AbãÈåw³öÌغæ¶Éuis«O§Bà@ßNÌ®üÆ¡ãÌW]`åAíÈÌ£ÍÉ¢ÄàêèÜ·`vÆ̱ÆŲu¢½¾«Üµ½B
ÅVÌO§BàÌ¡ÃÉ¢Äͨb¢½¾«ÂlIÉÆÄà×ÉÈèܵ½B
³çÉåÏ°kȱÆÉçtåwåAíÈÌ©UXChÜŲpÓ¢½¾«¨bµÄ¾³¢Üµ½I(ÈñÄÇ¢æ¶ÈÌŵå¤)
¡ñ²QÁ¢½¾¢½üÇðl¦Ä¢éæ¶ûÉàغæ¶ÌÂéÊèçtåwåAíÈÌtNÅí¢í¢Æµ½µÍCð´¶æÁÄ¢½¾¯½çðµ¢Å·ËI

»ñȱñÈÅïͽÌûɲQÁ¢½¾«·µÆÈèܵ½B
Ýȳñ¨Zµ¢Æ±ë«ð^ñÅ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½I
¶ÓFãú¤Cã@ºã T÷
}[VA©çJasmineæ¶@çtåtF[Vbvñ
LÍAȺðNbNµÄ²¾³¢B
³çTCGXvO
2023Nx®|[giêÊöåvOjæ015 iBR[Xj
O§BàÛ¤¯¤ A-CaP(Asisan Prostate Cancer)study ÌAg»
çtåw©çÌñ
æ110ñ ú{åAíÈwïï
{Nx4æèaw³ºÉÄåw@mÛö1N¶ÆµÄåwa@Åα¨æѤ³¹Ä¢½¾¢Ä¢éδåÆ\µÜ·B
eÅ·ÌÅ©ÈÐî©çüç¹Ä¢½¾«Ü·B
¶Üêàç¿àçt§Å2018NÉåAíÈüÇãàçtåwa@Açt§ªñZ^[Æçtðo½±Æª èܹñŵ½B
»ñȪðNÜÅ2NÔFs{ŤC³¹Ä¢½¾«A{NxæèÄxçtÖ¢ßé`ÅwιĢ½¾¢Ä¨èÜ·B
TbJ[A
jÆw¶ãÍ¢ë¢ëâÁĨèܵ½ªAÅßÍuTEivðnßĢܷB
ÈاÉÍS{ì·òðͶßL¼È·òâTEiª½³ñ èA·Á©èÍÜÁĵܢܵ½B
¡NÍA¢¿TEi[ƵÄTEi̹nuµ«¶vÉà¨àޫܵ½B

Ri´õÇÆÌü«¢ûàXÉÏJµÄ¨èA¡ñÌåAíÈwïÅÍ\ÒÌ»nQÁÅÌ\ªK{ÆÈÁ½wïÆÈèܵ½B
OEA϶ïFs{a@Å̤CÊð\·é@ï𢽾«Üµ½ÌÅñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
æ110ñÌú{åAíÈwïïÍ_ËRxVZ^[Åsíêܵ½B


ÄóñÌCuïêÌßÅ è°ëµ¢UfÉ©çêܵ½ªAwïåï·ÌìXºæ¶ðfƵ½½ÌplÌU±à èÀ¢ÈïêɽÇè¯ܵ½B
ïêàÍÄÃÌRT[gïêÉÔá¦ÄüÁĵÜÁ½©Æv¤ÙÇÌMCÉïÜêĨèܵ½B
¦«Ê^ÍÄÃRT[gïêßÌóµÅ·B

¢Á»Ì±ÆÄÃRT[gïêÉðïµæ¤©Æàv¢Üµ½ªAåAíÈwïïêàÌû^Áæ¶ÌÁÝR[i[iåãåÌOgÅ éKmªñÌwÒj̽µÈßà ÁÄ©SðÆèàǹܵ½B
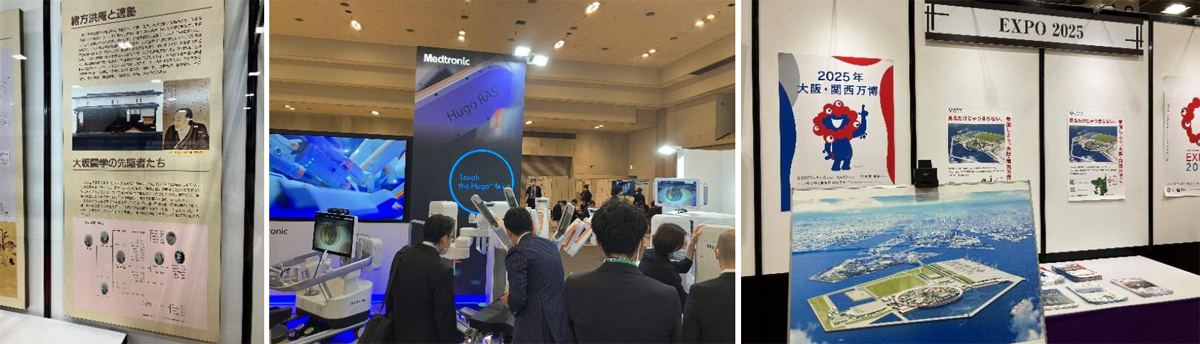
éÆu[XÅÍAåãEÖ¼EXPO2025ÌÐîâY{bgxuÌHINOTORĮo}¦à èܵ½B
ʸÉHINOTORIV~
[VÌðÂðs¢Üµ½ªA·ÅÉO\ñâI¹µÄµÜÁĨèA@BÉGêé±Æ·çūܹñŵ½B
HINOTORIÍXÉVFAðÐë°é`Åk¢åwA¹æåwÅÒ³êÄ¢éÆ̱ÆÅ·B

¡NàwïÉĽÌè\ª èܵ½ªAÈñÆçtå©çjãÆÈéïÜ_uóÜŵ½II
¨ßÅƤ²´¢Ü·IIçtååAíĘ̀¢ÍÆÇÜé±ÆðµèܹñII
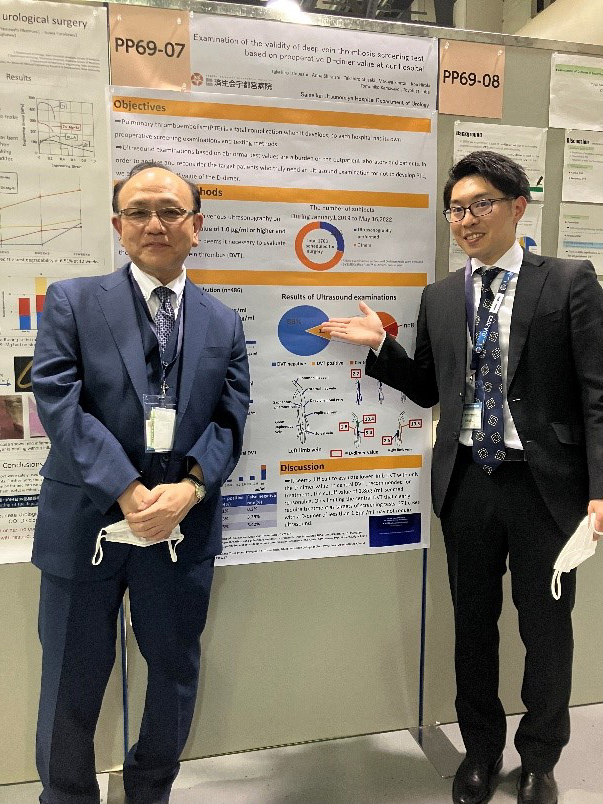
¦\ÒÈãÉÀgÌÎÝðݹľ³éËç²æ¶iÊ^оèjÆ©ªiÊ^ݬj
»ñȱñÈų©gÌ\à¨íèð}¦Üµ½B
ãiÌImÈRgà è|X^[ïêà·èãªèðݹĢܵ½B
ea@ÌÕ°IÈïèÉηéHv_ª·¯ÄñíÉ»¡[¢|X^[\ª½ èܵ½B
©gÌ\Éཿ⢽¾«A¡ãÌÛè_âËç²æ¶©çÌhèࢽ¾±ÆªÅ«Üµ½B
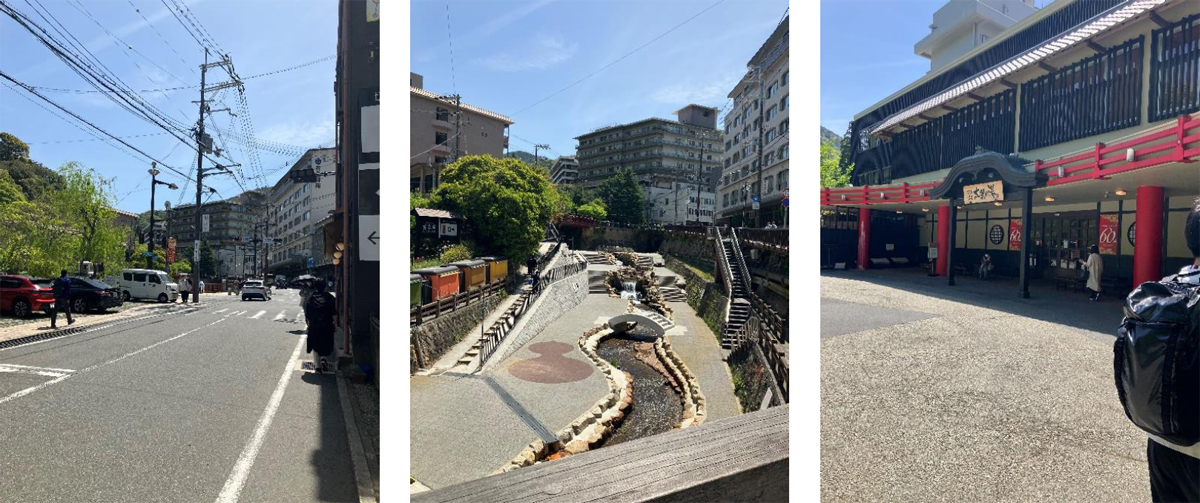
wïÌIíèÍßÌLn·òɨ׵ܵ½BVCÉàß®ÜêAC¿Ì¢¢IVCð¡í¤±ÆªÅ«Üµ½B
¨«ÜèÌTEiãÌIVCÅÌOÍiÊŵ½B
ÜèÌ ÁÆ¢¤ÔÌwïÅrCð¸ÁÄ¢½ÌÅÍÈ¢©Æv¤ÙÇŵ½ªAwï¨æÑ·òÅÌMdÈåAíȯuÌM¢êèà¥Ü¦A¡ãÌÕ°¨æѤɢ©¹éñíÉwÑÌ éêŵ½B
¡ãàDGÈæyûðÚwµ³çÈéãÃÌWÉÞ¯¸iµÄQè½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFçtåwãw®a@@δ å
2023/3/10-13 EAU2023Milan, Italy
±ñÉ¿ÍAéåw¿ÎãÃZ^[ÌáäÅ·B
¡ñÍ3ÉC^AE~mÅJóêܵ½¢BåAíÈwï(EAU)ÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñ³¹Ä¸«Ü·B
obNio[Éà èÜ·ªAEAUÅ\·éÌÍ2015NÌ}h[hÈÉÈèÜ·B
»ÌÛÍâ{æ¶Æs«AO§Bà³ÒÌtestosteroneÚÉÖ·é\ðµÜµ½ªAÈñÆ¡ñàâ{æ¶ÆÆàÉsÁÄQèܵ½B
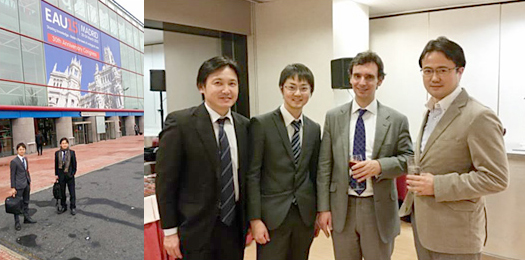
2015NMadridÅÌÊ^

¡ñMilanÅÌÊ^@8NoÁÄAñlÆàÏíÁ½Åµå¤©H
Hcó`©çòs@ÅoµA15Ô©¯Ä~mɽÇè
«Üµ½ªA
ÉÍæJ¢Þŵ½B
½¾AêÂ~íê½ÌÍ~mÅÍXMÔ²ªÙÆñÇÁĢȩÁ½Æ¢¤±Æŵ½B
¿å¤ÇÐÇ¢Ô²ÇÅ_@E_᪩¹È©Á½ÍåÊÌ|PbgeBbV
ð¢ñÅ¢Á½ÌÅ·ªAÙÆñÇoÔÍÈÆÄà©èܵ½(Î)
ܽRiÉ¢ÄàAC^AÅÍ}XNðµÄ¢élÍÅAó`ÅÌ`FbNàÙÆñÇ èܹñŵ½B
ÀÛÌ´õÒÈÇÍí©èܹñªAú{ÆÍÎôÌdûªå«ÙÈéÌÍóÛIŵ½B

æJ¢ÞÈñl

MilanÌlXÌlq
wïêÅÍÅVÌm©É¢Ľbð·±ÆªÅ«Üµ½B
O§BÌsessionÅÍA2021NÉEUÅA2022NÉÍú{ųê½V^{bgxèpVXeÌhugo RAS(Medtronic)Ì\ª½Ýçêܵ½B
ú{àÅÍdaVinci(Intuitive)ªå¬ÅhugoÌbð·@ïÍܾÙÆñÇ èܹñªAEUÌåKÍZ^[ÅÍda VinciÉÁ¦Ähugoð2äÚƵıüµÄ¢é{ݪ½AärÌb෱ƪoܵ½B
ÎjÓÉp¢çêÄ«½z~jEYAG[U[ÆAVKÉJ³ê½cE[U[Ìäràå«ÈgsbNŵ½B
Best of EAU sessionÅÍeÌæÅÅàCpNgðcµ½èÉ¢ÄÌuª èAAPCCC sessionÅÍÅVÌO§BàÉÖ·éRZTXÌbª èA³|IÈîñÊŵ½B

ïêÌlq
̤ÆàÖA·éƱëÅÅàóÛI¾Á½ÌÍAXegÂÇð\h·é½ßÌAÇXegÌi»Ìbŵ½B
\ÊÌ`óðÁêÁH·é±ÆÅÎt
ð\h·éTriaXeg(Boston scientific)É¢ÄÍà³F³êĨèÜ·ªA»ÌÙ©ÉàVRR[eBO·é±ÆÅ×Ût
ð\hµ½ñâAòÜno«XegA¶Ìàªð«XegÈÇÌJÉ¢ķ±Æªoܵ½B
±¤µ½Jóµð·±ÆÅ©ªÌ¤Ìûü«É¢ÄàÄl·é±ÆªoAñíÉÇ¢@ïÆÈèܵ½B
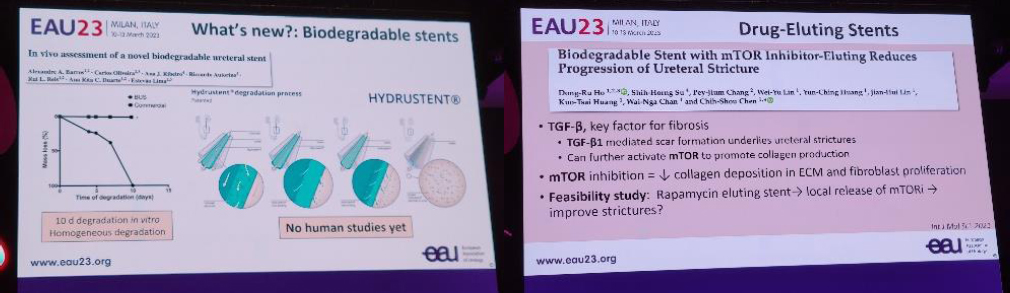
(¶)¶Ìàªð«Xeg ¨Ôð©¯ÄÌàÅzû³êéÌÅ٨ƵÄcçÈ¢I
(E)òÜno«Xeg
2úÚÉÍÌVX`ÎÉÖ·é\ª èܵ½ªAå«Èïê¾Á½ÌÅåªÙ£µÜµ½B
¿^ÌÓ}ªÝØê¸AܾܾpêÅÌc_ÉÛèª éÆ´¶Üµ½B
â{æ¶ÍÊZbVÅÀ·ð±ßÄçÁµá¢Üµ½ªA¬¨Èpêͳé±ÆȪçAïêÌ®OÉèð³¹AûÌæ¶ÆàkÎð·éÈÇ]TÌñµÅµ½B
COÅànè¦é\ÍÆ^̳ð©K¢½¢Æ´¶Üµ½B

(¶)áä\@(E)ÎÌîb¤åÅÍAWAÌ涪½\³êĢܵ½
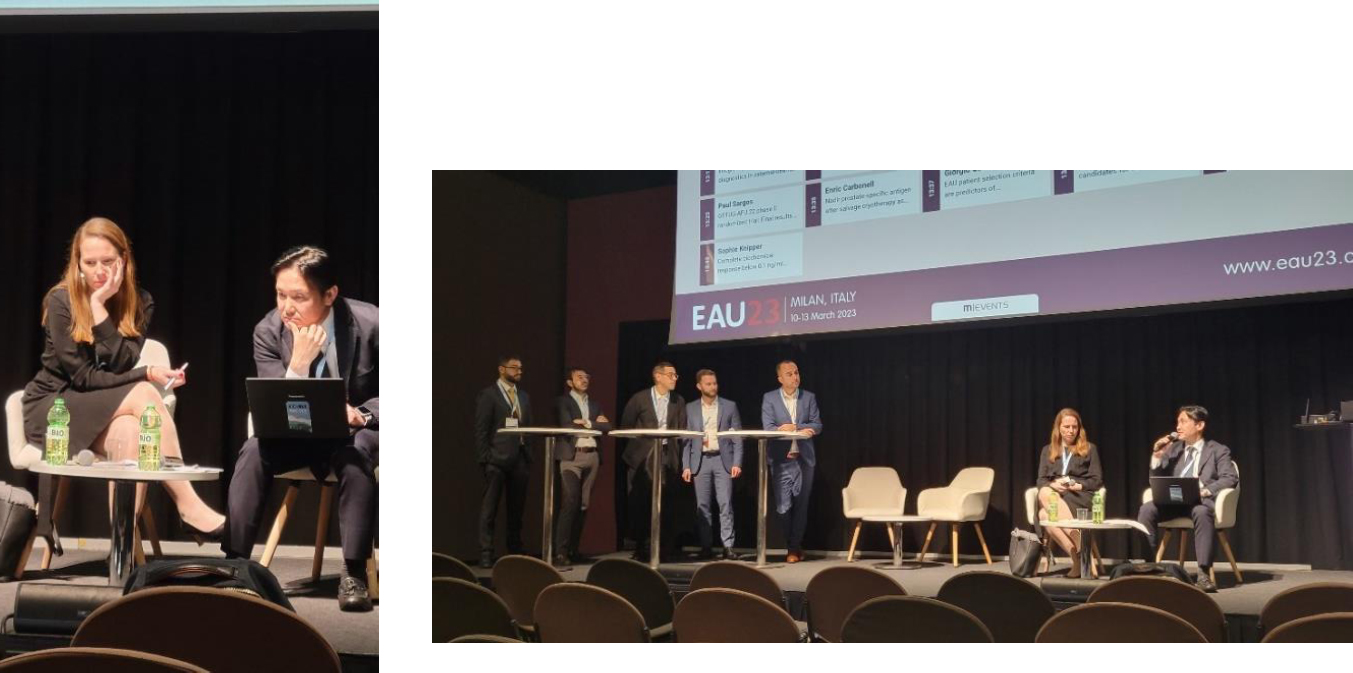
(¶)À·Ìâ{æ¶Æ_ÌSophie@(E)°X½éiïŵ½
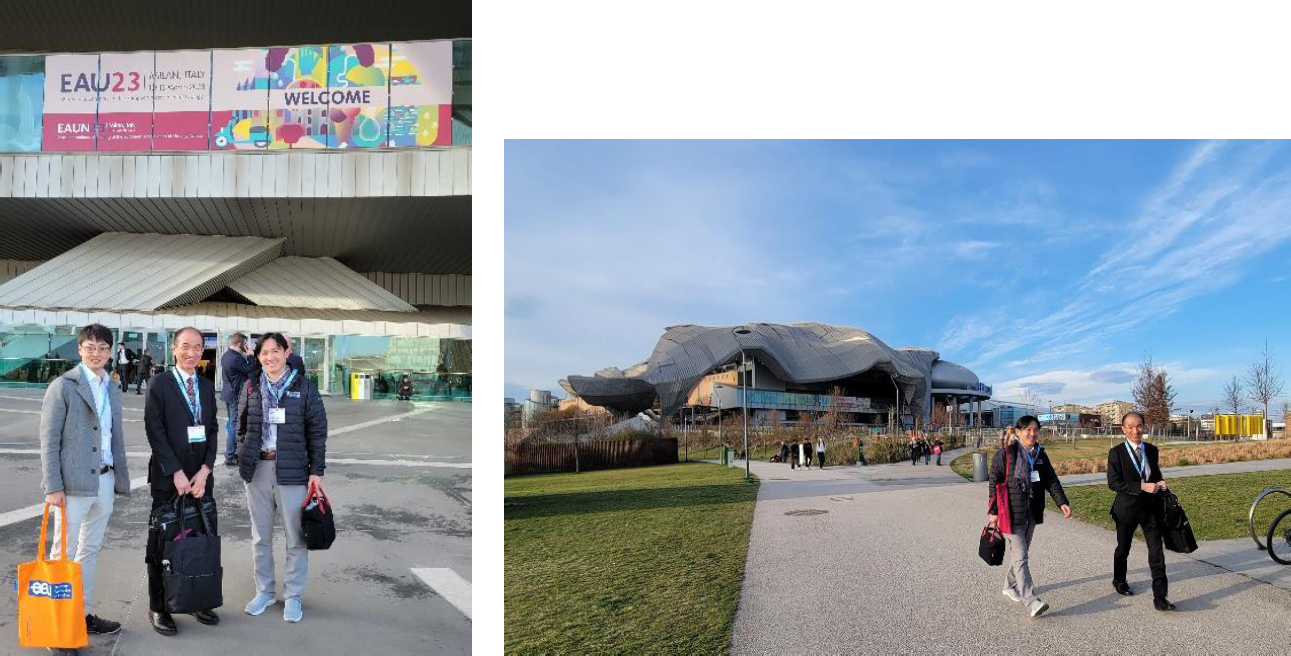
(¶)sì³öÆଷé±Æªo½ÌÅ3shotB
(E)çtåðwÁÄ«½¨ñlMilano Convention Centre
äXªhµ½zeÍ~mÌSnÉ èA©ÌL¼ÈDuomo(å¹°)©çkà10ªöx̣ŵ½B
wïêÜÅ̹ðྯÅàðjIÈ¢¨ª»±©µ±É©çêÄAIVÈCªÉÈèܵ½B
·®ßÉuÅãÌÓ`vÌ´æªüçêÄ¢é±ÆÅL¼ÈT^E}AEfEOcBG³ïà èܵ½µAKAâXJÀÈÇÉàs«A~mÌXÀÝðyµÞ±Æªoܵ½B

DuomoOÅLOBe@â{涪håiÈ(?)NX`ÈÌÅòR̳ïðñèܵ½
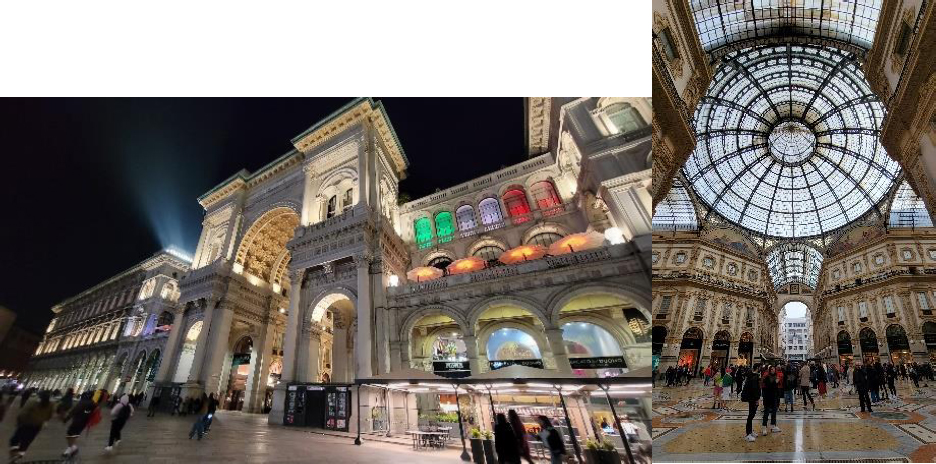
KA
ÅãɵԪo½ÌÅA׬ÌtBcFÜÅ«ðLεܵ½B
~mæèàXÉgȬÀݪc³êA|pIȬŵ½B
EtBbcBüpÙÅÍL¼ÈGæàòR©é±Æªoܵ½B

(¶)FbLI´@(E)EtBbcBÌu¹êqÆñVgvu_rfv

à¿ëñVenchiÌWF[gหܵ½B
¡ñC^AÉͲƷsÈ12NÔèÉs«Üµ½ªAÏíçÈ¢ªÆÏíÁ½ªªÍÁ«èµÄ¢Üµ½B
ðjIÈ¢¨âXÀÝA¶»Í¸dµÂÂàALbV
XÏEwifiEðÊÔÌ®õAzeâXgÌ¿ÌüãÈÇÍ°ÅA³|IÉñèâ·¢ssƵÄi»µÄ¢Üµ½B
äXçtå௶æ¤ÉKV[ðçèÂÂA_îÉi»µÄs¯êÎÆ´¶Üµ½B
ܽA¡ñÌEAUÅÍÅVÌm©ÉGêé±ÆÌdv«ðÉ´µÜµ½B
ÁÉV^Ì@íâ¡ÃÉÖµÄÍàÌm©ÅÍǢ¯Ȣªª éÌÅAܽ±Ìæ¤È@ïð¾ÄACOÖwÑÉ¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
ÅãÉA¡ñ̤ÉֵIJw±¾³Á½sì³öEâ{æ¶AîáawÌr´³öðnßÆ·éæ¶ûAT|[gµÄê½Äcdæ¶(»çt§ªñZ^[)A¨xÝðº³Á½éåw¿ÎãÃZ^[ãÇÌÝȳÜÉS©çäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
±ê©çàêwæ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
¨Ü¯
i»µÄ¢½C^AÅ·ªAEHV
bgÍyµÄ¨èܹñŵ½B
±êÉ¢ÄÍrfª®õµÄ¢é̪wiÆµÄ éæ¤Åµ½B

S{涪gCƵÄgpµ½rf
¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[ ³ / çtåwãw®a@ ÁC³@áä
çtåwåAíȯåï
ßܵÄãú¤C1NÚÌäYåÆ\µÜ·B
ÍsüæogÅQnåwð²Æµ½ãA϶ïKuìa@Åú¤CðµÄ¢Üµ½B
{NxæèçtååAíÈÉüǵ»ÝD´a@ÉĤCð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
úX©ªÌm¯EZps«ðÉ´µÈªçàæ¶û̲w±ÌºA[Àµ½¤Cðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
ï¡Í£nÅ·B
MuIȤÊÅ}CiXC[Wð½êĵܤ±ÆརŷªAWJ\zEÌ[³ÈÇ\zt@N^[ª½¢±ÆâAXÌh}ð¶Å̴ū鴮ͽ¨Éà㦪½Aï¡ÆµÄyµÜ¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B

(¶)ÆNÃa@åAíÈÌnÓæ¶

Ì1ÔD«ÈnÅ·I

Äcæ¶ÆD´a@åAíÈ·ÌÖcæ¶Æ
³Ä{èÖÆÚç¹Ä¢½¾«Ü·ªA10NÉ1x̦gPÆ¢íê½2023N128úÉçtwyGz[ÉÄçtåwåAíȯåïªJóêܵ½B
©gÉÆÁÄÍüÇãßÄ̯åïÅ Á½±ÆÆÇá\ðT¦Ä¢½±Æà èåÏÙ£µÈªç»nÖü©ÁĨèܵ½ªAnÜéÆInaâ©ÈµÍCÅisµÄ¢« ÁÆ¢¤ÔÉ©ªÌoÔàIíÁĢܵ½B

Ì\à³Iíèܵ½B(«ªsV«¢c)
¡ñÍ¡Nüǵ½¯úÌ\ཀྵÁ½±Æà èAG³êéªà½åÏhðó¯Üµ½B
ܽæyûÌ\É¢ÄA\àeÍà¿ëṉ̃ÆAXChÌìèûâbÌ\¬ÈÇÉ¢ÄàwԱƪ½åÏ×ÉÈèܵ½B

¯åïwp§ãÜöÜ®
(¶©ç)Väæ¶AÜ\æ¶Aáäæ¶

xXgv[^[ܨßÅƤ²´¢Ü·B
(¶©ç)Xìæ¶Anæ¶Asì³öAÁêæ¶A·ªæ¶

X[YÈïÌisðx¦Ä¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½I

WÊ^
ÅãÉNxæèçtåwt®a@ÅåAíÈ2NÚƵĤC³¹Ä¢½¾«Ü·B
ܾܾ×s«ÅçÈ¢±ÆིÀf𨩯µÄµÜ¢Ü·ª¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@ä Yå
æ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï
Âta@ŤCÌ|{Æ\µÜ·B
ÂtŤCðJnµÄ©çÔàÈ1NªoƤƵĢܷB
@ÌÁFƵÄHoLEPÌÇá̽³ª°çêAàúXo±ðÏܹĢ½¾¢Ä¨èÜ·B
èpÉñV½È©ª èAñíÉ[Àµ½¤C¶ðÁĨèÜ·B
ƱëÅAFlÍLxcEjð²¶mŵ天B
{ìÎÛÆÈÁÄ¢éEjÆpüLxcðpµ½æègÝÅA¡í¢ÌdzÍÜ_̱ÆAEjªLxcðH×élqªÂ¤¢AÈÉÈéA¸ÁÆ©Ä¢çêéEEEÆèúIÉoYÁÄ¢é ÌEjÅ·B

æoTF¢ç·Æâ
HoLEPÍåÉ[U[ÉæéBîÌ£ÆA[Z[^[ÉæéBîÌ×ØzøÌHöɪ©êĢܷBͶß̤¿ÍAäNã÷ÇðzøµÈ¢æ¤É×SÌÓð¥¢Èªçs¤KvÍ éàÌÌA£ÉεÄ[Z[VÍǤµÄàn¡ÅP²ÈìÆÉ´¶çêĨèܵ½B
µ©µ éúËRCëܵ½BBîª[Z[^[É×Øzø³êÄä³ÜÍAEjªLxcðH×élqÉAÈñ¾©Ä¢éæ¤ÈCª·éEEEB
»ê©ç[Z[Và£Æ¯¶ç¢yµD«ÈàÌÆÈèܵ½B
å«ÈBîÌ[Z[VðI¦½ÌB¬´ÍÐƵ¨Å·B
Âta@Å̤CàcèÐÆƵÆÈèܵ½ªA¡ãà1Â1ÂÌÇáðåØÉãñÅQè½¢¶Å·B
³ÄAxêιȪçA2022N1119úÉsíê½æ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWïÉQÁvµÜµ½ÌÅA²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B


ïêÍ£bZÛïcê
úÍààN³ñÌCxgÅwüÓÍJtÅØâ©ÈûXÅìêĨèܵ½B


ïêÌlq
êÊèÍ20èÅA½Ì{Ý©çæ¶ûªQÁ³êĨèܵ½B
¼{ÝÌlqâio±Å«È¢æ¤ÈÇáÈÇAåÏ»¡[q®³¹Ä¢½¾«Üµ½B
àÇá\ÅQÁ³¹Ä¢½¾«AåÏMdÈo±ÆÈèܵ½B
ÅãÉú{åwãwåAíÈwnåAíÈwªì@åC³ö@´åæ¶æèOABÉ¢ÄÌÁÊöðèܵ½B
åÏMdÈ\ð èªÆ¤²´¢Üµ½B
¡ãúíÌfÃɶ©¹é椸iµÄQè½¢Æv¢Ü·B
¡ñÌ\É۵ĽåȨÍY¦ð¸«Üµ½æ¶ûÉASæè´ÓµÄ¨èÜ·B
¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨è¢\µã°Ü·B
Èãðà¿ÜµÄæ2ñú{åAíÈwïçtnûïwpWï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B
¶ÓFãú¤Cã@|{ Wq
æ46ñçtåAíȯåïwpWï
ßܵÄA±ÌxçtåwåAíÈÉüÇ¢½µÜµ½nÇêÆ\µÜ·B
ognÍçt§ØXÃsAåwÍOdåwÅA¬cÔ\a@Eçtåw®a@Åú¤CðC¹µA»ÝÍJCHOVhfBJZ^[ŤCµÄ¨èÜ·B
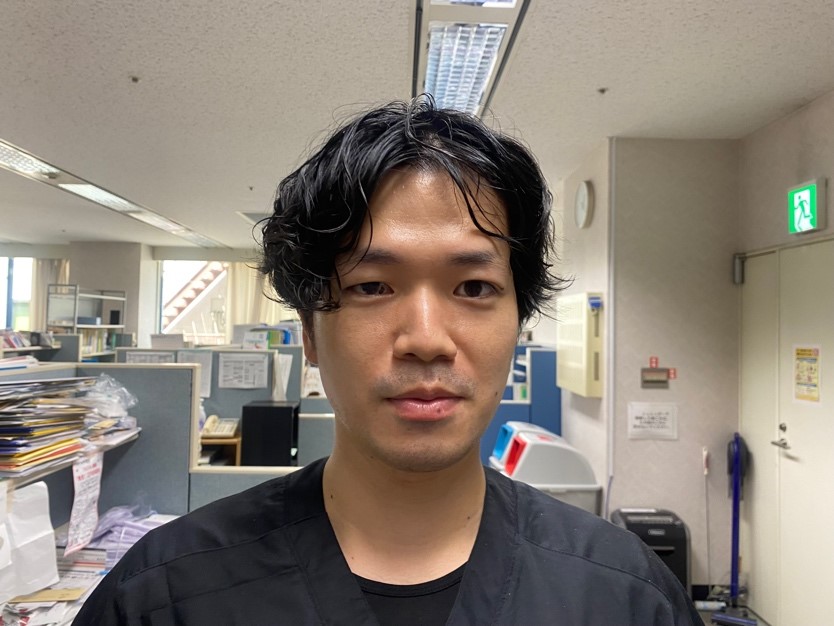
ï¡ÍjOÆOÅ·B
»ÝÍci[ɬ´ÁÄAjOðµÄ¨èA¡N11ÌØXÃÅJóêéANACn[t}\®Éü¯ÄAg[jOðµÄ¨èÜ·B
êûÅA_yą̂XðJ·×A çÎACÉÈÁ½¨XÉüèAúXTÉεñŨèÜ·B
F³ñɲÐîÅ«é¨Xð©Â©èܵ½çA²ñµ½¢Æv¢Ü·B
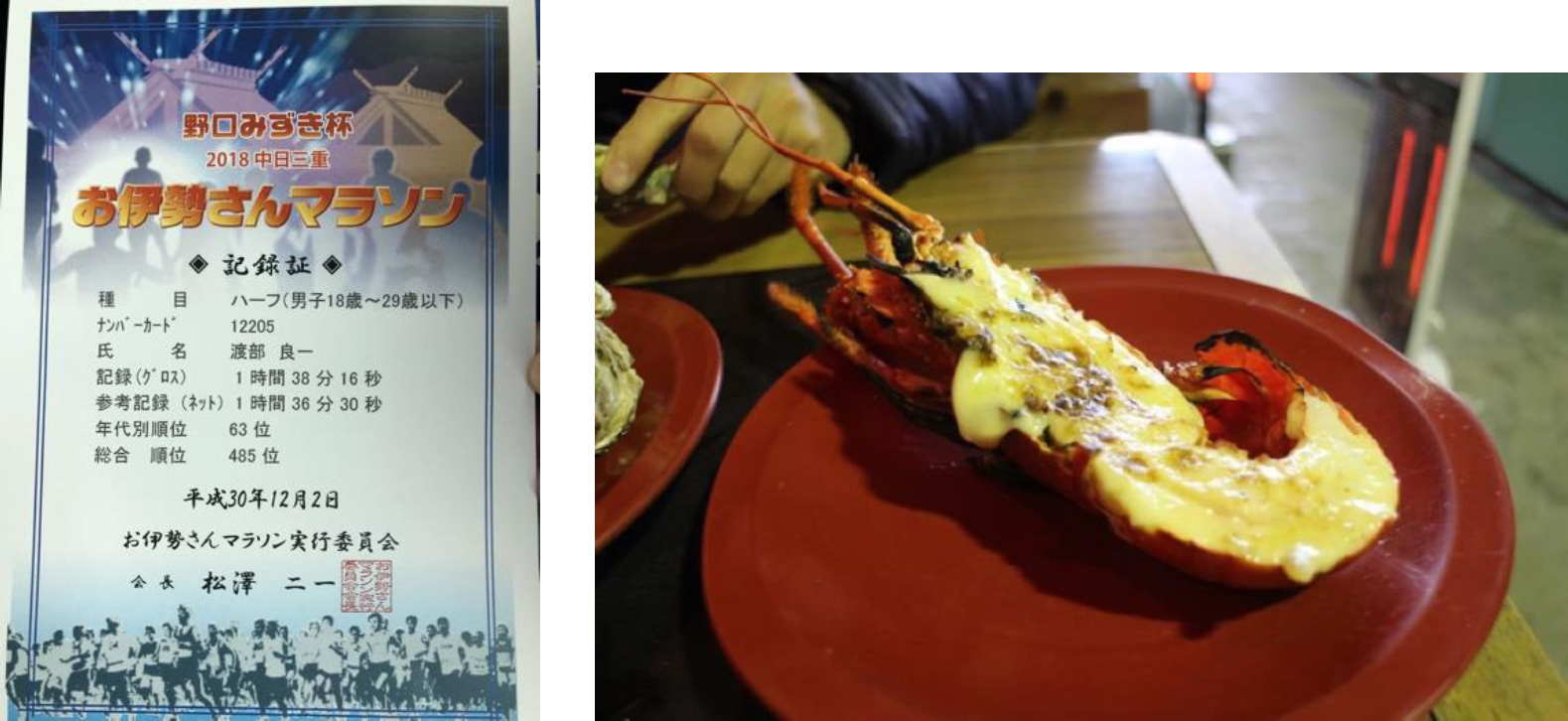
Ê^(¶)Íw¨É¨³ñ}\xÌL^Å·BßÌhõÅ·B
Ê^(E)Íü¡µ¢ð´¦ÄAû̪K¹Å½³êéwɨCVÌ}l[YÄ«xÅ·B
Od§ÉKê½ÛÉÍA¥ñêxH×ÄÝľ³¢I
Ou«ª·Èèܵ½ªAÄ^Á·èžÎÞCóÌAsìæ¶AÜ\æ¶Aâ{æ¶ðͶßÆ·éæ¶ûªA±±OäK[fzeçtuV½vÉ«ð^Îêܵ½B
©gÍßÄ̯åïÌQÁÆ¢¤±ÆÅAââÙ£µÈªçAïêÖÆü©¢Üµ½B
µßÉïêÉüéÆA·ÅÉïêÌÅOñÉÍAsìæ¶Aâ{æ¶Ìwª èA»ÌwÍÆÄàå«´¶çêܵ½B

sìæ¶æèAJïÌ«ðèARiECXÌe¿ÅÈ©È©»nÌÝÅÌQÁªïµ¢Añ̯åïÅÍ»nÌÝÅÌJÃðÚwµ½¢Æ̱Æŵ½B
¼_ïõE÷JÜÌóÜ®ÅÍAàÕ¦ãÈåwr@\Z^[åC³öÌR¼FT涪\²³êܵ½B

Ü\æ¶æènCubg`®ÅÌöÜ®B
~ð¾¦ÎX^[EH[YÌæ¤É§ÌIÈC[WðïêÉeÅ«½çÆÜ\æ¶ÍcOªçêĢܵ½B
»µÄ¢æ¢æAVüÇõÌÐîÖB
â{æ¶æèAMNðòεĢ¯Æ¾íêAVüÇõÉíɪèAæèêwÙ£[hËüI
-ÌÆfÆΩÉæé¯úÐî-
ì@kÌ©çzoomÅQÁµÄê½iCXKCB
ä@StÍ̲ª½B©ªÌMOÍÈ°È¢ºB
ºã@åAíÈÌpassionŹOÈ©çåAíÈðu·B
¡´@cute smileÌDµ¢¨Z³ñB
|{@¯ų́o³ñI¶ÝBüp̹©çãw̹ÖB
Vä@ ¾¼Íu çä¤vBAs[|CgÍAºªå«¢AAA¾¯¶áÈ¢ºB
n@jOªï¡ÅA¡Íci[ÌÔüèBH×éªAçËÎB
§e@±ÌxAêÌppÉBuWÜźw̤ð©ÔB
Rº@QN«ª¾ÓB¢ÂÅàÎçSJB
ª@@¯ṳ́³êLÅ èA¢¶çêLÅà éB
r´@«ê¶ÜêÌuâ©boyB¯úÌ[_[I¶ÝB

¯úÅLOBeB
cOȪç¡ñçêÈ©Á½¯ú̪àrVbÆ[B
ÅãÍAl¼ãÈåwãwåAíÈÌOîG¾æ¶æèwisO§BªñÉηéò¨Ã@ÉÖ·éÅßÌbèxÅÁÊuðµÄ¢½¾«Üµ½B

l¼©çICÅÁÊuI
ܾܾAO§BàÌ¡ÃIðÉ¢Äðªïµ¢Æ´¶Üµ½ªA³Ò³ñÌÐïIwiàl¦ÄA¡ÃIðð·é±ÆàåؾÆwÑܵ½B
Oîæ¶Al¼©ç²uµÄ¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½B

ÅãÍSõÅ[II
ܾܾåAíÈãƵÄçÈ¢±ÆརŷªA`[ŧhÈåAíÈÉÈêéæ¤Éç°iµÄÜ¢èÜ·B
¡ãÆàA²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
ܾܾ³ª±©ÆvíêÜ·ªA¨ÌÉ\ª¨Cð¯ÄA±ÌÄð¨ß²µ¾³¢B
ñA~̯åïÅF³Üɨï¢Å«é±ÆðyµÝɵĨèÜ·B
¶ÓFãúÕ°¤Cã@n Çê
2022/8/4 Chiba Young Urologist Seminar with University Malaya
¨vµÔèÅ·B4©çéåw¿ÎãÃZ^[ÉCµÄ¨èÜ·áäÅ·B
a@Ì és´sÍΪ½AÆÄàóCªãYíÈynÅ·B
³öÌ[Jæ¶Ì¨U¢ð«Á©¯ÉStð·éæ¤ÉÈèܵ½ªAfGÈStêªßɽ éÌÅ[Àµ½Tðß²¹Ä¨èÜ·B
 ¶FáäAö£æ¶(¼Ã®så)A[J³öA¡´æ¶(çt)@EFéØêOæ¶(M²q)Æ
¶FáäAö£æ¶(¼Ã®så)A[J³öA¡´æ¶(çt)@EFéØêOæ¶(M²q)Æ
³ÄA¡ñÍ8ÉJóê½æ3ñChiba Young Urologist SeminarÉQÁvµÜµ½ÌÅA²ñð³¹Ä¸«Ü·B
±ÌZ~i[ÍáèåAíÈãðÎÛÉèúIÉJóêÄ¢éÌàÌÅAðNÍ`åwÆR{³¹Ä¸«Üµ½B
Ú×Íäæ¶ÌLð²Qƾ³¢B(æ2ñ@Chiba Young Urologist Seminar@2021/10/7¬ze~}[)
¡ñÍ}[VAÌ}åwÆÌR{ÅAáN¯lpêÅÌÛZbVŵ½B
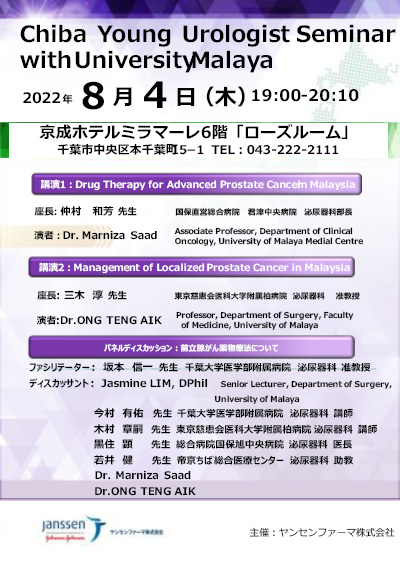
¡ñÌvO

NAv[Æq¢ÅÌweb~[eBOŵ½@SÂRrÌâ{æ¶Eºæ¶
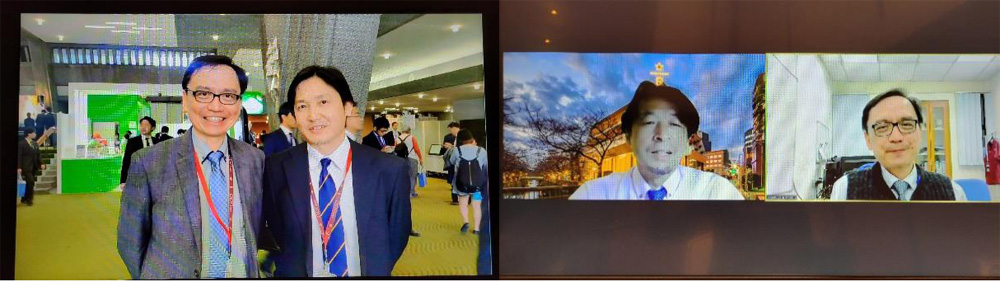
¶Fâ{æ¶ÆeðÌ[¢Dr. Ong@@EFbãåÌOØæ¶Éà²QÁ¸«Üµ½
Dr. SaadâDr. Ong̨bÌÅóÛI¾Á½ÌªA}[VAàÅÌ[LOO[v̨bŵ½B
²©gÌNjbN©çåwa@E¤{ÝƧÉAgµÄÓ©ð·ðs¢ÈªçA½EíÅÌJt@XàåóêĨèA{[_[XÈ®©ç}[VAÌãÃðx¦Ä¢élqªí©èܵ½B

}[VAàÅÌ[LOO[vÌlq
ܽAda VincįbàÕŵ½B
da VinciVXeÉæéèpÍ¢E67©Ì6700{ÝÅA±êÜÅÉ1000síêÄ¢éªA}[VAÉÍܾP䵩±ü³êĢȢÆ̱Æŵ½B
»Ì½ß{bgèpªó¯çêé³ÒÍÀè³êĨèAzÈãÃïð¥¦é³ÒÌݪDæIÉó¯çêéóµÅ éÆ̱Æŵ½B
à¿ëñJ â o¾ÅÌèpÍsíêĨèAÇáIðð«¿ñÆ·êλêÅàÈñÆ©ÈÁÄ¢éÆ̨bŵ½B
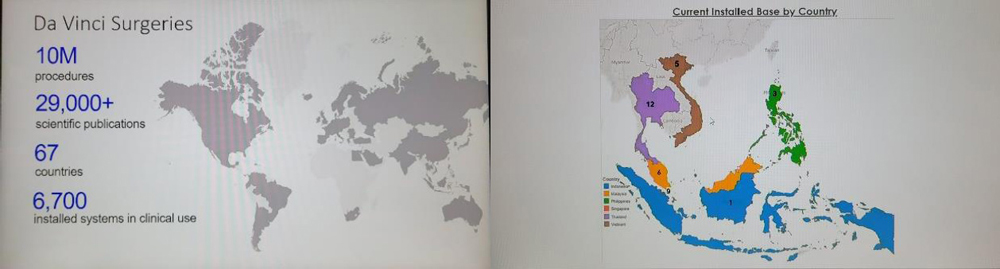
¶F¢EIÈdaVincièpE±üÈÇ@EFìAWAɨ¯édaVinci±ü
UèÔÁÄÝéÆAú{Åà10NOÜÅͽèOÉJ â o¾ÅÌO§BSEªsíêĢܵ½B
µ©µA ÁÆ¢¤ÔɽÌda Vinciª±ü³êA¢ÂÌÔÉ©{bgèpªj
[X^_[hÆÈÁīĨèÜ·B
}[VAÌlû3200lÅda VinciPäÉεÄAú{Í12000lÅ450äAçt§630lÅà15äÙÇ èA¢©É}¬ÉZ§µÄ«Ä¢é©ªí©èÜ·B
à¿ëñAèp̸xðßéf°çµ¢@BÅÍ éÌÅ·ªA1ä2~ANÔÛïª2000`3000~©©èAú{ÌãÃoÏð¥Ü¦ÄFXÆl¦³¹çêܵ½B
±üµ½daVinciðǤp·éÌ©ASÌƵÄdaVinci̪zðǤRg[·éÌ©AlXÈÛèª éæ¤Évíêܵ½B
ã¼Í}åwÌæ¶ûÆO§BàÌgvbgÃ@(zÃ@+VKzò+»wÃ@)É¢ÄfBXJbVðµ½ÌÅ·ªAXs[h´Ìá¢É³|³êܵ½B
l¦½±Æð®µÄ¦ÀÉpêÅM·éÍA\»Í̳ÉÁ©³êܵ½B
ðÜßå½Ìú{lÍAú{êÅvlðµÄp¶ð\¬µÄ©çb·½ßÉuͪoܹñªA}[VAÌæ¶ûÍbµÈªç»ÌêÅb·àeð\¬Å«Ä¢é(pêÅvlÅ«Ä¢é)æ¤È´¶ª èܵ½B
¯¶AWAÅ·ªAi©çÌpêÖÌæègÝûâpê³çÉà·ª éÌ©àµêܹñB
ܽAäX໤È̾Æv¢Ü·ªAAWAÁLÌæaèà èA»¤¢Á½pêð·«æéÍÉàÛèð´¶Üµ½B

fBXJbVÌlq
¡ñÍvXÌpêÅÌfBXJbVÆÈèܵ½B
RiÐà ÁÄÛwïÌQÁªïµÈèACO©ç̳ҳñà¸éÅApêðg¤@ïªIɸÁÄ¢é±ÆðÀ´µÜµ½B
»ë»ëCOo£àÂ\ÉÈÁÄ«»¤ÈÌÅAܽpêÅÌ\ªÅ«éæ¤webpïbÉʤ±Æð§©ÉӵĨèÜ·B
AWuHDMMHÀÁÄ¢éÌÅÇȽ©¨©ßª êγ¦Ä¾³¢B
ÅãÉA±Ìæ¤ÈMdÈ@ïð^¦Ä¾³Á½â{æ¶Éúäç\µã°Ü·B èªÆ¤²´¢Üµ½B

»nQÁÒÌWÊ^@jVrÈlª¢Ü·
¶ÓFéåw¿ÎãÃZ^[@³@áä
æ1ñ@ú{åAíÈwïçtnûïwpWï
ÝȳÜͶßܵÄI
åAíÈüÇ1NÚÌVäT¾YÆ\µÜ·B
»ÝD´s§ãÃZ^[ŤCð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
æúJóêܵ½æ1ñú{åAíÈwïçtnûïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
¡ñàèð峹Ģ½¾¢½Æ±ëAæêÒÆ¢¤åðð¹©èܵ½B
ͶßÄÌnûïÅEà¶àª©çÈ©Á½ÌÅAi©ç²w±µÄ¾³ÁÄ¢éäæ¶Ék¢½µÜµ½Æ±ëAnû覆èãªéæ¤ÈXChðAÆÌAhoCX𢽾«Üµ½B
úíÌƱÌTçAXChì¬Éæè|©èܵ½B
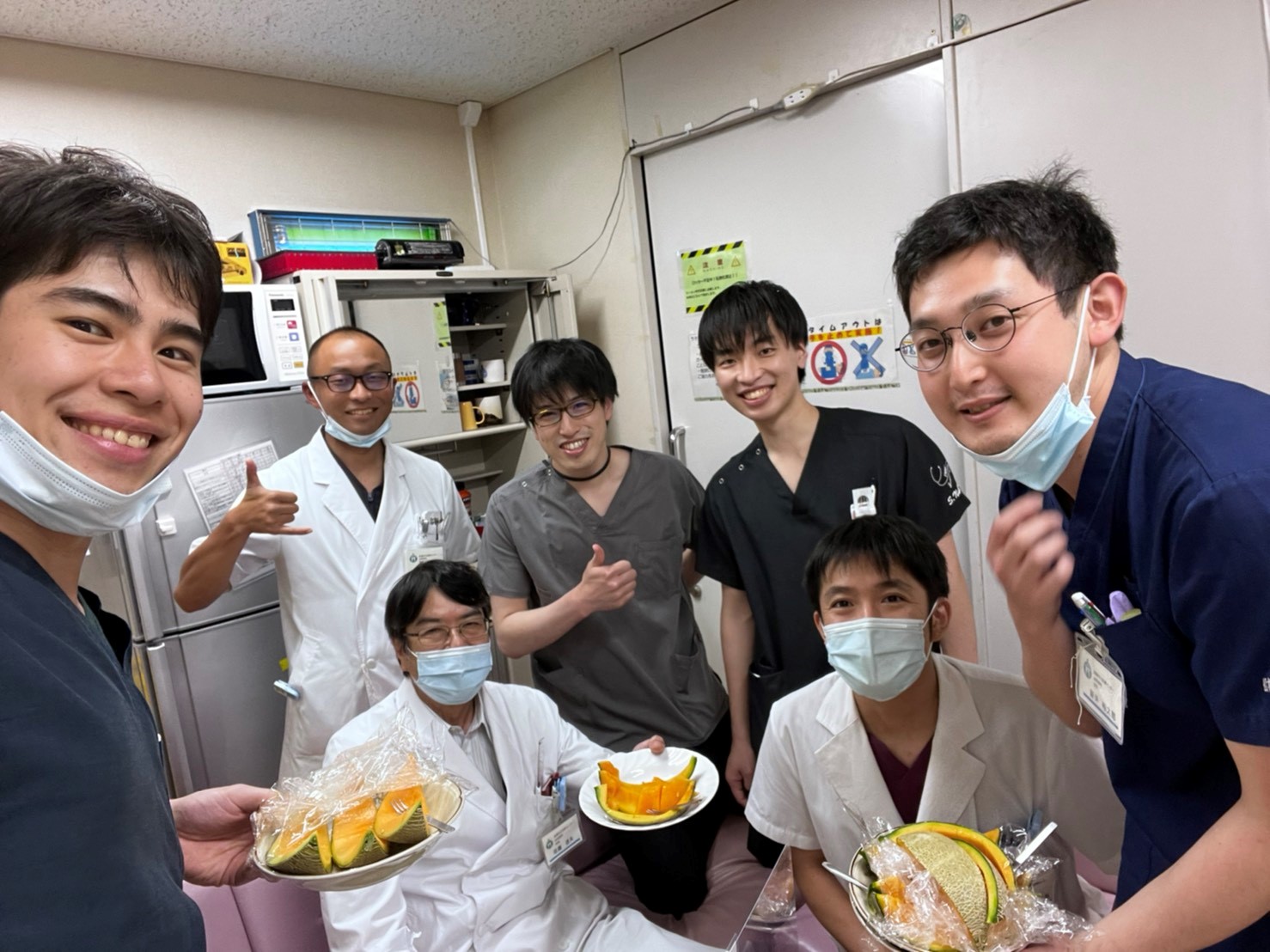
¢ÂਢbÉÈÁÄ¢éD´s§ãÃZ^[åAíÈÌæ¶ûÆiEj
·Å 鲡æ¶Ìa¶úð¨j¢µÜµ½
»¤±¤·é¤¿Éæêñçtnûïúð}¦Üµ½B
ïêÍ£bZÛïcêŵ½B
ÛW¦êÅACxgà¯JóêÄ¢ÄAïêüÓÍX[cpÌlÅìꩦÁĢܵ½B
SõçtnûïQÁÒ¾Æv¢ñÅ¢½ÌÅCâµ»¤ÉÈèܵ½B

ïêÍ£bZÛïcêÅ·
æ23ñú{³í³
ªÇwïà¯JóêĢܵ½
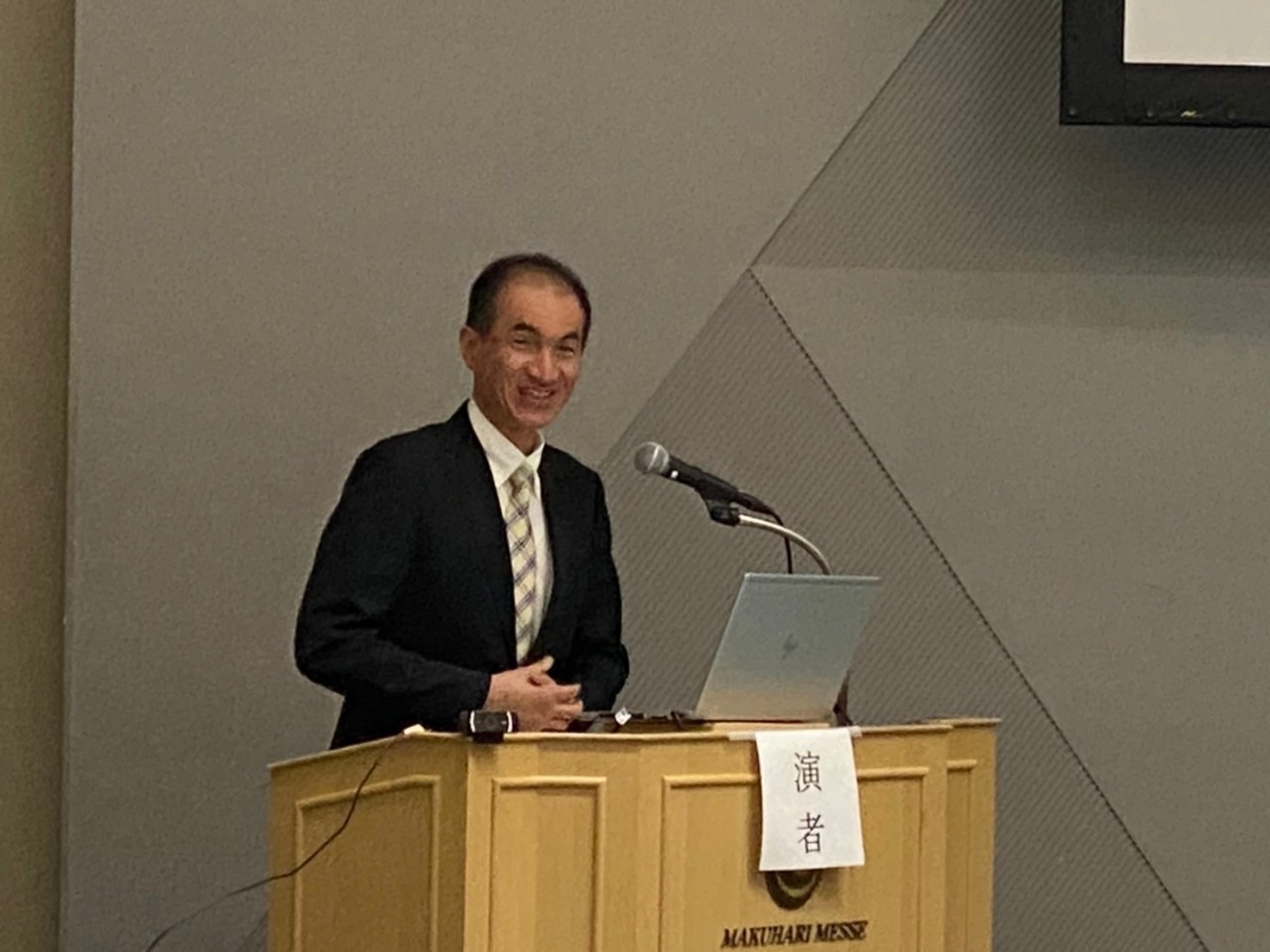
sìæ¶æèJïÌ«ð¸«Üµ½@NN

ÁÆ¢¤ÔÉÌ\ÌԪĵܢܵ½
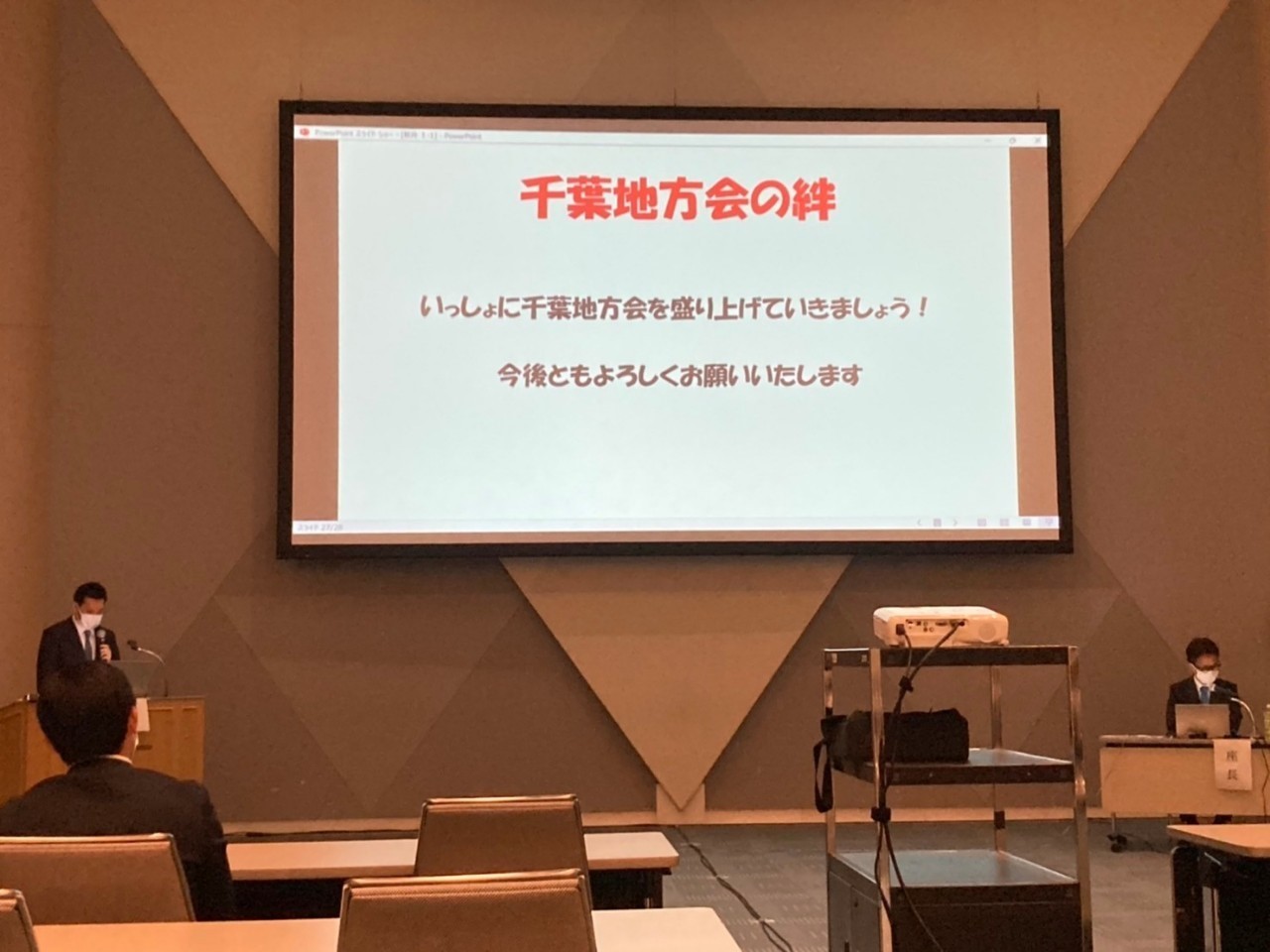
çtnûïÌãJ@æ뵨袵ܷI@Æ¢¤±ÆÅ\ͳI¹µÜµ½
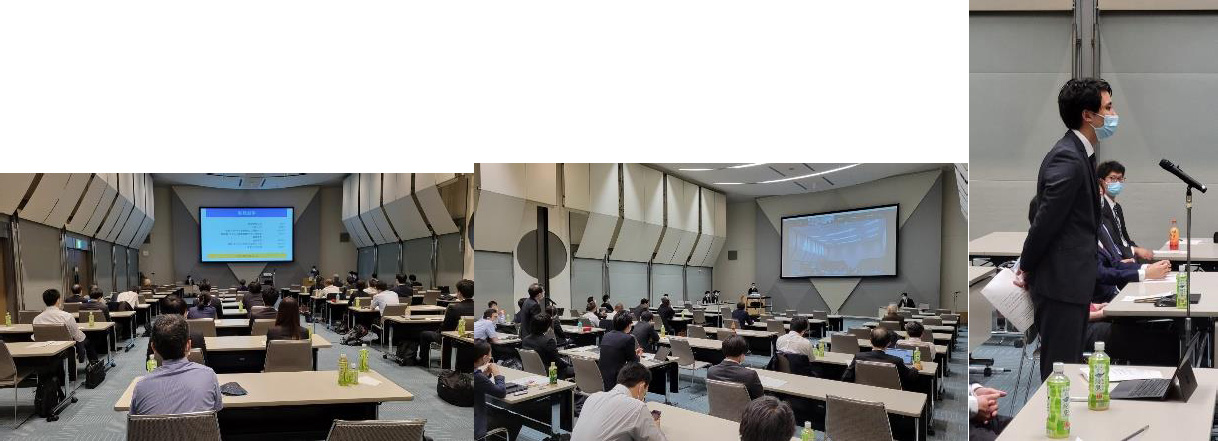
êÊèÌåÍ22èAÉàÌÚèܵ½@¿âàòÑð¢å·µÅµ½
¯úÌr´æ¶às¢¿â𰩯Ģܵ½
¡ñAçtåa@âçtåÖAÌsa@ðͶßAbïãÈåwt®a@AMåwãÃZ^[²qa@AV°åwt®YÀa@Aú{ãÈåwçtka@AÛãÃåw¬ca@AqãÈåw®ªçããÃZ^[Aéåw¿ÎãÃZ^[ÈÇñíɽÌ{Ý©çQÁµÄ¢½¾«Üµ½B
åwÌ_ªð´¦AgOne TeamhÅ é±ÆðÀ´·é±ÆªÅ«Üµ½B
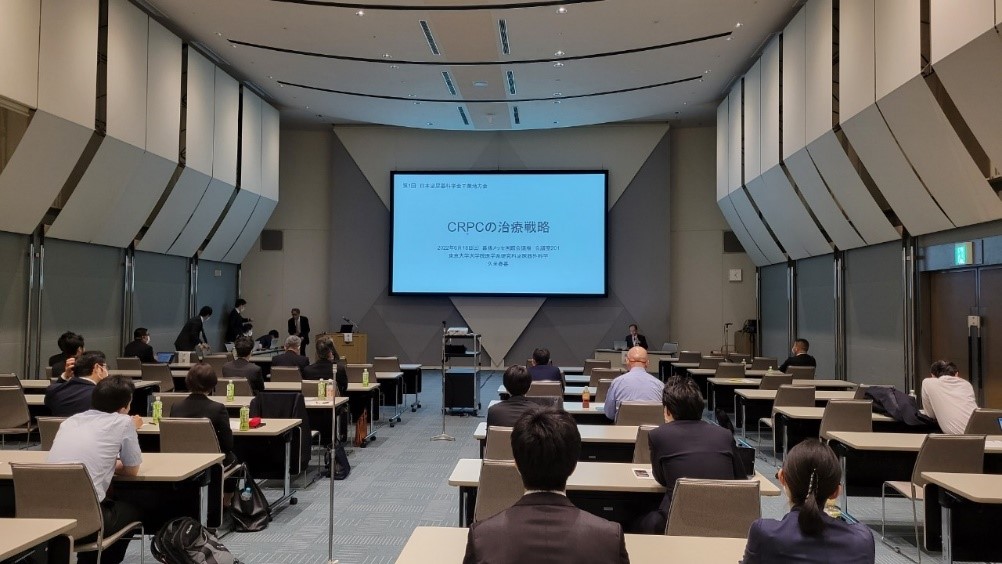
ܽåwãw åAíÈw³º ³ö vÄ tì 涩çÍCRPCÌ¡ÃíªÉ¢ÄÁÊöðµÄ¢½¾«Üµ½B
åÏMdÈ\ð èªÆ¤²´¢Üµ½B

ÅãÉWÊ^
[IÌ|[YÅ·ËI

¡ºæ¶ðͶßƵÄ^cðµÄ¾³Á½çtåÌæ¶û@{ɨæêlŵ½I
èªÆ¤²´¢Üµ½I
ÈãÅæêñçtnûï̲ñƳ¹Ä¢½¾«Ü·B
½³ñÌ\ð·±ÆªÅ«ÄAåÏMdÈo±ªÅ«Üµ½B
ßÄÌnûïÅ èËf¢ÌA±Åµ½ªAi¨¢bÉÈÁÄ¢éD´s§ãÃZ^[Ìæ¶ûAçtåa@Ìæ¶ûÉà²Í¢½¾«©gà³É\ðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
èªÆ¤²´¢Üµ½B
±Ìo±ð¤C¶âúífÃÉඩ·±ÆªÅ«éæ¤æ£ÁÄÜ¢èÜ·B
¡ãÆà²w±ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@Vä T¾Y
Urology Today in Chiba 2022
FlAßܵÄI2022NxüÇÅçtåwãw®a@α̪´iÆ\µÜ·B
ܸÍy©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«Ü·B
ogåwÍmåwÅ·B
ÜíèÉÍìƨÆRµ© èܹñI
åwÜÅ̹ÌèÍáiãÌáÌòj¾ç¯ÈÌÅAûÌÉáªüèȪçàÈñÆ©ÊwµÄ¢Üµ½B
»êÅà¨ðâhgͨ¢µA¡v¦ÎZßÎs¾Á½ÈÆv¢Ü·B

¶ÍmÅC`IV̨Xu¸vÌ̽½«Å·B
EÍÆÌÚÌOÌiÅ·B
²ÆãͳiHjçtÉAèAú¤CÍ϶ïKuìa@ÉsÁĨèܵ½B

¶©ç϶ïKuìa@ÌR£æ¶A¯úÅ»ÝD´a@Ìäæ¶AÅ·B
»ÌãçtåwåAíÈÉüǵAçtåwÅåÏ[Àµ½¤Cðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
³Ä©ÈÐÈèܵ½ªA¡ñÍUrology Today in Chiba 2022ÉQÁ³¹Ä¢½¾¢½ÌÅ»Ìlqð²ñ¢½µÜ·I
Urology Today in ChibaÍçtåwåAíÈÉ»¡Ì éw¶³ñâüÇðl¦Ä¢éú¤CãðÎÛÉNsíêÄ¢ésÅ·B
ðNÍRiÌe¿ÅWebJÃŵ½ªA¡NÍïêQÁÆZoomQÁÌnCubg`®Åµ½B
ïêÍI[NçtzeED´ãÃZ^[E¡lJÐa@Ì3 èA»nQÁÍv53¼AICQÁÍ33¼ÅAãw¶6¼Æú¤Cã10¼ªQÁµÜµ½B
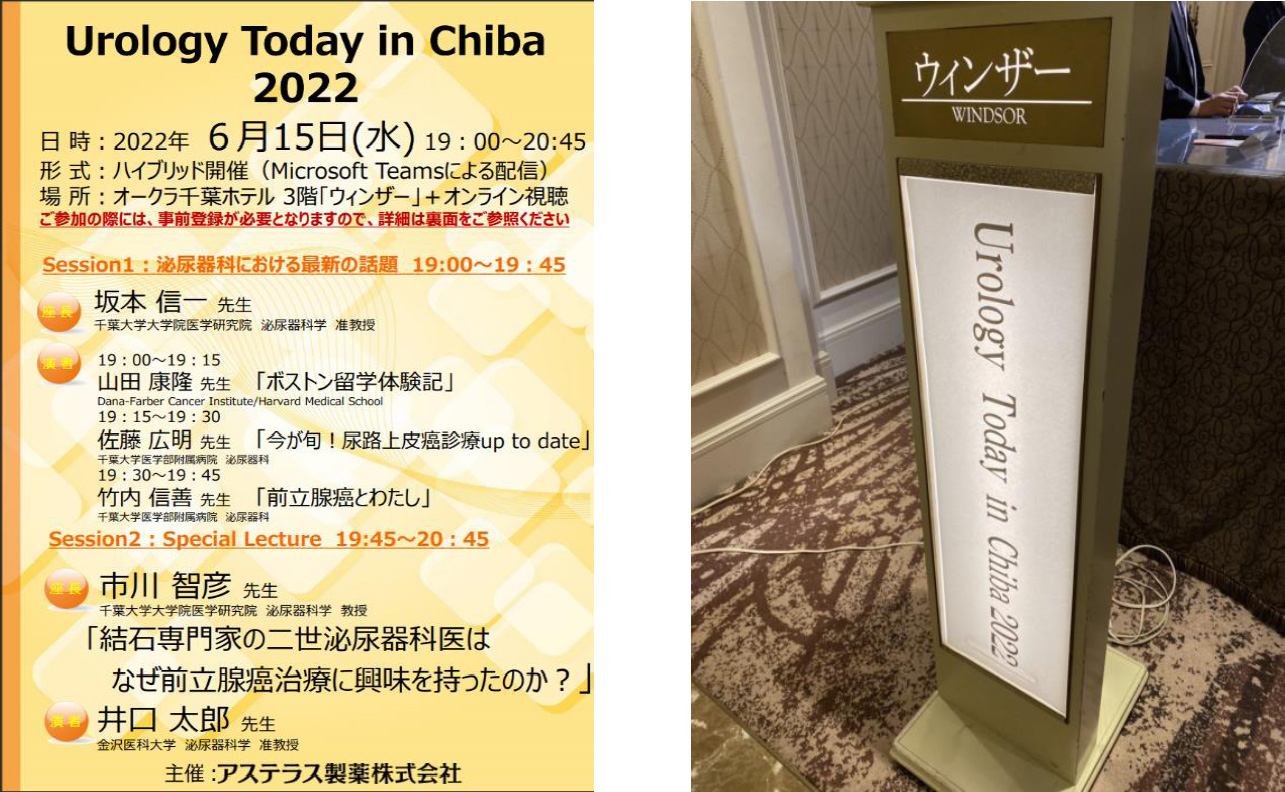
O¼ÍRcN²æ¶A²¡L¾æ¶A|àMPæ¶Ì²uÅAçtåwåAíÈÉ¢Ļê¼êñíÉj[NÈÏ_©ç²ÐîµÄ¾³¢Üµ½B
ïê̵ÍCÍÆÄà·©Aw¶³ñâú¤CãÍçtåwåAíÈ̵ÍCð´¶æê½ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·I
Rcæ¶Ì²uÉÍÔÉí¸AcOȪçq©·é±ÆÍūܹñŵ½ªA{Xg¯wÌlqÉ¢IJñµÄ¾³Á½»¤Å·I

À·Ìâ{æ¶@@@@@@@@@@@@@@ïê̵ÍC

²¡æ¶Ì²uu¡ª{IAHãçàfÃup to datevÅ·B
è¼ÊèA²¡æ¶Ì²uÉÍu{vªlÜÁĢܵ½B
{Ìδâ{ÌåAíÈͱê©çà·èãªÁÄ¢«»¤Å·ËI

|àæ¶Ì²uÅ·B
¿[ÎñªäNã÷ÆO§BÌ`ÉÄ¢éÆ¢¤aV·¬éØèû©çu¿[Îñ in ¿[ÎñvÆ¢¤¼¾ðìèAïêÍå·èãªèŵ½I

ã¼Ísì³öÉÀ·ªÏíèAàòãÈåwåAíÈwy³öÌäû¾Yæ¶Ì²uŵ½B
O§Bà¡ÃÌIðÍlXÅ·ªA³Ò³ñÌó]Éí¹Ä_îÉεĢKvª é±ÆðwÑܵ½B
©ªÍ¡Nxã¼úÅA`[É®³¹Ä¢½¾¢Ä¢é½ßAO§BàÉÍܾ ÜèGêĨèܹñªAB`[ÅÌfÃàyµÝÉ´¶Üµ½B

ÅãÉI[NçtzeïêÌSõÅÊ^ðBÁÄðUÆÈèܵ½B
QÁµ½ú¤CãÌÉÍA¤CããÌãyâZ̯¶âOÎæÌãyÈÇÌmè¢à½ANÇñÈãyªüǵÄéÌ©úÒ·éƯÉA±ÌlÉ¢Ģ«½¢Ævíêéæ¤ÈæyÉÈé½ßÉ¡ãà¸iµÄ¢«½¢Æ´¶Üµ½B
·XƸ碽µÜµ½B
çtåwÅ«nßÄ4©ªoƤƵĨèAܾܾª©çÈ¢±Æ¾ç¯Å·ªAúX¬·ðÀ´µÄ¨èÜ·B
ããÌæ¶ûÉÍ¢ÂàJȲw±ð¢½¾¢Ä¨èA{É´Óµ© èܹñI
2NÚÌæyûÉàåϯçêĨèÜ·B
¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·I
¶ÓFãú¤Cã@ª ´i
New Generations Prostatic Night vol.2@¬ze~}[
F³ñ±ñÉ¿ÍIåw@mÛö3NÌâV¡S½Æ\µÜ·B
µ¸ÂÄÌCzªßâī½¡ú±Ì Å·ªAFl¢©ª¨ß²µÅµå¤©BSIÉRñÚÌN`ÚíàLªèA±Ì·¢V^RiECX´õÇÆÌí¢Éàó]Ìõª©¦Ä«½ÅAµ¸ÂÅÍ èÜ·ªÎÊÅÌ×ïÈÇÉàQÁÅ«éæ¤ÉÈèAåÏðµvÁĨèÜ·B
³Ä±ÌxAáèåAíÈãðÎÛƵ½O§Bà¡ÃÉÖ·é¤ïuNew Generations Prostatic Night vol.2viÊÌFviCjÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B¤ïÍïêQÁÆzoomÉæéICQÁÌnCubh`®ÅJóêܵ½BúÍçtåwÉÁ¦AD´s§ãÃZ^[Açt§ªñZ^[AbïãÈåwa@Aú{ãÈåwçtka@ÈǽÌåAíÈÌæ¶ûªQÁ³êÈc_ªsíêܵ½B
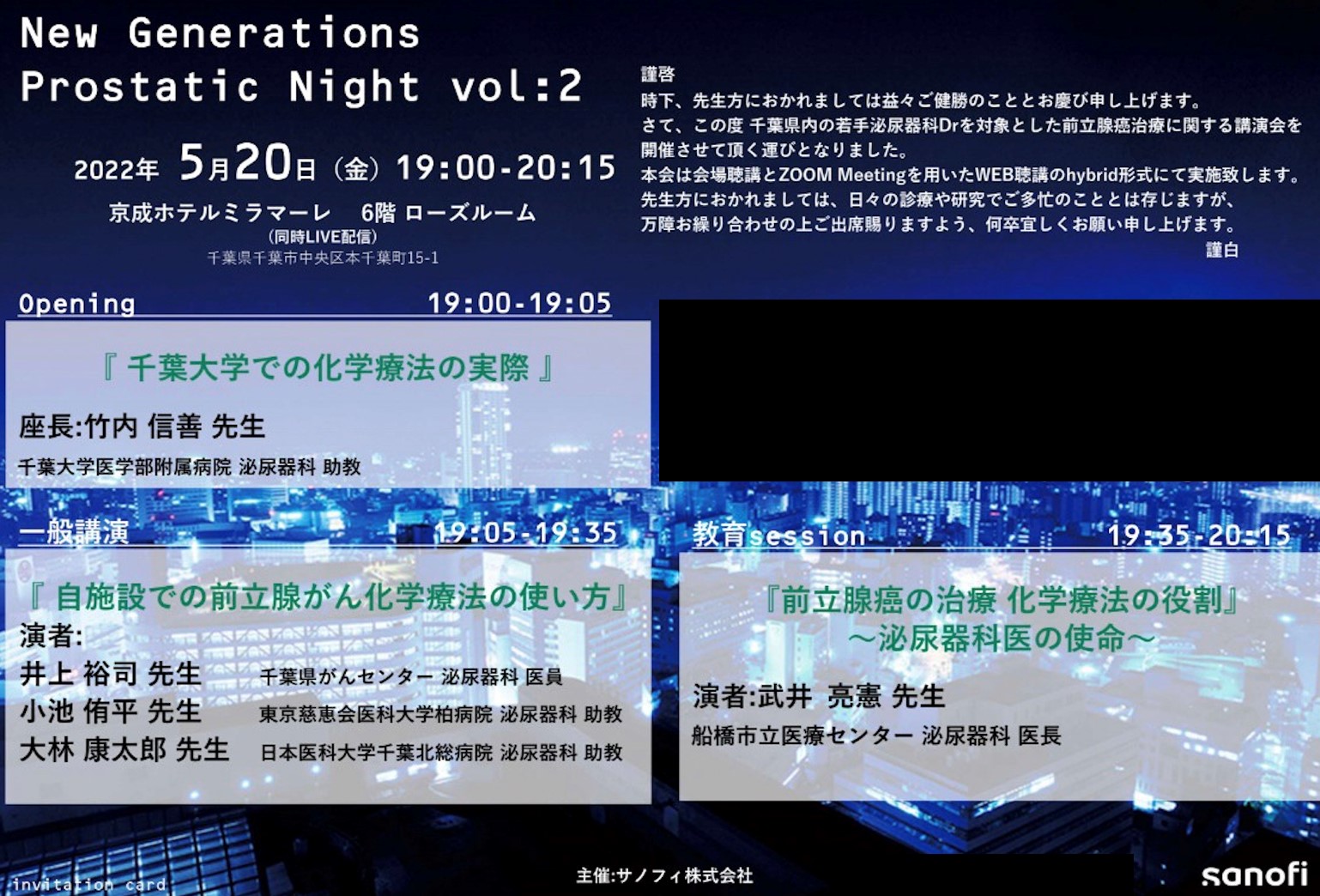
úÌuïXPW
[
uL^æèL¯ÉcéïvðRZvgÉAÀ·Ìçtåw|àæ¶ÉæéïêSÌÌSðhÍÝÉ·éj[NÈopeningɱ«Ae{ÝÌO§Bà¡Ãɨ¯é»wÃ@Ìgp@É¢Ä\ª èܵ½B¯¶RªñÜÅàe{ÝÉæèü@AOÆ^û@ªÙÈéÀÛðmé±ÆªÅ«åÏ×ÉÈèܵ½B

À·Ì|àæ¶@@@@@@@@@@@@@@@@@@úÌïê̵ÍC

çt§ªñZ^[αůåÌäãæ¶F¤¢ÌÊ^ƤɻwÃ@ÌÀÛð¨bµ³êĢܵ½I

bïãÈåw®a@̬ræ¶Fu©ç¢EÖvM¢X[Kð¨¿Åµ½I

ú{ãÈåwçtka@ÌåÑæ¶F©{ÝX^btðÆ©Ì_ÅÊÐîµÄ¾³¢Üµ½I
»µÄ³çsessionÅÍD´s§ãÃZ^[Ìäæ¶æèuO§BàÌ¡ÃE»wÃ@Ìð`åAíÈãÌg½`vÆ¢¤^CgÅu𢽾«Üµ½B

CÌüÁ½ÅMu³êéäæ¶
uÌ`ªÅÍA¡ðÆ«ßZ¢ãi1990N¼Î©ç2010Nã¶ÜêÌ¢ãÅîñMEûWð¾ÓƵA±ê©çÐïÌSÆÈÁÄ¢lXjÉÖ·é¨b𢽾«A½¿åAíÈãàãþ¯ÅÍÈAîñÌMâûW\ÍÉà·¯½¶ÝÖÆi»µÄ¢©ÈÄÍÆ¢¤¢g½´ðo¦Üµ½Bã¼ÉÍA³Ü´ÜÈòÜÉæè¡G»µÄ¢éO§Bà¡Ãɨ¯é|CgÉ¢Äu¢½¾«A¾ú©çÌfÃÉÂȪéñíÉLÓ`Ȩbð·±ÆªÅ«Üµ½B

uïãÉSÌÅLOBe@¦BeÈOÍ}XNð
pµÄ¨èÜ·B
¡ñ̤ïðʶÄAçtåwÌÖAa@ÈOÌæ¶ûÆàð¬ð[ßé±ÆªÅ«Üµ½BO§BàðÜßAæèæ¢fÃ̽ßÉÍãÃÒ¯mÌÇDÈÖW«Ìm§ªs¾Æl¦Ü·Bäæ¶ÌuÉà èܵ½ªAæ1ñviCÉQÁ³ê½bïãÈåwa@åAíÈöàVæ¶Ì¨¾tu³Ò³ñðHappyÉIvA±±ÉSĪlÜÁÄ¢éÆ´¶Üµ½B
©gAãwIÈm¯Íà¿ëñsÂÅ·ªAlÆÌqªèðL°AãtƵÄlÔƵÄæèêw¬·Å«é椱ê©çàfÃA¤ÉãñÅ¢«½¢Æv¢Ü·ÌÅAFl±ê©çà²w±²Ú£Ìöæ뵨袢½µÜ·B
åAíÈÉ»¡Ì éw¶³ñâ±ê©çÌiHƵÄl¦Ä¢é¤CãÌF³ñAçtåwåAíÈÌbg[Å éhOne TeamhÆÈèAçtÌãÃAú{ÌãÃðêÉ·èã°Ä¢«Üµå¤I
¶ÓFåw@¶@âV¡ S½
a@·\²ÌóÜñ
çtåwãw®a@a@·\²ÌóÜÉ«Aâ{Mêy³öæèåAíÈÊMÌñeð²E¢½¾«Üµ½ÌÅAMðÆç¹Ä¢½¾«Üµ½B²ËqaÆ\µÜ·B
ÍAitàEäNã÷àÌfÃâ¤ðS³¹Ä¢½¾@諾AúXO[vÌo[ɯÄàç¢ÈªçǤɩâÁĨèÜ·B{bgxèpâ¡G»µÄ¢éSg¡ÃÌe¿à è@ÅÌà¡ÃÌÓ±Íå«ÈÁÄ¢éÆ´¶Ä¢Ü·B³Ò³ñÌÐîɨ«ÜµÄÍÖAa@Óßß×Ìæ¶É±Ìêð¨ØèµÄäç\µã°Ü·BJ èpâ o¾èpÅÍΪﵢêà{bgxèpÅ êÎÎÅ«é±Æà½X èAèpÌNIeB[ªüãµÄ¢é±ÆðÀ´µÄ¨èÜ·BܽX^btÌæ¶ÉàèðʵÄèpÌHöâèZÌÓ`ððµÄàçÁ½Ì¿ÉApÒðÏÉIÉsÁÄàçÁĢܷB
æqÌÊèAÐî³ÒÌÁà ètàEäNã÷àÌ{bgxèpÌ\èÍ5©öxæÜÅÜÁĨèAfÃÈàÌæ¶Éà½åȲS𨩯µÈªçA³Ò³ñÉ¿Ì¢¡ÃðKØÈ^C~OÅñÅ«éæ¤ÉæègñŢܷBèp³ÒÌÁͽ¾èpªåÏÉÈ龯ÅÍÈAüpúÌÇâAð¡ÌãÃÀSÌÓ¯Ìüãðl¶µ½×â©ÈCtH[hRZgªKvÅ·BÐÆÌOÆär·éÆ1Çá ½èɨ¯éÎÔª¦Ä¢Ü·BOfÃɨ¯éX^btêlÌSÍåÌêrð½ÇÁĨèÜ·B»êÉÁ¦COVID19Ìe¿Åü@³Ò§ÀâRiÎô`[ÖÌlõhà èܵ½B
»±ÅsìqF³öɲw±ð¢½¾«ÈªçAVä²V³A²¡L¾³ðͶßçtåw̽ÌX^btÌtH[𢽾«A·ÔÌc_ðdËAäNã÷àÉηé»wÃ@GCÃ@ɨ¯éÝÍÜa@ÆÌaaAgAtàpãÌæoßÏ@ɨ¯é¯åÌNjbNæ¶ûÆÌafAgðJnµÜµ½B½ÌÖAÌæ¶û̲sÍðèJn·é±ÆªÅ«Üµ½B¯åÌæ¶û̲ðÈçÑɲ¦ÍȵÅÍißé±ÆªÅ«È©Á½vWFNgŲ´¢Ü·BSæèäçð\µã°Ü·BK¢Éà±êçÌæègÝð]¿¢½¾«A±Ì½Ñuçtåwãw®a@a@·\²vð2021NÉÝÍÜa@ÆÌAgA2022NÉNjbNÆÌtàpãoßÏ@AgÉ«óܳ¹Ä¢½¾«Üµ½BÊ^ÍVäæ¶A²¡æ¶ÆêÉÜó𢽾¢½ÉBeµ½àÌÉÈèÜ·B2lÌæ¶ÉÍA©gª`[ÌN·ÒÆÈÁ½Æ«©çêÉêyðÆàÉo±µA`[ðOi³¹é½ßɽåÈsÍðµÄ¢½¾«Üµ½B³¼©ÈèæêÄ¢éÆv¢Ü·BúêÉdðµÄ¢é½ßAÊÆü©ÁÄäçð`¦é±Æ͵ÆêL¢Å·ªA±Ìêð¨ØèµÄ´ÓÌÓð¨`¦³¹Ä¢½¾«Ü·Bܽ¡ãàiæ뵨è¢\µã°Ü·B
æè¯ßàÈ¢¶ÍÉÈÁĵܢܵ½ªA¡ñÌóܾ¯ÅÍÈAªâÁÄ¢édÍAüèÉ¢éæ¶É¯Äàç¢Èªç¬è§ÁÄ¢é±Æð±Ì¶Íð쬵Ģé¡àÉ´µÄ¨èÜ·BêlÅAÅ«é±ÆÍ{ɬ³¢±ÆÅ·ªAÌüèÌX^btÆêÅ êΡãà³Ü´ÜÈÛèÉ`WÅ«éÆmMµÄ¢Ü·B¡ãÆàæ뵨è¢\µã°Ü·B

¶©çVäæ¶A²ËA²¡æ¶
¶ÓFut@²Ë qa
åAíÈXNuvæ&tbV }¯×ï
FlͶßܵÄB
ðNxæèüÇ¢½µÜµ½nç²LBÆ\µÜ·B
¢àÌÅåAíÈƵÄαµÄñ1NÔo¿Üµ½ªAßÍí©çÈ¢±Æ¾ç¯Åµ½ªæyûÌw±Ì¨©¯Åµ¸ÂÅ·ª¬·ð´¶çêé[Àµ½1Nðé±ÆªÅ«Üµ½B
LÉ槿ܵÄÌ©ÈÐîð³¹Ä¸«Ü·B
ogåwÍçtåwÅú¤CÍ϶ïKuìa@ÅsÁĢܵ½B
ðNxÍåwa@ÅêUãƵĤC³¹Ä¢½¾«Üµ½B¡NxæèNÃa@ÉαµÄ¨èÜ·B
w¶ãÍd®ì
É®µÄ¨èAâ{æ¶ðnßƵ½½³ñÌæyûªåAíÈÉüǵĢܷB
åAíÈüÇãà`[v[Ìdv«ðÉ´·éúÅAg¤_ªobg©çà®Je[eÉÈÁÄàª{ͯ¶¾ÈÆÉ´µÄ¨èÜ·B
³ÄA¡ñÍåAíÈƵÄXNuð쬵½ÆA3É Á½tbV
}¯×ïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
NÃa@Ìãǧ¿ã°ÌÛÉXNuð쬵½ÆÌîñð¨Éµ½â{æ¶ÌACfAÅn®µ½åAíÈXNuvæÅ·ªAæú[i³êܵ½B

¶)t}âáäæ¶Aâ{æ¶ÆÓ©ðoµÁÄfUCµ½XNu
E)XNuì¬ÇÌáäæ¶Ænç²
»Ýåwa@ÍAÇABÇÅÊêĨèÜ·ªA±ÌXNuð
ÄOne teamƵÄíɦ͵ȪçúXfÃðµÄ¨èÜ·B
XNuÌwÊÍuChiba University Hospital Urology TeamvÆVvÈÌÅA¯åÌæ¶ûÉà
ĸ«â·¢àÌÉÈÁĢܷB
¡N¢ÁÏ¢ÍÇÁàó¯t¯Ä¨èÜ·ÌűÌLð©Äµ½¢ÆvÁ½ûª¢Üµ½çÜŲA¨è¢µÜ·I
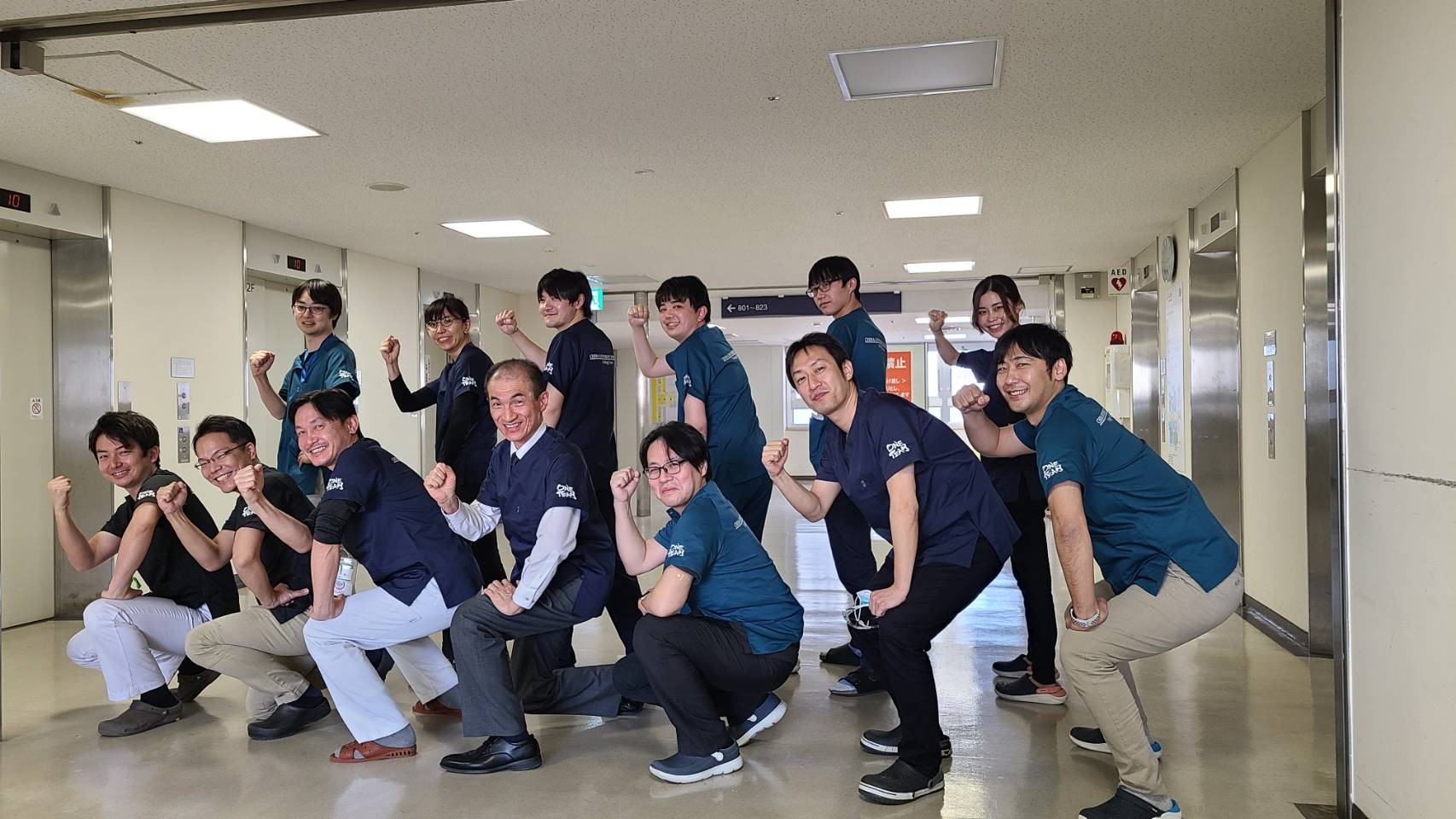
åAíÈXNuÅ[Ì|[YðÆéåAíÈê¯
±«ÜµÄæ2ñtbV
}¯×ïÉ¢Äñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
OñÉø«±«çtåwãw®a@ANÃa@AD´ãÃZ^[Ì3a@ðzoomÅq¢Åsíêܵ½B
¡ñÍNÃa@óûæ¶ÉæéHoLEPÌu`AD´ãÃZ^[Ìäæ¶ÉæéTURBTÌu`A»µÄfBXJbVÆ¢¤¬êÅsíêܵ½B
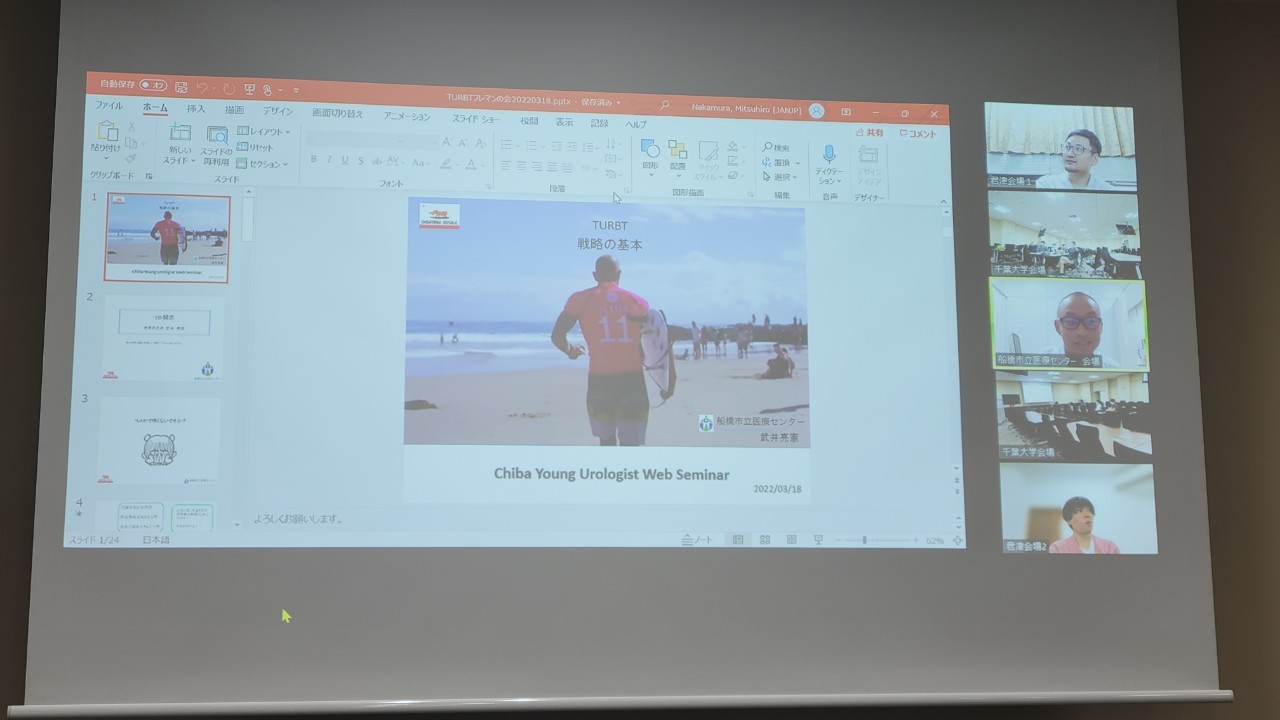
TURÌu`ð·éäæ¶Æäæ¶ÌLwØÉÁóûæ¶A¬Ñæ¶
ea@ÅèpÌÛÉlXÈHvðµÄ¢é±ÆðmêÄåÏLÓ`ÈÔŵ½B
¡ñwñ¾±Æ𩪪··éÛÉæèüêÄÝæ¤Æv¢Üµ½I

çtåïêÌo[ÅWÊ^
±ÌxͱÌæ¤ÈMdÈ@ïð^¦Ä¢½¾«AéæµÄ¾³Á½áäæ¶Aäæ¶Aóûæ¶Éúäç\µã°Ü·B èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFãú¤Cã@nç² LB
HoLEPúg[jOÉ¢Ä
åAíÈ1NÚÌXìÅ·B¡NxÍÂta@ÉαµAåÉHoLEPÉÅ¿Ýܵ½B
üEÍAO§BÌ«ÚÁÄ©Äàæí©çÈ¢µA[U[Æ©ÅÁ½±ÆÈ¢µcÆ¢Á½´¶ÅX^[gµÜµ½B
oIÈîñÍ ÁÄàDZ©çèðt¯Ä梩í©çÈ¢c
\\\»êÍ¿å¤ÇAïðÈÊðáOÉAÇÝðnßéÆ«Ìæ¤Åµ½B
Æ¢¤í¯ÅGzÅ·ªA¡NêNðʵÄwñ¾HoLEPÌúg[jOÉ¢ÄAï¡ÌsAmÅêÂÌÈðæègÞHöÉȼç¦Äêç¹Ä¢½¾«Ü·BiÞèâèj
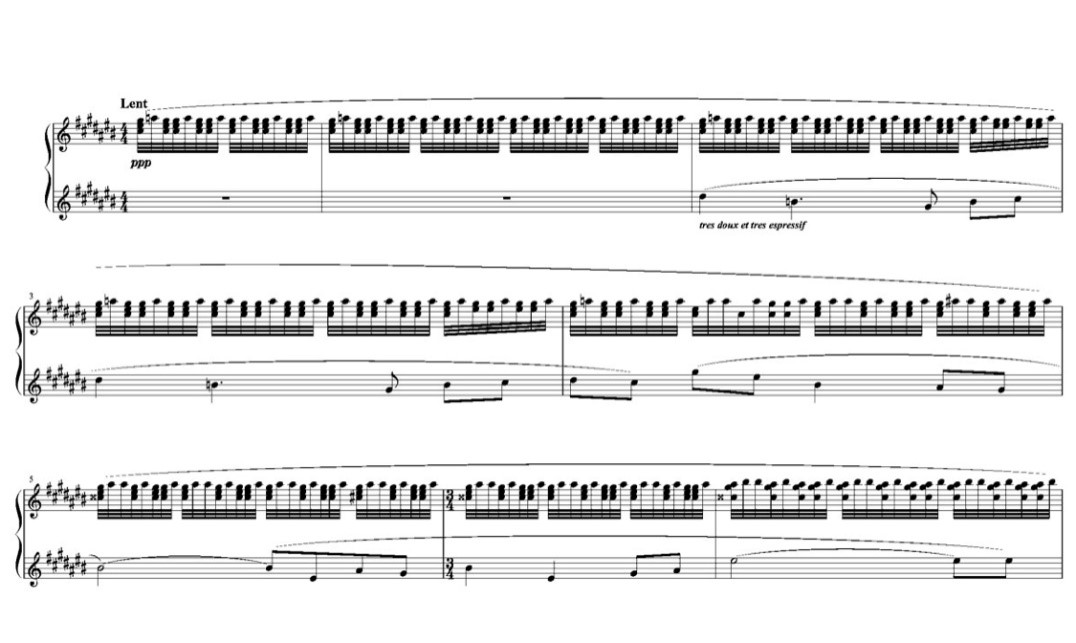
ª[XEFwéÌKXp[xiGaspard de la nuitj
🎼åÏFFÍ¿«ªüµ¨È¶Ýª¢¢È²Å·ªA»ÌÀÔÍßãaºÌãk§Ègí¹Å èAa¹Ì\ªªµÉ(a¹ðÇÞÆ«1¹1¹mFµÈ¯êÎÈçÈ¢)AuÇÝßñÇcvÈìÈÆÌã\iÅ·B
±ÌÈÍe«½¢¯ÇÇÝÅSªÜêÄèªt¯çêĢȢŷB
gthe óÛhhÈAj
CŨµáêÈÈÅ·B
ôܸAVµ¢ÈðͶßéÆ«ÍÇÝÅ·B
ÈÌåܩȬêðêÊèCvbgµÜ·B
½àmçÈ¢óÔÅÇñÅ¢ÌÍÔª©©èÜ·ÌÅܸ͹¹ðTµÄ·« ³èÜ·B
˼ÌÇáÌèpL^âA³çrfIÈÇð© ³èܵ½B
¹ºtÅSÒü¯ÌàeðྵÄêéÌÅAoîñt«Å¬êðo¦éÌÉdóµÜµ½B
ôêÊè¨Åo¦½ ÆÊðÝéÆA©ÈèÈðC[Wµâ·ÈÁĢܷÌÅÇÝðµ¿á¢Ü·B
¨Çݪ¨íÁ½çÆè ¦¸wÉȶÞÜÅe«ÝÜ·B
ËÆè ¦¸êlŮūéæ¤ÉÈéÜÅo±ðÏܹĢ½¾«Ü·B

ôÈð±¤\»µ½¢Æ©Èðoµ½ÈèÜ·B
©ªêlÅÍÀEª éÌÅw±Òɲө𢽾«ÂÂAש¢\»Lâw¦LÉÚðü¯Ä ç½ßÄyðÝÜ·B
©ªÌzÉ¿©¢¹¹ðTµ½èàµÜ·B
ËÈñ©±±¤ÜÈ¢ÈcÆv¤Æ±ëðÈéשª©Â¯Ä(àµÍ©Â¯Ä¢½¾¢Ä)ñÓ¯µ½èA¼Ìæ¶ûÌèpð©wµÄÍVµ¢©ª èAwιĢ½¾«Üµ½B
ÈãA©È豶¯ÄAHvµÄÜ·É©¹Ä¢½¾«Üµ½ª(E_E;)AAA
ÆÉ©±ÌêNÔA½³ñÌo±Ì@ïð¾³èAtÙÈ^â¿âÉÐÆÂÐÆÂJɦľ³èAÈÉæè¢Âਨç©É²w±¾³Á½a@ÌæyûÉεA´ÓÌOÅ¢ÁϢŷB
¡ṈÌo±ÍA©ªªæyãtÉÈÁ½ÛÌãyw±É¶©µAҳū½çÆv¢Ü·B
¡ãÆཱིñ̲w±ð¢½¾¯Ü·ÆK¢Å·B
æ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@Xì ^ß
2022.2.10@t}ø«p¬
FlͶßܵÄI
2021NxüÇÌc d÷(³Æ«)Æ\µÜ·B
¡NÍú¤C©çø«±«¡lJÐa@ÅZµà[Àµ½¤C¶ðç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
¡lJÐa@ͧOÅ£à£êĨèAéõÝÌÈ¢æ¶à½¢çÁµáé±ÆÆv¢Ü·B
äçªic·¦¢é«L©È涪µ¢AúX½Ì³Ò³ñÌfÃɽÁĢܷB
ÁÉt¾³ÉÖµÄÍàÅàLÌ{ÝÆÈÁĨèANÔ60-70áÌtèpð¨±ÈÁĨèÜ·B
ܽA@åAíÈÌÁ¥ÆµÄÛO®ÍO¹Ü¹ñI
jOâ
jAØgÈÇ^®s«ÅYÜêéûÉÍsb^Ì«ÅAJid`¾Á½là±Ì3NÔÅtÙȪçj°éæ¤ÉÈèܵ½B
lƯ¶
jªêèÈûÍ¥ñ{èR[`Ìw±ð¢ÅÝÄÍ¢©ªÅµå¤©I
³ÄA©g̲Ðîªxêܵ½B
kC¹¶ÜêkC¹ç¿¶Ìu¹YqvÅ·I
ÀÆÍ_ÆÅÌÑÌÑçÄÄàç¢Üµ½B
(ÌÑÌÑçÄçê·¬½©àµêܹñªAA)

ÄÌØÌÔ¨

~̨
ÍZ©çåwÜÅd®ejXðµÄ¢Üµ½B
EejXª êÎ¥ñQÁ³¹Ä¸«½¢Å·I
(jOAØgÉàt«ÁÄ¢½¾¯éûAåååWÅ·)
³ÄAµOÀª·ø«Üµ½ª{èÌt}ø«p¬Éüç¹Ä¸«Ü·B
WÍ12:30 lÍÎÊÌt}¯úà½AµhLhLµÄ¢Üµ½B
VCÍ ¢ÉÌáŵ½ªxÒÍ1làÈ(H)Jt@X[ÅWÅ·I

WÊ^ (lÍܾµÙ£µÄ¢Üµ½Î)
Ê^èO¶©ç¬Ñæ¶AXìæ¶AcAV[æ¶Aæ¶Aâäæ¶
¶©çªæ¶Ar´æ¶
{{涪SÆÈèø«p¬ðµÄ¸«A±¢Äfusion biopsyÌà¾É¤Âèܵ½B
1ÔÙÇÔð©¯AÆÒÌûÉJÉྵĸ«Üµ½I
4ÜÅYêÈ¢æ¤ÉAAÆÝñÈæ£ÁÄðæÁĢܵ½B
¢â[»êɵÄàÞ¸©µ¢I

ÝñÈ^È᷵ŷI

ÀHûKÉãÞr´æ¶
±ÌãàüêÖíèÝñÈÅûK..ûK..
»ÌãÍ{{æ¶A¡æ¶É@àÄàðµÄàç¢ø«p¬I¹Å·I
¤ÅÍäæ¶A»µÄ¤Cãã̶t̲¡qåæ¶Éà¨ï¢·é±ÆªÅ«Üµ½B
»ÌãÍN̨_ñðÏܵAúÒɹðcçܹȪç¡lÖÆAÒ¢½µÜµ½B
4ͲÀfð¨|¯·é±Æà é©àµêܹñªAµÅàƱɵê`[o[ƵĨðɽÄéæ¤A»µÄåAíÈãƵĬ·Å«éæ¤t}ê¯Íðí¹Äæ£ÁÄQèÜ·I
·©¢²w±ÌÙǽ²æ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@c d÷
2022.1.29@æ45ñçtåAíȯåïwpï
FlAßܵÄI
üÇ1NÚA»ÝçtãÃZ^[αÌâä½Æ\µÜ·B
LÉ槿ܵĩÈÐĢ½¾«Ü·B
ç¿Íçtåw®ct`wZÉ_bV
ÊwA§§çtZÉ`ÊwƶÌçts¯Å²´¢Ü·B
VåwðoÄA̽çtÌåAíãÃÉv£·×ßÁÄÜ¢èܵ½B
Ísì³öƯ¶oXPbg{[I
ï¡ÍLvÈÇÌAEghAÅ·B
ELvÈÇ èܵ½çºÐü³¹Äº³¢B

VÌ·ªÔÎ@tBi[ÌtFjbNXÍê©Ì¿l èÅ·I
ܽJÃÅ«éúÉÍF³ñàºÐsÁÄÝĺ³¢

VÍÁÊL¼ÈÏõX|bgÍ èܹñªAÄI ú{ðI CNI
[àü¡µ¢¨Xª½A[¤çµ¢Å·B
Ê^Íw¶ãÌoCgæÊïÌ1B
ÀÍVsÉà|W³ñª¢éñÅ·I
VŨÀ~VÑðµ½¢ûÍâäÜÅB
¨Úµ¸çµÜµ½(¨ðÅçªÔÈÁĢ龯ŷAÍ¢)B
Ou«ªåÏ·ÈÁĵܢܵ½ªA±Ìx¯åïÖQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·I
yGz[ÅÌnCubh`®ÌJÃÆÈèܵ½B
ïêͧñð̽ßee[u1ļŵ½ªAïêÉüÁÄ·®R[gðEª´éð¦È¢ÙÇÉMCìêéÈ¢_ªJèL°çêĨèܵ½B

zoomðʵÄSE¢âS¢E©çå¨Ì涪QÁAÈө𷪳êĨèܵ½
Ê^Í¿â·éÌú¤CæED´s§ãÃZ^[Ìt äæ¶
àêåAíÈãƵİXÆfBXJbVÉQÁÅ«é椸iµÜ·
ZbVÅÍtbV
}̯úàå¨\µÄ¨èAea@É¢é¯úÌdÔèª_Ô©¦åÏ`x[VªÜèܵ½B
æyûÌ\ÍAàeͳéȪçXChÌ©â·³â¿^ÖÌÎÈÇQlÉÈé±ÆªòR èܵ½B
åw@Ìæ¶ûÌ\ÍAªNãÉ»Ì|WVÉ¢éÆÍêv¦È¢æ¤ÈnCxÈàÌų|³êܵ½B
àÇáñÅ°kÅͲ´¢Ü·ªAZbVÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ÀͯlÌèðwïÅà\³¹Äàç¢Üµ½ªA¡ñ̯åïÌûªÙ£µÜµ½B
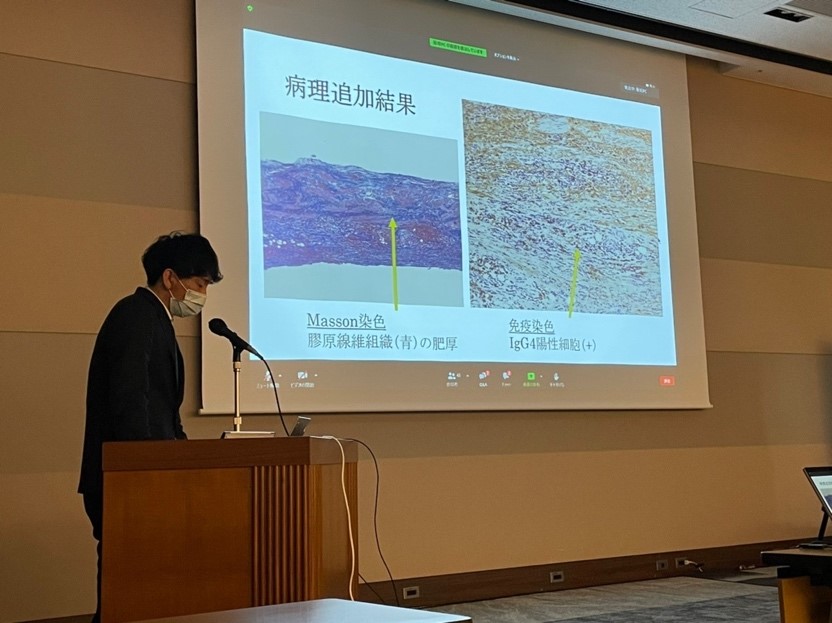
\·éâäANxÍOðàÁÆ©Äs¨¤Æ½ÈÌ1
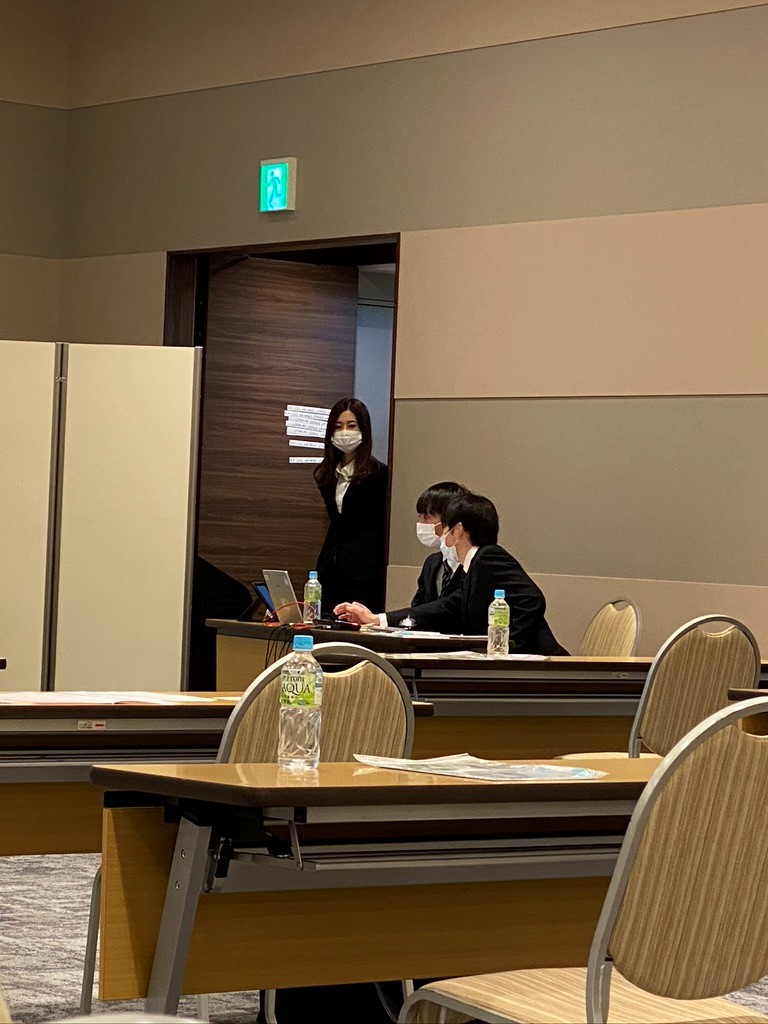
~È\Ì½ß ûÌdðµÄ¾³ÁÄ¢éغæ¶(¶)Anç²æ¶(E)Æ»êðÄ·é¡æ¶()
Nxà¨C¹º³¢I
ïÅÍ÷JÜâ¯åïwp§ãÜAxXgv[^[ÜÈÇÌöÜ®âAäçVüÇõÌÐîÈǪ èܵ½B
ÇÌ\àf°çµ©Á½Å·ªAxXgv[^[ÜÁÊÜ̬Ñæ¶Ì\ÍåAíÈIÈCpNgª èÂlIÉàóÛ[©Á½Å·B
VüÇõÌÐî[r[ÍǤ¾Á½Åµå¤©H
»ÝçtåÉ¢é{{涪YouTuber³ÈªçÌÒWÍÅ10làeÉUçÎÁĢĢé¯úÌ®æðÜÆßÄêܵ½B
Nxà11lüÇÆ̱ÆÅAãy̨¢É¯È¢æ¤æ£èÜ·I

¯åïwp§ãÜðóܳ꽶©ç²¡æ¶Aàâæ¶Acæ¶ÆoN[o[É¢çÁµáéìæ¶(j^[º)

ïêQÁÌtbV
}¯úWÊ^A¼É4¼¢Ü·

ÅãÉWÊ^ÅPáÌ[I
±Ìæ¤ÈLð¡ÜÅ@ïª ÜèÈAtÙȶÍÆÈÁĵÜÁÄ¢é±Æð²eͺ³¢B
à¤3NÚÉËüµÄµÜÁ½RiÐÅ·ªAnCubh`¬ÉÈÁ½±ÆŽÌæ¶ûÌ\ð·±ÆªÅ«åÏMdÈo±ÆÈèܵ½B
ÂlIÉÍAiï¦È¢ùßÈ¢¯úƼÚ櫓ƪūANx¨¢bÉÈéåwa@Ìæ¶ûÉà¨ï¢Å«½hIÈúÆÈèܵ½I
¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓF§çtãÃZ^[@ãú¤Cã@âä ½
æ21ñçtåAí o¾³çvO+áèåAíÈïc
ͶßܵÄA{NxæèçtåwåAíÈÉüdz¹Ä¢½¾«»ÝÍNÃa@ŢĢé¬Ña÷Æ\µÜ·B
µ¾¯Ì©ÈÐîð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
ogÍçtåwÅú¤CͻݢĢéNÃa@ÅsÁĨèܵ½B
ï¡Í¹ytFXâCuÉs±ÆÅ·B
²¶¶ÌÊèAð¡ÌRiÌ ¨èðó¯~ª¬XyµßÈ¢úXðß²µÄ¢Üµ½B
½¾Åß͵¸ÂK§àÉa³êīĨè[ÌÍÍàÅQÁÅ«éæ¤ÉÜÅÈÁīܵ½B
Ê^ÍNÉJEg_EtFXÉQÁµÄ«½ÛÉBeµÄ«Üµ½B
1là´õÒðo³È¢æ¤ÉSÌÎôÅÕñŢܷB
¢Â©}XNàÈåºÅyµßéúªéÆ¢¢Å·ËB

Oêµ½´õÎôª¤©ª¦Ü·I

Don'stop the music & festivalIII
³Ä¡ñÍæ21ñçtåAí o¾³çvOÉ¢ÄÆN2ñZoomÅsíêÄ¢éáèåAíÈAïcÉ¢Äñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
ܸAæ21ñçtåAí o¾³çvOÍ2021/12/11RBfBGWplÌä¦ÍÌàƲËæ¶AVäæ¶Ì²w±Åsíêܵ½B
çtåwÌãÇ©çÍtbV
}6l(¬ÑAjæ¶A¡æ¶Acæ¶A{{æ¶Anç²æ¶)AR¨æ¶A¼äæ¶A涪QÁµÜµ½B
ßÄs¤t(Ø)EoÉ«íꬵȪçàAÈñÆ©EoµÀg·éÆÆàÉiAãÌæ¶ûª½CÈsÁÄ¢és®êÂêÂÉÓ¡ª é̾ÈÆÀ´³¹çêéêúÆÈèܵ½B
²Ëæ¶AVä液w± èªÆ¤²´¢Üµ½B

vOJnOÌLOBe
É2021/12/13ÉðNÉø«±«ZoomÉÄçtå¯åÉæéáèåAíÈAïcªJóêܵ½ÌŲñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
¡ñÍsìæ¶Ì¨bÉÁ¦ÄAO´æ¶Éæé϶ïFs{a@AéØæ¶Éæé¬cÔ\a@Aúìæ¶ÉæéJCHOVhfBJZ^[ÌÐîª èܵ½B
©gA¤Ca@©çø«±«üEµ©a@Ìݵ©o±µÄ±È©Á½½ß¼a@Ì»ó𤩪¤±ÆªoéÌÍñíÉMdÅ èAÆÄàgÉÈé¨bΩèŵ½B
«ÉηéC[WÍܸmé±Æ©çÆüßÄ´¶Üµ½B
{Å êÎAÀÛÉWµÄÓ©ð··é±ÆÅæè«ð`±ÆªoéÌ©àµêÈ¢Æv¤ÆµcOÅ·B
RiªI§µ½ÅÉͼ¤àÈ¢bð½³ñµ½¢Å·ËIII
ܽÊ^ÍÈ¢ÌÅ·ª¡ñÌZoomïcÉÍNx©çüdzêéæ¶ûÌpà èA¢æ¢æÉàãyªÅ«éÌ©ÆúÒ·éÆÆàÉAµÁ©è©{ÉÈêéæ¤Èpð©¹È«áÈÆgªø«÷Üév¢Åµ½B
ÅãÉÈèÜ·ªNxÍçtåwãw®a@Å©¹Ä¢½¾\èÉÈÁĨèÜ·ÌÅA²w±ÌÙÇæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFãú¤Cã@¬Ñ a÷
yà¯wLzãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤å
Fl±ñÉ¿ÍAåw@2NÌcºM¾Å·B
çtåwð2014NɲƵA»ÝAwãÈåwãw¤ªq×E¡Ã¤åxÆ¢¤ÅåAíªñÌîb¤ÉgíÁĨèÜ·B
¦HçtåwÌåw@¶ÈÌÉHÆ´¶çêé©àµêܹñB
äXçtåwåAíÈw³ºÉÍãÇÌæy½¿ªz¢Ä±çê½½lÈlbg[Nª èÜ·B
åw@¶ÍAK¸µàåAíÈw³ºàŤð·éí¯ÅÍÈAwà̼¤ºÉó¯üêÄ¢½¾±Æà êÎAí½µÌæ¤É¼{ÝÉó¯üêÄ¢½¾¢Ä¤¶ðé±Æà èÜ·B
lXÈáðm轢Ƣ¤ûA¥ñÆàí½µÌæyûªe³ê½åAíÈÊMÌßLð²¾³¢I
³ÄAí½µÌó¯üêæÌ{XÅ éJFL³öÍAgGN\\[hÆ¢¤¨¿Ì¢EIȤÒÅ·B
àÆàƧªñ¤Z^[¤ªq×E¡Ã¤ªìªì·ÆµÄAGN\\[Éæéªñ««»@\Ìð¾ÆA»êÉîÃffE¡Ã@ÌJɨ¢Ä¢Eð¡ø³êܵ½B
ãÈåwÉÚÁ½¢ÜàȨAªñÈOÉà¤ÌæðL°A¢EÌæêüŲôÌæ¶Å·B
©ÂÄpÅ|pÆðuµAܽ¶ïðÒ®½ßÉI[g[T[ð³êÄ¢½oðਿŷB
í½µÍãÈåwɤºªÚÁÄ©çAJ³öÉtµÄ¨èÜ·ªAÌåÈw©çwÔƱëͽA[Àµ½CsÌúXðÁĨèÜ·B

2020N3AãÈåwÉÄJ³öÆ

2022N1^úÌÀ±ºi
GN\\[ÍA×EO¬EÆ¢¤ çäé×Eªªå·ébZ[Wöq̤¿ÌÐÆÂÅ èA¼añ100 nmÆARiECXÆÙÚ¯¶å«³Ì¿ñ\\¢ðÆéè÷±ó¨¿Å·B
×EͱÌGN\\[ɽñÏ¿â}CNRNAÈÇ̶«ªqðÚµÄ^Ô±ÆÅÊÌ×EÉbZ[Wð`¦Aó¯èÌ×EÉÏ»ðN±µÄ¢é±Æªª©ÁĢܷB
TCgJCâPJCƯlAªñÌ««»É½iKÉÖíÁÄ¢é±ÆàmçêĨèAá¦ÎAá_f«ºÉ¨¢ÄAªñ×EÍÇV¶ð£·½ßÉÇàç×EÉGN\\[ðèÝîáÇð쬵ܷB
ܽAªñ]Ú@\ɨ¢ÄàA¶ÌoAƵÄdvÈt]ÖåðËj·éæ¤ÈGN\\[ð´©çBµA]]Ú𬧵ⷳ¹é±Æàñ³êĢܷB
i§¤J@l§ªñ¤Z^[ªq×E¡Ã¤ªì¤vWFNg, §¤J@l§ªñ¤Z^[LñvX[X j
¼ÉàAGN\\[ÉæÁÄÆu×EÌ«»ð}§µÄµÜ¤ÈÇAªñ×EÍ©gÉÆÁÄLÈ«ðGN\\[̪åÉæÁÄÀ»µÈªç¶¶µÄ¢±Æªí©ÁÄ¢éÌÅ·B
ÆÄ໡[¢Å·æËB
±Ìæ¤ÈGN\\[ðÎÛƵ½AªñffE¡Ã@ÌJ¤ÍAßNA¢EÅIÉiñŢܷB
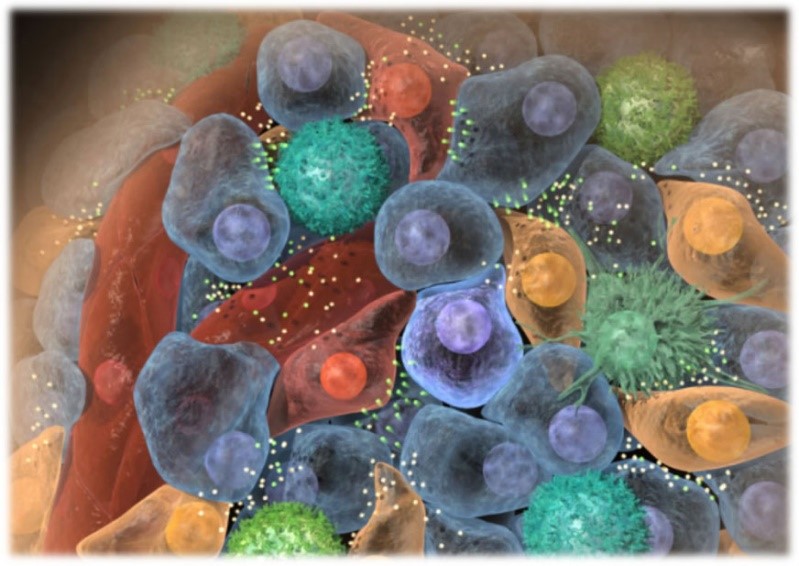
ªñ÷¬Â«ÆGN\\[
GN\\[̤ͪñÌæÉÆÇÜéí¯ÅÍ èܹñB
éíÌGN\\[ÍRÇERüÛ»ìpðà±ƩçRiECXÖAxÌ¡ÃÉp³ê èÜ·µAܽA`GCWO̶¬É¨¢ÄüeãÃÖÌpàiñŢܷB
³çÉÍ»ÏiâHiATvgÆpÍÍÍÆÇÜé±ÆðmèܹñB
qgÉÀ縮¨ÉÖíé¤à è¾éí¯Å·©çA³ºªø¦é¤¯¤æͽûÊÉnèA½í½lÈvWFNgÌbèÍåÏhIÅ·B
åAíÈAÆ¢¤ggÝÉÆçíêĤðµÄ¢ÄÍÜÌÈ¢ÈAÆf¼É´¶Ü·µATCGXÉÖíéÒƵÄL¢©¯ðõ¦é±Æâ¼Ìæ̤Òðª«ÞlÔÍàKvÅ é±Æð§Å´¶Ä¨èÜ·B
¤ºÍÌÇ^ñAs¡ÌÙÇßÉ èÜ·ªA±ÌRiÐɨ¢ÄÍUfÌíà èܹñB
¤Évª·éÉÍâDÌå`XÅ·B
©g̤ªA½©lÞ̽ßÉv£Å«é©Íª©èܹñªA¡µÎçÍCsÌgƵÄAJ³ö̺ÅTCGXÆ^Éü«ÁÄÝæ¤Æv¢Ü·B
åAíÈwAãwA»ÌæÌ¢EÖBçtÌãÃAú{ÌãÃA»ÌæÌ¢EÖB
±ê©ç±Ì¹ÖiÜêéF³ñAçtåwåAíÈÅêɪñÎÁÄÜ¢èܵå¤III

2020IsbNu[CpXW¦òsi¤¡ÌVhöÅBej
¶ÓFåw@¶@cº M¾
SGLT-2jQÜÌãå@àäD³ö@çtåqõ³öÉAC
±ÌxAAaÌ¡ÃÉv½ðN±µ½SGLT-2jQÜðnò³ê½åãåw@àäD³öªçtåwÌqõ³öÉAC¢½¾«Üµ½B
àä³öÍA2020NÉàtåbÜðóܳêA¡ãAm[xÜðæéÌÅÍÆ\³êÄ¢él¨Å·B
½ðB»¤Aàä³öÍAÌåw@ã̼ÚÌw±³¯Åµ½B
AåµÄ»¡È¢ð¤Ì¢EÉø«ñÅ¢½¾¢½ûÅà èÜ·B
µµ¢w±Ì ÉÍA¤ÉηéîMƶ½Éηé¤îð´¶Üµ½B
»ÝàAÈƪñÁÙIA~m_gX|[^[FLAT1jQÜÌnòÖü¯Ä¤¯¤ðsÁĨèÜ·B
åw@ã©çAà¤20N½¿Üµ½ªA¢Ü¾ÉAqíÖWðۿȪç¤É©©íé@缾ÌlÉ é±ÆðñíÉðµv¢Ü·B

2020N@àtåbÜóÜÌàä³öiÀ{ñÌE×èj

àä¤Kâi¶@¤Ìt Å é^CMahidolåwÌArthitæ¶AE@àä³öj
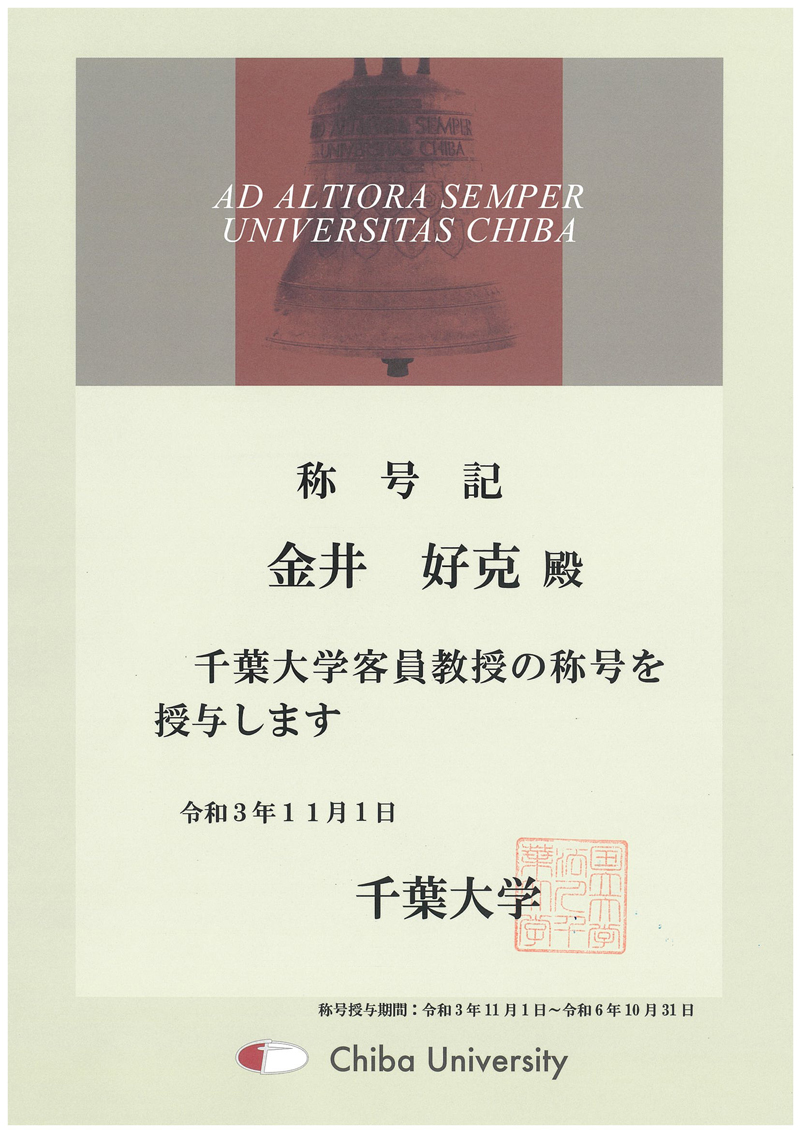
¶ÓFfÃy³ö@â{ Mê
çtååAíÈvsbãååAíÈ
F³ñ±ñÉ¿ÍB»Ýçtåwa@ÉÄãú¤C3NÚÌغÁÆ\µÜ·B
æúçtååAíÈvsbãååAíÈÆ¢¤ðjIÈtbgTÌð¬íªJóêܵ½ÌŲñvµÜ·B
ÜèÖW èܹñªA±±Å߸ÁÆl¦Ä¢é±ÆÍAåwÅÌw¶¶6NÔ©¯ÄAçtåTbJ[Å|Á½Ag«Å{[ðµ¤hÆ¢¤ZpðA¢©ÉÕ°Ép·é±ÆªÅ«é©Æ¢¤±ÆÉ«ܷB
é
ZÌÅA]©çÅࢫðCÅg¤£ZÍTbJ[AtbgTiAZp^N[Hj碩Æv¢Ü·B
»_ÅlÂlƵÄÍAèô¢ðµ½ãIyºÌhAðJ¯éÆA³Ò³ñðÚ®³¹éÆ«ÉÅè³ê½xbhðð·éÆ«ç¢Éµ©»ÌZpðpūĢȢÌÅA¡ãÍTURâ{bgèpÉàpÅ«éæ¤úXvlðß®ç¹Ä¢Ü·B
{èÉüèÜ·B
»ÝD´s§ãÃZ^[ÌãÃðêgÉwÁħÁÄ¢éäæ¶ÆAåwTbJ[ã©çÌ·NÌíFÅ ébãåogA»Ýbãåa@åAíÈÌìæ¶ÌéæÅAçtååAíÈAbãååAíÈÌR{tbgTåïLFtbgTR[gªJóêܵ½B
çtå`[Ìo[ҬŷªAäçªêé`[ÌS@çtÌCjGX^±ÆäDrAçt©çªñZ^[ÖÌSjèÌâÅSx@\ðW}CJlÀÝÉi»³¹½Æ¢¤\ÌnêDrA
³ðªçȢƢ¤V¡ÃÌJɬ÷µ³ð®¡³¹AJfT^ð©ÈxòAtreatment freeO´DrAD´ãÃZ^[ÌIyºNsÆaeðñ÷ɬ÷µ½D´Ìy[±Æú¤Cã2NÚÌr´DrA
çtåwH¹Ý°OÈÉhbyQK[̶ݪ³³â©êĢ鱿çàD´ú¤CãÌVäDrA
»µÄ2020NÉÍT[t{[hðwüµCð§·éÆv¢«â2021NÍóð§·é±ÆðÚ_ñŨèÜ·
í½µcaptain غÌ6lÆÈèܵ½B

SÌÌWÊ^@XyVQXgâ{æ¶ (¦v[Í}XNð
pµÄ¨èÜ·)
bå`[à8¼ÙÇÌæ¶É¨WÜ袽¾«A17ªn[t~214ªÌð4|5ÙÇs¢Üµ½B
¨Ý¢êàà÷çÊM¢ªJèL°çêAvXRAÅÍɵàçtå`[ª1àyθÉsÆ¢¤ÊÆÈèܵ½B
i_ªüè·¬ÄÚµ¢XRAÍo¦Ä¢Ü¹ñB\µó²´¢Ü¹ñBj
äçªçtåªÖé¸s½¿ðµWµÕñ¾êí¾Á½¾¯ÉcaptainƵÄÆÄà÷µv¢Ü·B
ñJóêé±Æª êÎÊÉà±¾íÁ½í¢ðǵĢ«½¢Æv¢Ü·B

bãå̸s½¿@ybg{gÌÊ©çàí¢Ìµ³ª¤©ª¦Ü·
RiÐÅICÅÌ益éA¼åwÌãÇÌæ¶ûƱÌæ¤È`Åð¬ªÅ«½±ÆÍÆÄàMdÈ@ïŵ½B
ãÃÈOÌêÊÅR{[V·é±ÆÉæÁÄV½Èzª¶ÜêAÊƵÄãÃÉvXÉÈé±Æà é©Æv¢Ü·ÌÅA¡ãÏÉIɱÌæ¤È@ïðâµÄ¢¯êÎÆv¢Ü·B
ÂlIÉÍTbJ[ÅÍÈtbgTðvµÔèÉo±Å«AtbgTÅÍ·¢R[gÌÅAóµ»fªµÅàxêĵܤƷ®ÉèÉÍÜêĵܤ±Æ̵µ³ðüßÄv¢mèܵ½B
·¢Â«Æ¢¤±ÆÅAtAÇSE̺ ìâAßN͸ÁÄ«Ä¢é©àµêܹñªJ O§BSEÉàtbgTÌ®«ðpÅ«éæ¤CgðµÄ¢éƱëÅ·ªAǤà¤Ü¢«»¤É èܹñB
ÇȽ©¢¢ACfA¨¿Ìû¢çÁµá¢Üµ½çÂlIÉA¢½¾¯Üµ½çK¢Å·B
·¶Aʶ¸çvµÜµ½B
¡ã´õÇÉÍӵȪçàA±Ìæ¤Èð¬ðâµÄ¢¯êÎÆv¢Ü·B
tbgTÈOÅàãÇSÌðʵķèã°Ä¢«Üµå¤B
¶ÓFãú¤Cã@غ Á
StanfordåwÆçtååAíÈñg@Creating Social ValueiCSV)Öü¯Ä
ÈO©ç𬢽¾¢Ä¢éStanford åwÌr춺³öªFumiaki Ikeno's Profile | Stanford Profiles@çtåwÌqõ³öÉAC³êܵ½B
rì³öÍAX^tH[håwɨ¯éãwnTranslational Research & Entrepreneurship EducationÌêåÆÅ·BåwÈOÉàA©çàVenture CapitalistƵÄAVRo[Ìx`[éÆÖÌÈÇàsÁĨèÜ·B
¡ãAçtåwåAíÈÆStanfordåwÆÌð¬ðʵÄAVµ¢ãÖÞ¯ÄAoCIfUCAãHwAnòÈÇCreating Social ValueðǵĢ«½¢Æl¦Ä¨èÜ·B
rìæ¶ÌYoutubeÌLink@From Rural Medicine care(future)to Silicon Valley(present) | Fumiaki Ikeno | TEDxHamamatsu - YouTube

rì³öÆÌZoomïcÌlqi¶ãFrìæ¶A¶ºFû¢æ¶AEºFcºæ¶AEãFâ{j
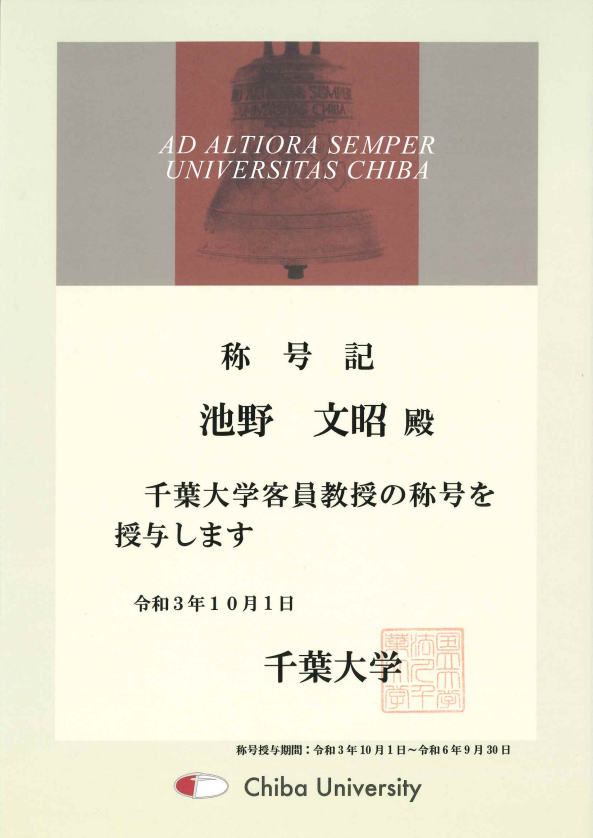
¶ÓFfÃy³ö@â{ Mê
o¾g[jOfìiJ@`KOTOBUKI Medical`NHK WorldæÞ 2021/10/17D´s§ãÃZ^[èpº
Fl¨vµÔèÅ·AD´s§ãÃZ^[åAíÈã·T[tBõÌäÅ·B
¡ñÍAD´ãÃZ^[OÈÄÚæ¶ÆKOTOBUKI medicalÌR{ÉÄ o¾g[jOfÌJðs¤éæÉAåAíÈÌæÌÓ©àæèüêé×QÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½BÈñÆA{éæÍNHK World³ñÌæÞªüèܵ½I
KOTOBUKI MedicalÍu·×ÄÌlªÀSµÄèpÉÕßéÐïðÂévðRZvgÉèpg[jOp@íðJµÄ¢é[J[Å·Bihttps://kotobukimedical.com/æèøpj
KOTOBUKI MedicalÌã\ìÅ éASVµ¢Í[íuVTTiVersatile Training TissuejvÍççqìâDÌÝÈç¸dCXÉàÎÂ\ÈRjNð嬪Ƶ½Í[íÅ·BVTTÍlÌgDÉñíÉߢ´GÆxð¿A3Dv^Å`óà©ÝÉϦçêé½ßAlXÈíÖÌJX^}CYªÂ\Å·BA¨RÌ´¿ðgpµÄ¢é½ß«ÉàDµ¢ÌªÁ¥Å·B
¡ñÍåÉ_r`èpg[jOÅgp·éhC{bNX¨æÑAVTTÌìiÌJÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B

ÕfÌhC{bNXìi
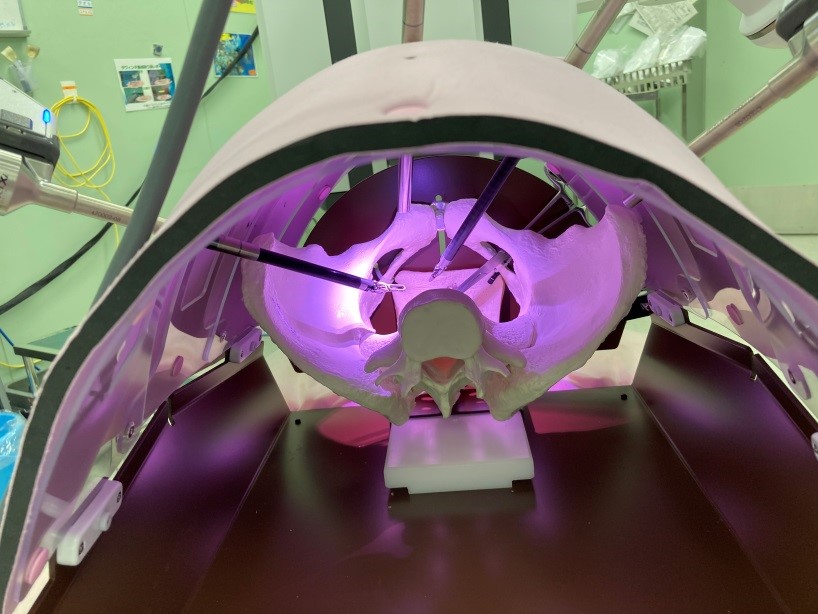
{bNXàÉAÈÕÍ^ð}ü

ÕàÅÌäNã÷A¹DÌg[jOɧí
èpÉÕÞOÉV~
[^[â_r`À@ðgÁÄÌDg[jOðs¢Ü·ªA±êÜÅÍt[Xy[XÅÌg[jOµ©Å«È©Á½½ßAÀÛÌèpÅÍÕàÌ·¢óÔÅÌìɵêĨç¸ïa·éo±ðFªµÄ¢é©Æv¢Ü·BÕfÌhC{bNXÅÌìÍAAÈèpÉÉßÄߢ·¢óÔÅÌDÌg[jOªÅ«é½ßAñíÉLpÈf¾Æ´¶Üµ½B
»µÄ±ÌhC{bNXAçÉ©§Ä½\ÊÌfÞÌeÍÍç»ÌàÌŵ½BfÞͽÅoÄ¢éÆv¢Ü·©H
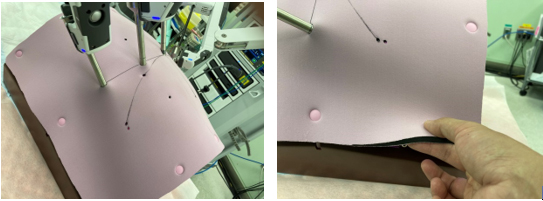
{bNX\ÊÌfÞͽÆI@T[t@[äpBÌEFbgX[c¶nŵ½I
éfÞðµ½ÊA±ÌEFbgX[c¶nªÅàçÉߢeÍÆ̱Æŵ½B¦¢~É·ÔAT[t@[ªCÉüÁÄ¢çêéÌà[¾Å·ËB±Ì{bNXÅÍ|[g}üÌûKàD«ÈÓÉ©ÝÉÅ«éÌàf°çµ¢Å·ËB
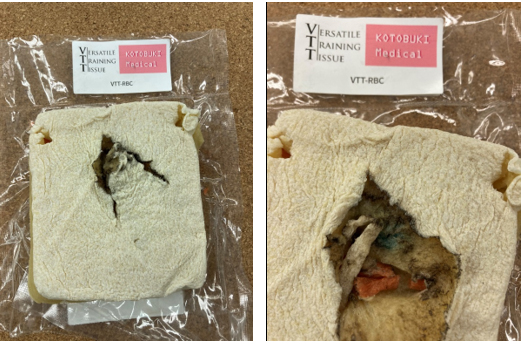
KOTOBUKI MedicalÌã\ì@RjN©çìçêéÆ¢¤uVTTv
gDÌÉÍÇâpßÉ©§Ä½\¢ªßÜêÄ¢é
ÀÛÉdCXÅÌØJâoC|[ÅÌÃÅÈÇàµÄÝܵ½ªA»Ì´oâ¹âõ¢ÜÅ{¨³Èªçŵ½BßÜê½ÇÆüÍgDÌ£ìà©ÈèAÉĻūA»Ì®¬x̳ÉÍEXŵ½BäNã÷A¹«ÉݽĽAwTbNÆVTTÌ«ðs¢Üµ½ªAgDÌxâLkÌG´ÍñíÉAÅwTbN¯mÌ«æèàAÀíÉߢg[jOªÂ\¾Ævíêܵ½B
ÕfÌhC{bNXÆAO§BâäNã÷AA¹ðfƵ½VTTðgÝí¹êÎA®¨ðgpµ½EFbg{ðsíÈÄàA¯lÌxÌg[jOªÂ\¾Æ´¶Üµ½Bãt1lª_r`R\[Ìið¾é½ßÉAu^1ªª½ðƵĢé»óðϦé±ÆªÅ«éÌÅÍȢŵ天B

NHKÌæÞÉMêéOÈÄÚæ¶

KOTOBUKI Medicalã\R³ñ(Ê^)ðÍñÅ
ÅVÌèpg[jOfÌìiJÉQÁ·é±ÆªÅ«åÏMdÈo±ÆÈèܵ½BKOTOBUKI Medicalã\ÌR³ñAú{dgj
[XÐc³ñAIntuitiveR³ñAOÈÄÚæ¶A¨Zµ¢È© èªÆ¤²´¢Üµ½BçtååAíÈÅà±Ìæ¤Èf°çµ¢Zpð¤LµÄ¢¯êÎÆv¢Ü·B
¶ÓFD´s§ãÃZ^[@åAíÈ@äº
2021/10/13 tbV }¯×ï
ßܵÄA{NxæèçtJÐa@ÉÄãú¤Cð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·tbV
}ÌV[Å·B
úXA©ªÌm¯s«AZps«ðÉ´µÈªçà¤èrðÏÝAæ¶ûÌäw±ÌàÆ[Àµ½úXðß²³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
æúA1013úÉtbV
}×ïªsíêܵ½ÌÅ»Ìñð³¹Ä¢½¾«Ü·B
¡ñÍZt@[}³ñ¦ÍÌàÆAçtåwa@ANÃa@AD´ãÃZ^[ÌOa@ÌåAíÈáèãtÉæéZOOMðgÁÄÌ×ïªsíêܵ½B
o[Íea@ÌtbV
}Æçtåwa@©çÍáäæ¶Acæ¶Aغæ¶AD´ãÃZ^[©çÍäæ¶AåËæ¶A·ªæ¶AOYæ¶ANÃa@©çÍóû涪QÁ³êܵ½B
ÍçtJÐa@ŤCµÄ¢égÅ·ªK^ÉàçtåwïêÉÄñÅ¢½¾«QÁ·é±ÆªÅ«Üµ½B

ªåwa@ïêÌlq
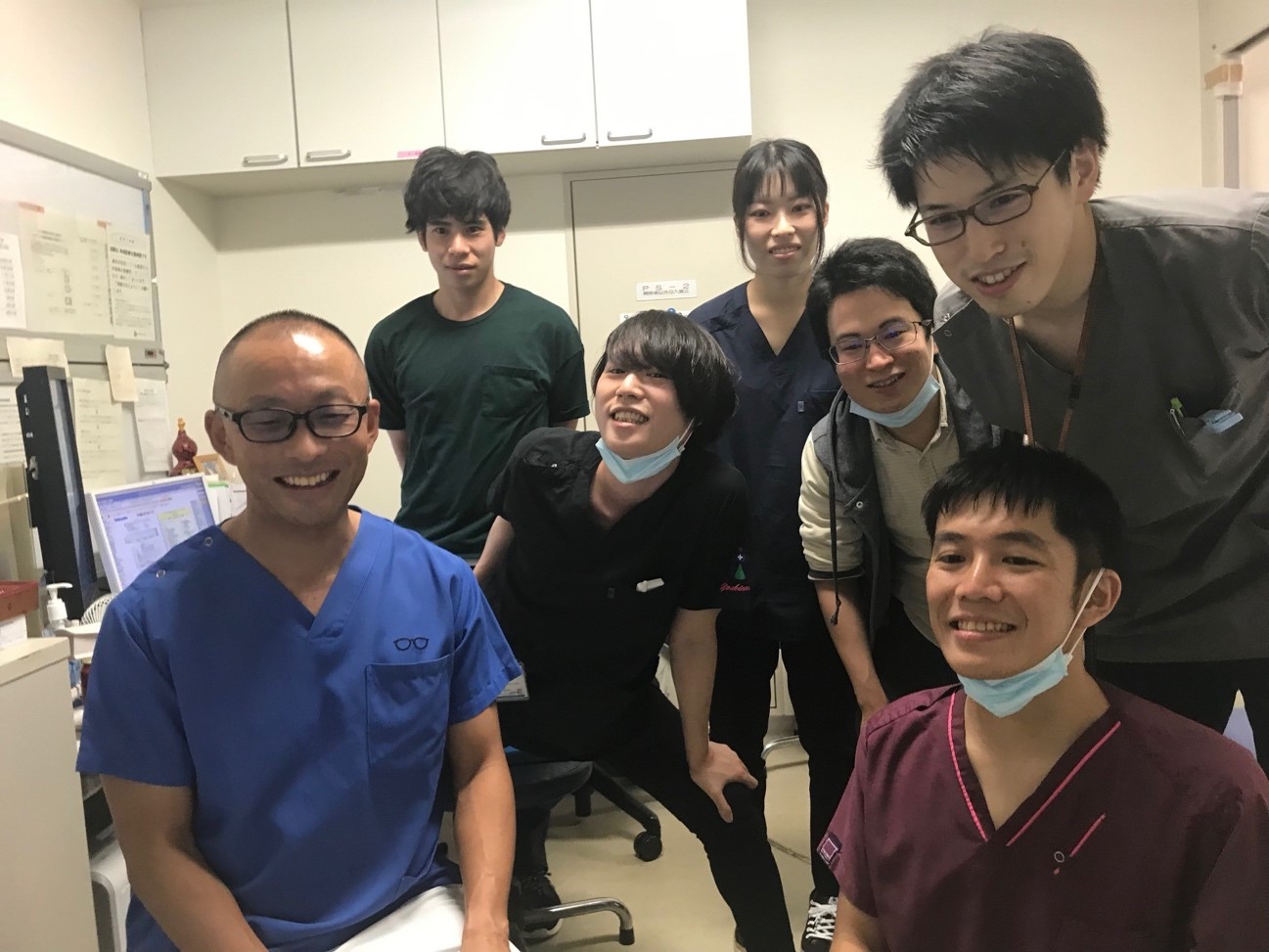
ªD´ãÃZ^[Ìlq
ea@Å̤Càeâ¶É¢Ļê¼êÌt}ª\µAñíÉhÉÈéàeŵ½B
¼Ìa@̯úªÇÌæ¤È¤CðµÄ¢éÌ©ðmé±ÆªÅ«é@ïÍARiÐÅùÝïÈÇÌð¬ªÅ«È¢åÏMdŵ½B
¼Ìa@ÌÁFðmé±ÆÅ©ªÌ¤Ca@ÌÁFðÄF¯Å«½Æv¢Ü·AÎçâ΢à½ñíÉyµ¢ïÆÈèܵ½B
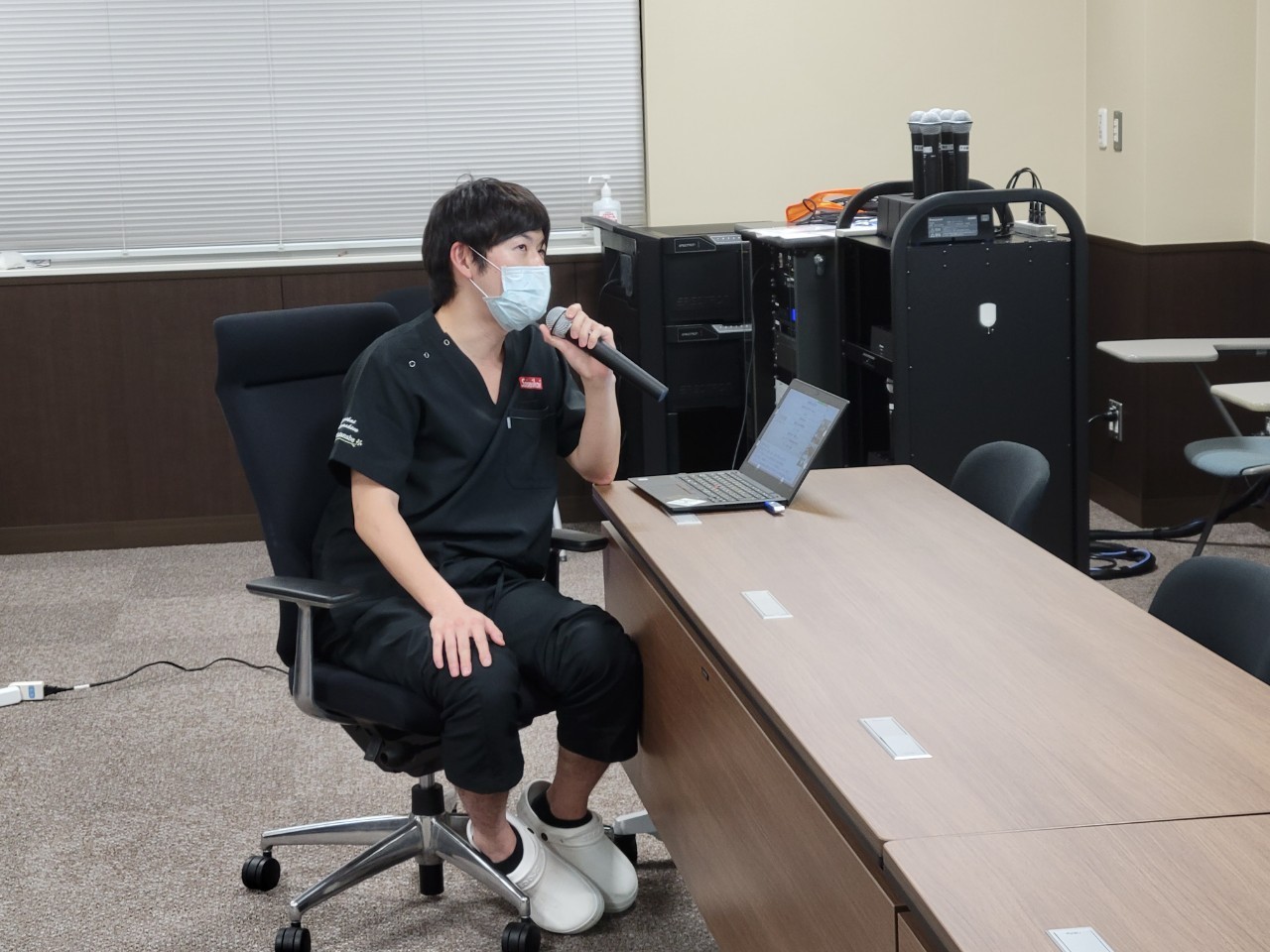
ªåwÅ̤CÉ¢Ä\·énç²æ¶

ªåwÅ̤CÉ¢Ä\·é¡æ¶
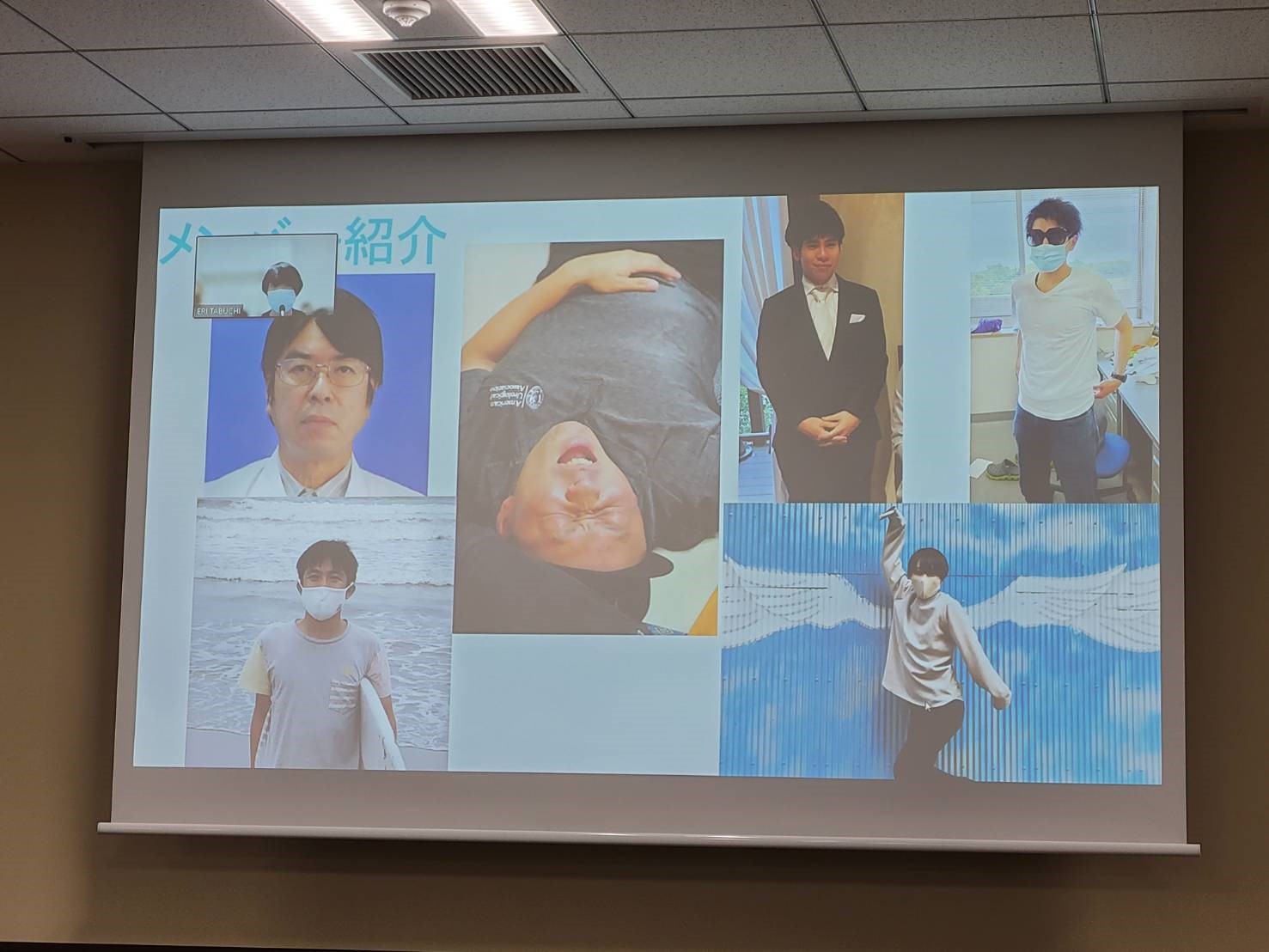
ªD´ãÃZ^[Å̤CÌ\ð·éæ¶(Cv¶ã)B
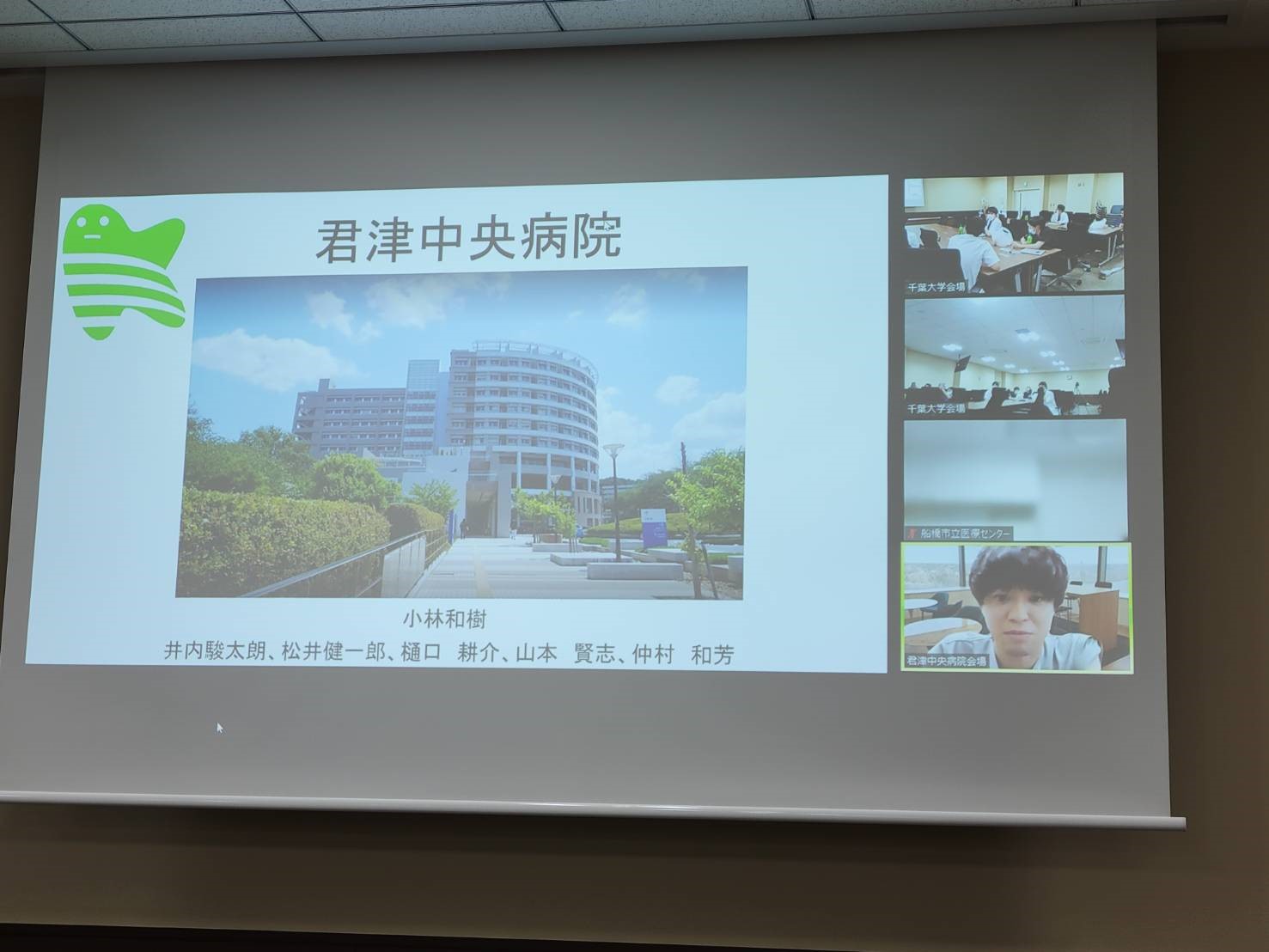
ªNÃa@Å̤CÉ¢Ä\·é¬Ñæ¶(CvEº)B
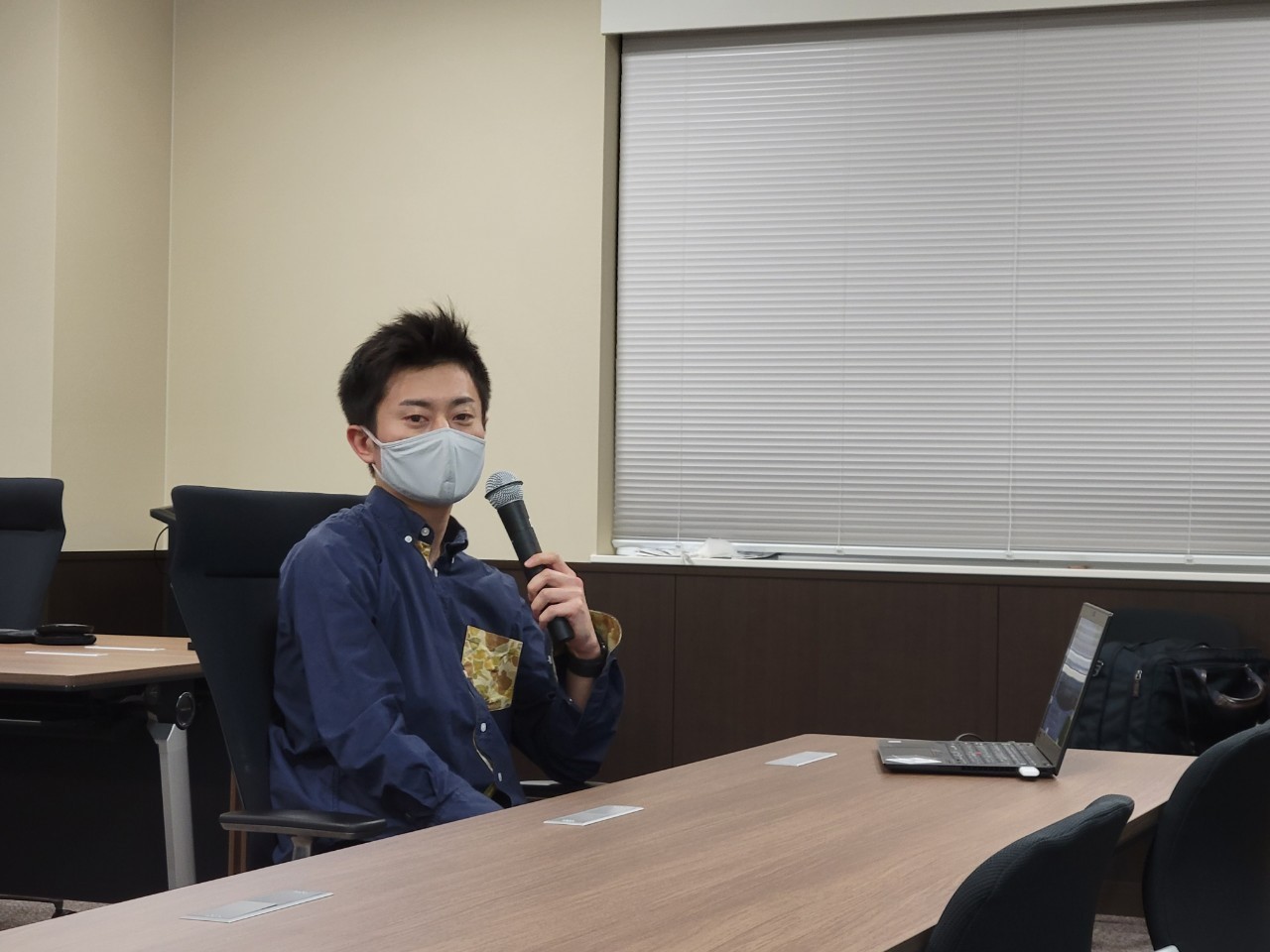
ªçtJÐa@̤CÉ¢Ä\µÄ¢é V[B

ªÂta@̤CÉ¢Ä\µÄ¢éXìæ¶
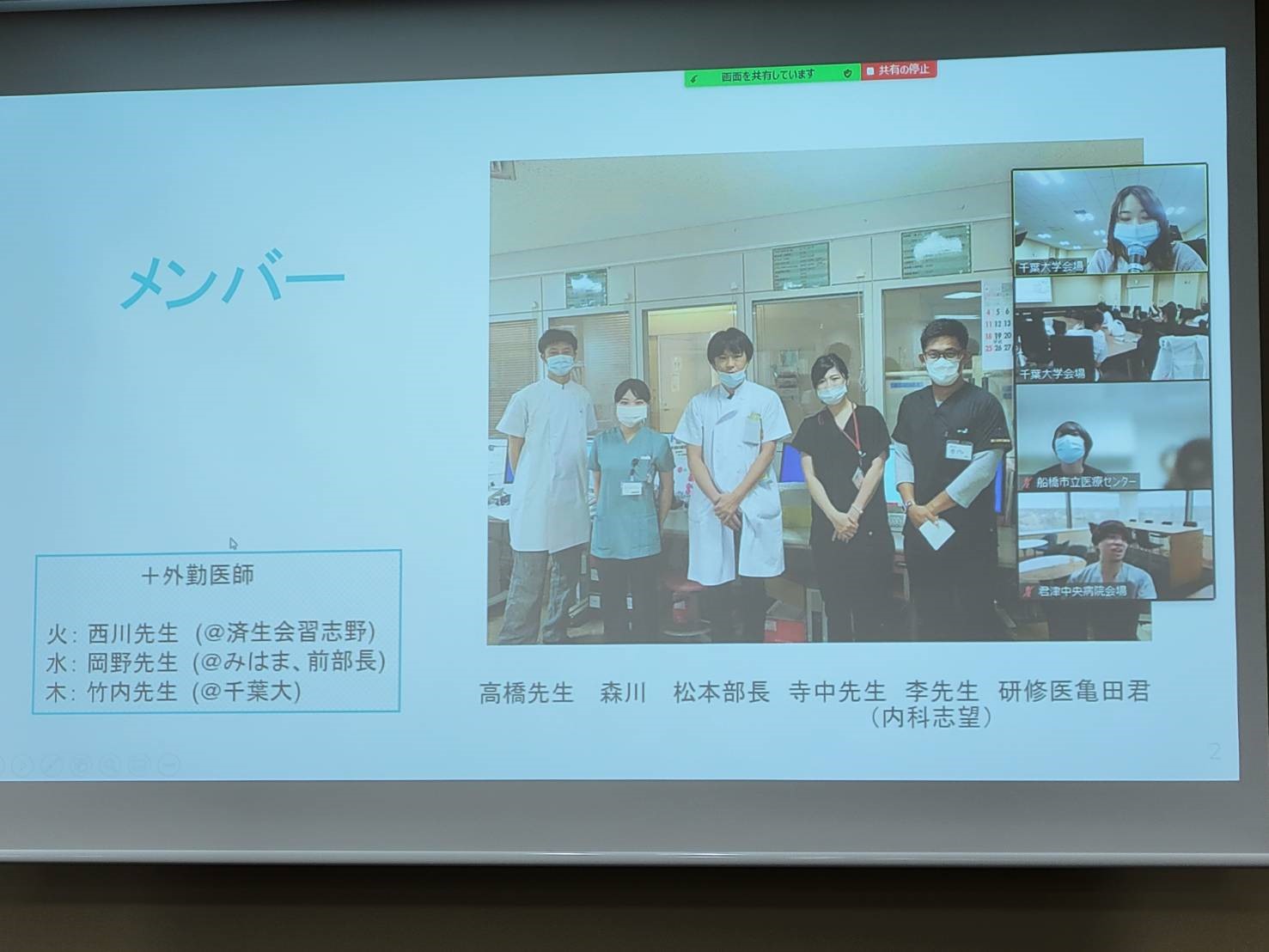
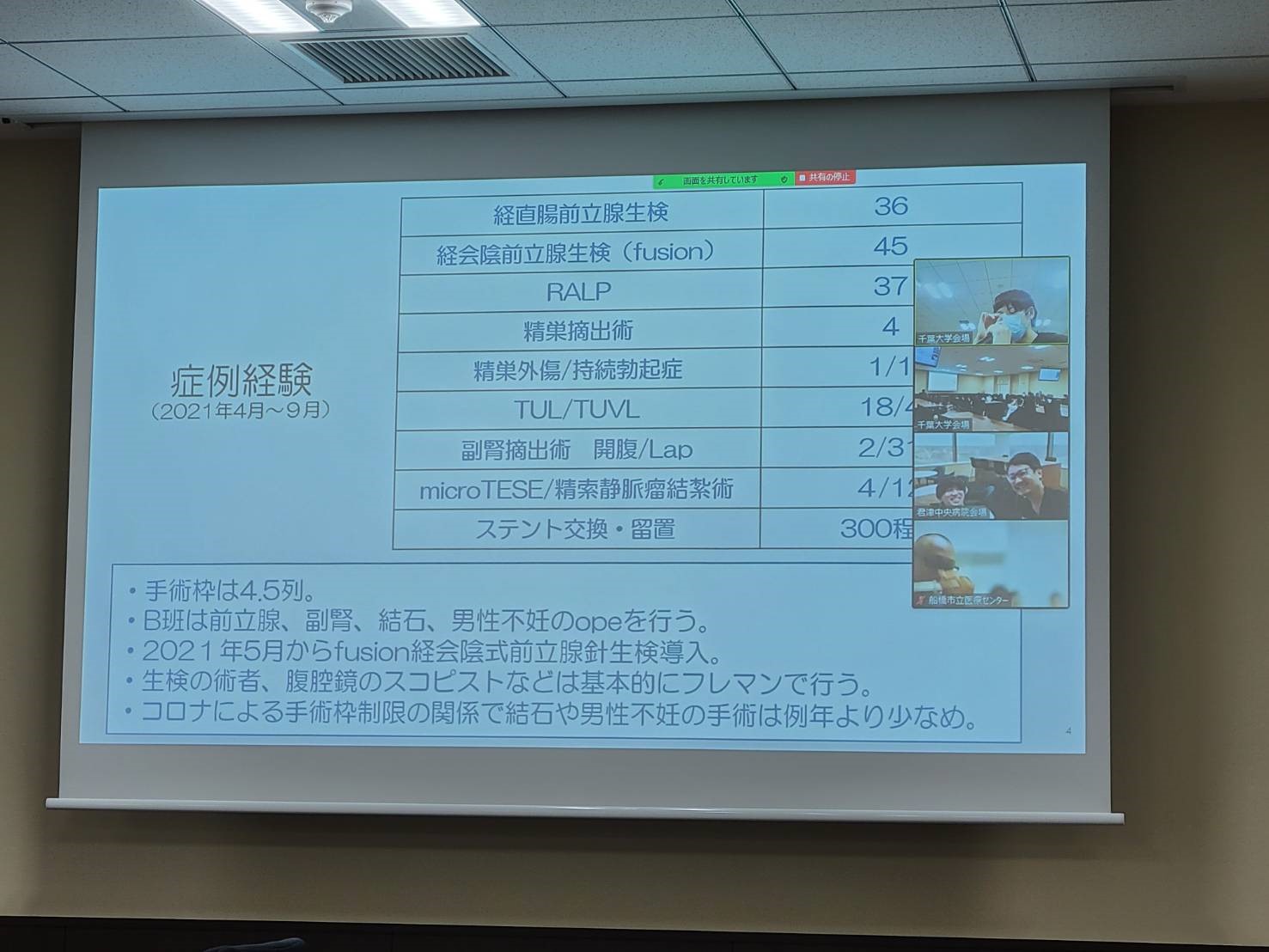
ªÇÌ\àƱàeâo[Ìæ¶ÌÐîÈÇA¤CæÌlqªM¢mêé\ŵ½I
ÅãÉóûæ¶Aáäæ¶Acæ¶Aä涩çãú¤CÌS\¦ð¨bµµÄ¢½¾«Ayµ¢ïàI¹ÆÈèܵ½B

ªÅãÉSõÅ1
RiÐÅÈ©È©±¤¢Á½@ïªÈ¢ÌÍcOÅ·ªAñíÉyµ¢Ôŵ½BRiª¿
¢½ÛÉÍSõÅWÜêéæ¤ÈïªÅ«êÎÇ¢ÈÆ´¶Üµ½B
±ÌxͱÌæ¤ÈMdÈ@ïð^¦Ä¢½¾«AéæµÄ¾³Á½áäæ¶Aäæ¶Aóûæ¶A¦ÍµÄ¾³Á½Zt@[}³ñÉúäç\µã°Ü·B èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFãú¤Cã@V[
æ2ñ Chiba Young Urologist Seminar 2021/10/7@¬ze~}[
Fl¨vµÔèÅ·AD´s§ãÃZ^[åAíÈã·T[tBõÌäÅ·B
µµ¢Äªß¬AúÌZ³©çHÌ[Üèð´¶éúX¢©ª¨ß²µÅµå¤©B
ÅßD´ÌËcÅ_ÆðcÞA¼Ës§ãÃZ^[̺æ¶É¨U¢¢½¾«AHÌûnÕðyµÝɵĢé¡ú±Ì Å·B

D´¼¨Ìðûn·é¼Ës§ãÃZ^[ºæ¶
³Ä±ÌxAÛIÉàX[p[X^[Å éçtåwâ{æ¶éæÌáèåAíÈãü¯ÌZ~i[ªJóêܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
CibvͺLÌÊèÅ·B

ÈñÆA¡ñÌZ~i[Í`åwÆÌR{ApêÌÛZbVII

`åw©çX[p[X^[ÌJeremyæ¶(¶)
m«ÆüeðËõ¦½Steffiæ¶(E)ªQXgƵÄQÁ
RiÐÅWebÌu諾ÈÁĨèÜ·ªAÛIÈð¬ªZoomïcÅeÕÉÅ«éæ¤ÉÈÁ½±ÆÍRiÐ̶bÌÐÆ©àµêܹñB
±Ìæ¤ÈO[oȤïªJÃÅ«½ÌàA¢ÄÌÝÈç¸A`AäpAØAÆ¢Á½AWAÆÌRlNVð[ßÄ¢éâ{æ¶Ìl¬ª ÁÄ̱Æŵå¤B
»ÌpêÍâËÍ(H)ÍçtååAíÈ̯åFÅ©KÁÄ¢«½¢Å·ËB
¿ÈÝÉÅ·ªASteffiæ¶ÍJUA UAAð·vOÉÄçtåwɯwð\è³êÄ¢éÆ̱ÆÅ·B
¯wɨzµ¢½¾¢½ÛÍAåwX^btÌÝÈç¸åAíȯåÅð¬ð[ßÄ¢«½¢Å·ËB

Lecture1 â{æ¶ÉæéO§BàÌò¨¡ÃÌu
à¿ëñ·×ÄpêÅÌuI
COÉ¢é©Æöo·éÙÇB

Lecture2 Jeremyæ¶Éæé{bgèpÌu
À·ÍbãåÌX[p[X^[OØ~y³ö
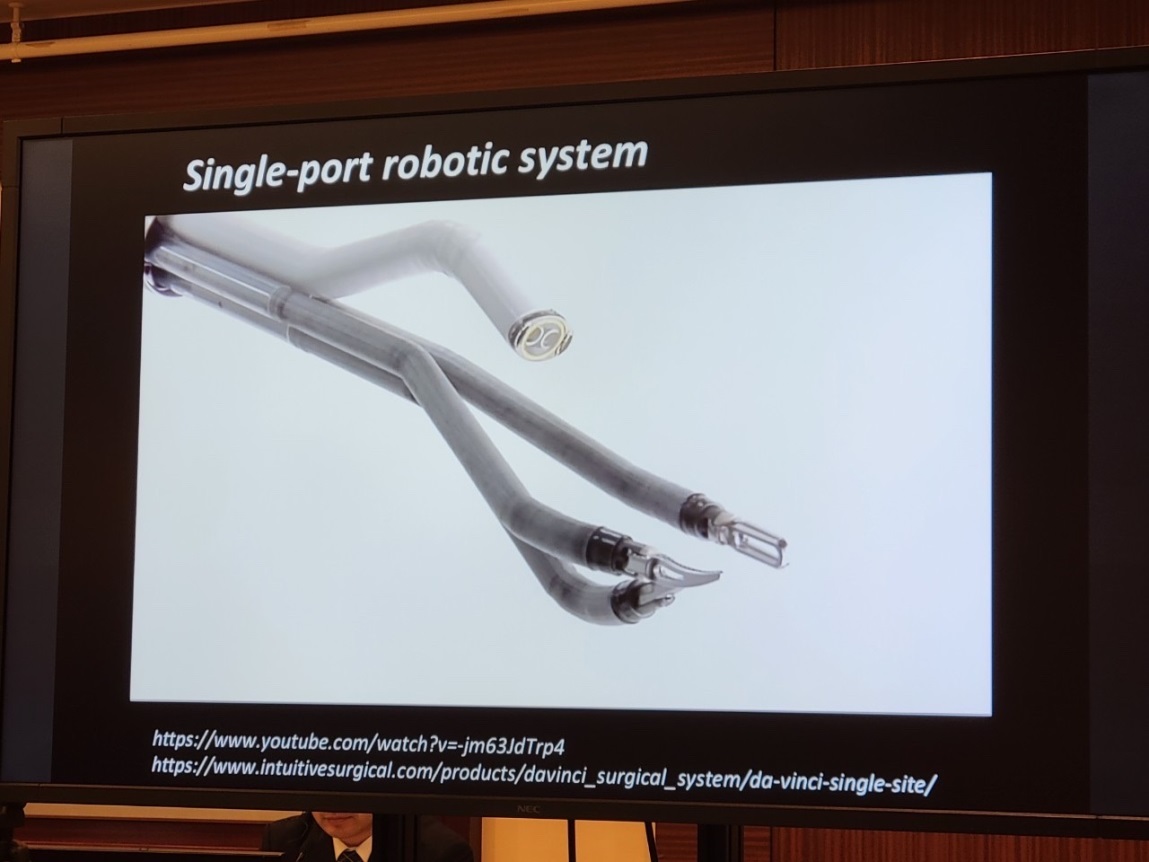
uÌÅàÅàóÛI¾Á½ÌÍASingle-portÌ_r`èpI
Jeremyæ¶Í¢EÉæì¯ÄAVO|[gÌ_r`èpðsÁÄ¢éÆ̱Æŵ½B
¬³¢½Á½êÂÅO§Bªæêéúªß¢«éÌŵå¤B
uú{Å̱üÍAçtåwåAíȪÖéèpÌVËANÃa@̺æ¶É¥ñIvÆGzȪçJeremyæ¶É¨`¦³¹Ä¢½¾«Üµ½B

s¢¿â𰩯éçtåtbV
}Ìjæ¶I
¿^ÅÍAj涪u{bgèpªå¬ÆÈéãÅAJ èpÌZpÌüãÌâèÉ¢ÄÍÇÌæ¤É¨l¦©vÆ¢¤¿âÉεÄAJeremyæ¶Íu{bgèpÅÍæèÚµ¢ðUÌF¯ª[Üé½ßAJ èpÉàpªÂ\ÆÈévÆÌ©ðð¦³êܵ½B
jæ¶Ìæ¤ÉAObVuÉ¿â·éQÁp¨AÆÄàf°çµ¢Å·ËB
±Ìæ¤ÈáèãtÌGlM[űê©çÜ·Ü·åAíȪ·èãªÁÄ¢Ìŵå¤I

â{æ¶ÌiïÉæéO§Bàò¨Ã@ÉÖ·éMµ½Panel Discussion
â{æ¶Ì¬êéæ¤ÈpêÌiïÉ£¹çêA©ªàpêÅgCµÄÝܵ½ª``N·¬ÄJeremyæ¶àê΢ŵ½B
ïêÉ¢½New YorkerÌáäæ¶ÉãíÁÄà碽©Á½Ìª{¹Åµ½B
O§BàÌò¨¡ÃÍßNIðª¦AÉGÉÈÁÄ«Ä¢é½ßc_Ì]nªâ¦Ü¹ñB
ÇÌæ¤È³ÒlÉÇÌò¨IðªÅKÈÌ©A¡ãà³çÈ餪Kv¾Æl¦³¹çêܵ½B
kåÖAÌuÝ¿ÌstudyvÌæ¤ÉAçtåwàÖAa@Ŧ͵ÄrbOf[^ðWßuÚ¤»¤study(H)vªÅ«éÆæ¢Å·ËB

ÂßÍâÁÏèu[IvÌ|[YÉÄ
ÅVÌãÃZpâ¤ÉçtåwåAíÈàQüµÄ¢ÉÍA±Ìæ¤ÈÛð¬Ís¾ÆÄF¯³¹çêܵ½B
±Ìæ¤ÈÆÄàMdȤïÉQÁ³¹Ä¢½¾«A´Ó\µã°Ü·Bçt©ç¢EÖIFÅæ£ÁÄ¢«Üµå¤B
¨Ü¯
oqÌZí©HI ZMRÌvÛ³ñÆ
ÅãÜŨt«¢¢½¾« èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFD´ãÃZ^[ã·@ä º
DÀK& o¾X[`Og[jO
ͶßܵÄB
{NxæèçtåwåAíÈŨ¢bÉÈÁĢܷ{{üÆ\µÜ·B
çtåwð²Æã2NÔsàŤCðµÄ¢½ÖWÅA2NÔèÉçtÉAÁÄÜ¢èܵ½B
åwãµêeµñ¾nÅdªÅ«éìÑð©ÝµßȪçúXÌfÃÉ¢»µñŨèÜ·B
³ÄA¡ñÍJohnson&JohnsonlAETHICONlä¦ÍÌàÆsíêܵ½DÀKÈçÑÉ o¾X[`Og[jOÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñµÜ·B
DÀKÍ714úAâ{æ¶A¡ºæ¶w±ÌºAtbV
}5l({{Ajæ¶A¡æ¶Anç³æ¶Aغæ¶)Aåw@¶ÌyGæ¶AO_æ¶AãõÌáä涪QÁµÄsíêܵ½B
{¨Ìç³ÈªçÌ¿´ED¢Sn(H)ðÖélHçAØÌçðèÉAvDÌûKð³¹Ä¢½¾«Üµ½B
çDÍèpÆØÁÄàØ裹ȢåÏdvÈZpÅ éÆF¯µÄ¢Ü·ªA¡ñÌÀKðʶÄDÌ[³ðÀ´·éÆÆàÉA©ªÌZpÌ¢n³ðÉ´·é±ÆÆÈèܵ½B
¡ãàSðYê¸æ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
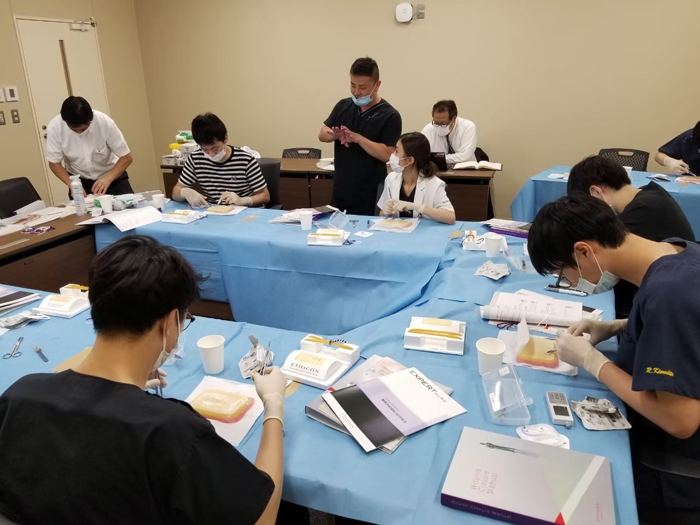
↑¯úÌÔ½¿àFvªµÄ¨èܵ½B
Ê^©çMʪµÅà`íéŵ天B
±¢Ä o¾X[`Og[jOÌñÅ·B
±¿çÍ727úA{@NjJXLYZ^[ÉÄsíêܵ½B
ÀÛÌ o¾èpÅgíêÄ¢é@Þðgp³¹Ä¢½¾«ADâççqìðûK·é±ÆªÅ«Üµ½B
ú ããÌæ¶ûÌ o¾èpÉJ¿ÆµÄQÁ³¹Ä¢½¾@ïརÌÅ·ªA¢´©ªÅìµÄÝéÆSvÁ½æ¤É®©·±ÆªÅ«Ü¹ñB
ããÌFlÌNâ©Èèrð©ÈªçAÄO©ªÅàÅ«»¤¾ÈƧ©ÉvÁÄ¢½±Æð±ÌêðØèĨlÑ\µã°Ü·B
»êÅà«íê¬ÌA½Æ©ÌDðâè°é±ÆªÅ«Üµ½B
¡ñÌo±ð³ÊɵȢæ¤úX¸iµÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
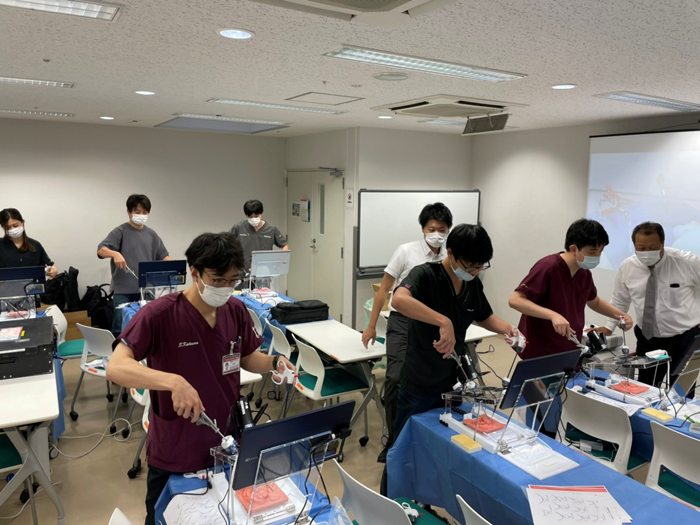
↑g[jOÌlqB
úÍSgØ÷Éŵ½B
åwa@Æ¢¤@ÖÌ«¿ãAǤµÄàsa@ÅúX±¬µÄ¢é¯úÌÔ½¿Éä×ÄÀZÌ@ïªÈÈ調ÆvÁĢܵ½ªA±¤¢Á½MdÈ@ïðpµÞçÉÇ¢t¯Ç¢z¹Åæ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
ÅãÉAMdÈÀKÌêðñµÄ¾³Á½Johnson&JohnsonlAETHICONlA¨Zµ¢w±µÄ¾³Á½ããÌæ¶ûɱÌêðØèĨç\µã°Ü·B
èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFãú¤Cã@{{ ü
Urology Today in Chiba 2021AáèåAíÈAïc
FlAͶßܵÄB¡NxçtåwåAíÈÉüÇvµÜµ½jÅ·BEà¶àí©çÈ¢æ¤ÈóµÅ4©çåAíÈƵÄÌêàð¥ÝoµÜµ½ªA¢àÌÅCªÂ¯Î3ªo¿Üµ½B©ªÌ¢n³ÆÍs«ðÉ´·éúXÅ·ªAåwÌæ¶û̲w±à èA[Àµ½úðÁĨèÜ·B
³ÄA¡ñÍæúJóêܵ½Urology Today in Chiba 2021ÆáèåAíÈAïcÌlqð²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
Urology Today in ChibaÍçtåwåAíÈÉ»¡ª éw¶³ñâüÇðl¦Ä¢éú¤CãÌæ¶ûðÎÛÉNJóêéZbVÅ·BáNÅ êλnJóêé͸ŵ½ªARiÌóµðÓÝÄ¡NàICÅÌJÃÆÈèܵ½Báäæ¶Ì[AìêégWhy Urology?h̲uÉnÜèAìjæ¶ÌoN[o[Å̤¯wÌúXÌÐîAÜIîæ¶Ì¯wÆ»ÌãÌÕ°ÌúXÌÐîAåw©çͲËqaæ¶Æâ{Mêæ¶ÌåAíÌ»ÝƢƢ¤e[}Å̲uB»µÄÅãÉÍçtåwåAíÈÌÖAa@Å é¡lJÐa@Ì·ÌicáÁ÷æ¶Ì²uª èܵ½B
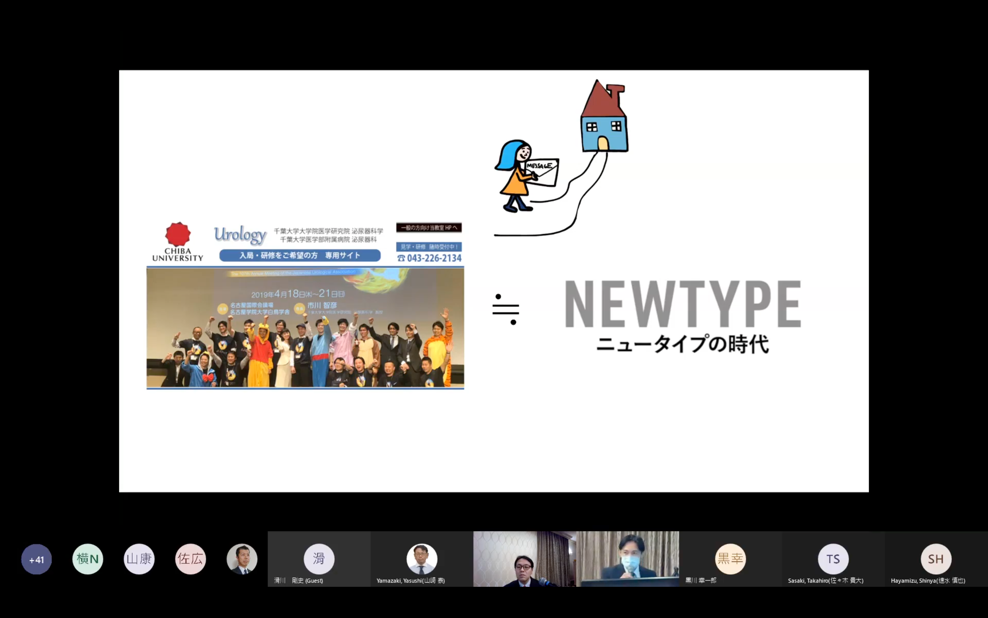
â{æ¶Ìtake home massage gåAíÈÍNEW TYPEIIh
w¶³ñâú¤CãÌæ¶ü¯ÌZbVÌ͸ªAÇÌæ¶û̲uàåÏ»¡[A޵멪ª·«üÁĵܢ2ÔÆ¢¤Ô𴶸 ÁÆ¢¤ÔÉIíÁĵܢܵ½BåAíÈ̪ìÌL³A[³ðÄmFµüßÄåAíÈãðuµÄÇ©Á½ÆÀ´µ½ZbVÉÈèܵ½B
áNÅ êÎuãɧeïªJóêÜ·ªARiÅ~ÉÈÁĵÜÁ½ÌÍåÏcOÅ·ªAICJÃÆ¢¤±ÆÅQÁÖÌ~ªºªè70¼ÈãÌûXª®³ê巵̤¿ÉI¹¢½µÜµ½B

(ãi¶æè)áäæ¶A²Ëæ¶
(ºi¶æè)¬{æ¶Asì³öAâ{æ¶
ܽæúÍáèåAíÈAïcªJóêܵ½BçtåwåAíȯåÌáèhN^[ðÎÛƵ½ICïcÅA¡ñÍ϶ïKuìa@Ì´
Måæ¶A¼Ës§ãÃZ^[̺³mæ¶A®a@ÌP«çæ¶Aåw@îáaw³ºÌÄcd涩ç»ê¼êÌÖA{ÝÌÐîÆúX̶Ðîª èܵ½BÖAa@É»ê¼êÌÁ¥ª èA¡NxÍåwa@ɢ驪ÉÆÁÄNxÈ~Asa@Åα·élqðïÌIÉC[W·éLÓ`È@ïÆÈèܵ½B
ܽ50¼ßÌáèåAíȪê°Éï·éICæÊð©ÄAüßÄ»ÝÌçtåwåAíĘ̀¢ðÀ´¢½µÜµ½B
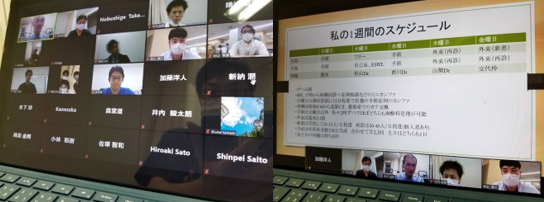
ICÅÌJÃÆÈÁ½áèåAíÈAïc
ãÃ]ÒÈOÖÌN`ÚíàXÉiñūܵ½ªAÏíç¸RiÌÒЪ¯ÜéƱëðmçÈ¢óµÅ·BܽIsbNÌJï®ÜÅ1ðØèܵ½ªAúñ¹³êÄ¢éæ¤ÉJÃÖ̹Ìèàs§¾ÅÈ©È©¯µ»¤Å·B¡NÌIsbNÍáNÌæ¤È4NÉ1x̨Õè¬ÆÍÈèܹñªAl¶É1x«è©àµêÈ¢©JÃÌIsbNA³Jóê½ÅÉÍr[ðÐèÉerÌOÅú{IècÌôðSÍŵ½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFãú¤Cã@j ¾
çtåw@åAíÈ@10NãÌ¢Öü¯ÄGCreating Social ValueiCSVj
åAíÈ@ut@â{ Mê
ðNAú{åAíÈwïïÅAu10NãÌ¢ðêévÆ¢¤ZbVÅÌuÌ@ï𢽾«Üµ½B»ÌßöÅA©ªÈèÉuçtåw@åAíÈÌ10NãvÉ¢ÄAÈñÆÈl¦éæ¤ÉÈèܵ½B
10NãAÇÌæ¤È¢Åµå¤©H
[gfÃH@`hÌæF¯A©®{bg§äÌèpH@¢ÜAäXª\úÅ«È¢¢·çÒÁÄ¢é©Æv¢Ü·B
êûÅAåwðl¦éêA20NãÉÍA©çÌâàªÈÈéÆ¢íêĢܷBƧs@l»·éÅA¾ç©ÉAåwA é¢ÍAÈƵÄÌ©§ªßçêĢܷB
Àçê½lÞÆÔÌÅAèpð⹽ƵÄ๢º¢1.5{öxB
OfÃðâ·±ÆÉàÀEª éÅAuåwƵÄÌ©§ÖÌVµ¢ûü«vª¡AâíêÄ¢éÆv¢Ü·B
2020N2ÉAStanfordåwÌrì¶ºæ¶ https://www.link-j.org/report/post-3344.htmlðKê½ÛAåw{VRo[ÌR{Éæéx`[ASPARK https://sparkmed.stanford.edu/Æ¢¤åw{NÆÆ{ÆðÂÈ®V|WEÈÇAAJf~AÌNÆÌêð½³ñ©é±ÆªÅ«Üµ½B
SPARKðå÷é_A涩giîb¤ÒjàA·ÅÉñÂÌNÆðpµA»Ýàx`[ÌзàC³êĢܵ½B

rìæ¶ÆCXGlNÆÆÆVRo[ÉÄ

Stanfordåw@SPARKÌïêÉÄ
¡ãAú{AÀÑÉAçtåÌãÇàAÖAa@ÌÇâÕ°E¤ÌÝÈç¸AVµ¢Ðï¿lÌn¢FuCreating Social ValueiCSVjvªâíêÄ¢éÆv¢Ü·B@
ÂÜèAåw©çAãÃÌUnmet NeedsÉεÄAÕ°¤Aîb¤AlÞÌNet WorkÆMpðpµÄux`[NÆv·éæ¤ÈãÉÈéÌ©àµêܹñB@
êÊIÉéÆâïÐð¦·uCompanyvÆ¢¤¾tÍAuðÛA«¢AÔAF¾¿AlÌWÜèvÈÇÌ깩ç«Ü·B
»¤l¦éÆAãÇâ¯åàuCompanyvÅ·B
«IÉÍAãÇA é¢ÍA¯åàAuçtåwåAíÈÆ¢¤¼ÌCompanyvƵÄAçt§A»µÄA¢E̳ÒðµÅàK¹É·é½ßÌSocial Valueð\zµÄ¢¢ªéÌ©àµêܹñB

ASCO GUÌÛAStanfordåwãwKâ Team CSVƺÉ
i¶©çARcæ¶Aäæ¶Aâ{Acºæ¶Aäæ¶j
2021N7»ÝAÈÅÍAÁÉãHwªìÌCSVÉü¯ÄA
}gåw@}ÙîñfBAnEfBAn¢ªì@zêæ¶ https://digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp/
(æ¶Ì®æuWEEKLY OCHIAIvͱ¿ç)A
StanfordåwoCIfUC@rì¶ºæ¶ https://techblitz.com/aging-stanford-ikeno/
(rìæ¶Ì´®IÈTED®æͱ¿ç) ÆàR{ðJnµÄ¨èÜ·B
Vµ¢ãÖü¯ÄA¡àA¢àAOne TeamŧíµÄ¢¯½çÆv¢Ü·B@

çtåKâAzêæ¶Æsì³ö
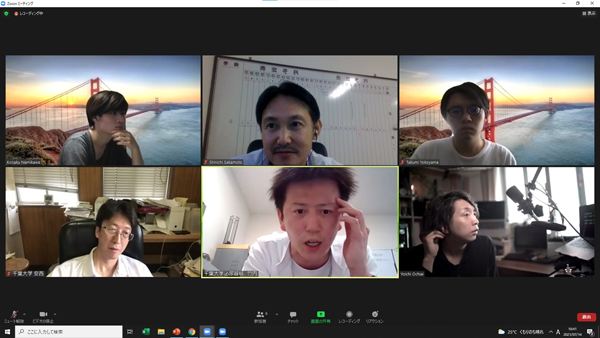
æ¶ÆÌZoomïcÉÄDiscussion·é|àæ¶i^ñºj
¶ÓFåAíÈ@ut@â{ Mê
yà¯wLzéÊãÈåwQmpãw
2021N3ÜÅéÊãÈåwQmpãwÉà¯wð³¹Ä¢½¾«Üµ½A2011N²ÌcC½Å·B
éÊãÈåwQmpãwÍ2ÂãÌì涪æÉC³êÄ¢½¤ºÅAÍ2017N4ÉãCÌåw@¶ÆµÄîb¤ðwÔ½ßɯw¢½µÜµ½B
¤ºðåɵĢéÌÍAåwVNaÈogÌàÈãÅ éäã³öÆA»ÌlÅáÈãÌx]ömq³öÅ·B
¤ºÆµÄÍAjàóeÌâãÓÉÖ·é¤ðe[}ƵĨèAªñ̪ìƵÄÍO§BªñâûªñðåɵÁĢܵ½B
ªñÈOƵÄÍAØ÷â~gRhAÉ¢Ä̤à¸ÍIÉsÁĨèÜ·B

Qmãw¤Z^[̨
¿å¤Ç2016N ©ç³ÒRªñ×Ef̤ðnßĨèAìã³öªåÉ·ééÊãÈåwãÃZ^[åAíÈ©çeíåAíªñÌðàç¢AMÌãÅ·úIÉ|{µÄA³çÉ»êðÆusS}EXÉÚA·éÆ¢¤À±fÌm§ðÚwµÄ¨èܵ½B
»ÌÅAÍåÉtªñðS³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ÍܾZpIÉàêt¾úÅ èA·ú|{Â\Èfð¦É쬷éè@ªm§³êĢܹñŵ½ÌÅA͸s±«Å ÁÆ¢¤ÔÉÅÌ2NªoÁĵܢܵ½ªAúé¢ë¢ëȶ£ðèȪçsöëðJèÔµAµ¸Â~ϳê½o±âZpÌüãÉæÁÄuCNX[ðoÄAÅIIÉÍ¡nÌfð÷§·é±ÆªÅ«Üµ½B
tªñÈOÌåAíªñɨ¢Äà¯lÌÀ±nÌì¬É¬÷µÄ¨èAÁɸîáɨ¢ÄÍì涪¢EÅÅ̬÷áƵijÒRªñ×EEÙíÚAfð쬷éÈÇAÍðí¹ÄàÌåAíªñɨ¯é¯ªìÌWÉv£Å«½ÆvÁĨèÜ·B
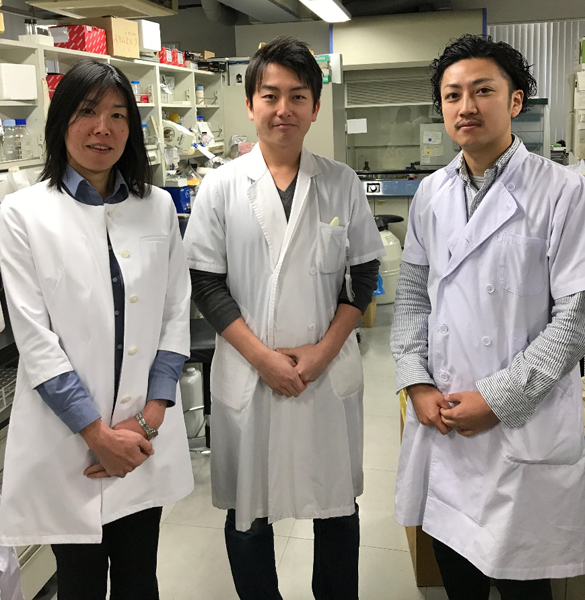
éÊãÈåwQmpãwåAíÈ`[
i¶ÍãÈÈåÌkRæ¶AEÍoN[o[¯wÌìæ¶A^ñÍMÒj
ܽAéÊãÈåwÅsÁ½À±è@ÅÍAªñ²×El×EÆæÎêéAªñÌeÊÌæ¤ÈªæðZkµÄ|{·é±ÆªÅ«Aªñ×EWcÌÅà¡ÃïR«Ì¢×EÌÁ«ðð͵A»êðWIƵ½¡ÃÌJªÚw¹éÆ¢¤Ýª èÜ·B
±Ìæ¤ÉAÕ°Æîb¤ÌÔðÂÈ®æ¤È¤Íãt¤ÒÉÆÁÄÍÆÄ໡[AZµ¢Èªçà[Àµ½¤¶ðé±ÆªÅ«Üµ½B
¤ÒƵÄàApê´_¶2ñApêà2ñAú{êà2ñAwïÜ1ÂAÁ1ÂÆ¢¤`ÅoXædð³¹Ä¢½¾±ÆªÅ«Üµ½B
éÊãÈåwÌLpXÍéʧÌ`¼É èÜ·ªA±êÜÅ©Á½éʧàÌ¢ë¢ëÈnæÉKêé±ÆªÅ«A¶àyµß²·±ÆªÅ«Üµ½B
©gÍçt§ogÅA²ãÍ_Þì§Ì¡lJÐa@ÅÕ°ãƵÄ̤èrðÏÝܵ½ªA¡ñîb¤ÒƵÄéʧÅwÑA4©çÍܽçtåwÉßç¹Ä¢½¾±ÆÉÈèܵ½B
ðñs3§ð®éÁÆêüµ½10NÔŵ½ªA»ÌÅéÊãåâ¡lsåÌåAíÈÌæ¶ÆàÇÈèA³çÉ¢ë¢ëȲà ÁÄåãåâªåÈÇ¢næÌæ¶ÆàùÝFBÉÈé±ÆªÅ«Üµ½B
AEF[Ì«ÉêJµ½êÊà½X èÜ·ªA»ÌªA©¯ª¦ÌÈ¢o±à¾çê½æ¤Év¢Ü·B

¬{æ¶Aâ{æ¶A¡ºæ¶ªéÊãÈåwɲK⢽¾¢½ÛÌÊ^
±ê©çåw@Éiw³êéæ¶ûàAµçt©ç£ê½Æ±ëÅ ÁÄàA`Xª êÎêxçtå©ç£ê½Â«Égð¨¢ÄÝéÌà«È¢©àµêܹñB
ºÐêxÍ¢µÄÝÄÍ¢©ªÅµå¤©B
¶ÓFc@C½
åAí o¾vO
±ñÉ¿ÍB
åAíÈ1NÚ Ôê åMÅ·B
¡NxtbV
}ÌÅãÌXVÆÈèÜ·III
v¢ÔµÄÝéÆ1NOÉêZÅ éçtåwÉAÁÄ«Ä©ç·®ÉÙ}Ô龪߳êÄAÁÉa@ÆÆð·é±Æª½©Á½Å·B
NxÍव¾é¢êNÉÈéÆ¢¢ÈÆv¤¡ú±Ì Å·B
³Ä»ñÈúXÌA213úÉæ20ñçtåAí o¾³çvOÉsÁÄQèܵ½II
vXÌz§É»í»íµÈªçAìèÌJohnson&Johnson{ÅØÌ o¾ºÅÌtEðsÈÁīܵ½B
ããÌæ¶ûªiâÁÄ¢éìð½Év¢oµÈªçAǤɩ±¤É©Eo·é±ÆªÅ«Üµ½ªAúXÌûKÌKv«ð´¶éÆÆàÉA¡ãÌ©ªÉ«èÈ¢±ÆªæðÅ«éMdÈo±Åµ½B
w±µÄ¢½¾¢½¡ºæ¶A|àæ¶AǤà èªÆ¤²´¢Üµ½B

eXÅÌLOBe
bèªÏíèÜ·ªA224úÉNxçtåa@ÅtbV
}Ì涽¿{غ涪\µè̽ßÉÄêܵ½B
ÝȳñÆÄà^ÊÚÉ\µèÌbð·¢Ä¾³èA èªÆ¤²´¢Üµ½B
Ù¢à¾Å²ßñȳ¢B
¡ãXVÍNÌæ¶ûÉõµ½¢Æv¢Ü·B
ܽNxàçtåwåAíÈðå¢É·èã°Ä¾³¢III

¶©ç¡æ¶Aغæ¶Anç²æ¶A{{æ¶Ajæ¶
ÅãÉÅ·ªANÍ®a@Åα³¹Ä¢½¾±ÆÉÈÁĨèÜ·B
æw¶ãͬ·sÅ^~ÌCÉüÁ½èAÌŪµ½v¢üêÌ énÅ·B
Æè ¦¸çtÌ[H×µĩçøÁzµ½¢Æv¢Ü·B
Zpàm¯à½³ñzûµÄ±æ¤Æv¢Ü·B
1NÔ²w±¢½¾¢½æ¶ûÉÍ{É´Óµ© èܹñB
{ɨ¢bÉÈèܵ½IIIII
¶ÓFÔê@åM
åAíÈ©UpHP ÒWãL
»Ýåw@3NÚÅAçtåwîáaw³ºÅ¤ÌáäÅ·B
±ÌLðÇñž³ÁÄ¢éûÍA·ÅɲÉÈÁÄ¢é±Æ©Æv¢Ü·ªA2020N12æèãÇÌ©UpHPªVݳêĨèÜ·B
¡ñͱÌVHPÌì¬ðSvµÜµ½ÌÅA±ÌêðØèıêÜÅÌãÇHPÌÏJðUèÔç¹Ä¸«Ü·B

(¶)ãÇHPÆ(E)Vݵ½©UpHP
2010Næè11NÌðjðàÂuåAíÈÊMvÅ·ªAJnæèâ{涪êlÅLÌËÈÇðsÁĢܵ½B
FXƨZµ¢æ¶æèªåAíÈÊMWðC³ê½Ìª2019Nx©çÅA»ê©çãÇsÌÊ^BeâLÌ·MËEÒWðsÁÄQèܵ½B
±¤¢Á½LÒÌæ¤ÈƱÉgíÁ½±ÆÍ èܹñŵ½ÌÅAñíÉVNÅyµæègܹĸ«Üµ½B
ܽñeÒÌæ¶ÆìÁ½LªlÌÚÉGêAANVð¸¯éÌððµv¢Üµ½B
uO«çêÈ¢RecvðÚWÉ2019NxÍLÌXVpxðßA21ÌLðo·±Æªoܵ½B
±êÍVL^©ÆvÁĨèܵ½ªA¦ÄÝêÎ2011NxÉ24ÌLªoĨè(¤¿13ªS涷MI)AL^XVÍÈèܹñŵ½B
üßÄ»Ì Ìæ¶ų̂¢ÉÁ©³ê½æÅ·B
2020NxÍRiÐÅsà¬ÀÝ~ÆÈèXVpxªºªÁĵܢܵ½ªA2021NxÍCªðV½ÉòRÌLð쬵Ģ«½¢ÆvÁĢܷB

Sæ¶Ì{ÌLXVB
»ñÈAÈÌêå©UsÅ éUrology Today2020ªRiÐÅ~ÉÈèܵ½B
ONÌ2019NÌUrology TodayÅÍAãw¶Eú¤Cãí¹Ä20¼ÌQÁª èܵ½ÌÅA»ê¾¯Ìæ¶Ì©UÌ@視íê½±ÆÉÈèÜ·B
©gà2010NÌ©UïÅlXȨbð·¢ÄüÇðß½o¦ª èÜ·B
RiÐɨ¢ÄOnlineÅÌ©UªdvÆÈéÅA©UpÌHPðVݵæ¤Æ¢¤bÉÈèܵ½B

(¶)2019NUrology TodayB·ÅÉüǵÄê½æ¶ªòR¢çÁµá¢Ü·B
(E)2010NÌ©UïB±Ìo[àÙÆñÇüǵܵ½B
®«nß½ÌÍ2020NÄB
HPXVðSµÄº³ÁÄ¢éÆÒÌu¢ÇνîÑv³ñƲkµÄ¢«Üµ½B
RecÍHP©çÚݵ½àÌà èܵ½ªAãÇÐî̶ÍÈÇÍÙÚSÄ2020NÅÉXVµÜµ½B
´eðñeµÄ¾³Á½sì³öAZ³ðµÄº³Á½¡ºæ¶Eâ{æ¶ èªÆ¤²´¢Üµ½B
ܽÍvO~OSÒÅ·ÌÅAC[Wð`ɵĺ³Á½ÌÍu¢ÇνîÑv³ñŵ½B
rÅXChV[ðÇÁµ½èASÌÌ\¬ðϦ½èÈÇA\ZàÅÍÆÄàoÈ¢±Æà˵ܵ½ªZÊðø©¹ÄâÁĺ³¢Üµ½B
u¢ÇνîÑv³ñ̲sÍɱÌêðØèÄäç\µã°½¢Æv¢Ü·B
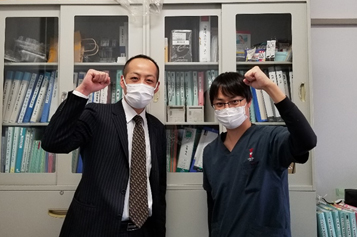
u¢ÇνîÑvã\En³ñÆáä
©µÄ4©ÙÇ©¯Ä©UpHPª®¬µÜµ½B
±ê©çÍuO«çêÈ¢vÌÝÈç¸u£ÍðM·évHPƵÄÏÉIÈXVðµÄ¢«½¢ÆvÁĨèÜ·B
2021NxÌÚÊƵÄÍuÖAa@ÐîvÌy[WÌÇÁðl¦Ä¨èÜ·B
»Ý̯å̤¿åwÉ¢élͲêÅ èAÖAa@ÅdðµÄ¢éûªy©É½ÈÁĢܷB
ÁÉáèÍv16ÌÖAa@ÖoüµÄ¨èANªÇÌa@ÉÝеĢéÌ©í©çÈÈÁĵܤæ¤ÈóµÅ·B
»±ÅA¯åƵÄÔÌßµðmé±ÆAܽea@ÌAs[ðµÄ¸±ÆðÚIÉuÖAa@Ðîvy[Wðìë¤ÆbµÄ¨èÜ·B

æêeƵÄNÃa@É·MËÅ·B
4©çÍåwa@ÌհƱÖÚèÜ·ªAø«±«Recð[À³¹ÄAçtåwãw®a@åAíÈÌ£ÍðMµÄ¢¯êÎÆvÁĨèÜ·B
éæ̲ñÄâ²v]ÈÇ èܵ½çAáäàµÍåAíÈãÇ(urohisho@chiba-u.jp)ÜŨm繸¯Ü·ÆK¢Å·B
êÉHPð·èã°Äêé¯uà¨Ò¿µÄ¨èÜ·B
¡ãÆàæ뵨è¢vµÜ·B
¶ÓFáä@
åw@¶É¢Ä
åw@3NÌÀ¡Æ\µÜ·B
¡ñÍåw@¶É¢IJÐĢ½¾«Ü·B
çtåwåAíÈÍ»ÝAåw@¶ª12¼¨èA®³ºÍåAíÈwAòwAªqîáwAîáawAffawAAIilHm\jA¼å̪q×E¡Ã¤åÈǽòÉí½èÜ·B
åAíÈÌåw@¶Íxbht[ŤÉſޱƪūܷB
±ÌbÜê½Â«ÍAsì³öðͶ߯åÌæ¶ų̂ÍY¦ª ÁÄ©ç±»À»µÄ¨èÜ·B
ÌXPW
[ͺ}ÌÊèÅA½úÍ3úöxð¤É Äé±ÆªÅ«Ü·
BÀ±ÌúöæÅÍIúOÎúâyúɤðs¤±Æà èÜ·B
ܽAT1.5úöxÌOÎâ3úöxÌO¼à é½ßûüÊÅêJ·é±ÆÍ èܹñB

»Ì¼Ìåw@¶ÌƱƵÄÍAÌñûâðUÌÌÞAT1ñÌåwOSÈǪ èÜ·B
ÅßÅÍVãwÖÌøÁzµìÆðs¢Üµ½B
±êçÌƱðåw@¶ÅªSE¦ÍµsÁĨèÜ·B
É1x̤ºïcÅÍAe³º®Ìåw@¶ªWÜèAîñ¤LÆfBXJbVðsÁÄu`[vƵÄAgð[ßĨèÜ·B

¤ºïcFûÌæ¶ÍWEBQÁ@@@@êÔEªsìqF³öAêÔ¶ª
Íòw³ºÉ®µAÀ¼®F³öÌäw±Ì³Aîb¤ðs¢Üµ½B
O§BàÌVK¡ÃòƵÄA~m_gX|[^[jQò̤ðsÁīܵ½B
VK¡Ãò̤ÍãûêÅ·®É©¹éàÌÈÌÅÆÄ໡̦àÌŵ½B
òw³ºÍAbgz[ÅAß²µâ·¢Â«Å èAÌÑÌÑÆÀ±ðißé±ÆªÅ«Üµ½B

òw³ºF¶Ê^OñªÀ¼®F³öAãñE©ç2ÔÚª 3ÔÚªÖ¡æ¶
EÊ^¶©ç|ºæ¶Aóûæ¶A
ܽAÈutÅ éâ{Mêæ¶Ìäw±Ì³AÕ°¤às¢Üµ½B
O§BàÌÕ°f[^ðð͵Aj«zieXgXejâǽXRAiGlasgow prognostic scorejÈǪ\ãÆÖA·é±Æð¾ç©ÆµA2{_¶»·é±ÆªÅ«Üµ½B
The Prostate uHigher serum testosterone levels predict poor prognosis in castration-resistant prostate cancer patients treated with docetaxelv
cancers uPrognostic Value of High-Sensitivity Modified Glasgow Prognostic Score in Castration-Resistant Prostate Cancer Patients Who Received Docetaxelv
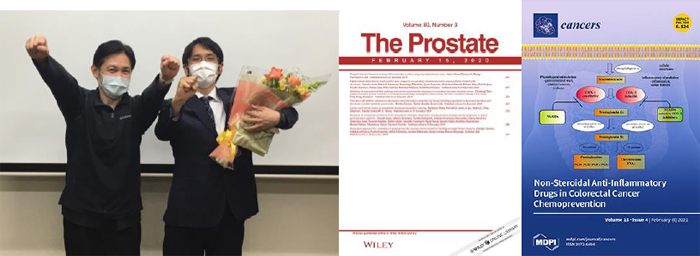
â{Mêæ¶i¶jÆÌc[Vbg@@@@@@@@@Ìp_¶ÌfÚ\@@@
ÍAîb¤ÆÕ°¤ð¼ûs¦é@ïÉbÜêA[Àµ½åw@¶ðé±ÆªÅ«Üµ½B
åw@¶Í¤ÉvªÅ«éMdÈÔÅ·B¤ÉµÅ໡ª 驽ͥñçtåwåAíÈÖ¨zµ¾³¢B
ÅãÉÈèÜ·ªAÕ°¤É²¦Í¢½¾«Üµ½D´s§ãÃZ^[̲¡Mvæ¶A_¶ì¬Ì²w±ð¢½¾«Üµ½sìqF³öA¬{°y³öAâ{Mêæ¶A¡ºLCæ¶AJCHOVhfBJZ^[ÌÔq÷êYæ¶ÉSæèäç\µã°Ü·B
¡ãÆà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨è¢\µã°Ü·B
¶ÓFÀ¡@hC
ãwÐt¯ìÆI
2020NxüÇÌOYÅ·B½fæ訢bÉÈÁĨèÜ·B
25úAICÅsíê½åAíȯåïÅAsì³öªçtåwåAíÈÌ60Nðjâå@LpXÌ¡ÌÌÏ»ðÐîµÜµ½B
»ÌÅàGêĢܵ½ªA®a@ÌVfêI[vµAãwVàOÏÍ®¬·éÈÇAå@LpXÍ»ÝHÌbV
Å èÜ·B
åAíÈÌãwVÖÌøzµÍNxð\èµÄ¢Ü·ªAæúøzµÉü¯Ä̳ºàÌÐt¯ìÆðs¢Üµ½B
¡ñÍ»ÌÍlð¨`¦µÜ·B
úÍsì³öAåw@¶AtbV
}3lÆZt³ñAé³ñªQÁµÜµ½B
2ã{ƵÄÍg©AâDÌìÆúaÅ èܵ½B

¨Qµ½Èéæ¤ÈzCÅ·B

sìæ¶àìÆÉQÁ³êܵ½B
ãw5KÌÉÉ
µA±ê©çª·écåÈÊÌGAÞÌ©Ævp[gÌüÁ½P[XA@BÞÆÎÊÅ·B
ܸͶ£ÞÌ^Ñoµ©çJnµÜµ½B
é³ñAZt³ñªOɩɵĺ³ÁÄ¢½ÌÅA»êðoPc[û®ÅLºÜÅoµAäÔÉæ¹Ä¢«Ü·B
äÔ²ÆGx[^[ÅãwOÌWÏêÜÅ^Ñܵ½B
®ÌêpðèßÄ¢½{ÌRŵ½ªAlCípÌbãà 轿ܿ^Ño³êܵ½B

Íðí¹ÄÇñÇñ^ÑÜ·B

äÔ20tªÍ èܵ½B

Gx[^[ͬ㤬ã¤Å·B
Éavp[gÌ®ðs¢Üµ½B
s¨ÈÌÅPKðµÈ¢æ¤ÓµÄìÆÅ·B
ÅãÉâ@BÞ̪ÉÚèÜ·B
°÷¾©ç©ªÉͽ©æª©çÈ¢@BÜÅåÊÉ èܵ½B
êlÅÍ¿ã°çêÈ¢öå«È@Bà èA«³à«¢Ü³Éone teamÌìƪßçêܵ½B

äæ¶ÌOrª¢¢Å·ËB

d©Á½Ìŵå¤BÉßÈ¢æ¤ÉB

Nã¨Ì@B½¿B
JͮS}j
AÌtBJÅ·B
iMac(Ì )Í1999N²ëÌ»iÌæ¤Å·B
©çåAíÈÉÍ}J[ª¢½Ìŵ天B
2ÔÙÇ©¯ÄSõÅÌìÆÍI¹µAãÇé³ñ©çJñVƵĨÙq𢽾«Üµ½B
i·Á©è^®µÈÈÁ½±Æð½ÈµÂªâðµÄAa@ÅÌƱÉßèܵ½B

ªÖÌõªiÞõiB

ÅãÉQÁÒÅWÊ^Å·B
¨æê³Üŵ½II
©gÍçtåwÌogÅÍ èܹñªAãwÉüéÆdú´ÆðjÉñ³|³êÜ·B
¡ñÌìÆÅàåAíÈÌ60NÌðjðÀ´·é±ÆªÅ«Üµ½B
cè©Å·ªAÅãÜÅãwð³ÉgpµÂÂøzµª®¹·é±Æðè¤Î©èÅ·B
OÉõ¢½¾¢½FlAúQÁ³ê½ûXAåϨæê³Üŵ½B
¶ÓFOY@žY
AUA ASRMj«sDÇKChC
Ji_EBritish ColumbiaåwÌVancouver Prostate Centre ɯwÌìjÅ·B
2021N1ÉÄåAíÈwï¨æÑĶBãwïæèj«sDÇÉηéffE¡ÃKChCª\³êAThe Journal of UrologyyÑFertility and SterilityɯfÚ³êܵ½B
(PMID: 33295257/ PMID: 33295258)
±êÍj«sDÇÉÖ·é§ðÅVÌGrfXÉîâÄñ¦·éÅVÌKChCÅ èA¡ã{MÌsD¡Ãɨ¢ÄàS[hX^_[hÉÈéÆv¢Ü·B
¡ñÌKChCÌøp¶£ÉçtåwåAíÈw³º©ç\µ½uTesticular function among testicular cancer survivors treated with cisplatin-based chemotherapy (Namekawa et al, Reproductive Medicine and Biology, 2016, PMID: 29259434)vªú{©ç\³ê½_¶ÆµÄBêÌp³êܵ½B
»wÃ@ãÌ¢¸@\áºÉ¢ÄÌÅY_¶ªøp³êĢܷB
¸ªñ»wÃ@ãÌ¢¸@\É¢ÄÌ_¶Ík¢ðSƵ½ éê_ÅÌ¢¸@\ð]¿µ½¡f¤ª½¢A³ºÌ_¶ÅÍA»wÃ@ãÌ¢¸@\É¢ÄÅ·20NÔð´¦éÏ@úÔÉí½ÁÄoIÉf[^ð~ϵA¢¸@\\ãüPöq¨æÑüPÜÅÌúÔðñµÄ¢Ü·B
çtåwåAíÈÌæyûª·úÉnèL^³ê½f[^ª Áı»A¼ÉÍÈ¢LpÈîñð¾é±ÆªÅ«A¡ñÌKChCÖÌfÚÉÁ½Æl¦Ü·B
¸ªñͶBÂ\NîÌj«ÅÅརªñÅ·B
èpÃ@â»wÃ@ÌiàÉæèärI\ãÇDƳêÜ·ªAêûÅ»wÃ@Éæé«BÖÌáQªâèÆÈÁĨèÜ·B
ÀÛɳҳņ̃êÉÈÁÄÝÜ·ÆAáNÅ èȪçªñÆ¢¤dåÈaÆü«¤^C~OÅA«ÌsDÉ¢Äàl¦ÈÄÍÈçÈ¢ñíÉåÏÈûÅ·B
»ÌÛAïÌIÉÇÌöxsDÉÈéÂ\«ª éÌ©A¢¸@\ªñ·éƵÄÇÌöxÌÔª©©éÌ©A±Ìæ¤ÈÀÕ°ÅÌ^ââsÀɦéªÆÈè¤é¤ÍÕ°ãƵÄñíÉÓ`Ì éà̾ƴ¶Ä¢Ü·B
ú{Í·ÅÉ¢EL̶BâãÃiARTjåÆÈÁĨèÜ·ªAæ¾ÁÄÌåbÌï©©çARTÌÛ¯Kg媩ÜêéÈÇXÉÚªWÜÁĢܷB
Á¡æ¶ªåAíÈÊMLÅq×çêÄ¢éæ¤ÉçtåwåAíÈÉÍú{Ìj«sD¡ÃÌjðS¤sì³öA¬{y³öª¨çêÜ·B
à¡ñÌ_¶øpðãÝÉAêw¶BãÃÌհƤÉæègÝAçtåwåAíÈ»µÄú{̶BãÃÌWÉ÷ÍȪçàv£µ½¢Æv¢Ü·B
ܸÍÁ¡æ¶É±¢Ä¶BãÃêåãð澷פèrðÏñÅܢ轢Æv¢Ü·B
±ÌLðÇñŶBãÃÉ»¡ðÁ½áèÌæ¶Í¥ñêɱ×ðµÜµå¤B
ÅãÉÈèÜ·ªAÍ¡Ji_ÌoN[o[ÉÄîb¤ÉæègñŢܷB
¢EªV^Ri´õÇÅåÏÈóµÌA¢¿ãÃÒƵÄv£Å«È¢±Æðªäv¢Aܽú{ÌãÃÌf°çµ³ðO©ç©é±ÆÅÄmFµÄ¨èÜ·B
¡ÉÅ«é±Æ͹Á©¸¢½MdȯwÌ@ïð³ÊÉ·é±ÆÈA¸êt¤ÉÅ¿ÝAAãͱ¿çž½m¯âo±ðçtåwåAíÈÖÒ³·é±ÆÅ·B
Bðܽ®±Æ·ç§À³êÄåªÔªo¿Üµ½ªAK¢©RÉbÜê½Â«Å é½ßå«ÈXgXÈÆ°Åß²µÄ¢Ü·B
(ڵ͡ºæ¶Ì¯w¶¾æèðQƾ³¢)
¢Â©«ðz¦ÄF³ñɨï¢Å«éúªé±ÆðyµÝɵĨèÜ·B

§¾xÌ¢
ªüµ¢Lindeman Lake

VancouverÌXð]ÞCypress MountainÌ[éê
¶ÓFì@j
Ù}Ôé¾ÄÑ
2020N1218úɨÌ
Åsíê½ú{åAíÈwïnûïÅ\ðs¢Üµ½B
V^RiECX´õÇgåÌû©Ì©Êµª§½¸AðNxðÜßwïÌJêÙÆñÇs¦È¢Ü½ÍwebJÃÌóÔÌÅA§í³¹Ä¢½¾¯½±ÆÍÉÆÁÄåÏMdÈo±ÉÈèܵ½B
æ¶ûæèèܵ½²Ó©ðQlɵÄA¡ãÌdɶ©µÄQè½¢Æv¢Ü·B
ܽ¡ñåAíÈwïÌ\É۵ܵÄA½åȨÍY¦ð¸«Üµ½æ¶ûÉSæè´ÓµÄ¨èÜ·B
ƱëÅAXÑÌêÌátÉͲQÌEÛͪ éƾíêA½¿lÔÌÆuÍðß黤ŷB
»ÌÍð¾é×ÉðNRÎÉsÁÄQèܵ½B
xmÌ[ÉÄRÎêü14kmÌjOƤÉXÑÅSgðüâ³êA±±ÉC¿ðV½É¸iµÄQè½¢Æӵܵ½B
»ÝÌñíÉ¢ïÈóµÅàAK¸àðJ¯éúªéÆSÉè¢ÈªçúXÌƱÉgíÁÄ䫽¢Æv¢Ü·B

RÎÈ
ܽÅßÍs¯Ä¢È¢ÌÅ·ªA´õgåOÉÍT[tBåD«â{æ¶Æl¶CsÌêAuçtÌCvÉsÁĨèܵ½B
»ÌÛAâ{æ¶Ì²FlÅ éO{[hú{`sIÌvT[t@[äã éIèð²ÐAêÉT[tB·éªÅ«Üµ½B
Åŵ½B
(äãéIèÉ»¡Ì éûͱ¿çðQlÜÅ@https://www.youtube.com/channel/UC9fqwJbcuGEH-YtxBA9nQ9A)
ÅãÉF³Ü̲NðSæèFO\µã°Ü·B

¶©ç@â{æ¶@éPro@
¶ÓF@ª
«åAíÈãÌõ
çtåwåw@ãw¤@åAíÈw@³@Á¡qÅ·B
±ÌxAæ17ñú{¶Bãwï¶BãÃêåãFè±ÉiµA«åAíÈã̶BãÃêåãÆÈèܵ½ÌÅA²ñ\µã°Ü·B
sDÇÌ´öƵÄA«ÌÁîªDP¦áºÌåvöƳêĢܷªAj«¤Éàñ¼Ì´öª éƾíêĢܷB
»Ì½ßsDÇfÃÍA«Æj«ª¯Éóf·é±ÆªdvÅ·B
µ©µAÀÛÉÍj«¤Ì¸Í\ªÉsíêĢȢP[XàÈ èܹñB
»Ì´öÌêÂƵÄAj«sDOEêåãÌs«ª°çêÜ·B
2020N41ú»ÝAú{¶BãwïªFè·éYwlȶBãÃêåãÍ790lÅ·ªAåAíÈãÍí¸©65lµ©¨èܹñB
åAíÈðêU·é¶BãÃêåãÌݪj«sDÌfÃÉgíé½ßAÐïÅÌùvªÜÁÄ¢éÉàÖíç¸AKØÈfÃðñ·é«ª®ÁĢȢ̪»óÅ·B
»Ìæ¤ÉóȶBãÃêåã̤¿Aú{¶BãwïÄÌsì³öAú{¶Bãwï̬{y³öA»µÄ¡{æ¶Æ3là̶BãÃêåãðçtåwÍyoµÄ¨èÜ·B
çtåwÍj«sDfÃÌSƾÁÄàß¾ÅÍ èܹñB
çtåwɨ¯é¶BãÃÌðjɼðAËé±ÆªÅ«AñíÉõhÉvÁĨèÜ·B
¶BãÃêåãÍA¶BãÃɨ¯éL¢m¯Aû³ê½Z\Ƣϫðõ¦½ãtð{¬µAXɶUÉí½é¤Cði·é±ÆÉæÁÄA¶BãÃÌ
ðßé±ÆðÚIƵħè³êܵ½B
¶BãÃêåãÌæ¾ÉÍAú{åAíÈwïFèêåãæ¾ãAFè¤C{ÝÌJL
ÉÁ½3NÔ̤CªKvÅ·B
¤CC¹ãAFè±ðó±µAiµ½ÅÉÍA°êÄú{¶Bãwï¶BãÃêåãÆÈèÜ·B
ª¶BãÃêåãæ¾ðuµ½RÍAsì³öÉæ¾ð©ßç꽩çŵ½B
»êÜÅÍ©ªªj«sDfÃÉgíéÆͲÉàvÁĢܹñŵ½ªA¤CðißéÉÂêAj«sDfÃÌ[³ÆÐïIdv«ð´¶éæ¤ÉÈèܵ½B
¼Úsìæ¶æè²w±ð¢½¾¯éæ¤ÈÅÌ«ŤCðÏޱƪūAåÏõhÉv¢Ü·B
ܽAåwa@ÈOÅàj«sDfÃÉgíé±ÆªÅ«é椲z¶¢½¾«A®a@ɨ¢Äj«sDêåOðJݵAfÃðsÁĨèÜ·B
¡ãÍAêå«ð¶©µAæè½Ì³Ò³ñÌfÃÉgíÁÄ¢«½¢ÆvÁĨèÜ·B
ܽA÷ÍȪçA¶BãÃðu·æ¶ûÌêÆÈêéæ¤A¸êtwÍ¢½µÜ·B
ÅãÉÈèÜ·ªA¶BãÃêåãæ¾É½èA²w±ð¢½¾«Üµ½sìqF³öA¬{°y³öAõj«sDOJÝðø«ó¯Ä¾³Á½A®a@AÃTbæ¶A_¶Ìw±ðµÄ¢½¾¢½¡{hæ¶ÉSæèäç\µã°Ü·B¡ãà¶BãÃðʶÄÐïÉv£Å«éæ¤Aæèêw¤èrðÏñÅQèÜ·ÌÅA²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨è¢\µã°Ü·B


çtåw̶BãÃêåã@¶©ç ¬{y³öAsì³öA¡{æ¶AÁ¡
¶ÓFÁ¡@q
2020N@æ2ñáèåAíÈAïc
ÝȳñAͶßܵÄB
çtåwa@åAíÈüÇ1NÚÌÛöÅ·B
êxÍ¿
¢Ä«½©Ævíê½RiàA~ÉüèASIÉĬsµÄ«Ä¨èAIíèÌÈ¢í¢ÉÝñȪ澵ĢéóÛÅ·B
êà¢Riû©ðèÁÄâÝܹñB
³ÄA»ñÈAçtåwåAíÈÅÍAOñ9Éø«±«12ÉàAzoomÉÄçtå¯åÉæéáèåAíÈAïcªJóêܵ½B
¡ñÍAÖAa@Eåw@Å̶ÐîÆ¢¤e[}ÅA¼äæ¶AÄcæ¶Aäàæ¶Aàâæ¶AÖ¡æ¶æè²ñª èܵ½B
æ¶û̪©èâ·¢XChÆà¾Ì¨AÅA«ÌC[WªæèïÌIÉÈèA©ªààÁÆæ£ë¤Æ±N·é±ÆªÅ«Üµ½B
æ¶ûAf°çµ¢²ñ èªÆ¤²´¢Üµ½B
ܽAáNÅ êÎAÀÛÉWµÄßµñµÄ¢Üµ½ªAQñÚàwebWïÅÌJÃÆÈÁĵÜÁ½ÌÍcOÅÍ èÜ·B
»êÅàAáèÌÝÅzoomæÊãɨæ»TOlãªê°ÉïµÄ¢éæðÝÄAçtåwåAíÈÌáè̽³ÉüßÄÁÆÆàÉA¡ã䪯åͳçɨ¢ð·Éá¢È¢Æv¢Üµ½B

ZoomÅÌïcÌlqB
QÁÒªêæÊÉûÜçÈ¢ÙÇÌåÑŵ½B
bÍÏíèÜ·ªA±¢Ä©gÌßµñð³¹Ä¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
NÌ£ÆÈèA{ÈçAYNïEVNïÆyµ¢ïV[YÅ é͸ŷªARi©l̹¢ÅïͳÈèA©îÅÌùðʪ¦éúXª±¢Ä¨èÜ·B
ÍAðSʪD«ÅÍ èÜ·ªAÅàr[ðDñÅæùÝÜ·B
r[ªD«·¬ÄAðṈÆÉÈèÜ·ªAr[è3E2ð澵ܵ½B
r[èÈñÄ éÌ©Æv¤ûª½¢Æv¢Ü·ªAr[èÍ2012N©çnÜÁ½iÅAr[ÌðjE»¢û@EíÞEj
[XðèÞƵ½MLÌÝ̱ŷicOȪçeCXeBOÌÀZ±Í èܹñBBjB
æWñÜÅÅiÒÍÈñƨæ»15000là¢é»¤Å·I

¨CÉüèÌgGOOSE IPAhB
zbvÆA}ÌâÈꡪÅÅ·I
ÅßÍSIÉNtgr[à¦AFXÈ¿µ¢r[âü¡µ¢r[ªùßéæ¤ÉÈÁīĢܷB
{ÈçÎAr[ÚÄÉùÝ૽¢Æ±ëÅ·ªA¡NÍAÁÄAÁÄÆÅùÞ©AÊÌÅCÉÈér[ðÁÄyµñŢܷB
ªÁÉD«ÈíÞÍAIPA(CfBAEy[EG[)ÅAzbvª½gp³êÄ¢é½ßèÆꡪ¢ÌªÁ¥Ìr[Å·B
±±ÅßÌxúÍA¨CÉüèÌr[ð©çnÞ̪ÅÌtbV
ÉÈÁĢܷiÎjB
àµAr[D«Ì涪¢Üµ½çARiª¿
¢½ÅÉÍA
ºÐêÉùÝÉ¢«Üµå¤I
³ÄAr[Ìbͱêç¢ÉµÄ¨¢ÄANx4æèVµ¢a@ÉÄα·é±ÆÉÈèÜ·B
ܾܾåAíÈƵÄÍ¢nÅAÌEêÌæ¶ûÉàFXƲÀf𨩯·é±ÆÉÈé©Æv¢Ü·ªAêàêଷūéæ¤ÉúX¸iµÄ¢±¤Æv¢Ü·B
¡ãÆàǤ©æ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFÛö@§j
¡NÌÄÌß²µû
FlA½fæèåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
åAíÈüÇ1NÚÌnÖÅ·B
¡ñÍARi¬sÉÄ©lª]VȳêéAÅßÌÂlIÈoyÑüÓÌßµñð³¹Ä¢½¾«Ü·B
æ뵨è¢vµÜ·B
8̱ÆÅ·ªA¢ÂàÊè`[SÌÌñfÅWÜÁ½Æ«Au¡NÌÄÌß²µûvÌbèÉÈèܵ½B
ìhâT[tBðͶßAãÇÉÍlXÈï¡ðà«L©Èæ¶ûª½¢çÁµá¢Ü·B
©ªà¬w¶ÌÄxÝÉÍAúÌæ¤É©©çeÆJugVðßèÉsÁ½v¢oª èÜ·B
»Ì±Æðb·ÆA`[Ìâ{æ¶æèu¶á A¡xßèÉs±¤æIvÆñĵÄàç¢AÐåñȱƩç§ðð¯½jñlÌJugVÌWÌ·ªnÜÁ½Ìŵ½BBB
äÍAçtÌkRsB
çtÍrXÌæ¤ÈsSÌpà éêûÅACâRÉÍÜ꽩RL©ÅÌÇ©ÈêÊà èÜ·B
19ð߬ ½èªÃÈéAJugVTµÍnÜèܵ½B
·éÆA1{ÚÌØ©çRNK^©I
làâ{æ¶àeVMAXŵ½Î
»ñȱñÈÅAÌWð±¯Ä¢éÆAAA

±êÍà¤}ÓÅ·I
â{æ¶àåìÑŵ½I
ÊAJugVNK^í¹Äv10CÈãßlµAßÌz[Z^[Å©²ðwü@â{æ¶îÅç³êé±ÆÆÈèܵ½BB
±ÌoÍlÌ¡NÌÄÌåØÈv¢oÆÈèܵ½B
±Ìæ¤ÉA§ðð¯CâR¼ûÌ©RÆCyÉGꤱƪūéÌÍçtÌå«È£ÍÌêÂÅ·B
ÂlIj
[XͳĨ«ARi¬sÌe¿Å¯åïâwïªWebÅÌJÃÆÈéAãÇƵÄÍ9º{ÉáèÌæ¶ûðSƵ½Zoom~[eBOªsíêܵ½B
~[eBOÉÍACOÖ¯w³êÄ¢éæ¶ûÉà²QÁ¢½¾«AÀÛÌ»êÌb𽷱ƪūñíÉLÓ`ÈàÌÆÈèܵ½B
ÀÛÉWcÅçðí¹é̪¢ïÈóµÌA±Ìæ¤ÈïÍêðIθQÁÅ«é±ÆÍå«ÈbgÌê¾ÈÆÀ´µÜµ½B
±ê©çàRi¬sÌe¿Í±±Æª\z³êÜ·ªAÕ°à¤àÕ@ÏÉ_îÉεĢ«½¢Æv¢Ü·B
¡ãàXµ¨è¢\µã°Ü·B
¶ÓFnÖ@Må
ðæèÍÞ«@`å©R©çEêÜÅ`
çt§åAíÈãïÌFlA±ñÉ¿ÍB
çtåwãwt®a@t}ÌR¨@åSÅ·B
¡ñÐïS̪¢]LÌRi¬ÌA¢¿ãÃÒƵĻêÉÖAµ½L𱤩Æàv¢Üµ½ªA±±Í¸¦ÄÖWÈ¢±Æð«AËÄݽ¢Æv¢Ü·B
æ뵨袵ܷB
ͪogÈÌÅ·ªAåw©ççt§Ö³¹Ä¢½¾¢Ä9NÚÅ·B
½©çuÉ¢ÂÅࢯ飾¯Ç©RL©Å¢¢Æ±ë¾ÈvÆvÁĢܵ½ªAw¶Ì ÉoïÁ½æyɻ̩RðSgÅ´¶é±ÆªÅ«é±Æð³¦Ä¢½¾«Üµ½B
»êÍìhÅ·B
âèûƵÄܸÈñÆÈ©ªÌs«½¢Æ±ëðßÄA»±Ö©]ÔÅü©¢Ü·B
rÅÊ»¤ÈÆ±ëª êÎKɧ¿ñèAgÑÌ[dªØê½ç¾zÌü¢Ä¢éûüânæÌlðèÉÈñÆ©½Çè
«AéÍöÈÇÅQÜÉüÁÄQÜ·B
ÙRâYÈÇì[ÍåÌ¢«Üµ½ªA¡NÌÄͶqÜÅ¢Áīܵ½B
©8Éoµ5ÔÙÇ©¯Ä®sÉ¢éFBÉï¢A»ÌãÍ Yâ¶qÌCÌKð¬\µAß̨ÆÌû©çi{[𢽾«Aã\ã¢lÅìhðB
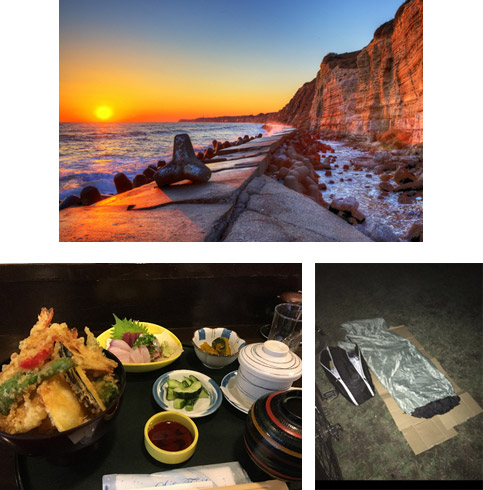
CÝÍvÁ½ÈãÉg̹ªå«ArßO3碩çJà~ÁÄ«½½ßAìhÍfOµÄAHɱÆɵܵ½B
^ÁÃÈArpHêÈÇÅJhèµÄ¢Üµ½ªA_ðÚÅǤÆçtûÊ©ç·±å«Èü¹_¾Á½½ßAGêÈ¢±ÆÍXÉúßĸÔGêÉÈèȪçAÁīܵ½B
u±ñÈÉǵáÔèÌ©]ÔÅéÈñÄålÉÈÁÄAÈ©È©Å«È¢æÈvÆjjµÈªç¢Å¢½ÌÅA³¼â΢z¾Ævíê½±Æŵå¤B
³ÄA±Ì©]Ô·ÆìhÍ»ê©Ìª©RânæÌlXÆÌð¬ð´¶Äyµ¢àÌÅ·B
µ©µAªêÔSk¦éÌÍA©îÌ·©¢xbhÉ¡½íè u ÈñÄbÜê½Â«É©ªÍ¢éñ¾BúíɴӵȢÆBv Æƪ é±ÆðìÑA»µÄ¡©ªªu©êĢ髪¢©É[ÀµÄ¢é©Év¢ðy¹½Å·B
Ou«ª·Èèܵ½ªA¡u©êĢ髪[ÀµÄ±Ìæ¤ÈìÑð´¶çêéÌàAâÍèçtåwa@ÌããÌæ¶ûA¯úÌt}ÌF³Ų̈©°¾ÆvÁĢܷB
ÀÛúEêÉé̪yµ¢Å·µAããÌæ¶ûànð¯Ädð·éÆ«Í^ÉAdÈOÅÍC³Éڵĺ³èA{É èª½¢ÀèÅ·B
¯úà6lƽAFůÁÄØáöô³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
ܽ¡NàùÉ10lßÌüÇé¾Òª¨èAÌÌãyàüÁÄ«Äêéæ¤Å·B
âÍè£Íª éƱëÉÍ©RÆlªWÜèA»êð©Ä³çÉlªWÜÁÄ«ÄA³ÌA½ª¶ÜêÄéÌŵ天B

ªNüÇ\èÌXì^ß³ñBãñÍt}ÌÊXÅ·B(t}Íãñl¢Ü·)
±ê©çà©gªãy©ç͸h³êéæyÆÈêéæ¤ÉAæy©çÍoéãyÆvÁÄ¢½¾¯éæ¤É¸iµÂÂAçtåwåAíȪ¡ÈãɳÌA½Ì¶Üêé£ÍIÈone teaÆÈéæ¤vXæ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
»µÄAääÍåAíÈone teamÅìhÅ«êÎƲÝĢܷB
¡ãÆàǤ¼æ뵨袵ܷB

¶ÓFR¨@åS
2020N7@Surfing with 2019 Japan Long Board Pro Champion
æúAú{w¶T[tBA¿(NSSA)̳ñ(¦1)ÌÐîÉÄAðNO{[hProcA[ÅNÔDµ½AäãéPro.(¦2)ÆêÉucÆç|CgÉüèܵ½B
äãProÍAXyCAAJÈÇ¢EÅôÌWSLcA[àñÁÄA»ÝLOª12ʾ»¤Å·B
¦·¬Ü·II
¬gÅàA·²¢CfBOðâIµÄ¢Üµ½B
¡ñA{è©ççtÜÅêeª^]·éoÉÄÆ°4lŬðgí¸º¹ÅÔÉÄÚ®³ê½Æ·«åÏÁ«Üµ½B
»ÌRÍA¬ãÅqB3lÉVµ¢T[t{[hðÁÄã°½¢ÆÌeS©çÅ·(Ü)
T[tBÍATbJ[âì
ÆáÁÄAX|T[ªWÜèÉ¢X|[cÅ·B
DZ©ÅA@ïª êÎAåAíÈT[tBƵÄàéProðT|[gÈÇÅ«êÎÆv¢Ü·B
éProA±ê©çàAæ£Áľ³¢I
ȺÅßÌíðÅ·B
ú{ÌvcA[DÌCfBOͳªÅ·I
https://surfuu.com/profile/taka-inoue
COcA[WSL(World Surfing League)Ì®æ
Semi FinalÜÅioµÄAViCsÌáèƵÄÚ³êܵ½I
(O{[hÅ·ªAWSLÍAV[g{[hÌIsbNã\ÌÜ\JmAƯ¶cA[ÆÈèÜ·)
https://www.youtube.com/watch?v=LQ7gz1-3i40

¶©çAâ{AäãProAäPro(åAíÈèpÌFD´ãÃZ^[α)
¦1)³ñÍú{T[tBA¿Æ¯É»ð}\i[Åà èA»Ì^CÍÈñÆ3ÔðØé2Ô50ªäI
NãÊÌt}\S4ÊÌÆÑÌ¿åB
sì³öƯ¢ãÆ̱Æŵ½ÌÅA³öÌ}\ÖÌîMàÁ¬·éÌŵ天HI
¦2)äãéProÍgO¬hÌÙ¼ðÂíOðíEµ½T[t@[I(O¬O{[hAV[g{[hASUPÌ3íÚÌProiðL·é)
O{[hÌ`sI¾¯Åà\ª·²¢Å·ªAá¤íÚÅàProÈÌÍ·²·¬Ü·B
åAíÈÅá¦éÈçÎAO§BàAtàAAHãçàSÄÌÌæÅïÜðæèAtà̪ìÅm[xÜðæéæ¤ÈàÌB
»Ìæ¤ÈåAíÈãͱêÜÅÉ©½±Æª èܹñB
ÅãÉÅßÌT[tBÌ®Ìêð²ÐîµÄ¨ÊêÅ·B
CÉ»¡Ì éûàÈ¢ûà¥ñêÉüèܵå¤I

¶ÓFâ{@Mê
O§BàAIðÍlHm\(AI)ãw@ìãpÇæ¶
NÃa@åAíÈ@óûkîÆ\µÜ·B
ÍðNxåw@ð²ÆµANÃÉCµÜµ½B
åw@ÅÍVµAIÉæéðÍðnß½ÌÅAµÐîµ½¢Æv¢Ü·B
çtåwåw@@lHm\ãw³ºÍ2019N4ݧÌVµ¢³ºÅ·B
³öÍìãpÇæ¶ÅAܾ30ãÌÆÄàá¨¢Ì éæ¶Å·B
æ¶ÍåwogÅwIsbNÉoê·éÈÇãtÅ èȪçwÌXyVXgƵÄAAIãw¤ÌæêlÒƵÄô³êĨèÜ·B
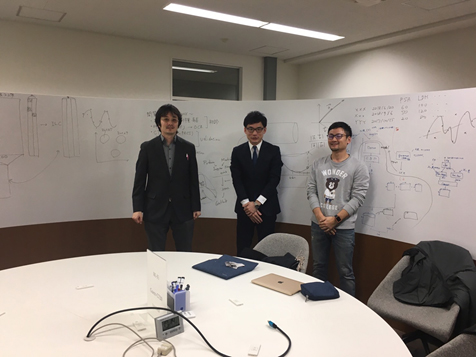
¶©çìã³öAâV¡æ¶Aóû
~ÉÈÁ½ÂÉ®âACfAð«oµÄs¤º
»ÝlXÈAIðp¢½¤ª¢EÅȳêĢܷªAù¶ÌAI¤ÍvO}[Éãtâ¤ÒªËµÄðÍð·éX^CÅ·B
³ºÌÁ¥ÍAIâvO~Oªí©éãÒªV½ÈACfAðoµAAIÌÂ\«ðL°éÆ¢¤_É éÆv¢Ü·B
¢ÄAƾÁ½OÅÍf[^ÌʪcåÅ èAvO}[Ìlà½AÇ᪸xɼ·éæÌ[wwKÈÇÍú{Ì곺Å;ſsÂ\Å·ÌÅAäXÍACfAżƵÈÄÍÈèܹñB
»Ì_AãtªÕ°Iâè_â^â_ðoµ¢ÈªçAIÅð͵ĢƢ¤X^Cª¼Ì¤ÆÙÈèAܽDêÄ¢éÆl¦Ä¨èÜ·B
Íåw@Éüè2NÔͪñ×Eðp¢½îb¤ðsÁĨèܵ½B
ðN10â{æ¶ÆòwÀ¼³öÌÐîÅAI³ºÉoüè·éæ¤ÉÈèܵ½B
¡ÜÅvO~OÈÇSGê½±ÆàÈ©Á½ÌÅAAIª½©àSí©çÈ¢A¤ðJnµÜµ½B
e[}ÍuO§BªñÌzÃ@ð@BwK(AI)ðp¢ÄðÍ·é(¼)vÅA¼NÔÌÅìã³öÉð͵Ģ½¾«A éöxÌf[^ðo·ÜÅÉèܵ½B
Jef[^pÅàAvO~Oðpµ¼ÚdqJeæ貫oµÄmÀÈf[^ð¾éƤÉA½¼»ÉæèÂlîñÉà¯ÓÅ«éæ¤É\zūܵ½B
½Á½¼NÅ·ªAAIâvO~OÍ·²¢àÌÅïµ»¤Æ¢¤F¯©çA¡ãÍK{ÌXLÉÈÁÄsŠ뤱ÆðmMµÜµ½B
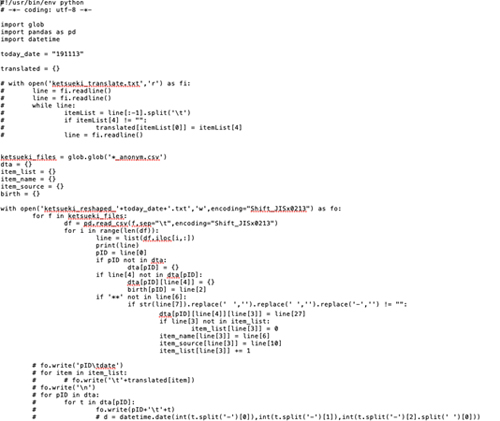
Je²×ÌÛÉp¢½pythonR[h
Íåwðoé±ÆÉÈèܵ½ÌÅAãCÌâV¡æ¶ª»Ýͤðø«p¢Å¢Ü·B
(V^RiECXÌgåÅ»ÝÍe[NÆ̱ÆÅ·ªAPCª êÎDZÅàÂ\Æ¢¤Æ±ëª±Ìè̤Ì_Åà èÜ·B)
w¶âú¤CãÌûÅAãwÉüÁ½¯ÇwªD«AÕ°àâè½¢¯ÇvO~O໡ éÆ¢¤ûAçtåwåAíÈÆAIãw³ºÅAI¤ðµÜ¹ñ©H
¢ÅÉհɵ©»¡È¢Æ¢¤ûÍNÃa@åAíÈÅà¨Ò¿µÄ¨èÜ·B
¶ÓFóû@kî
YÆpÂ\Èèp®æf[^x[X\zÉü¯½vWFNgyS-accesszn®
åw@¶Ì|º¨dÅ·B
Í»ÝAçtÌÌtLpXÉ éA§ªñ¤ªñZ^[a@ÉĤðsÁĨèÜ·B
NEXTÆ¢¤¨È¼OƨÌÉ éANEXTãÃ@íJºÆ¢¤åÉ®µÄ¨èÜ·B
NEXTÍ¡ÌéÆâAJf~AªüµAYwAg_ÆÈÁĨèAæèÕ°»êƧڵ½V[XÈJ«ðõ¦Ä¨èÜ·B
ÀÛÉèp@íJÌÅOüðÔßÅ´¶é±ÆªÅ«A«Ìèpª_Ô©¦éuÔÍå¢Éhð¤¯A»±µÜ·B

NEXT

NEXTãÃ@íJZ^[ÉüµÄ¢ééÆâAJf~A
³ÄA2019N10æèJnµ½AMEDx̤Égíç¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·ªA¤ÉÖµÄvX[XÆÈèܵ½ÌÅA²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
¤Ûè¼Fà¾OÈèpÌf[^x[X\zÉ·é¡fIîÕ®õ
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2020/0303/index.html
èp@íJÈÇÉéƪQüÅ«éîÕìèƵÄÌèp®æÌf[^x[X\zðÚIƵĢܷB
åAíÈÌèp®æÌûWÍçtåwªSÆÈèA¡ã®æûWðsÁÄ¢\èÅ·ªAsì³öÌÐîÉÄAsì³öÌZ̯¶Å é¡cãÈåwÌسöA[Jæ¶ÆÆàÉAiß³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
ܽèp®æûWðsÁ½ãÉAèpHöâpïAðU\¢ÈÇÌîñð®æÉtÁ·é³tf[^ð쬵A¡ãèpHöâðU\¢ð\ª·é±ÆªÅ«éæ¤æègñŨèÜ·B
¤¾¯ÅÈAYÆpàÂ\Èf[^x[X\z̽ßAܾܾÛèà èÜ·ªµ¸ÂiñŨèÜ·B
{¤ÍAå°èpðSÉsÁÄ¢½¤ðàÆÉAp®âÚIðL°A2019N10ÉJn³ê½¤Å·B
{¤ÓCÒÅ éÉ¡æ¶ÌwïuðÈO®uµ½â{æ¶ÌÂȪèÉæèA»Ý¤ð³¹Ä¢½¾¢Ä¨èÜ·B
É¡æ¶â|ºæ¶(å°OÈÌæ¶Ag½¯µ½@ÌÔhÜżOª¯¶Ì½ßÔá¢dbªúíÆÈÁĨèÜ·)ÍçtåwogÆ¢¤²à èAlXȲÌåسɴÁµÄ¨èÜ·B
sì³öAâ{æ¶A{É èªÆ¤²´¢Ü·B
ܾܾ¤ÍJnÆÈÁ½Î©èÅ·ªA¤úÔà2N¼ÆZ¢½ßAèØè½¢Æv¢Ü·I
ÖA{ÝÌæ¶ûÉÍAèp®æûWÉÖµÄA²¦Íð¨è¢·é±Æª é©Æv¢Ü·B
¨Zµ¢Æ±ë°kÅ·ªA²¦ÍÌÙÇǤ¼æ뵨袵ܷB
൤Ìàeâ{ÝÈÇÉ»¡ª éûª¢çÁµá¢Üµ½çAºÐ²A¾³¢B

¶©ç|ºCRæ¶APMàFàVìlAÉ¡ëºæ¶APM½ö²_A|º
(PM: Project Manager)

¶ÓF|º@¨d
ASCOGU2020@ÔOÒ
ÀÍwïJÃOÉúßÉJtHjABTtVXRüèðʽµAVRo[ÆX^tH[håwð©wµÄÜ¢èܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
|Pg[NÆ¢¤»ið·Åɲ¶mÌûXར©àµêܹñB
¾ÎƳñܳñª|ó@ðìgµÄOlÌ«ðûàpªóÛIÈCMðo¦Ä¢éûརÆv¢Ü·B
±Ì|Pg[NÆ¢¤»iAú{Ì\[XlNXgÆ¢¤ïЪ¶Ýoµ½|ó@ÈÌÅ·ªAAIÍà¿ëñAX}zÅÍê¾Å¿Å«È¢xÈ}CN@\ªÚ³êA¬êéæ¤È¾êF¯E|óEAEgvbgðÀ»µÄ¢Ü·B
gÁÄÝéÆ{ɸxƬxÉxÌð²©êÜ·B
±Ì»iÍú{̾¯ÅÍ®¬µÈ©Á½Å ë¤Æ̱ÆÅAз©çªVRo[ÉÚZµAlXÈVRo[ÌéÆÆÌÂȪè©çÀ»µ½Æ¢¤bð²¶mÌûÍÈ¢ÌÅÍȢŵ天B
VRo[ÆÍAwïïêÅ éTtVXRxCGAÌìÉÊu·énæêÑÌÌÅAAbvECeEt[EtFCXubNÈÇÉã\³êé½Ìéƪ¶ÜêAØáöô·éITéÆÌêå_Å·B
àÆàÆX^tH[håwogÌZpÒ½¿ªCÝÉÎRµÄ©¼CÝÉ éX^tH[håwÌ~nàÉRs
[^[EGNgjNXéÆðݧAUvµ½±Æª«Á©¯Å¶Üê½Æ¾íêĨèAX^tH[håwÆÌÖíèª[¢Æ¾íêĢܷB
çtååAíÈƵÄATtVXRÌ·®ßɱñÈÉ໡[¢¢EªLªÁÄ¢éÌÉÝ·Ý·òÑÜÈ¢í¯ÉÍ¢©ÊAÆ¢¤í¯ÅAâ{æ¶Eäæ¶ÆÆàÉ\[XlNXg¼cзA»µÄX^tH[håw¯wÌçtåãwOB̼æ¶(d®ì
08N²)ðdKâµÄÜ¢èܵ½B
\[XlNXgÆ¢¤ïÐâ|Pg[NÆ¢¤»iÉ»¡ª¨ èÌûÍAuêéÍv_ChÐ@ðÇñÅÝľ³¢B
1ÂÌïÐâ»iªÇÌæ¤É¶ÜêA¬·µÄ¢Ì©AܽзÌvzªÐµÐµÆ`íÁÄéǾÆv¢Ü·B
\[XlNXg¼cзÖÌC^r
[ÍVRo[ItBXàÌÚºÅsíêܵ½B
ÅÍAú{©çËRâÁÄ«½3lÌäÌåAíÈãÉ¢fµÄ¢élqÌзŵ½ªA|Pg[NÌãÃIj[Yâó`ɲÜê½çt§ÅÌãûêÖ̳çÈéyÌÂ\«ÈÇÌb©çbÍ͸ÝAÅãͼcзÌVRo[ÖÌÚZébAVRo[ÌÐðEÌbÉ¢½éÜÅõ¨b¾³¢Üµ½B
ÅãÍALOBeàÎçÅpVB
hIÈÔðß²³¹Ä¢½¾«Üµ½B
¼cзA èªÆ¤²´¢Üµ½I
(¡ñ̲à èA Ol³ÒÉηéa@àÎÚIÉÄAçtåwãw®a@E ÛãÃZ^[ÆÖAÌÝÍÜa@É|Pg[Nª±ü³êܵ½B)
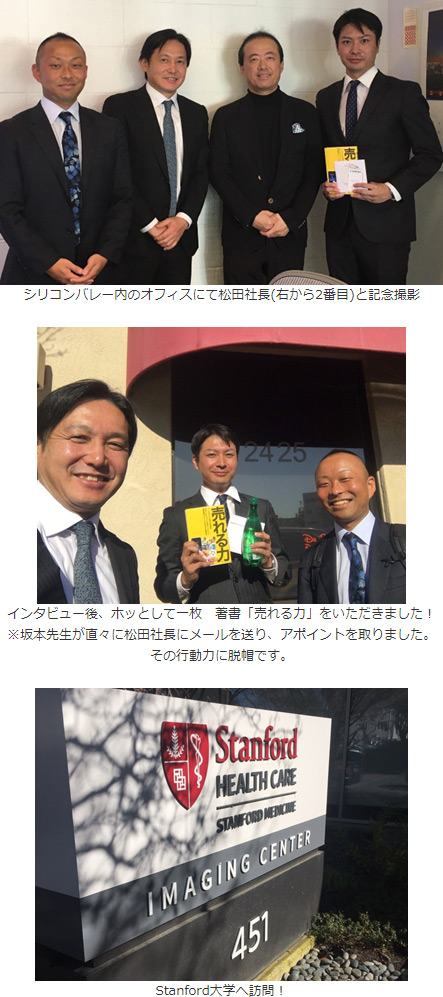
±¢ÄAX^tH[håwðKâB
±¿çÍäæ¶ARcæ¶ÆÆàÉK⳹Ģ½¾«Üµ½B
SÄüw̼å§åwÅ é±ÆÍ¢í¸àªÈAÀÍ¢EüwÌLåÅüµ¢LpXð±ÆÅàL¼Å·B
¤ÌÔ̼æ¶Æ¬µALpXðÄàµÄ¢½¾«Üµ½B
1NðʵÄõ°ª±±ÌnæÅÈçÅÍÌË«²¯éæ¤ÈÂóAüµ®õ³ê½Å¶AeÉUèÎßç꽬
ÌXAAADZðØèæÁÄàаXAà¢Ä¢é¾¯Å©MâACfAªN«ãªÁÄéæ¤ÈA»ñÈLpXŵ½B
¨Éw¶H°Åno[K[ðÞ³ÚèA³CXÌäXÍAX^tH[håwãwÌR[g𨵢ÅwüµÄåwa@ÌOÅpVB
v¢oÌ1ÆÈèܵ½B
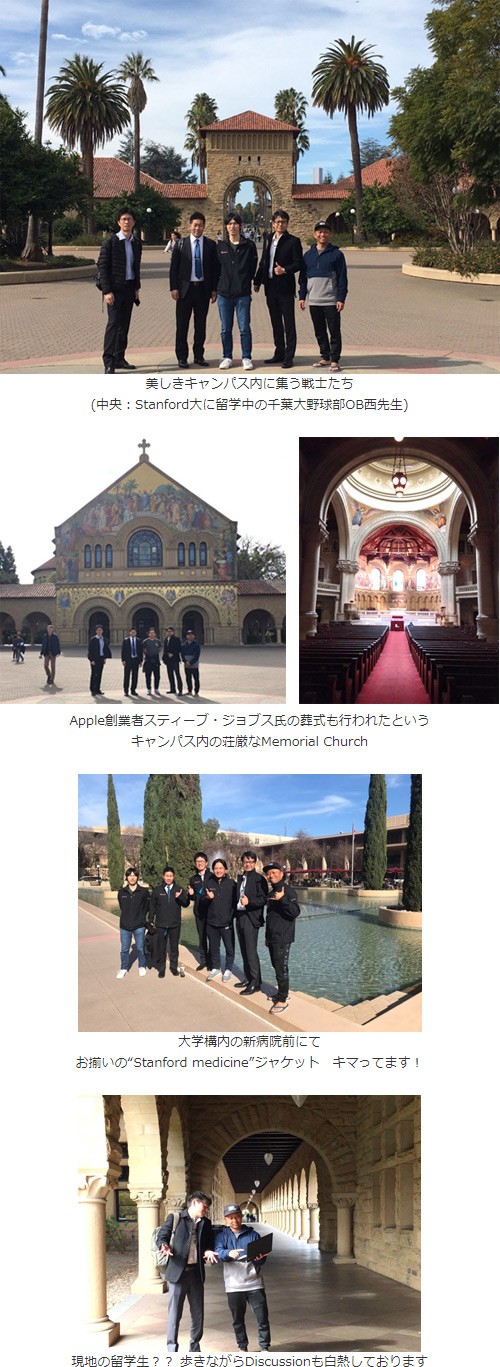
»ÌãAÍÂlIÉX^tH[håwÅ°à×Ûð¤µÄ¢éPhDÌmè¢ðKËܵ½B
{ð©w³¹Ä¢½¾«AAJÅÌîb¤ÌÀÔâAà¹É¢ÄÈÇlXȤÊÉ¢Äú{ÆärµÈªçbð·±ÆªÅ«Üµ½B
ÞÌ®·é{ͤààLxÅ(Æ éÆ©çàæú\~ÌZðó¯½Î©èÆ̱ÆAAA)A¢E©ç40lÙÇÌG[gªWÜÁĢܷªANÔÉ_¶ªSÌÅ1{oé©oÈ¢©B
_¶ªoÈ¢±ÆÉêµñÅ«ßÄ¢³ºõརÆ̱ÆÅ·B
ܽA×Ì{ÍAZÉ_¶ðoµ½ÀѪ éÉàÖíç¸AÅßêCɬÊðo¹¸ÉµA{ªðUµ½Æ̱ÆAAA Üèɵµ¢ê¬Ìîb¤Ì¢EÉÂûµÜµ½ªAmÁĨ¢Äæ©Á½ÆgÌø«÷Üév¢ªµÜµ½B
²ÉÈÁÄbð·¢Ä¢é¤¿ÉéàÓ¯ATtVXRÖÌArÉ«ܵ½B
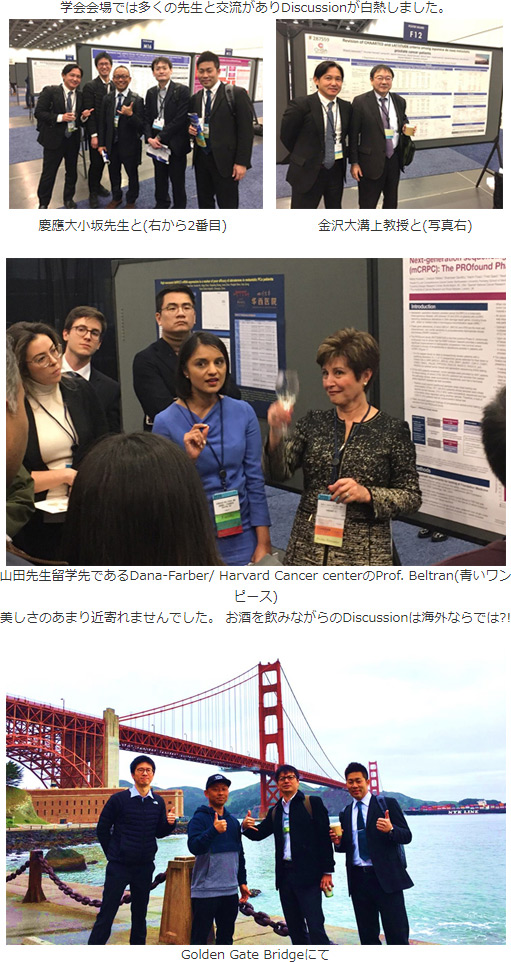


ÔOÒ{¿ÌàeÆÍÈèܵ½ªAÈwZpJÌÅOüÉGêçê½MdÈ̱ŵ½B
ÅãÉÈèܵ½ªA±Ìæ¤È@ïð^¦Ä¾³Á½¯åÌæ¶ûAÖAa@Ìæ¶ûAÈçÑÉäw±¢½¾¢½â{æ¶ÉS©ç´Ó¢½µÜ·B
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
NxàASCO GUÉçtå©ç¡Ìèªo¹éæ¤AçtåwåAíÈê¯æ£ÁÄ¢«Üµå¤B
¶ÓFcº@M¾Aä@º
ASCOGU2020
åw@¶1NÚÌäÅ·B
½fæèåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
±Ìxâ{Mêæ¶Aåw@¶ÌRcæ¶A®a@Ìäæ¶A¡lJÐa@Ìcºæ¶ÆêÉASCO-GU2020ÉQÁ¢½µÜµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
áNÊèTtVXRÅ213`15úJÃÆÈÁĨèÜ·B
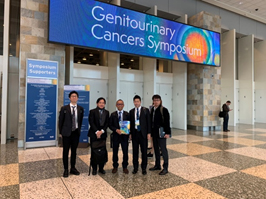
úÉ¿²ÆÉíÊŪ©êĨèAúÌ213úÍ©©çÓÜÅO§BàÉÖ·éoral sessionªA1000lÍûeÅ«éÅ ë¤ïêÅsíêĨèܵ½B
XChàSÄ_E[hÂ\Å èAÛ1úQÁ·éÆO§BàÌÅVÌm©ðzû·é±ÆªÅ«ÄÆÄàø¦ªÇ¢Æ´¶Üµ½B

QÁo^Ò4500lA´^900èÈãÆNXKͪå«ÈéAçtåwåAíÈÖA©çÍÈñÆ5èàÌð³êܵ½B
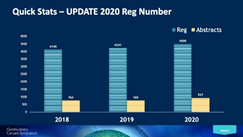
|X^[\ÅÍ¡ãÌ©ªÌ¤Éqªè»¤È\à èAܽNàèðʵÄQÁµ½¢Æví¹éæ¤ÈAÆÄàLÓ`Èo±ÆÈèܵ½B
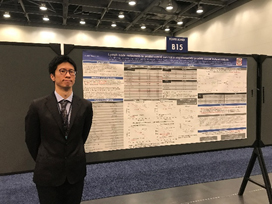
±¢ÄwïÌyµÝÌêÂÅ éA»nÅÌ¿EùÝïÌÍlð¨`¦µÜ·B
wïOúÌéÉÍAbãÈåwÌغæ¶Eª®æ¶(áèÌz[v©ÂCP)A¡ls§åwÌODæ¶ð}¦ASFÅMêè¢Üµ½B

(¶æè@ª®æ¶AäAغæ¶AODæ¶ARcAcºAäAâ{æ¶)
»ÝA»µÄߢ«ÌåAíÈð[h·éæ¶ûÆÌùÝïÍ·èãªèð©¹A ÁÆ¢¤ÔÉԪ߬AðUµ½ÉÍùÉútð´¦Ä¢Üµ½B

(XOÅÊêÛÉêBzCÈAJªêl¬¶ÁĢܷªA¨»çåAíÈãÅÍ èܹñB)
wïúÌéÉÍAçt§ªñZ^[ [òæ¶ÆASFKâÅ écºæ¶¨©ßÌ^C¿XÖB
^C¿XÉàÖíç¸Aú{ŨéõÝ̶tª«âgNªÈAJ`[VbNðó¯ÂÂà»±Í~V
1¯X¾¯ èAÇêàü¡Åµ½B
(¿ÌÊ^ªF³Å\µó²´¢Ü¹ñB)

úSFÖ
³êAÆÄà¨æê̲êµÄ¸«Üµ½[òæ¶A èªÆ¤²´¢Üµ½I(ÈãRcæ¶S)
ÄÕ°îáwïåAíàV|WE(ASCO-GU 2020)óÛLÉO§BàèÌTOPICSðSÉÜÆßĨèÜ·B
¶ÓFä@¹H
2020.1.25@æ42ñçtåAíȯåïwpWï
åçtåwÌVä²VÅ·B
±Ìx125úÉæ42ñçtåAíȯåïwpWïªçtw¼ÌyGz[ÉÄJóêܵ½B
ãÇõà¦Ä«½ð¡AáèÌæ¶ûSɽ³ñÌè\à èAçtåwåAíĘ̀¢ð´¶¸ÉÍ¢çêȢ巵ÌïÆÈèܵ½B
Fl²QÁ¢½¾«A½É èªÆ¤²´¢Üµ½B

ðNx©çݯçêܵ½AeZbVɨ¯éxXgv[^[ÜÉÍ¡ñAX°¹æ¶AqFæ¶Aäºæ¶A²¡L¾æ¶ª©Io³êܵ½B
ܽAïSÌðʶÄÅà·èãªè𩹽\É¡çêéÁÊÜÉÍúìån涪IÎêܵ½B ¨ßÅƤ²´¢Ü·I

¶©çæ¶A²¡æ¶Aúìæ¶AXæ¶Aäæ¶
¨ßÅƤ²´¢Ü·I
ܽA§eïÅÍA¡NxÌt}ÉæéÓgÌÐîv[V[r[ª¬³êܵ½B
±¿çàñíÉNIeBÌ¢àeÅA¯åÌæ¶ûÍ΢ðÊèzµA©üÁÄ¢çÁµá¢Üµ½B
1NʶĬ·³ê½t}Ìæ¶ûÌEpª`íÁ½ÌÅÍȢŵ天H NxÌ»ê¼êÌoüæÅà«ðöµA³çÈéòôð°Äêé±Æŵå¤B
æ£Áľ³¢I

¶©ç·ªæ¶Aغæ¶(D´ãÃZ^[)APæ¶Aäàæ¶A´
æ¶(϶ïKuìa@)A
éØæ¶(¬cÔ\a@)AO´æ¶
NxA·ªæ¶ÆPæ¶Í®a@Aäàæ¶ÍNÃa@AO´æ¶Í϶ïFs{a@Åãú¤Cð³êÜ·B æ£Áľ³¢I
ÅãÉÈèÜ·ªANxÉÍAºaFutðMªÉAR{«u³ÜßãÇõª½ANÃa@ÖC³êÜ·B
nC{
[Z^[̧¿ã°ÍAâÍè¨¢Ì éãÇɵ©Å«È¢å«Èd¾ÆvíêÜ·B
¡ãàFÅÍðí¹ÄAÕ°ÊE¤ÊÆàÉçtåwåAíÈð·èã°Ä¢«Üµå¤I
¶ÓFVä@²V
D´s§ãÃZ^[ŤCÌغÁÅ·B
Ít}Ì_©ç¯åïÌlqðñ³¹Ä¸«Ü·B
cOȪçsì³öÍCtGUÅÈÆ̱Æŵ½B
1úà¢AðèÁÄâÝܹñB
ÍÙÚßÄÌQÁÅ èÜ·ªA±êÙÇòRÌ涪WÜéÆÍÁ«Üµ½B

æyûÌèð·¢Ä¨èܵ½ªAtbV
}ÌÉÆÁÄÝêÎP©µ¢àÌΩèÅ èA©ªªß¢«±Ìæ¤È\ðÅ«éàÌ©Æl¦éƦÍNoŵ½B
ÁÉwp§ãèÜðóܵ½Väæ¶AR{æ¶Ì²\ÍAnCx·¬ÄsƱȩÁ½±ÆÍNÉྦܹñµNÉྡྷܹñB
æè¢Á»¤¸iµ½¢Æv¢Ü·B

(Ê^Ͷ©ç@æ¶A²¡L¾æ¶Aúìæ¶AXæ¶Aäæ¶AWÌû)
îñð·ïÅÍxXgv[^[ÜAÁÊÜÌ\ª èܵ½B
èBX½éÊXªÀñŢܷªAÈñÆ5l3lªçtåwTbJ[ÌæyÅÍ èܹñ©I
àTbJ[ƵÄÇÅ«é椸ivµÜ·B
ÁÊÜðóܳê½úìæ¶Ì\ÍÁÉGíÅ èA©éÒSÄÌSðhÍÝɵĢܵ½B
àNxÈ~±ÌÁÊÜðÕá¼XÆ_¢½¢Æv¢Ü·B

½¿©çÍPáÆÈèܵ½tbV
}Ì©ÈÐîXCh𬳹ĸ«Üµ½B
¶©çH¢Ì·ªA¤ÂÞ¢½ªÃغ(
ßver.)AÌPAàâµ±ÆäàAt@U[´
A½¾ÌéØA
15ÅsÇÌO´Ì7lŨ袽µÜµ½B
(h̪)
CâÄÝêÎéÌ21B
yµ¢ÔAæyûÆß²·ÔÍ{É ÁÆ¢¤ÔÅ·B
¡ñÍÔá¢È¡ÜÅÈãÉÈc_AMdȲuAyµ¢ð¬ïªJèL°çêĢܵ½ËB
ÈãtÙȶÍŸçvµÜµ½B
±ê©çàǤ¼²w±²Ú£ÌÙÇXµ¨è¢vµÜ·B
¶ÓFغ@Á
æ24ñ¶BàªåwïwpWï
FlA½fæ訢bÉÈÁĨèÜ·B
ãú¤CãÌ·ª_¾YÆ\µÜ·B
2020N111úA12úÉJóêܵ½Aú{¶BàªåwïwpWïÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
wïÍAsì³öªSÆÈèAãÇõªüOÈOõðs¢AúÌisAPCìA³çÉÍótAN[NÈÇÜŦ͵Äs¢Üµ½B
¶BàªåÉÖAµ½ÅVÌm©âc_ªÈ³êAåAíÈÌæÌÝÅÈAYwlÈÌæÜÅèªL èAÆÄ໡[¢àÌÅ èܵ½B
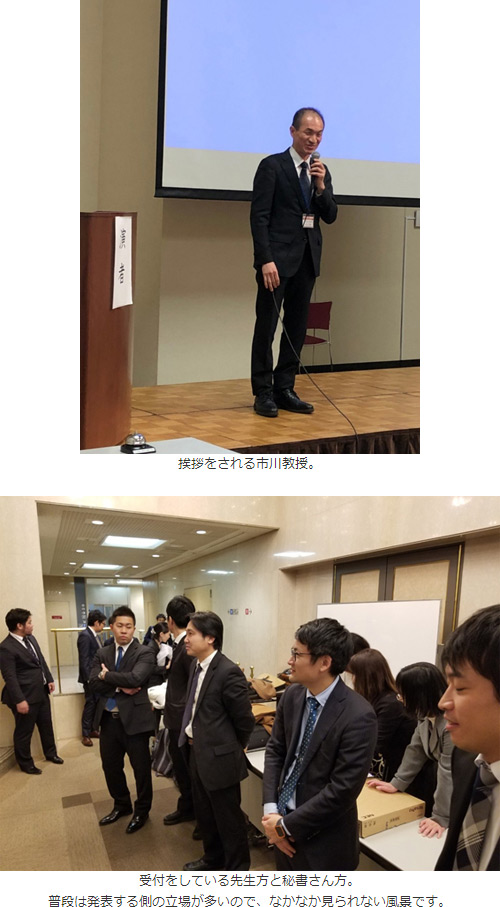

äÌÊèAúÍ`[[NðöµAå¬÷ÉÄwïðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
çtåwåAíÈ̵ÍCÌdzðÀ´·éÆÆàÉAæèêwA©ÍªÜÁ½ÌÅÍÈ¢©Æv¦éwïÅ èܵ½B
Fl{ɲêJlŵ½B

wïIíèÉj5lÅCX^f¦(Î)B
wïïê©çkà5ªÙÇÌêÉu¯[·¯pP[LvÈéàÌðHµÄ«Üµ½B
2800~(Ų«)EEEB ±êð¢ÆÆé©Í ȽæEEEB
¶ÓFãú¤Cã@·ª@_¾Y
ãïj [X@fÚñ@çt§ÌC `Fisher©çSurferÖ`
çt§åAíÈãïÌFlA±ñÉ¿ÍB
®a@åAíÈÌäºÅ·B
¬Å·ªAFlÍçt§Æ·¢Ä½ðܸv¢©×éŵ天B
fBYj[][gA`[oNÉÓÈÁµ[Æ¢Á½LN^[©çAÔ¶AÈßë¤ARXËÆ¢Á½HרâAçtbe}[YÉJEFçtAçtWFbcÆ¢Á½X|[cÜÅFñÈà̪©ñÅ«Ü·ªAçt§ÉZñÅ¢ÄØÁÄàØ裹ȢàÌA»êÍܳµuCvŵå¤B
»ÌÌAçt§Í¾Á½Æà¾íêĨèÜ·ª(}1)A;½mA¼ÍpƧÌÙÆñǪCÉʵĨè»Ì¶bðó¯Ä¨èÜ·B

}1(çtúñ2017N117úæèøp)
©ªÍ¬³¢±ë©çCªD«¾Á½ÌÅACÌ éçt§Éiwðßܵ½B
D´s§ãÃZ^[ÅαµÄ¢½ ÍApÅV[oX(éç)ÌA[tBbVOÉεñŨèܵ½B
10pö̬³ÈA[Å70-80pÉà¨æÔåðÞé ÌExciteÍo¢Å·B
l¶ÅÅàV[oXðÞÁ½úŵ½B
¤CãƵÄÂ\ÈÀèUß±¯Üµ½B
EF[fCOÅ«Ì©Ȣ|CgÉ˵Apɬ³ê©¯½±Æà èܵ½B
ÍìAÍû©ç±ÜÅpÌV[oXtBbVO|CgÍ»êÈèÉmÁÄ¢éÂàèÅ·ÌÅA»¡ éûÍ¥ñºð©¯Äº³¢B
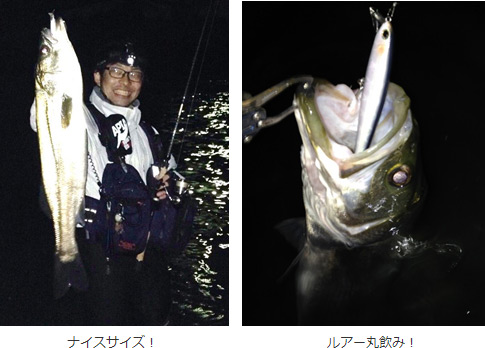
»µÄ»ÝÍ®a@ÉαµÄ¨èÜ·ªA±¿çÍpƽΤ̾½mÉʵĨègðßÄÚZÒà¢éöÌT[tBÌbJƵÄàmçêĨèÜ·B
DZÅÞèðµÄ¢¢Ì©ª©ç¸·ÔÁÄ¢½úðoÄAÐåñȱƩçT[t{[hÆè¢AgæèÌ¢EÉßèñÅ¢Á½Ìŵ½B
ÅÍgɳêCÌãɧÁÄ¢éÆ¢¤´oªA½¾½¾Snæ©Á½Ìŵ½ªAÅßÅÍT[tBÌ»êÈãÌ[³É£¹³êĨèÜ·B
±Ì´eãÅÍêè¹ܹñªAT[tBÌçí¡Íu±ÌFÆêÌ»·év±ÆÉ èÜ·B
g¾¯ÅÈA»Ì©RÆA[JÌlXÆêÌ»·éAT[tBŵ©¡í¦È¢»ñÈf°çµ³ª èÜ·B
ÏÈ@³cÌ©I ÆËÁݪü軤ŷªB
ð¡Ì¢ÌÍÖ«ªÇy³êA½Å੪SÉ©ªÌD«ÈÉD«Èà̪èÉüéæ¤ÉÈèܵ½B
ØðØèöµÄ®õ³ê½StêâXL[êAlHÅÌTbJ[R[gAó²Ì®Á½WB
¯¶X|[cÅàlÔª®¦½Â«ÅlÔSÆàÌÆÈÁĢܷB
à¿ëñ±êçàf°çµ¢X|[cÅÍ èÜ·ªAT[tBÍ»êçÆÍêüðæ·éAܳµ©RªSÌgªåðÌX|[cÈÌÅ·B
»±É½¾½¾¶Ý·égÉæèA©ªª»ÌgÆêÌÉÈêé©B
»ÌgÆA»Ì©RÆA»ÌFÆêÌÆÈê½uÔÌC¿æ³Í¼ÅÍ¡í¤±ÆªÅ«È¢ÌÅÍȢŵ天B
»ãÐïÌúXZE³êéÅA±Ìæ¤ÈÔð^¦ÄêéCÉÍØhÌOðø©´éð¾Ü¹ñB
ܽAT[tBðʵÄúíÅ͵Äo櫓ÆÌÅ«È¢lÆÌo é±Æà£ÍÅ·B
»òïÐðèN^CAµÄêlÅ^J[®ðocµÈªçàȨBig waveÉæ豯é{èÌLegend surferAäpÉÚZµ´Z¯ÉT[tBð`¦ú{ÆäpÌ˯´ÆÈÁÄ¢éQG~
[WVÈÇÆGꤱÆÅÙíÈÜÅÌGlM[ⶫûÌqgðà礱ƪūܵ½B
ܾܾêè¹ܹñªA±êÈ㱯éÆÏÈlµ¢³êĵܢܷÌűÌÓÅB
±«ÍDZ©Å¨ï¢µ½ÛÉ¢½µÜµå¤B
çtÌCð±ê©çàFŤµåØɵĢ«Üµå¤B

¶ÓFä@º
2020N110ú@åãåwåw@ãw¤ÈEãw@¶ÌVXeòw@àäD ³ö
uæ3ñú{ãäJåÜ@àtåbÜvóÜñ
â{ÍàÆæèAÎcæ¶A¢gæ¶Aaûæ¶AXÉÍAÈñÆA»çtåwãw@òw³ºÌÀ¼³öÜÅàA½ÌçtåÌæ¶ûɲw±¢½¾¢½Aåãåwåw@ãw¤ÈEãw@¶ÌVXeòw@àäD ³ö(Ê^Fü©ÁÄêÔE)ªAàt¯[@NãÃíªi{uæ3ñú{ãäJåÜ@àtåbÜv ðóܳêܵ½B
¨ßÅƤ²´¢Ü·I
«IÉÍAm[×ZÜóÜÉ©Îñ¿Åêɯs·é½ßÉAúXT[tBÅrðb¦ÈªçyµÝɵĨèÜ·B

2020N110úAñ¯@ÉÄ\²³êܵ½(\²®)B
cÓOH»ò®ïÐÆ̤¯óÜÅA óÜ^CgÍuSGLT2̪q¯èÆ»ÌjQòÌJvÅ·B
http://www.med.osaka-u.ac.jp/archives/20563
(åãåwãw@Home PageÌæèøp)
ȺÈåAíÈÊMÌàä³öÌBack NumberÅ·B

¶ÓFâ{@Mê
2019/12/26@NX}Xï
åAíÈÊMt@ÌFlA±ñÉ¿ÍB
åAíÈÊMt@ÌZtûü´Å·B
GzȪçAüEã¼N̪åAíÈÊMð©¹Ä¢½¾±ÆÉÈèܵ½B
¡ñÌNX}XïÍsì³ö̲úÓÅJ⽵ܵ½B
¢ÂàãÇo[ðnßAFlɨC¢¢½¾«A´Ó\µã°Ü·B
11Ìsì³öa¶úïÌÛÉAé@V¡³ñ̲ñÄÉæèAEEtcª¬³êܵ½B
ªSµ½ENÍSR¹ª·±¦È¢Æ¢¤S{涩çÌhû]¿à¢½¾«Üµ½ªASÊIɨJß̨¾t𢽾«Üµ½B
BÌtð®¢Ä¾³Á½FlA èªÆ¤²´¢Üµ½B
¡ñàFl̲v]ɨ¦µÄ(Î)Ay«æµ±ÌézðR[_[AØÕAsAjJAgCAOAENðp¢Ät¢½µÜµ½B
úÍAwöÒ̢ȢguÉ©íêܵ½ªA²¡(æ¶)R_N^[Éæéf°çµ¢wǫ̈©°Å³ÉtðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
ËR̨è¢ÉàÖíç¸Aõó¯üêľ³Á½²¡æ¶É´Ó\µã°Ü·B
ܽAñàXµ¨è¢¢½µÜ·(IH)B

y[ogÌFlÉæéÆAplg[l¦ðNX}XâƧLOúÉH×é±Æª½¢»¤Å·B
±êÍAåAíÈÌNX}XïÉsb^Æv¢A·µü곹Ģ½¾«Üµ½B
FlɲD]¢½¾¯ÄÇ©Á½Å·B
¦plg[lFhCt[cÌüÁ½pÅAóÍT¦ßB

ÅãÉQÁÒSõÅÊ^Be(o^\^o)
¡ñÍA²sªíÈ©Á½FlAñ̲QÁðEEtcꯨҿ\µã°Ä¨èÜ·(^^ô
¶ÓFåAíÈZt@ûü´
2019N122ú@çtåwáèåAíÈãtÌï
åw@2NÌàâÆ\µÜ·B
122úÉçtåwáèåAíÈãtÌïªJóêܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
±ÌïÍåw@¶ªeX̤ºâ¤àeðÐîµ½èAÖAa@É¢éáèհ㪻ÌÕ°o±ðÐîµ½è·éïÅANÉ2ñJóêĢܷB
ÅÉâ{æ¶æèçtåwåAíÈw̤̻ÝÆ«É¢IJÐ¾«Üµ½B

çt§à¾¯ÅÈA_ÞìâÈØÌÖA{Ý©çàáèÕ°ãªWÜèܵ½B
»ÌãAåw@¶ª»ê¼ê̤Ìi»óµâA¡ãåw@Öüwðl¦Ä¢éæ¶ûÖޯĤºÌÐîðs¢Üµ½B
¯¢ãÌÔ½¿ªSÙÈé¤ðsÁÄ¢é±ÆÍ©gÆÄàhÉÈèܵ½B
Áɱê©ç¯wðT¦éRcæ¶Ì¯wÜÅ̹ÌèâAV½ÈvWFNgÉÖíé|ºæ¶ÌbÍÝȪ»¡ðÁÄ·¢Ä¢½Æv¢Ü·B

üÇ1NÚÌP涪¡ñQÁµÄêܵ½B
SSÌîb¤Ìbð·¢Ä`vJvA¢âPæ¶Èç·×ÄðµÄ¢½Æv¢Ü·ªAåAíÈãªèpâO¾¯ÅȢƢ¤ðm龯ÅàáèÉÆÁÄMdÈ@ïÈÌ©àµêܹñB
æúA¬sêåܪuONE TEAMvÆ\³ê³Or[ƵĻ±µÄ¨èÜ·ªAåAíÈàÙÈ餺¯mA³çÉÍÕ°Ìæ¶Æàhµ ÁÄAONE TEAMðz¢Ä¢«½¢Å·ËB
¶ÓFàâ@wl
2019/11/27 sì³öÒïj¢
FlåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
ãú¤Cã1NÌäàÆ\µÜ·B
¡ñÍæúsíê½sì³öÌÒïj¢Ìlqð²ñvµÜ·B
ÅÉâ{æ¶æèçtåwåAíÈw̤̻ÝÆ«É¢IJÐ¾«Üµ½B
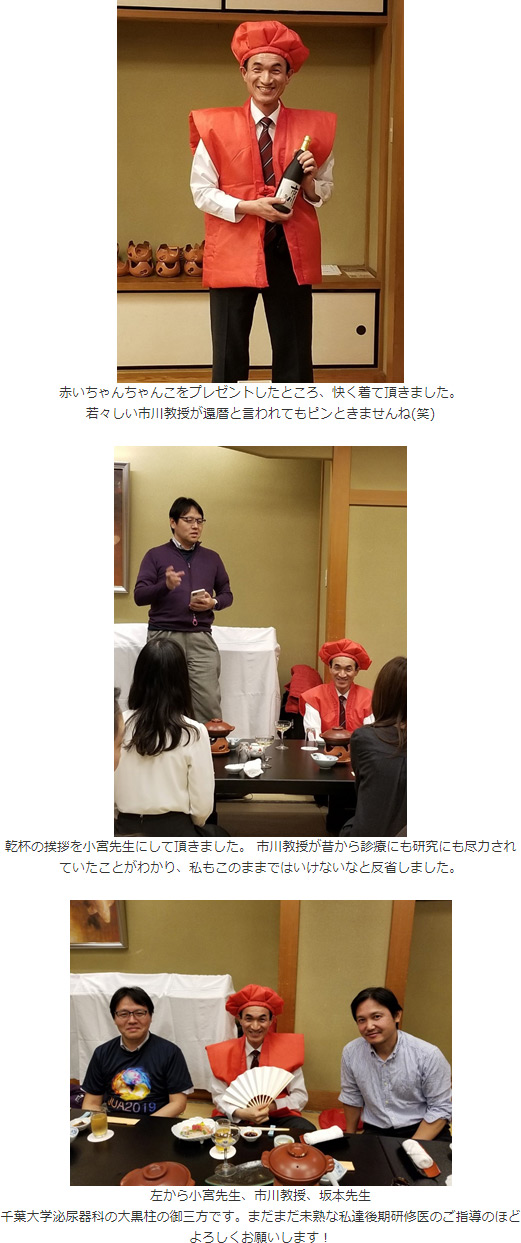

JUAÌÛÉJõ½w`ÅÍsì³öÌyõÈjOðq©µ½èÆAsì³öÌÍâs®ÍÉÍÁ©³êéΩèÅ·B
±ê©çà³çɲô³êé±ÆðãÇõꯨFèµÄ¨èÜ·I
¶ÓFäà@x¾N
2019/11/20 åw@ïc
çtåwåw@1NÌnê°ìÅ·B
1120úɤïcªJóêܵ½ÌŲñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
e³º©çÌñA¤àeÉ¢Ä\ª èܵ½B
ßÄQÁ³¹Ä¢½¾¢½ÌÅ·ªåÏ×ÉÈèܵ½B
(s×Ƚߪ©çÈ¢±Æà½X èA©ªÌOr½ï³ðÀ´µÜµ½B)
¾³ÉεĪqîáwAòwAawÈÇlXȪì©çAv[`·é±ÆÅ©ª éʳª èܵ½B
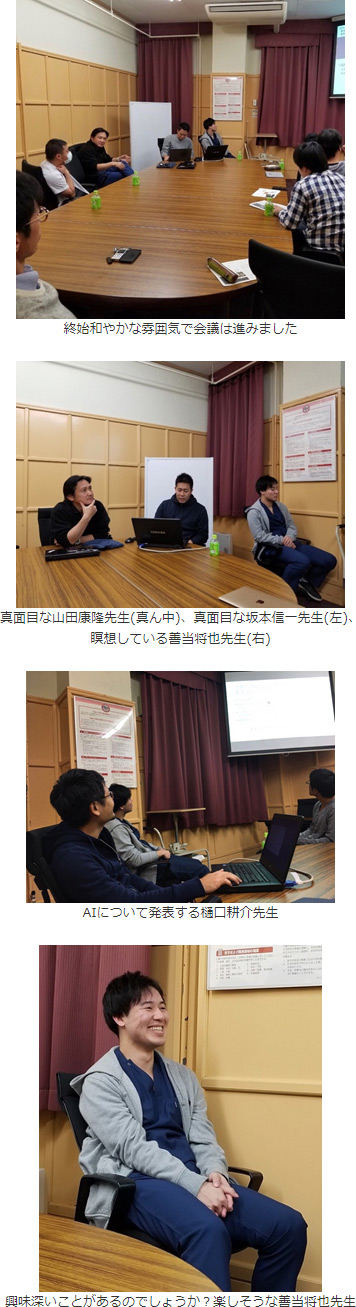
d¢µÍCÅÍÈ©RÉDiscussionÅ«é½ß¤CãÌæ¶â¤É»¡ éæ¶ÈÇCyÉQÁµÄ¢½¾¯êÎÆv¢Ü·B
¶ÓFåw@¶@nê@°ì
åAíÈåw@¤ºcA[
åw@4NÌóûÆ\µÜ·B
æúAåAíÈåw@̤ºÐîðsÁ½ÌÅñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
çtåwåAíÈÍ»ÝAåw@¶ª12¼A®³ºÍåAíÈwÈOÉà6³ºÉyÑAÕ°©çîbAAIÉæéðÍÜÅlXȤðsÁĨèÜ·B
»Ì½ßANx©çåw@Ť·éæ¶ûÌ×ÉAe³º©çæyûª©ª½¿Ì¤ðÐî·éAèµÄåAíÈåw@¤ºcA[ðJõܵ½B
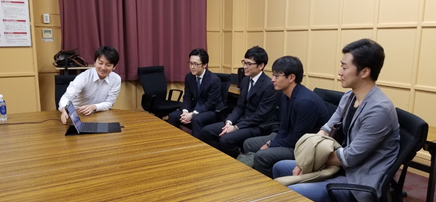
©ªÌ¤Ìà¾ð·écæ¶ÆNxÌåw@¶½¿B
cæ¶Í¡ñéÊ©çQíµÜµ½B
ãyÌ×Éí´í´çtÜÅéÈñÄCPÅ·ËB
e³ºÌྪIíÁ½ãÍerð[ßéHïB
wNªß¢à̯mbàeÝܵ½B
N©çåw@Éüé涽¿ÍA¡ooÕ°ðâÁÄ¢éÌÅAîb¤ÉεĽàí©çÈ¢óÔªsÀÆÌŵ½ªAæy½¿Ìbð·¢ÄµsÀªðÁ³ê½æ¤Å·B

¶©çàâAáäAÖ¡AÄcAàAóûAcºAcA²¡
çtåwåAíÈÅÍÕ°Íà¿ëñîb¤A³çÉÍ»Ìæ̯wÜÅ©¦ÄA¸ÍIÉ®µÄ¨èÜ·B
Õ°A¤¼ûâ轢Ƣ¤ûAçtåwåAíÈÅÒÁĢܷB
¶ÓFóû@kî
2019/11/14 sì³öÒïj¢
ÝȳÜßܵÄI
±Ì4©çCmÌw¶ÆµÄsì³öÌàÆÅ׵ĢécA²¡AnÓÅ·B
1114úAsì³öÌÒïj¢ðåw@ãÇÉĨ±È¢Üµ½(^ ^)
¡NÍÒïj¢Æ¢¤±Æà èAãÇqo[ÅEEtcð¬µAâI¢½µÜµ½ô

v[gÉÍÔ¢}t[ð❤
±ê©çÌGßAgÁÄ¢½¾¯éÆðµ¢Å·c

ªv[gÉÔ¢}t[ÆACmVVÌJ`
[Vðv[gµAÍÉ©Þsì³ö
ÅãÍFÅÊ^ðc
ãÇÌF³ñÆcRµAçtåwåAíÈÌÌdzðÀ´¢½µÜµ½I

ªFÅWÜÁÄWÊ^_(^o^)^@sìæ¶gïÒhÉÈÁÄ¢éÌͲ¤g❤Î
oC^eB[ìêésì³öAÜ·Ü·[Àµ½êNðß²¹éæ¤ãÇõê¯SæèFÁĢܷB
¶ÓFcA²¡AnÓ
2019/8/23 C¥¢
ãú¤Cã1NÌO´Æ\µÜ·B
èáïÅ éC¥¢É¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
ðNÌÆÍÙÈè¡NÌÄÍ~Jª·ärIC·Í¿
¢Ä¨èAß²µâ·¢ÄÅ Á½ÆL¯µÄ¢Ü·B
»ñÈÄÅ èܵ½ªåAíÈÍ¡NàMA¸ÍIÉ®µÄ¢½©çŵ天AC¥¢ÉÍX^btA@¶AaÅìt³ñAIyºÅìt³ñACmÌûA»µÄú¤CãƽlÈcŨ40lÈãQÁµÄ¢½¾«AåÏ·µÈïÆÈèܵ½B
¡NJUAªçtåwå²Å èAsì液sÍÌàƬ÷ðûß½ÌÅ·ªA»ÌÛ쬵½JUA T-shirtðFl¯Ĩçêܵ½B

·èãªèÉ·èãªèAêïAñïÅÍIíç¸A©4ÜÅê辩µ½ÒÒ½¿à¢½æ¤Å·B
2019Nã¼à Óê騢ÆîMÅåAíÈð·èã°Ä¢«Üµå¤B
¶ÓFO´@MM
International Journal of Urology\fÚÌäñ
çtåwåAíÈÌR{«uÅ·B
Fl¢ÂàåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
±ÌxAÅåÏ°kÅ·ªInternational Journal of UrologyÌ\É_¶ÌFigureªfÚ³êé±ÆÉÈèܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
_¶Ìè¼ÍIntravesical irrigation might prevent bladder recurrence in patients undergoing radical nephroureterectomy for upper urinary tract urothelial carcinoma.Æ¢¤_¶Å·B
±Ì_¶ÍAãAHãçàÌpÉäNã÷àó¬ðs¤±ÆÅäNã÷àÄð}§·éAÆ¢¤àeÅ·B
ª¡lJÐa@É¢½©çAÜÆß³¹Ä¢½¾¢Ä¨è¡lJÐa@Ìæ¶ûÀÑÉ_¶Ì²w±¢½¾¢½¡ºæ¶Aâ{æ¶ðͶßçtåwåAíÈÌæ¶ûÉA´Ó\µã°Ü·B
±Ì_¶©ÌÍAaccept³êéÜÅ3NðvµÄ¨èArŶ¯»¤ÉàÈèܵ½B
½©ðâè°éãÅAn¹ÈwÍÌdv«AEÏæègݱ¯é±ÆâAüÍÌlX̦ÍÌåسªgÉÝܵ½B
¡ãà²w±²Ú£ÌÙÇæ뵨è¢\µã°Ü·B

¶ÓFR{@«u
TcJbv2019CÌú
725úÌCÌúÉ[ÌìÉ éL¼ÈTca@ªå÷éãÃ]ÒÎÛÌT[tBåïÉQÁµÜµ½B
~}àõAÅìtAãtAwÃ@mAãñÈÇlXÈãÃÖAÌûXªQÁ³êܵ½B
kÍkC¹AìÍA«ê¿V©çQÁ³êéÙÇÌåKÍÈêåCxgÅ·B
È©çÍAâ{Aäæ¶AÅìt̬ÑNAÖAa@©çÍwÃ@mÌÌèܳNA¤C³êÄ¢éæ¶Ac]涪QÁ³êܵ½B
±ÌlªçtåÖA©çQÁ³êéÌÍßÄŵ½B
NÍA½¼ÉÈéÌ©yµÝÉÈèܵ½B
gÌTCYÍAZbg¹AªÌ¿ø«ÅuCN|CgªÏíégÉ|M³êȪçÌåïŵ½B

WbWð±ßÄ¢½¾¢½AìogÌvT[t@[Éæéfà èܵ½B
ú{gbvxÌ´L¼ÈvT[t@[àI
öÝÉTca@ÉÍAIsbNóâÌ«ÅìtvT[t@[ª¢Ü·I


¡ñA¢«ÈèíÅAçtååAíÈÅìt̬ÑNÆâ{ª¯¶q[gŽèÙ£µÜµ½ªAÜlçtåÌñlª³EhAbv·éÈÇÌv¢oà èܵ½B
«êÉ é¿V¿Fïa@ÌT[t`[©çÍAeNXűXÆüÜÒð¾µÄ¢½ÌªñíÉóÛIŵ½B
a@ÌÚÌOª|CgÌæ¤ÅATca@ÉéÆàòçȢ«Ìlŵ½B
çtÍAT[tBÌIsbNïêÉÈéÈÇA[¼É½Ì¢EIT[tX|bgª_ݵĢܷB
a@©çàaØFreeÌ40ªÅ|CgÉÂÈÇAÕ°ÆT[tB̼§HHàÂ\©àµêܹñB
çtååAíÈT[tBE·ÆµÄAú{ÅÌãÃ]ÒT[t`[ðÚwµ¡ãàæ£ÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
T[tBÉ»¡ª élA·ÅÉnßÄ¢élÈÇA¥ñAçtÅêÉCÉüèܵå¤B
¶ÓFâ{@Mê
2019/7/20@çtååAíȯåï
Fl¨¢bÉÈÁĨèÜ·BåAíÈüÇ1NÚÌéØÅ·B
¡ñÍæú720ú(y)ÉJóê½çtååAíȯåïÉ¢IJñ³¹Ä¸«Ü·B
¡ñ̯åïÅÍAea@Ì®üÉ¢Ą̈bALåwåAíÈ̼´³öÌuÆA¡NxÌVüÇÒÉæé©ÈÐîª èܵ½B
O¼Ì®üÌñÅÍAܸ¯åÌ·Ì涪20lߢçÁµáé±ÆÉÁ«Üµ½B
ܽa@»ê¼êÉÁ·ª èA»ê¼êÌa@É¢ÄàÁÆm轢ƴ¶Üµ½B
ïÌrÅAäXt}(üÇ1NÚ)æè©ÈÐîXChð»ê¼ê2`3ÉÜÆßÄ\³¹Ä¸«Üµ½B
eX̶¢§¿â«ÌÚWÈÇA«IÉ\³¹Ä¸«Üµ½B
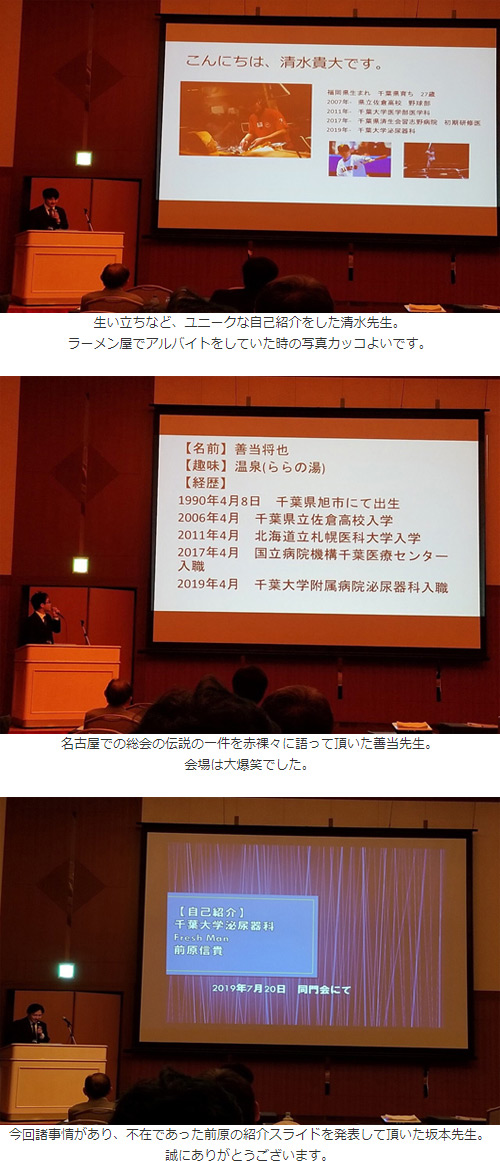
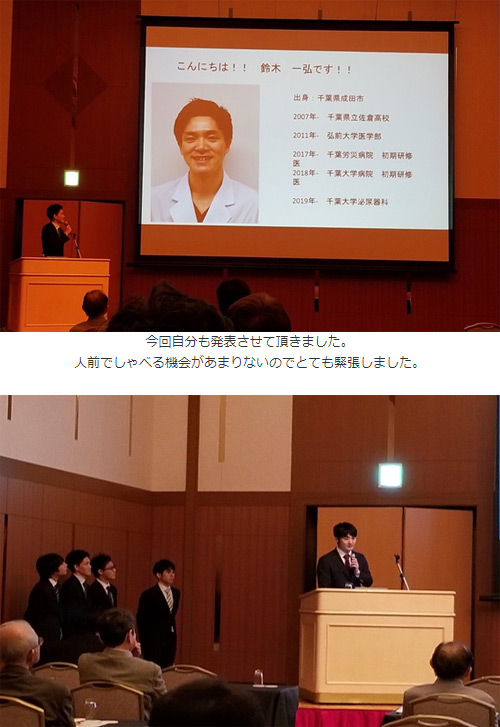
¡ñ©ÈÐîÌêð¸«A½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
æ¤âçtåwåAíÈÌêõÉÈê½Æ¢¤À´ªN¢Ä«Üµ½B
äXt}ê¯Ü¾Ü¾çÈ¢_ª½X éÆÍv¢Ü·ªA²w±²Ú£Ìöæ뵨è¢vµÜ·B
¶ÓFéØ@êO
2019/6/30 úìånæ¶@ÍéÅçt§åïDI@SåïÖ
2019N630úAÍéTçtÉÄA}`
AÍéEÌÅôð£¤uæ65ñSú{A}`
A{öVèíçt§åïvªsíêAãÇõúìån涪2NÔèÉ©AD³êܵ½B
ðNÍvCx[g̽ßê³êĨèÜ·B
úìæ¶Í¬w1N¶Ì æèí³ñÆeÌ©ßÉÄÍéðnß½»¤Å·B
úìæ¶Í¬AAÆNãÊú{`sIÉÈÁĨèÜ·B
í³ñà¯ÉNãÊ`sIÉÈÁĨèjãÌõÅ Á½Æ̱ÆÅ·B
úìæ¶ÆÍé𤿽¢¤CãÌûª¢Üµ½ç¥ñAüǵÄyµ¢ÍéCtðÁľ³¢B
¡ãASæåïª817A18úÉsJÉÄJóêéÆ̱ÆÅ·B
ºÐAv¢Øè²ôµÄ¸«½v¢Ü·B
OúͨððâßSÌ̲Å]ñź³¢B
ãÇõ꯵ĨèÜ·B

Urology Today in Chiba 2019/5/31
FlA¢Âà¢bÉÈÁĨèÜ·B
åAíÈüÇ1NÚÌ´
Å·B
¡ñÍæúJóêܵ½Urology TodayÉ¢IJñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
çtwÌyGz[ÉÄsíêܵ½uïÍAuåAíÈwɨ¯éfÃE¤ÌÅVÌbèvÆèµÜµÄAeªìÉ·¯éæ¶û©ç²u¢½¾«Üµ½B
ܽAÁÊuƵÄJCHOVhfBJZ^[@·Ôq÷êYæ¶æèO§BàÌîb¤©çÕ°pA»µÄPSAfÉ¢Ĩb¢½¾«Üµ½B

©gªÇ¤µÄåAíÈðIðµ½Ì©ÈÇàð¦ÂÂ[Aìêéu𢽾«Üµ½B
Ôqæ¶ÉͲ©gÌo±ð𦤩çPSAfÈÇnæAgÈÇà¨b¢½¾«A¶Á跱ƪūܵ½B

Ôqæ¶@O§Bà-îb¤©çÕ°pA»µÄnæAgÜÅ
½Ìú¤CãÌæ¶ûAw¶³ñɲQÁ¢½¾«AåAíÈÖÌÖS̳ð´¶Üµ½B
ÈñÆA¨20¼Ì¤CãÌæ¶âw¶³ñªQÁµÄêܵ½I

ÂïãÌWÊ^@½³ñ̲QÁ½É èªÆ¤²´¢Ü·B巵ŵ½I
ܽA»ÌãJóêܵ½§eïÉà½Ì²QÁ𢽾«Aerð[ßé±ÆªÅ«Üµ½B
ºLÊ^ÉÍg~OðÁ¦Ä¨èÜ·B

äÌæ¤ÉuïA§eïÆàÉ巵ŵ½B
çtåwåAíĘ̀¢ª»ÌÜܽf³ê½æ¤É´¶Üµ½B
NÈ~ÌüÇÒÉúÒªcçÞïŵ½B
¡ãà©UïÈÇðJõĢ\èÅ èÜ·B
»¡Ì éûͲA¨Ò¿µÄ¨èÜ·I
çtåwåAíÈðêÉ·èã°Ä¢«Üµå¤I
¶ÓFçtåwåAíÈ@´
@Må
`[oñAPonta@
5/16ÉQå}XRbgLN^[Å é`[oñAPontaªçtåwãw®a@É@³êܵ½B
`[oñÍAF³ñ²¶m(H)Açt§Ì}XRbgLN^[ÅAÖsªçt§Ì`ðµÄ¢é¢«àÌÅAÓÈÁµ[ðµÌ®lCÅ èÜ·B
erh}ÅàÅß½gp³êÄ¢éVµÈÁ½OÅ·ªAQå}XRbgÌïÕÌR{Æ̱ÆÅAÊ^ðßÄl¾©èªÅ«Ä¨èܵ½B
OðI¦½ãÉ`[oñAPontaÆBÁ½Ê^Å·B
ñíÉAbgz[ÈãÇÅ·ÌÅAüÇðl¦Ä¢éæ¶ûAºÐêx©wÉ¢çµÄ¾³¢I
¨Ò¿µÄ¨èÜ·B

2å}XRbgÆÌïÕÌR{Ê^
¶ÓFåw@¶@|º@¨d
AUA in Chicago, May 3-6, 2019
®a@åAíÈÌäºÅ·B
Fl¢ÂàåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
±ÌxAâ{Mêæ¶Æåw@¶CC³ñÆAUA2019ÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
¡NxÌAUAÍChicagoÅÌJÃÆÈèܵ½B
òs@Ũæ»12ÔAú{ÆÌ·Í14ÔAAJÌÙÚÉÊu·éChicagoÉ·§¿Üµ½B

ÙÆÙÚ¯¶ÜxÅ èA5ÅàR[gªÈ¢Æ¦Äk¦éCóŵ½ªAXÉͼ³Ét[YhNðÐèÉàAmericanÌpà è»ÌCh³ÉÁ«Üµ½B

çtåÖA©çÍ2è(ÎÕ°1èAäNã÷àîb1è)ŵ½B
©ªÌ\ÍSÎuw²¸ÌXüð¥Ü¦Açt§ðã\·éΡÃnC{
[Z^[Åà é®a@ÌΡÃÌuwÉÖ·éèŵ½ªAnative speakerÅà éâ{æ¶ÆÌOÌxdÈéDiscussionÉæè²ÈH\©ç¿^ÜÅæèØé±ÆªÅ«Üµ½B

AWA¨ÌÅÍú{Ì誽¢óÛŵ½ªA»ÌÅàcåAOOåA¼Ã®s§åͽÌèð\µÄ¨èA»Ì¨¢ð´¶Üµ½B
çtå²ÅcÉüǵ½Îcæ¶ÍêlÅ4èÌ\ð±ÈµÄ¨èEXµÜµ½B

ÎÌZbVÉÄcð©¹é¼Ã®s§åwÎ`[
wïÌéÍSBUR̳öwÌz[p[eBɲµÒ¢½¾«Üµ½B
ÅÍîb¤ðâÁĢȢ©ªÈñ©ªQÁµÄæ¢àÌ©ÆKݵĨèܵ½ªAÇÌæ¶àC³Å¾éºð©¯Äº³èAmerican Home Party̵ÍCðyµÞ±ÆªÅ«Üµ½B
ܶßɤ·é¾¯ÅÈAÐðIÉlbg[Nð`¬·é±ÆàdvȱÆÈ̾ÈÆÀ´µÜµ½B

AUAI¹ãAi^[V³öÉï¢Éâ{æ¶Ì¯wæÅà éUK(University of Kentucky)ÉeÛcA[Åü©¢Üµ½B
P^bL[BÍCmCÌ×ÌBÅ·ªAChicago©çÌ£ÍÈñÆ600kmB
^J[ðØèÄ6Ô©¯Ä
µÜµ½B
VOÌwrª§¿ÀÔSÄæ3ÊÌssChicago©çê]µA©n·ÀèÌüµ¢ÎÌŶÉÍÜê½KentuckyÌånÉiFªÏíèAÊ¢Eɽæ¤Åµ½B
KentuckyÍóCâ
àÝAlXਨç©ÅASªôíêéæ¤ÈÆÄàf°çµ¢êŵ½B
i^[V³öââ{æ¶Ì¯wãÌmlÆZ¢ÈªçàLÓ`ÈÔðß²·±ÆªÅ«Üµ½B
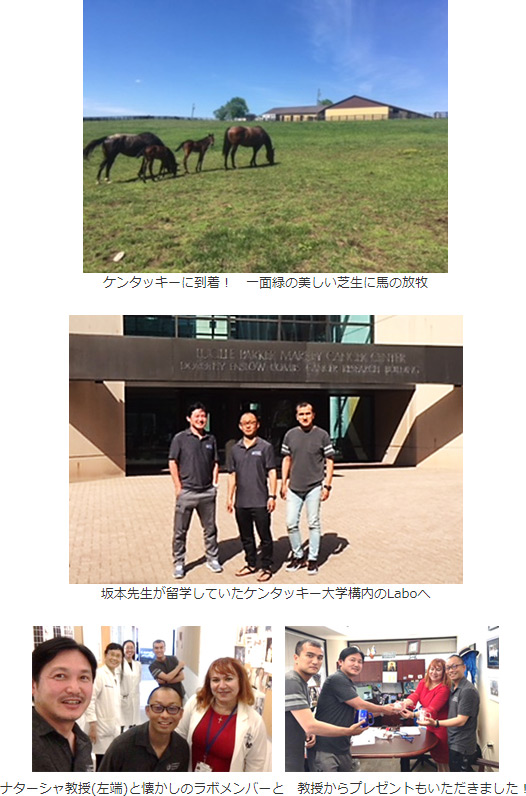

AUAÅÍÅVÌm©ÉGêé±ÆªÅ«é¾¯ÅÈA¼åwâCOÌæ¶ûÆð¬ð·é½Ì@ïª èAñíÉ¢hðó¯é±ÆªÅ«éÌà£Íŵ½B
{wïÌQÁÉ ½èAâ{æ¶ðͶßÖAÌæ¶ûA®a@ÌX^btÌFlAçtåwåAíÈãÇÌFlÉråÈx𢽾½«{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
±ÌêðØèÄúäçð\µã°Ü·B
¡ñÌo±ð©µAuÇ¢åAíÈãvðÚwµÄXebvAbvµAçtåwåAíÈãÇð³çÉ·èã°Ä¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
±êðÇñÅ¢éáèÌæ¶ûà¥ñAUAQÁðÚWÉæ£ÁÄàç¦êÎÆv¢Ü·B
ÅãÉA¡ñÌAUAcA[ÅÅਢµ©Á½Speedway(K\X^h)ÅÌ$1ÌzbghbOŨÊêÅ·B
sNXÈÇÌgbsO೿ÅAuÀ¢A¢A¤Ü¢vªlÜÁ½WNt[hÌÉÝÆྦéÅÌ1{ŵ½B

ÅÌ1{ÉæJðYêAÎçª ÓêoééÌSpeedway
¶ÓFä@º
2018/11/22 sì³öa¶úï
11/22Ésì³öÌa¶úïðåw@ãÇÉÄs¢Üµ½B
sì³öÌa¶úïÍAãÇPáÌsÆÈÁĢܷB

FÅÀè÷ðÀ×éƳöº©çüè«çÈ¢ÙÇ¡Nàå·µÈa¶ïŵ½B

sì³öÌÌNîÍ30ãð¢¾ÉÛ³êÄ¢éÆ̱ÆÅA{ÉlXÈdð³êÄ¢éÈ©ANÍå¾ÆüßÄ´¶Üµ½B

30ãÆ·¢ÄóðÝé|àæ¶
ãÇ©ç³³â©Èªça¶úv[gð¨nµµÜµ½B

NÍåAíwïïðsì³öªï·ÌàÆJóêAÜ·Ü·[Àµ½êNÆÈé±ÆðãÇõꯨFèµÜ·I
¶ÓFåw@¶ |º¨d
2018.7.23 çtåwãwd®ì @åAíÈ©Uï
çtåwd®ì
@åAíÈ©Uïðs¢Üµ½B
ãw6N¶Æ5N¶v6¼QÁ¢½¾«Üµ½B
åAíÈ©çÍA[Ì_a@@®a@©çäæ¶(^ñ)ªì¯Â¯Äêܵ½B
d®ì
ÍãÌðÈñÆñAeI@OAeÖü¯ÄÚºûKÆ̱ÆB
w¶³ñ©çÌåAíÈÉηéM¢v¢ð§Åѵѵ´¶ééŵ½B
úÒÉ»¦éæyÉÈêéæ¤Éæ£çÈÄÍÆAüßÄC¿ðø«÷ßév¢Åµ½B
ÌãÌæ£Áľ³¢I

¶ÓFâ{@Mê
ASCO/JSCOtF[VbvvOQÁñ
qõ¤õƵÄéÊãÈåwÅîb¤ðsÁÄ¢éìjÅ·B
ASCO/JSCOtF[VbvvOÉQÁµÜµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
±ÌvOÍASCOwpWïÉú{©çáètF[ðhµA¯wpWïI¹ãÉ3ú`1TÔöxAÄÌL¼È¤{ÝEa@ðASCOÌÐîÅKâµAæûÌVjAÉzXgµÄàç¢^[ÖWðz±ÆðÚIƵĢܷB
¡ñÍASCOI¹ãÉDetroitÉ èÜ·Karmanos Cancer InstituteÖKâµÜµ½B
ASCO meetingÒ @Chicago
ASCO meetingÍáNChicagoÌMcCormick PlaceÅJóêAªñ¡ÃÉÖíé·×ÄÌÌæÌãtªê°Éï·éñíÉå«ÈWïÅ·B
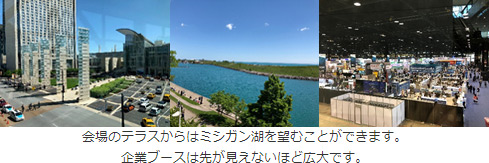
åAíÌæÍO§BªñÆñO§BªñÌZNVɪ©êA1®¸ÂŵI³ê½èÌ\ª èÜ·B
ÁÉåKͱÌñÈǪASCOÅßijêé±Æà èÚxÌ¢WïÅ·B
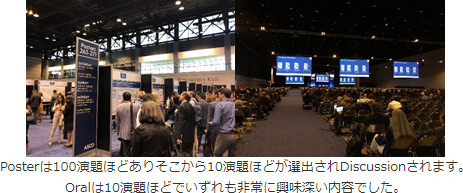
¡ñÌASCOÌPlenary sessionÅÍA]Ú«tªñÉηé¡Ã@ƵÄèp{X[eg^æèàX[egPơêDÊÅ éÆÌñª³êĨèAåÏÚðWßĢܵ½B
±êÜÅÌwtªñÍ]Úª ÁÄàܸèpxÆ¢¤ûjð¢·ñÅãÉKâµ½{ÝÅà±ÌñÉ¢ÄMc_ªðí³êĢܵ½B
O§BªñÌÌæÅÍÆuÃ@âlíÉæé¡ÃÌ´ó«ÌñªgsbNÉÈÁĢܵ½B
ASCOɨ¯éÚèÌÚ×É«ܵÄÍA{NÌú{ªñ¡ÃwïÅ\³¹Ä¢½¾\èÆÈÁĨèÜ·ÌÅA²»¡ª èܵ½ç«ð^ñÅ¢½¾¯êÎK¢Å·B
Karmanos Cancer InstituteKâÒ @ Detroit
òs@Å1Ô¼ÙÇÚ®µADetroitÉ éKarmanos Cancer InstituteÖKâµÜµ½B
Karmanos Cancer InstituteÍNational Cancer Institute©ç30NÈãOÉComprehensive Cancer CenterÌwèðó¯AlXȪì̪ñ¡ÃÌêåƪ½WÜÁĢĢéZ^[Å·B
ÁÉ¡±ÌPhase IÅÍ¢EIÉL¼ÅA¡ñª¨¢bÉÈÁ½Dr. Ulka VaishampayanÍåAíªñåÌOncologist(îáã)Å èAPhase I trialÌÓCÒÅ·B

ú{ɨ¢ÄÍäXåAíÈãªèpÌÝÈç¸zÃ@A»wÃ@ÈÇðs¤±Æª½¢Å·ªAÄÅÍ®Sɪƻ³êAåAíªñÌò¨¡ÃÍOncologistªSµÜ·B
f@Í`[ÉæÁÄsíêAܸÍPhysician Assistant (PA)ª³ÒîñðûWµãtÖv[e[Vðs¤AãtͳÒÖÌÊkðs¢AÀÛÌòÍêCÌÅìtªs¤Æ¢Á½¬êÉÈÁĢܵ½B
ÁÉPAÌdÍA¸f[^ÌðßâgÌf@A¡ÃvÌñÄÈǽòÉí½èÜ·B
¡ñÌKâÅÁÉ´¶½ÌÍPhase I±ªÊíÌ¡ÃÆV[XÉsíêÄ¢éÆ¢¤_ŵ½B
ÀÛɪ©wµÄ¢éÔÉà¼Ì³Ò³ñªPhase IÌ¡ÃòÖÚsµAܽÊíÌ¡ÃÖßéáà èܵ½B
Dr. VaishampayanÉæéÆÊíg¤¡ÃòƯ¶´oÅVòð¡ÃÉgÝÞ̾»¤Å·B
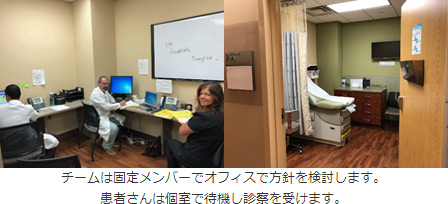
¡ñÌKâÅÍåAíÈãâúËüÈãAaãÆàfBXJbV·é@ïª èܵ½B
ÁÉO§Bàɨ¢ÄÍpãÌúËü¡Ãð©ÈèÏÉIÉsÁÄ¢é_ÆA¨ïR«O§BàÌ]ÚÉεÄCTKChºÉ¶ðsÁÄ¢é_ªóÛIŵ½B
OEÏõÒ
COwïÌçí¡Æ¾¦Î»nÌü¡µ¢HרÆÏõÅ·B
¡ñÍ©Èè^CgÈXPW
[̽ßÙÆñÇÏõÍūܹñŵ½ªHרSɲÐîµÜ·B
VJSÍÀSÈXÅ¿ÀÔwrÆXð¬êéìªóÛIŵ½B

VJSBOÆ¢¦ÎÉúÌDeep dish pizzaÆP`bvð©¯È¢Hot dogªL¼Èæ¤Å·B
Ç¿çàü¡µ©Á½Å·ªDeep dish pizzaÍåÊÌ`[YÉâçêÜ·B

êûAfgCgÍSÄ\ë¯ÈXÆ¢íêĨèKâæÌãt©çàêÌÀSÈêÈOÍúÅàoà©È¢Ù¤ªæ¢Æ¾íêܵ½B
MidtownÆDowntownÍärIÀSÉoà¯éæ¤ÅQlineƾ¤HÊdÔÅÎêĢܷB
ÎÌü±¤ÍJi_B
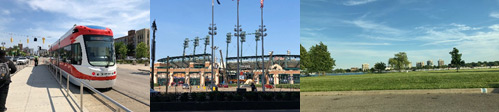
fgCgÍnÌÚ¯ª½¢XÈñ¾»¤ÅAGXjbNÈ¿ª¨©ßÆ̱Æŵ½B
ChäogÌ^[Ìæ¶ÉArA¿ÌXgÉAêÄsÁÄ¢½¾«Üµ½B
ܽADowntownÉÍMV¿Ì¨XªWÜéGAª èÜ·B
Ç¿çà{iIÈ¡ÉââËf¢Üµ½ªµêÄéÆü¡µ´¶Üµ½B

ASCOïúAãBåwåAíÈÌc^Èæ¶(ðNÌASCO/JSCOho[)ÆØpuæ¶(¯vOho[)ÉÍåϨ¢bÉÈèܵ½B
æ¶ûɨU¢¢½¾¢½¨©°Åü¡µ¢HÆyµ¢Ôðß²·±ÆªÅ«Üµ½B
Áɦó̺teenagerÉÍÜêÄϽTaylor SwiftÍYêçêÈ¢v¢oÅ·B
ܽA¯¶vOÅh³ê½æ¶ûÆ̨bÍAfÃÈâfõĢénæªÙÈé±Æà èåÏhðó¯Üµ½B

ÅãÉÈèÜ·ª{vOɲE¢½¾«Üµ½sìqF³öAú{à¡Ãwï gc aOÛÏõ·AMentorÌDr, Ulka Vaishampayan»Ì¼½Ìæ¶ûɱÌêð¨ØèµÄSæè[Ó\µã°Ü·B
{vOÍASCOQÁÖÌnqïAØÝïÈǪx³ê龯ÅÈAÄÌL¼a@ÅfÃÆ¡±ÌÀÔðw×éñíÉLÓ`ÈàÌŵ½B
»¡ª éáèÌæ¶Í¥ñåµÄÝľ³¢B
ÇL
ØÝæÌfgCg©çAérÉåKÍÈòs@xª¶µAfgCg¨VJS¨T[X¨`¨¬cÆåÏÈ··ÉÈÁĵܢܵ½B
ÅãÉÄçµ³ðÉ´·é·Åµ½B
¶ÓFì@j
2018.6.15`16 ú{AhW[wïæ37ñwpåï@QÁñ
qõ¤õÌìÆA¯¶|àÅ·B
2018N615úE16úÉ_ËÅJóêܵ½ú{AhW[wïæ37ñwpåïÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñµÜ·B
ú{AhW[wïÍsì³öª·ð±ßĨèA³ºÆàÖíèª[¢wïÅ·B
¡ñÍ_ËÌh}[NÅ é|[g^[ð]Þ¥XC[g_ËI[VYK[fÅJóêܵ½B
çtåwåAíÈ©çÍsì³öA¬{y³öAâ{utA|àAìAR{Æ»Ýåwa@ð[e[gµÄ¢éú¤CãÌéØæ¶Æ¡N©çåãåwÌòwÉÚ®µ½åAíÈåw@²Æ1NÚÌ涪QÁµÜµ½B

ìÆ|àÍ»ê¼êîbåÆÕ°åÅïÜɧÞàcOȪçóÜÍÈç¸B
{wïÌx̳ð´¶Üµ½B
¡ñÌïÜèÍYwlÈ̳ºªåÃƾ¤±ÆŶBãÃÉÖ·é\à½åÏ×ÉÈèܵ½B
ܽAâ{fÃutÍChina-Japan-Korea Andrology Session Å\µeÌGLXp[gÌæ¶ûÆMc_ððíµÄ¨èܵ½B

»µÄA³ºÌR{«u涪Clinical Genitourinary CancerÉfÚ³ê½Testosterone Reduction of ? 480 ng/dL Predicts Favorable Prognosis of Japanese Men With Advanced Prostate Cancer Treated With Androgen-Deprivation Therapy.Æ¢¤_¶Éεwp§ãÜðóÜ¢½µÜµ½B
¨ßÅƤ²´¢Ü·B
±Ì_¶ÍAú{lɨ¯éis«O§BàÌzÃ@ð{sµ½³Òɨ¢ÄAeXgXeÌáºÌâÎlªå«¢ûª\ãöqƵÄdvÅ é±Æ𦵽_¶Å·B

§eïêÌëÉÍAܳ©Ìøªc
éØNÌåAíÈãƵÄ̾颢𴶴éð¦Ü¹ñŵ½B

sì³öƪÁ¿è¬è·ééØæ¶
¨Ü¯
wïêÍúAè·ò{ݪ¹Ý³êĨèAwïÌÔÉ·òÆ¢¤æÒòÈÔðß²µÜµ½B
j¯mA·òÉ©èȪç«Ì±ÆÈÇäÁèb·ÔࢢŷËB

wïÌúÍÙlÙÉÏõÖ
(©{ÌÙÉÄANHKÌAhu×ÁÒñ³ñvÌBeÉgíêÄ¢½çµ¢)

ÈñÆAÙlÙVersionÌX^oð©II
ਵáê

ÜÆß
AhW[wïÍgj«ÈwhÉFocusµ½wïÅAj«@\â¶B»µÄO§BàA¸àÉ¢½éÜÅL¡fIÈc_ªÉðí³êĢܷB
RpNgÈwïÅ éªä¦Ì[¢c_ÍñíÉ×ÉÈèÜ·B
áèÌF³ñà¥ñêÉNQÁµÜµå¤B
üßÄAR{æ¶A wp§ãÜ óܨßÅƤ²´¢Ü·I
¶ÓF|à@MP
AUA in San Francisco, May 18-21, 2018

®a@åAíÈåCãõAçtåwåw@3NÚÌäºÅ·B
Fl¢ÂàåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B±ÌxAâ{Mêæ¶ÆAUA2018ÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
¡NxÌAUAÍSan FranciscoÅÌJÃÆÈèܵ½B
òs@Ũæ»10ÔAú{ÆÌ·Í16ÔAAJ¼CÝÉÊu·éSan FranciscoÉ·§¿Üµ½B

ssSÌzeÍ1~ªêÅ èASan Franciscǫ¿Ì³ÉÍÆÄàÁ«Üµ½ªAäXÍAir BNBÉÄ11~ȺÌRoom shareÅZ§ÉúöðÆàÉß²µÄQèܵ½B
JbƵ½·gÈCóðzµÄ¨èܵ½ªASan FranciscoÍ_ª½C·à5Ìú{Æä×éÆñíɦ¢óÛŵ½B

çtåÖA©çÍ4è(VX`ÎÖA1èAO§BàÖA3è)Ìo^ÆÈèܵ½B
©ªÍz¡ÃfãÌeXgXelÌRecoveryÉÖ·éèŵ½ªAµêÈ¢pêàNative speakerÅ éâ{æ¶Ì²w±Éæè²ÈH\·é±ÆªÅ«Üµ½B

eXgXeÉÖ·é\ãAäX̤ÉÙíÉ»¡ð¦µ½lÉÙíÉÜêéÆ¢¤à¶µÜµ½B
ÅIIÉͨ¢É³ê½ÜÜAÓCµ½´¶ÆÈèܵ½B
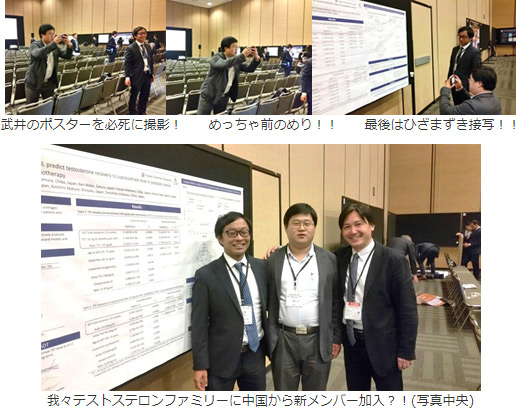
AUAÌèÌð¦1-2Å·ªA¡ãçtåàÆÑðLη½ßÉÍAUAÌèðⷱƪKv¾ÆÀ´µÜµ½B

cûæ¶()|X^[ÜóÜã@cð©¹é¼Ã®s§åwo[
³ÄA¢bͱÌÓÜÅƵAAUAüÓÌ®à²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
CaliforniaÅÅàL¼È§öÅ éYosemiteÜżîs§å̪cæ¶Æ²ê³¹Ä¢½¾«Üµ½B
YosemiteÍ¢EâYÉào^³êĨèA1000mÉàyÔÔ¼âÌâÇA»±ð¬ê¿é½ÌåÈêA¢EêÌϪå«ÈéƾíêéWCAgZRCAÌØÆ¢Á½YåÈ©RÆ»ÌÜÜGê¦é£ÍÉ Óê½öŵ½B
èÌÜÜÌu©RvðÛ·é½ßÉRΪN«ÄàÁι¸Éúu·éÆ¢¤OêÔèÉÍÕðó¯Üµ½B

¼Ã®s§åªcæ¶(Ê^¶)ÆYosemiteÉÄ
±Ì Æo[K[LOÅÎÌM¢u`ð}c[}Å·©¹Ä¢½¾«Üµ½B
úÌoOÉN«ðµÄAl¶ÌT[tBàyµÞ±ÆªÅ«Üµ½B
CaliforniaÍ»Ìsurf cultureª½ÌT[t@[𣹵ĢéêÅà èܵ½B
¼Ã®s§åwÌæ¶ûÆT[t`[ð¬·é±ÆªÅ«½ÌàA±Ì·Ìå«ÈûnÆÈèܵ½B


AUAÅÍÅVÌm©ÉGêé±ÆªÅ«é¾¯ÅÈA¼åwÌæ¶ûÆð¬ð·é½Ì@ïª èAñíÉ¢hðó¯é±ÆªÅ«éÌà£Íŵ½B
{wïÌQÁÉ ½èAâ{æ¶ðͶßÖAÌæ¶ûA®a@ÌX^btÌFlAçtåwåAíÈãÇÌFlÉÍråÈx𢽾«½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
±ÌêðØèÄúäçð\µã°Ü·B
¡ñÌo±ð©µAuÇ¢åAíÈãvðÚwµÄu¢¢gvÉæÁÄ¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
±êðÇñÅ¢éáèÌæ¶ûà¥ñAUAQÁðÚWɵÄàç¦éÆðµv¢Ü·B
ÅãÉAâ{æ¶ÉAêÄsÁÄ¢½¾¢½APacificaÌC¢ARÌãÌÆñÅàȵÍCÌ¢¢IVÈXgÅÌêŨÊêÅ·B
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B

PacificaÌ[zð]ÞIVÈXgÉÄ@[zª¾ñ¾ãÌv¢oÌê
¶ÓFä@º
2018.5.14 éÊãÈåwQmãw¤Z^[©w
åAíÈ@¡ºÅ·B
¡ñA¯åÌìæ¶Ac涪¤ðµÄ¢ééÊãÈåwQmãw¤Z^[ÖsÁÄÜ¢èܵ½ÌŲñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
2lÍéÊãÈåwQmãw¤Z^[â`qîñ§äå äãæ¶ÌàÆÅA»ÝåAí««îá̤ðsÁĢܷB

¤ºàðÄàµÄ¢½¾«Aäãæ¶Ax]æ¶Ì²úÓÅìæ¶âcæ¶ÌßµñƵĤàeÉ«fBXJbVàūܵ½B
(·¢Ü¹ñAÊ^BèYêܵ½B)
»ÌãAìzÍEiMªL¼Æ¢¤±ÆÅAåÆ¢¤¨XÖB
x¢ÔÉà©©í縨æêlŵ½B
ìæ¶Acæ¶A¥ñæ£Áľ³¢B
µÄ¢Ü·B

¤È¬¨¢µ©Á½Å·II
¶ÓF¡º@LC
2018/2/24`25@äpåAíÈwï@2ÌäpîáO[v(TUOA)Ìï
2018N224`25úAäpåAíÈwï@2ÌäpîáO[v(TUOA)ÌïÉQÁ¢½µÜµ½B
äp̬(ä)̶çÎ@http://www.sltung.com.tw/ÅJóêܵ½B
ÅßA5ñÙÇÄñÅ¢½¾«A¤êµ¢½ÊAá±wܽAÅ¢¢ÌHxÆ^âÉv¢ÈªçQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
OúÍAcåw@¬â ÐY æ¶ÌñíÉ·µÈuïÌ ÆA©725ªÌHcÌòs@Å°¢Úð±·èȪçäkÖü©¢Üµ½B

½Æ©Hcó`Ö(HDðYêåwÖ©ßÁÄ©ç) æmçÈ¢êÖÌêlÌuÍA³¼Ù£µÜ·B
äk©çAäÆ¢¤^ñÌss(ñÔÚÌlûÉÈÁ½Î©è)ÜÅA¼Ã®©çͱѱÜê½Æ¢¤ú{ÌV²ü(KChÌl©ç̤m¯)ÉÌÁÄ45ªÙÇÅ
µÜµ½B

KChªAñíɾéAXChð¼·Ôàн·çbµ©¯Âïé̪óÛIŵ½B
¨»çäplÉÍAKYÈñÄ¢¤¾tÍAKvÈ¢ÆmMµÜµ½B
äw©çÔÅA³çÉ40ªÙÇÅA½´ÉËR»Ñ¦§Â22KÄÌåÈa@(1300°)É
B

ãÃc[YÉÍðüêÄ¢ÄCO(}[VAA^CÈÇ)©çàòRéæ¤Å·B
úÍAoN[o[©ç½nÌJi_l³ÒðÐ¾«Üµ½B
ÊíÍA_r`ñäÅcÜÆ¢ÁĢܵ½(°é×µAA)B

ÖWÒÉo}¦Ä¢½¾«AwïÅÍA30ªO§BàÖAÆ15ªVX`AÇÖA(åÃÒÉæèvç¢ÉÄ)Ì\ð³¹Ä¢½¾«Üµ½B

µÒ¢½¾¢½A¢æ¶BÆ@äpÌûÍewðã°é̪ÊáÌæ¤Å·B
¢æ¶ÍAª
OúÉLive SurgeryÌRALPðñsÈÁ½Æ̱Æŵ½B
IíéÆAOñÌ¡ºæ¶ÆQÁµ½wï¯lA¨àÞëÉJIPªnÜèA´Kv̪ÌɾYÈÇA ÜèmçÈ¢ú{ÌÌðÜßÄAú{êÆêÌâÈHÍàèÅêÉ̢ܵ½B

Jermyæ¶ÍA`ÅASingle PortÌ_r`ÌÕ°¤(Phase I)ðIntuitive SurgicalƤ¯ÅsÈÁÄ¢éÆ̱Æŵ½B
ã Av[`ÌO§BSEâAäNã÷SEÈÇB
åAíÈÉÍAéÆÊÉ7lÌ誢ÄAÏR¸Ì\¿©çA¡±S(CRO)AÞì¬ÈÇðC¹Ä¢éÆ̱Æŵ½B
»ÌªAOgàÌçÈ¢ÆÆ¢ÁĢܵ½B
§eïÌãÍAésÉÂêÄ¢ÁÄ¢½¾«AI®Ý½¢ÈƱëÅDèâA´Þ¿s¾ÈsvcÈHרð½HµÜµ½B
¡ñAÎðsÈÁÄ¢éäpÌæ¶ðÐ¾«A³çÉAêÉQÁ³êÄ¢½`ÌJermyæ¶ðÜßÄAVX`AÇÌÛ¤¯¤ðÔ±ÆÉÈèܵ½B
½Ìæ¶ûª¡Nú{ÅJóêéUAAðñíÉyµÝɵĢé±ÆªóÛIŵ½B
¡ñAJIPâésÈÇA¢ÄÆÍÙÈéAAWAlÆ©ÌeµÝâ·³âg©³ð´¶é¬³È·ÆÈèܵ½B

ÅãÉA¨ülÅú{lVX`AdzÒ100lÌQmf[^ªµ¢Üµ½B
¡ãAÛ¤¯¤É²¦Í¢½¾\èÌwäpAØA^CA}[VAA`(Cystinuria Dream TeamGèɼ¯ܵ½)x©çÌAWAEVX`AÇÌf[^Æú{Ìf[^ðµÄ_¶»µ½¢Æv¢Ü·B
±ÌêðØèÄA±êÜÅVX`³ÒÌÐîɲ¦Í¢½¾«Üµ½Aæ¶ûÉSæèäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
2018/2/23 Young Urologist Investigator Seminar @¬ze~}[
¶ÓFÄc(Z~i[)Aئ(îñð·ïEñï)
223úÉYoung Urologist Investigator SeminarªJóêܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
±ÌïÍåÉáèãtðÎÛƵĨèAOÉÖWÌûXÖJÃÌ|ðCtHµÄ¨èÜ·ªA30loveràÌåªEµAJÃOÉå÷ØÆÈéÔÆÈèܵ½B

çt§ªñZ^[[òæ¶ÉæéuÌÍlBÙÚÈÅ Á½B
O§Bà¡ÃÉ¢ÄAçt§ªñZ^[Ì[òæ¶ÆAcä`måw̬âæ¶É²u¸«Üµ½B
zeÌ꺪®SÉlÅÜèA\ÌãÍ¿âªòÑð¢AÆÄàÈïÆÈèܵ½B

ïI¹ãÌWÊ^
ø«±¢Äîñð·ïà巵ŵ½B

ïêA¿SĪ¨ÅMÒÍÙ£µÄµÜ¢Üµ½
uÌàeͽﵢªà Á½æ¤Å·ªAåAíÈwÌC[W𵾯Åà´¶æê½æ¤Å·B
îñð·ïÅÍȨ¾ÓÌ·èãªèÅADZÌe[uÅàïbªeñŢܵ½(jL³ÍÛßܹñªÎ)B
2ïÉཱིñ̲QÁ𢽾«A40¼Å\ñµ½Xª¬ã¤¬ã¤lßÉÈÁĵܢܵ½B
»µÄÈñÆA¬âæ¶Éà¢çµÄ¸«Üµ½I

ÅãÍA¬âæ¶É²¥A𢽾«Üµ½B
uAîñð·ïA2ï·×Äå·µÌéŵ½B
æöàGêܵ½ªAuÍñíÉxÅAJf~bNÈàÌÅAáèÌãtÉÍ(MÒÉàÅ·ªÎ)µïµ¢ªà Á½Æv¢Ü·B
µ©µAåAíÈÆ¢¤àeðC[WµÉ¢fÃÈÌêØð´¶éÉÍæÒòÅAå«È´Áðó¯½ûརÌÅÍȢŵ天B
ܽA¨ðÌêÅÍåAíĘ̀¢âeµÝâ·³àöÅ«½ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B
½¿ÉÆÁÄàAáèÌæ¶ûÆð¬Å«éñíÉMdÈV[ÆÈèܵ½B
yµÝȪçתūéåAíÈÍAüßÄžÈÆ´¶Üµ½B
ÅãÉÈèܵ½ªA²½Z̲u¸«Üµ½[àVæ¶A¬âæ¶A{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFÄc(O¼)AyG(ã¼)
2018/2/2@FDPC in ú{´
A±eÉÈÁĵܢܵ½Î@åAíÈüÇêNÚÌO_Å·B
¡ñÍFDPC(free discussion of prostate cancer)ÌïÉâ{æ¶A|àæ¶ÆQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
áNÍêN¶ªQÁ·é±ÆÍ ÜèÈ¢»¤ÅAÆÄàÙ£µÄQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
¡ñÍA»ÝàÁÆàÓ©ªª©êéHO§BàÌ¡ÃûjƵÄA
①AWSð©é׫©A©È¢×«©H
②AAðÖÃ@ðsȤ׫©AsÈíȢ׫©H
ñÂ̧êÅPros and ConsƵÄuµADiscussion·ééæŵ½B
Pros¤ªçtåwACons¤ªbãåƵÄ\µÜµ½B
¼ÉAàZ^[a@Ak¢åwAãåAqãÈåwA¹HÁa@A¡ls§åwÌæ¶ûªQÁ³êܵ½B
\Ô10ªADiscussion 20ªÆ¢¤Ôzª©çàA@½Éc_ðdµÄ¢é©»èÜ·B
©ªª³µ¢ÆvÁÄ¢½¡Ã@ª{Ýâ液ÆÉ¢ë¢ëÈl¦ûª èܵ½B
c_ðʵÄmê½±ÆÍA{Å׷龯ÅÍí©çÈ¢±Æ¾Á½ÌÅñíÉMdÈo±ÉÈèܵ½B
íÉL¢ìÅúX×µÈÄÍÈçȢƴ¶½êúŵ½B

O§BàzÃ@ɨ¢ÄAWSmFÌKv«É¢Ä^¬¤É§ÁÄ\³¹Ä¢½¾«Üµ½B
bãåÌXæ¶(çtåw²ªAAWSð©È¢¤ÉÄ\³êܵ½)B

|àæ¶ÍuO§BàzÃ@ɨ¢Ävintage hormoneÜÌKv«É¢Ävð\³êܵ½B
QÁª¼OÉÜÁ½±Æà èAõs«ªÛßÈ¢´Í èܵ½ªAXChÌì¬â_¶Ìõðè`Áľ³Á½ªæ¶Æ|àæ¶A¡ñQÁ³¹Ä¢½¾«AéxÜÅõðè`Áľ³Á½â{æ¶É±ÌêðØèĨçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B

¶ÓFO_@÷º
2018/1/27@åAíȯåwpWï(TKPK[fVeBçt)
ãú¤Cã1NÚÌO_Æ\µÜ·B
127úÉJóêܵ½¯åïÉ¢IJñ¢½µÜ·B
¡NÍáNÉärµÄ½¢32Ìîb¤âÕ°¤Ì\ª èܵ½B
ÁÉ2018NxfÃñVüèÅÛ¯KªgåÆÈé{bgxºèpÉ¢ÄÍÈc_ªÈ³êܵ½B
¯åïwp§ãÇÍçtåw©çªæ¶ÆR{涪óܳêܵ½B
íÉL¢ìÅúX×µÈÄÍÈçȢƴ¶½êúŵ½B

´eXgXeláºÍzÃ@ɨ¯éú{lis«O§Bà³ÒÌ\ãð\ª·éBR{ «uæ¶

}CNRNAOìÌpre-miR-150ÉR·émiR150-5p¨æÑmiR150-3pÍO§Bàɨ¢Äà}§^}CNRNAƵÄ@\·éBª@Äæ¶
I¹ãÍîñð·ïÉÄeX·èãªÁĨèܵ½B
iGêé±ÆªÈ¢¤âoüæÌa@¶ÈÇÆÄ໡[¢àeŵ½B
úXÌÕ°ðæ£éÌÍà¿ëñÅ·ªAªæ¶âR{æ¶Ìæ¤É·Îçµ¢¤ðc¹éæ¤Éúí¶É¨¢ÄTSðYêÈ¢æ¤ÉµÈ¯êÎÈçȢƴ¶½êúŵ½B
¶ÓFO_@÷º
2017/12/25@ÅV|[g@϶ïFs{a@
fÃutÌâ{Å·B
¡ñAÈÅå÷éw¨ïR«O§BàÉηéRadium223ÆFlutamideÌOü«ãtå±±x̲¦ÍÌäçAÀÑÉAà¾ðËÄ϶ïFs{a@ðKêܵ½ÌÅ|[g³¹Ä¢½¾«Ü·B
ñíÉL¼ÈÖAa@Å·ªAÀÍA©gßÄÌKâÆÈèÜ·B
w©çAV²üÉæèp\RðL°Ä[ð`FbNµÄ¢é¤¿É(êÔã)Fs{wÉ
µÜµ½B
»±©çoXÉÌè10ªöxÉÄa@É
B
[ûÌ6É
µ½±Æà èAÃÅÌɻѦ½Â¨éÌæ¤È¶Ý´Ì éOÏɳ|³êܵ½B

a@ÌÉüéÆAVäªñíÉAXÌæ¤ÈƾâX^[obNXª éÈÇÝõª®ÁÄ¢éóÛB

³ÊºÖÉüÁ½óÛÍA·û`̨©Æv¢«âAÀÍA³û`Ì\¢ðµÄ¨èALºÅ³ÊÆãÊðÝÄàÊĵȱLºªLªÁĢܷB
Ç꾯AêLÊÏðLµÄ¢éÌŵ天H
çt§Åà±ÌTCYÌa@ͶݵȢƨà¢Üµ½B


Á¢½±ÆÉAuz[àÌÏqȪA®®ÅAû[·éÆAlp¢z[ÉàÈ黤ŷB
çtåãwÉà±ÌTCYÌz[ÍÈ¢ÌÅÍAAêÊa@Ìgð´¦Ä¢éÌÅÍAA
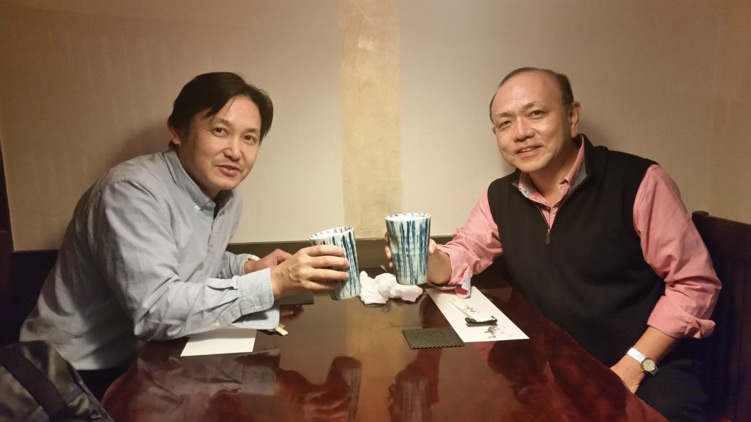
»ÌãAËç³æ¶ÆHïÉÄAFXȨbðf¤@ï𢽾«Üµ½B
ÅãÉA¡ñAßÄ϶ïFs{a@Öfí¹Ä¢½¾«Üµ½B
Fs{Ìja@¾¯ ÁÄAtA[ÊÏAuïêÈÇA\zðy©É´¦éKÍÌa@ŵ½B
PÈéÕ°a@Ìgð´¦ÄAåwÅÍH Æöo·éæ¤È«ŵ½B
Ëç³æ¶Ì¸â©È¨Ì ÉàAÕ°ÌÅOüÅÈاÌãÃðSÁÄ¢éÙ£´É´¶Üµ½B
NÉÍA_r`Xiªü黤ÅA¡ã³çÉAèpª¦é±Æªzè³ê黤ŷB
Ëç³æ¶ÍA©ÂÄÌGUCÇÌTopÅà èÜ·B
ÁÉAwºÐA_r`ðÜß½èpðoo¤Cµ½¢IxÆl¦éåAíÈÌáè©çÌæ¶ÉÆÁÄAñíÉbÜê½Â«ÅÍÆv¢Üµ½B
Õ°ªñíÉZµ¢ÉàÖíç¸AVKARÜâARadium223ÆFlutamide̹p±ÈÇAÕ°¤ÅàåwÆíɦ͢½¾¢Ä¨èAËç³æ¶ðSƵ½åAíÈÌæ¶ûɱÌêðØèÄSæèäçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
2017/12/25@NX}Xï
1225úÉAsì³öåÃÌNX}XïªJ©êܵ½B
11Ìa¶úï¯lAâ{æ¶Aåw@¶Aé³ñAÀ±Zt³ñí¹½·åÈïÆÈèܵ½B
sìæ¶Ìu[NX}XIvÌ|¯ºðX^[gÉAÝÈÅkεȪçAü¡µ¨²Ñð¸«ANX}XP[Lหܵ½B
±ÌïÍsìæ¶Ì²úÓÉÄäõ¢½¾¢½àÌÅAsìqFT^N[X©çÌðµ¢NX}Xv[gÉÈèܵ½B
åAíÈÅÍX±Ìæ¤ÈïðõĢܷÌÅ»¡ éûͺÐãÇÜÅI
sì涢Âà·©¢SzèA èªÆ¤²´¢Ü·B
¡ãÆàäw±æ뵨è¢vµÜ·I

2017/11/27@sì³ö@a¶ï
fÃutÌâ{Å·B
1127úÉsì³öÌa¶ïªJ©êܵ½B
¡NÅ5HÎÉÈçêܵ½ªA÷ÌNîÍ¢¾É30ãðvªµÄ¢Ü·B
»ÌéÍâÍè«ñɯĢéXgEFCgÉæé¨Åµå¤©B
¡NÍâ{æ¶Aåw@¶Aé³ñí¹A¨15¼Ìåa¶ïÆÈèܵ½B
ܸÍÝÈŲÍñðH×Ȫçð¡ÌåAíÈîÉ¢ÄbÉÔð穹ܵ½B
±«ÜµÄâ{æ¶æèv[gÌ¡æÅ·B

Ê^Í èܹñªA{[yð¨nµµÜµ½B
sì³ö̼OàüÁĢܷB
åØÈTCÌÛÍ¥ñAgÁĺ³¢B
¨Ù𸢽ãÍAü¡µ¢P[LàFŸ«Üµ½B

30ãÆvíêéxÊÉÄA뤻ÌÎðêCÉãYíÉÁµA·èãªéê¯B
óû涾¯á±eVªá¢Åµå¤©B
ÅãÉSõÅp`B

sì³öA±ê©çàäw±ÌöAXµ¨è¢µÜ·I
¶ÓFâ{@Mê
2017/11/16`17@æ62ñú{¶BãwïwpuïEï
åw@¶ÌìjÅ·B
2017N1116ú`17úÉRû§ÌC¬bZºÖÅJóêܵ½æ62ñú{¶BãwïwpuïEïÉQÁvµÜµ½B
³º©çÍAsì³öA¬{y³öAìºutAÁ¡æ¶AìªQÁ¢½µÜµ½B
K¢ÉàAuTesticular function among testicular cancer survivors treated with cisplatin-based chemotherapy (Reproductive Medicine and Biology, 2016)vÅRMBDG_¶Üð¸«Üµ½ÌÅäñ\µã°Ü·B
Ìæ¤ÈáyÒª` éú{¶Bãwï©ç±Ìæ¤ÈÜ𸯽±ÆÍgÉ]éh_ƶ¶AüßܵÄú{¶Bãwï· Õ´ «æ¶Aåï·ðnßäR¸¸¢½æ¶ûÉ[´Ó\µã°Ü·B
÷ÍÅͲ´¢Ü·ªA¡ãÆàú{¶BãwïÌXÈéW̽ßÍðsµÄ¢«½¢Æ¶¶Ü·B
¡ñÌóÜÍsì³öðnßA¶BãÃA¸ªñ¡ÃðSÁıçê½æ¶ûAܽx¦Äê½ãyâX^btÌFl̨©°ÆSæè´Ó¢½µÄ¨èÜ·B
ÁÉ¡{æ¶ÉÍA¡ñIlÌÎÛÆÈÁ½_¶ì¬©ç§ØJɲw±¢½¾«Üµ½B
±Ìêð¨ØèµÜµÄA²w±¢½¾¢½æ¶ûÉúäç\µã°Ü·B
±ê©ç©ªàãÖâ¹édªÅ«é椳çÉw͵¤èsðÏñÅܢ轢ÆvÁĨèÜ·B
¡ãÆàäw±AäÚ£Ìöðæ뵨è¢\µã°Ü·B
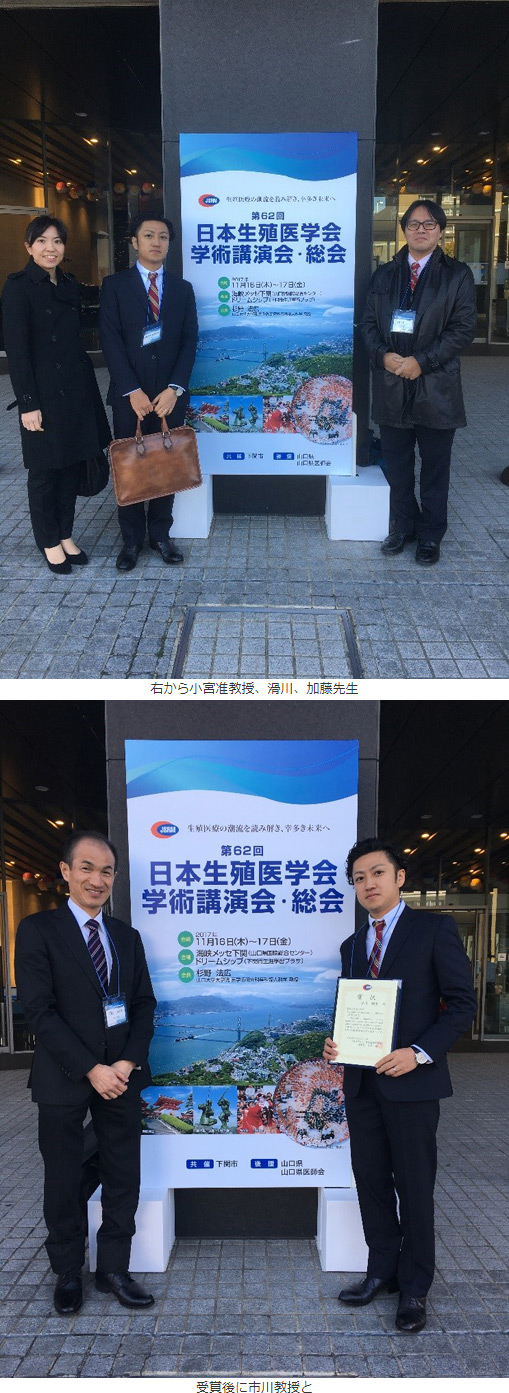
ºÖÖü©¤rARûåwÌ éFsÖ§¿ñèRûåwåAíÈÌR{`¾æ¶Aìäõvæ¶É¨ï¢µÄ«Üµ½B
¯wÌêJâyµ©Á½xĘ́bÈÇ𨷫·é±ÆªÅ«åÏyµ¢Ô𷲵ܵ½B
ܽ£ËàC̨¢µ¢îÆRų̂ðð·Á©è²yÉÈÁĵܢܵ½B
²ylŵ½B

¶ÓFì@j
2017/11/9`12@2017 International Uro-Oncological SymposiumÉQÁµÄ
çtåwÌ¡ºÅ·B
2017N11ÉäpÉÄJóê½2017 International Uro-Oncological Symposium ÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
äpAsÉ éChang Gung Memorial HospitalÅÌJÃŵ½B
AJÌ MD Anderson©ç(åAíÈãª4l@îáàÈãª1l)ÌQÁðßA{M©çÍA}gåw̼R³öArcæ¶A¼ÉàAChA}[VAAØÈÇ©ç½ÌãtªQÁ³êĢܵ½B
9úÍExpert meetingƵÄAfBi[ðH×ȪçExpertÌLectureð·X^C©çnÜèB

10úÍ©©çLive SurgeryB
MD Anderson©çÌåAíÈãª_EB`tªØpA_EB`äNã÷SEpðsÁĢܵ½B
äNã÷SEÍA oàÅñ°±Ç¢ÝðsÁĢܵ½B

»ÌãàßãÍAåAíîáSÊÌÅVÌm©ðÜß½Lectureª±«AéÍGala dinnerB
JIPðÌ¢©Èè·èãªèܵ½II

11úÉÍE-poster ZbVà èA\³¹Ä¢½¾«Üµ½B

e©ç̽Ì\ÌAK^ÉàA¡ºæ¶ªABest E-poster Awardðóܵܵ½B
óÜ®ÅÍAMD@AndersonÌChristopher Woodæ¶æèÜó𢽾«Üµ½B
¹Á©äpɽÌÅAµ¾¯äkÉÏõÖB

¬âÄïðH·II
©ÈèÌlCXŵ½ªA»êÙÇÒ±ÆàÈüêAÀĨ¢µ©Á½Å·B

³LO°ÖBêHŵ½
¡ñÌSymposiumÍMD Anderson Ìæ¶ûðäpÖµãÙµåAí««îáÉÖµÄALive SurgeryALectureADiscussionðs¤Æ¢¤àÌŵ½B
e[}àO§BàAtàAAHãçàA¸îáÆ·è¾³ñÅñíÉ×ÉÈèܵ½B
±êçðúífÃɶ©·×úXܽú{Åæ£è½¢Æv¢Ü·B
¶ÓF¡º@LC
2017NAhW[wïQÁ
2017N629ú©ç71úÜÅAȪwï±Çð±ßÄ¢éA
ú{AhW[wïæ36ñwpåï ÉQÁµÜµ½B
È©çÍAsì³öA¬{y³öA¡ºæ¶A³ñAâ{ªQÁµÜµ½B



ÜÆß
¡ñAq~ÉÄJóê½AhW[wïÉQÁ¢½µÜµ½BwïÍà¿ëñAðjÌ éXÀÝÉhðó¯Üµ½B
wï©ÌÍAsDAO§BìåÇAO§BàÆL¢ªìðÔ
µÄ¨èAú²ëÖíèª ÜèÈ¢ªìÌuÈÇñíÉ×ÉÈèܵ½B
üßÄAl¯w¶Ì³ñAwp§ãÜóܨßÅƤ²´¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
2017/4/20@¼ì¢À涪âûÜðóܵܵ½II
æ105ñú{åAíÈwïï()ÉÄöÜ®ªsíêܵ½B


2017/2/3@Ö¼ãåf-TULèp©w
çtåwåAíÈÎÇÌäºÅ·B
Fl¢ÂàåϨ¢bÉÈÁĨèÜ·B
±ÌxAâ{Mêæ¶ÆߪÌúÉåãÜÅo£³¹Ä¢½¾«AÖ¼ãÈåwãÃZ^[ÌAHÎèpuf-TULvÌ©wÉsÁÄQèܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
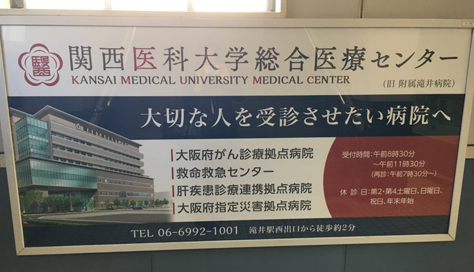
Ö¼ãÈåwãÃZ^[ÍAVåãw©çdÔÅ20ªö̧nÅΡÃZ^[ƵÄAZ^[·Å éäãMºæ¶ðSÉNÔ200áð´¦éÎèpâ½ÌÕ°¤âwï®É¨ÍIÉæègñÅ¢éÖ¼ãåÌÖAa@Å·B
2016NÉ£ÅJóê½æ13ñÛAHÎÇwï(çtåw³ösìqFï·Aàòãå³ö{àVl¤¯ï·)Aæ26ñú{AHÎÇwï(é¿ÎãÃZ^[³ö[JKjï·)ɱ«Aæ28ñAHÎÇwïÍ2018N8ÉåãÉÄÖ¼ãÈåw¼cöu³öªï·ÆÈèJóêé±ÆÆÈÁĨèÜ·B

ÄàÅÍqg^{bgybp[uÖãñHvª¨o}¦
¶©çäAäãæ¶Aâ{æ¶
Ö¼ãåÌäãMºæ¶ÉÍA±êÜÅÉÎÖAÌwïÉÄnYIZ~i[â»Ì¼ÌZbVŲw±¢½¾¢Ä¨èܵ½ªA¡ñÍâ{æ¶Ì`èÅèp©wð³¹Ä¢½¾¯é^ÑÆÈèܵ½B
¡ãÌAHÎÇwïð·èã°éÓ¡ÅàA¡ñÌæ¤Èð¬ðs¤±ÆÍåÏÓ`ª é©ÆvíêÜ·B
±Ìæ¤È@ïð^¦Ä¢½¾¢½¼c³öAäãæ¶Asì³öAâ{æ¶É´Ó\µã°Ü·B

2016NÉVa@ƵÄj
[A³ê½Ö¼ãåãÃZ^[èpº
LXƵ½Xy[XÉߢIÈfUC
³ÄAÀÛÌ©wàeÅ·ªAäãæ¶Ììzµ½èpZpÌf°çµ³ÉÕA´®ÌA±Åµ½B
ÂXÌÇáÉηéȧȡÃíª©çA[`[Nðf±È·½ßÌO굽«Ýè(Nàªî{ÝèðĻūéæ¤Aèpäâ§ÌA[ɳÌî{Ýèð}[LO·éÆ¢Á½Hvª½)ApìÌWJÌf³A³m«AèpºX^bt̳çXÉÄAÚIÆ·éÎÉB·éÜÅ̳ʪêØ èܹñŵ½B

äãæ¶(Ê^¶)Ììzµ½èpZpÉBt¯Ìâ{æ¶
äãæ¶ÌèÌãÅxÁÄ¢é(Ê^)
ÎÌjÓAÎÉÖµÄàî{IÉSÄpÒêlÅs¤X^CÅA»Ìf³âÍÍÜéÅhS{[Ìí¬V[ðÝÄ¢éæ¤Åµ½B
2pð´¦éªTSóÎð1Ô«ç¸ÅpÒPÆÌf-TULÉĮӵ½ÌðÚ̽èɵ½Í±ÌÚð^¤ÙÇŵ½B
±êÜÅÌo±âµÍCɽÆÈéÌÅÍÈA_IAqÏIf[^Éîâ½Õ°I¢ðàÆÉèpèZðWJµÄ¢é±Æªäãæ¶Ììzµ½èpZpðx¦Ä¢éÆvíêܵ½B
(ïÌIÈàeͱ±ÅÍ««êÈ¢ÌÅA»¡Ì éûͺð©¯Äº³¢B)

èpI¹ãͧeïɨU¢¢½¾«Aü¡µ¢¿ÆÆàÉäãæ¶Æerð[ßé±ÆªÅ«Üµ½B
èpèZÉÖ·éàe¾¯ÅÈAäãæ¶ÌÕ°¤Éηél¦ûâÀHû@ÈÇAñíÉRAÈàeÜÅc_·é±ÆªoAåÏLÓ`ÈÔÆÈèܵ½B
ÁÆ¢¤ÔÉÔÍ߬A¡ñÌo±ð¡ãÌÕ°¨æѤɶ©µÄ¢«½¢ÆAâ{æ¶Æ»±³ßâçÊ«æèÅçtÖÌV²üÉæèÝܵ½B
¡ãà±Ìæ¤Èð¬ð±¯Ä¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
¶ÓFä@º
åóÌï(59N²Ìï)
F³Ü¨É¨ÚÉ©©èÜ·B
¡NxüÇÌçtåwåAíÈãú¤C1NÚÌâV¡S½Å·B
é86úA7úÉ ê§ÅJóêܵ½åóÌï(59N²Ìï)ÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
±ÌïÍAçtåwÌsì³öðͶßƵ½Aºa59N²ÆÌåAíȳöÌæ¶ûÉæÁÄ«µ½wïÅ èA¡NÅ7ñÚÉÈèÜ·B
¡NÍ êãÈåwÌÍà¾G³öåÃÌàÆA ê§ÌúiÎÅJóêܵ½B
çtåw©çÍAsì³öA¬{æ¶Az{æ¶Aäæ¶ÆAâV¡Ì5lÅQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ïêÍ ê§ðã\·éLåÈúiÎð]ÞACNr
[ª£ÍÌA»Ì¼àuúiÎzevŵ½B
ÌSÌïêÅÌÊ^ªÈ³OÌÉÝÅͲ´¢Ü·ªACi ÓêéãiÈïêÅAgàSàø«÷Üév¢Å èܵ½B

úÚÌ[û©çÍeåw©çêè¸ÂÌ\ª èAçtåw©çÍâV¡ªAuO§Bàɨ¯éàªåÃ@~ãÌTestosterone RecoveryÌ¢vÆ¢¤èÅAwa¨Rg[ÇDÈ·úADTÇáɨ¢ÄAADT~àêÂÌ¡ÃIðÆÈè¤éÂ\«xÉ¢Ä\³¹Ä¢½¾«Üµ½B
wï\ÅÌo±ÉRµ¢ÉÆÁÄAeåwÌæ¶ûæèAÈ¿â𢽾«AåÏhðó¯Üµ½B
»ÌãͯïêŧeïªsíêA¡NxçtÌ£bZÛïcêÉÄJóê½LO·×«ú{ÌuÛÎÇwïvÅ èÜ·Aæ13ñÛAHÎÇwï(International Symposium on Urolithiasis; ISU)ð¤Ãµ½àòãÈåwåAíÈÌæ¶ûÆAn³¨··ßÌ¿ª¡í¦é¨XÉÄerð[ßA êÌéÍlXÆX¯Ä¢«Üµ½B

àòãÈåwÌæ¶ûÆÌêBñíÉC³Èæ¶ûÅ·èãªèܵ½I
2úÚÍ êãÈåwåÃÌoXcA[ªJóêܵ½B
ܸßÉKê½ÌÍA©ÌL¼ÈÅÉæèJ©ê½¢E¶»âYuäbRïvB
½ÀãÉJ©ê½ú{Vä@Ì{R@Å é±ÌÍAµÈµÍCY¤RÌÉÐÁ»èÆÈñŨèܵ½B
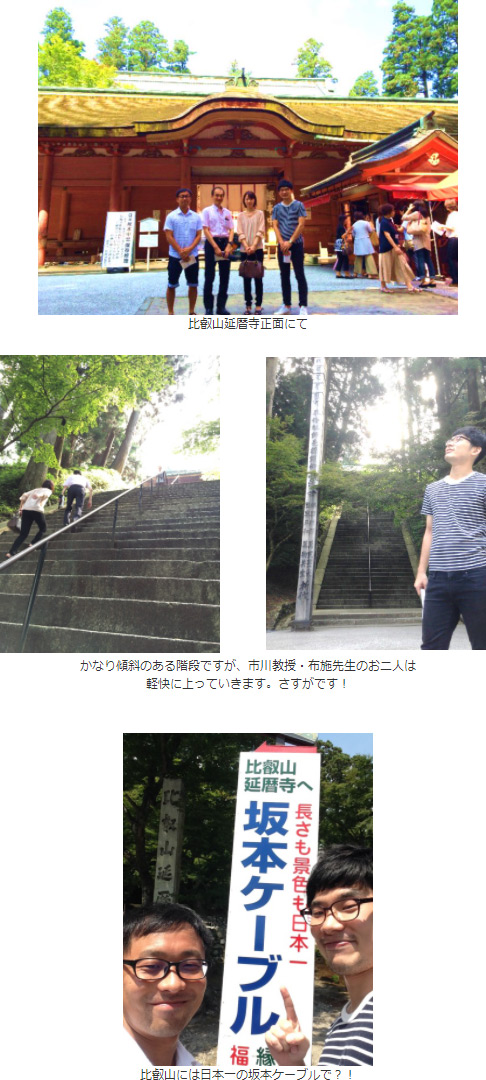
±¢ÄÍA±¿çàܽðjÌ éuúgåÐvB
»ÌN¹ÍÈñÆ2100NOÉàkéÆ̨bµB
ï¯lA±±à½¾ÈçÊp[X|bgÅ èܵ½B
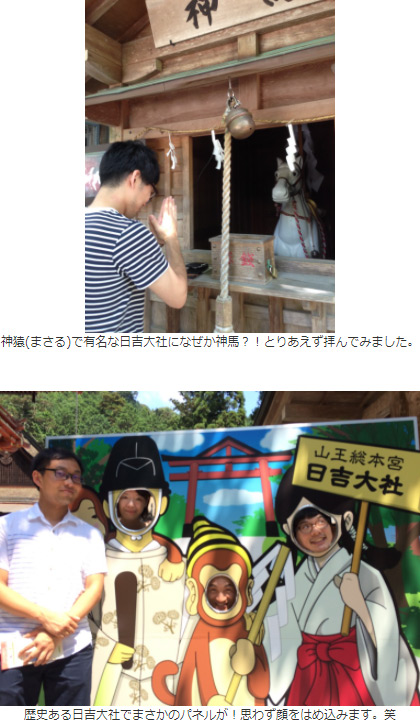
ÅIX|bgÍA{½ÌúiÎðSÍÅyßéuVDÅÌN[Yvŵ½B
»Ì¼àuMICHIGANv(úiÎÈÌÉEEEH)B
ÜÔµ¢ç¢Ìú·µÉbÜê½±ÌúÍAâDÌN[Yúaŵ½B
ñ1Ô30ªÌ±Ì½ÑÍäÁ½èƵĨèADàżåw̽Ìæ¶ûÆð¬·é±ÆªÅ«Üµ½B
1úÚÌ\A2úÚÌÏõÆA êð¶ªÉiµ½2úÔðß²µAAHÉ«ܵ½B
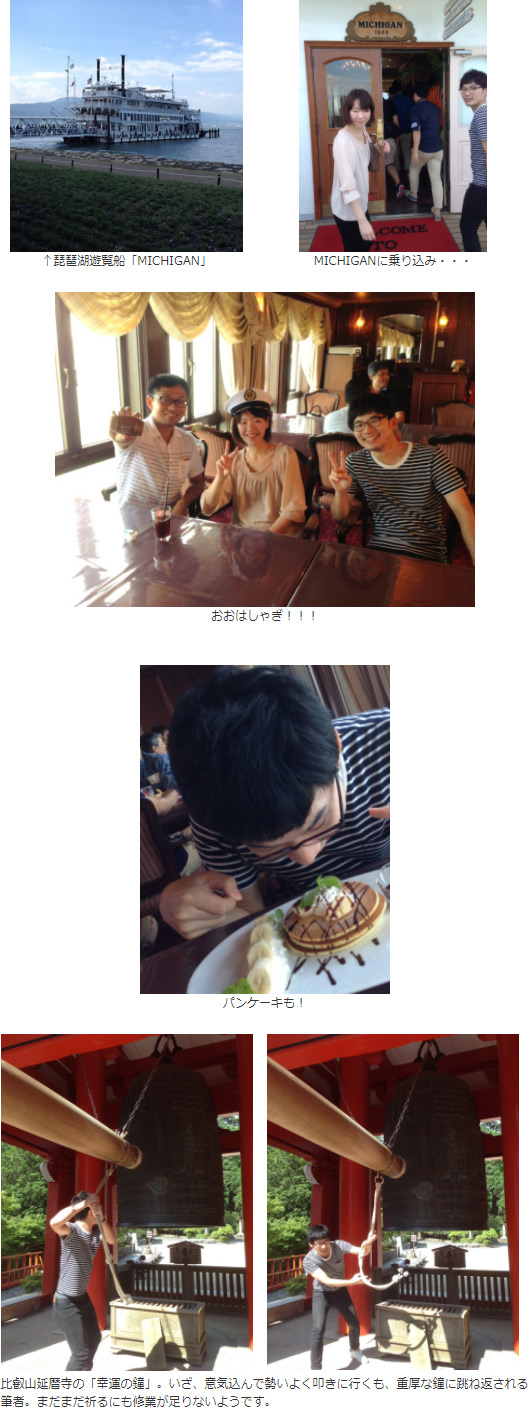
ÜÆß
¡ñåóÌïÉQÁ³¹Ä¢½¾«A¼åw̽Ìæ¶ûÆwïEÏõðʵÄð¬·é±ÆªÅ«Üµ½B
Z§È2úÔŽ³ñÌhðó¯A»µÄßÄÌ ê§ðiÅ«½±ÆAñíÉK¹Év¢Ü·B
NÍàòÅÌJê\è³êÄ¢éÆ̱ÆÅ·B
NQÁåwª¦Ä¨èA¡ãÜ·Ü·ÌWðèÁĨèÜ·B
¶ÓFâV¡@S½
2016/11/24@sìæ¶@¨a¶úï
sìæ¶Öú Ì´ÓðßÄA³³â©ÅÍ èÜ·ªãÇÉĨa¶úïðJó¹Ä¸«Üµ½B

æ13ñÛAHÎÇwïæ26ñú{AHÎÇwï
åAíÈã4NÚÉÈèܵ½çtåwåAíÈãõÌäºÅ·B
ÖWÒÌFlA½fæ訢bÉÈÁĨèÜ·B
´eÌ쬪¾¢ÔxÈÁĵܢ°kÅ·ªA2016N719ú`22úÉ£bZÛïcêÉÄJóê½æ13ñÛAHÎÇwï(International Symposium on Urolithiasis; ISU)Aæ26ñú{AHÎÇwï(Japanese Society on Urolithiasis Research; JSUR)ÉQÁµÜµ½ÌŲñ𢽵ܷB

ISUÍ1968NÉpÅæ1ñªJóêܵ½ªAú{ÅÌJÃÍ¡ñªßÄÆÈèܵ½B
LO·×«ú{ÌISUÍAäççtåwåAíÈsìqF³öÆàòãåÌ{àVl³öƤ¯ï·ÅÌJÃÆÈèܵ½B
ܽAJSURÍéåw¿ÎãÃZ^[[JKj³öªï·ÆÈèAçtåw̯åÅISUAJSURÌï·ðS¤Æ¢¤ñíɼ_ éwïÆÈèܵ½B

ISUÅÍA½ÌCO̼Èæ¶ûª£ðKêAAHÎÉÖ·éîbÈçÑÉÕ°ÉÖ·é½Ìäu𢽾«åÏÈ·èãªèÆÈèܵ½B
JSURɨ¢ÄÍA10NÔèÌAHÎSuw²¸ÌñATULÌnYIZ~i[AAHÎÉÖ·é³çuAMµ½|X^[\ÈÇAISUÉàòçÈ¢·èãªèð©¹Üµ½B

©ªÍ|X^[\ÉÄATULɨ¯éAR[fBIÌúgpo±É«\³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ÓêñΩèÌlÌåÏÈMCÌïêÌA½Ìæ¶û©ç²¿â²wE𢽾«åÏLÓ`È\ð·é±ÆªÅ«Üµ½B
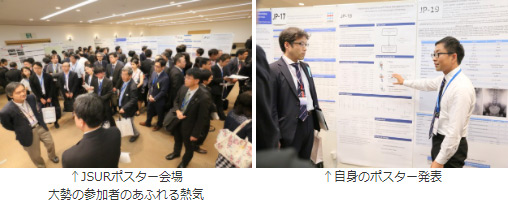
TULnYIZ~i[ÉàQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
¯åÌnê°ìæ¶(¬cÔ\a@)A¡{àæ¶(é¿ÎãÃZ^[)ÆàêÉASÌTULXyVXgÌæ¶û©çé`ÌZpð`ö¢½¾«Üµ½B
ÅVÌf-TULÌg[jOfÍAtÌÄz«Ú®âÎjÓÌjÓÐâoÉæéìÌÏ»ÜÅÀÉĻūéfÅ èA»Ì«\³ÉÁ±¢½µÜµ½B
ΡÃÉÍlXÈfoCXª èAÅÇÌèpðs¤½ßAíÉÅVÌm©ðwÑÀHµÄ¢±Æªdv¾ÆÀ´µÜµ½B

ÅIúÌéÉÍ}nb^zeÉÄGala DinnerªJóêܵ½B
â{æ¶Ì¬¨ÈpêÌiïÉCOÌzeÉ¢é©Ìæ¤ÈöoÉ×èAsì³öA[J³öÌf°çµ¢pêÌXs[`©ç£tÆÈèܵ½B
ü¡µ¢¿â¨ðAf°çµ¢tÆÆàÉA½Ì¯åÌæ¶ûâ¼åÌæ¶ûÆð¬ð·é±ÆªÅ«AÙ£àYêyµ¢Ôðß²·±ÆªÅ«Üµ½B
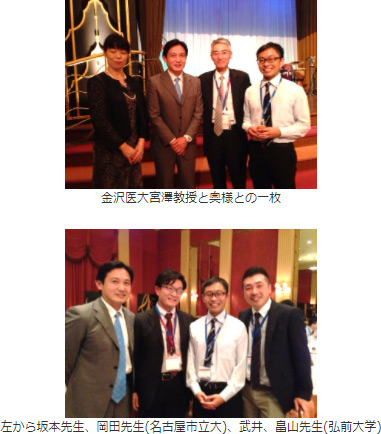
z[OhJÃÅÌISUAJSURÍsì³öA[J³öðͶßAçtåwåAíÈÖWÒÉÍåÏÈSà Á½©Æ¶¶Ü·ªA³É¬÷ðûßé±Æªoܵ½B
¡ãÌÎfèæѤÌWÉv£Å«êÎƶ¶Ü·B
¶ÓFä@º
2016/9/10`11@The Best of AUA in Japan 2016 vO
VãÇõÌcºM¾Å·B
¡ñ2016N910ú`11úÉ©¯Ä¨äêÅJóê½The Best of AUA in Japan 2016 vOÉQÁ·é@ï𢽾«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
±ÌïÍAUAÉÈ©È©QÁÅ«È¢áèåAíÈã̽ßÉ2010N©çnÜÁ½àÌÅANÌAUANïÌgsbNXð²µÄT}[µÄêéÆ¢¤åÏ èª½¢³çéæÅ·B
î{IÉú{ÌáèåAíÈãªeªìÌT}[ðSµA»êðäX®OÉñµÄ¢½¾¯éÌÅ·ªAAUA©çàv[^[ªµãÙ³êĨèAÄÌÅæ[ð¢æ¶ų̂bð¼Ú·±ÆàÅ«Ü·B
RȪç»ÌàeÍñíÉZ§ÅA¢E©çÌڷ׫ñðZÔÉÃkµÄ·±ÆªÅ«AÌæ¤ÈåAíÈ1NÚÌáyÒÉÆÁÄÍñíÉMdÈÔÅ èܵ½B
³¼Am¯âo±Ìs«©çðÅ«È¢ªà½X èܵ½ªAm¯ÖÌ~âÛIÈwïÖ̲êàø±ÆªÅ«AñíÉLÓ`ÈÔðß²·±ÆªÅ«Üµ½B
±Ìæ¤È@ïð^¦Ä¾³Á½±ÆɴӵĢܷB
±Ìo±ð³ÊÉ·é±ÆÈA¡ãÌ©ªÌ¬·É©µÄ¢¯êÎÆl¦Ä¨èÜ·B
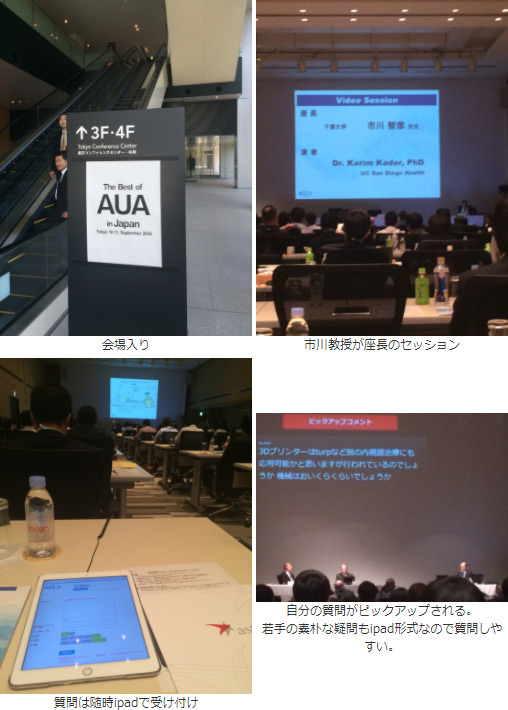
y§eï2ïz
¯åAXs[J[A¼åwÌæ¶ûÆMdÈÔðß²·±ÆªÅ«Üµ½B

¶ÓFcº@M¾
2016/7/15@æ2ñFDPC(Free Discussion on Prostate Cancer)ÉQÁµÄ
çtåwÌ¡ºÅ·B
2016N715úÉJóê½æ2ñFDPCÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½ÌŲñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
çtåw©çÍAâ{æ¶AR{æ¶Aäæ¶A»µÄªQÁµÜµ½B
±ÌïÍA»Ì¼ÌÊèO§BàÉεÄÌ©RÈe[}Å©RÈfBXJbVðs¤Æ¢¤ï|Å èA¡ñÍâ{涪uTSTÆO§BàÉ¢ÄvAªuCRPCÉηéVK¡ÃòÌÂ\«É¢ÄvA»µÄ¯åÅ è¹HÁÛa@ÌVÛ涪uRARPðß®ébèAePLNDâêawjAÉ¢Äv\³êܵ½B
̼Èåwâ{ÝÌæ¶ûªQÁ³êACyÉ»µÄÈc_ªsíêĨèܵ½B
»ÌãAWÜÁ½æ¶ûÆÌùÝïàsíêܵ½B
¯¶¢ãÌæ¶ûÆbªÅ«é@ïÅ èAæèe§ÉÈèÈbªÅ«éñíÉ[Àµ½Ôŵ½B
±Ìæ¤ÈïɽÌáèÌæ¶ûªQÁ³êA{ÝâåwÌ_ªðz¦Ä½©Vµ¢±ÆðMµÄ¢¯é«Á©¯ÉÈêÎÆv¢Ü·B

¶ÓF¡º@LC
2016/6/10@Urology Today & ½}ï
F³ñ±ñÉ¿ÍB
ªÆÔª½Áĵܢܵ½ªA610úÉsíê½AUrology TodayA»µÄ»êɱ½}ïÌlqð¨`¦µÜ·B
ܸAtâs¶»vUÅsíê½Urology Today 2016É¢IJñµÜ·B
±ÌïÉÍAãwÌw¶³ñâ¤CãÌæ¶ûÆAåAíÈãÈOÉཱིñÌûªQÁµÜ·B
çtåw©çÍz{æ¶Aºæ¶Aâ{涪²\³êܵ½B
ÁÊuÅÍAMåw²qa@åAíȳöÌéØ[xæ¶ÉæéAO§Bà¡ÃÌup to dateªÂÜÁ½¨bµð¢½¾«Üµ½B
¿^àÉsíêAåÏ×ÉÈéLÓ`ÈÔŵ½B
»Ìãsíê½½}ïÉÍäXåAíÈãÜßA¨50¼ð´¦éw¶³ñA¤CãÌæ¶ûÉQÁ¢½¾«A¡NÍßÅåKÍÌïÆÈèܵ½B
±¿çÅÍAàüÇé¾ð·éûà¢Üµ½II
±±NüÇÒÌÀèµÄ¢éåAíÈB
±Ì¨¢ÅNÌüÇÒÌÉàúÒªcçÞêúŵ½B

ÅãÉQÁµÄ꽤CãÌæ¶Aw¶³ñÆWÊ^B
¢Â©êɯé±ÆðyµÝɵĢܷI
2016/5/26`27@æ28ñú{àªåOÈwïï
åw@¶ÌìjÅ·B
2016N526ú`27úÉCz[Rn}ÅJóê½æ28ñú{àªåOÈwïïÉQÁvµÜµ½B
K¢ÉàAuClinical predictors of prolonged post-resection hypotension following laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. (Surgery 2016)vÅú{àªåOÈwャ28Nx¤§ãÜð¸«Üµ½ÌÅäñ\µã°Ü·B
Ìæ¤ÈáyÒª` éú{àªåOÈwï©ç±Ìæ¤ÈÜ𸯽±ÆÍgÉ]éh_ƶ¶AüßܵÄú{àªåOÈwï· ¼cöuæ¶Aåï·ð±ßçê½CåwãwOÈwn@åAíÈw@nqY³öðnßäR¸¸¢½æ¶ûÉ[´Ó\µã°Ü·B
÷ÍÅͲ´¢Ü·ªA¡ãÆàú{àªåOÈwïÌXÈéW̽ßÍðsµÄ¢«½¢Æ¶¶Ü·B
¡ñÌóÜÍsìqF³öðnßAtOÈåðSÁıçê½æ¶ûAܽx¦Äê½ãyâX^btÌFl̨©°ÆSæè´Ó¢½µÄ¨èÜ·B
Áɽ¬23NxÉ¡Üðóܳê½àCFMæ¶ÉÍA¡ñIlÌÎÛÆÈÁ½_¶ì¬©ç§ØJɲw±¢½¾«Üµ½B
±Ìêð¨ØèµÜµÄA²w±¢½¾¢½æ¶ûÉúäç\µã°Ü·B
±ê©ç©ªàãÖâ¹édªÅ«é椳çÉw͵¤èsðÏñÅܢ轢ÆvÁĨèÜ·B
¡ãÆàäw±AäÚ£Ìöðæ뵨è¢\µã°Ü·B

¶ÓFì@j
AUA annual meeting 2016@QÁñ
åw@¶ÌìjÅ·B
56ú©ç10úÌÔSan Diego Convention Center ÅJóê½AUA annual meeting 2016ÉQÁµÄ«Üµ½ÌŲñ¢½µÜ·B
¡ñÍú{åAíÈwï(JUA)ÆÄåAíÈwï(AUA)̯éæÅ éAUA/JUA@resident program©çÌhƵÄQÁ¢½µÜµ½B
±ÌvOÅÍAUAJÃúÔÌØÝïâregistration feeªx³ê龯ÅÈAÁÊÈo±ªÅ«Üµ½Ìű¿çà²Ðîµ½¢Æv¢Ü·B

¡ñÌïêÅ éSan Diego Convention CenterÅ·B
AUAÉQÁ·é½ÑÉ»ÌïêÌ嫳AmeetingÌKÍɳ|³êÜ·B¡ñÌïêÍCÉʵĨèAfbL©çÍJúIÈiFªLªèÜ·B
¡ñçtå©çÍ5¼Ì涪\¢½µÜµ½B
gbvob^[Í϶ïKuìa@Ì¡ºæ¶Å·B
MRIÉæéæffÌäNã÷àɨ¯édv«ð\³êܵ½B

(Ê^F\³ê顺æ¶)
y³ö̬{æ¶ÍA¹Je[e¯uÉηéfBJX^btÖ̳çÉ¢ÄÌ\Å·B

³Ìâ{æ¶Í o¾ºtEpÌ[jOJ[uÉ¢Ä\³êܵ½B

¬¨ÈpêÅÌdiscussionÅ·B
Üæ¶Í¨ïR«O§Bàɨ¯émicro RNAÉÖ·é\Å·B

tàɨ¯émicro RNAÉÖµÄ\³êéZæ¶B
±±©çresident programÉ¢IJñ¢½µÜ·B
¡ñJUA©çÍÆcåwÌOH涪h³êܵ½B
O¼ÌÚÊÍAUA resident bowlÅ·B
AUA resident bowlÍSÄ(Ji_ðÜÞ)ð8ÂÌnæɪ¯A»ê¼êÌnæðã\·éresidentªåAíÈÌm¯ð£¢ ¤åïÅ·B
CO©çexchange program ÅQÁµ½eÌresidentÍ»ê¼êÌnæÉÁíèÆàÉí¢Ü·B
äXú{`[ÍNortheastern teamÉÁíèܵ½B
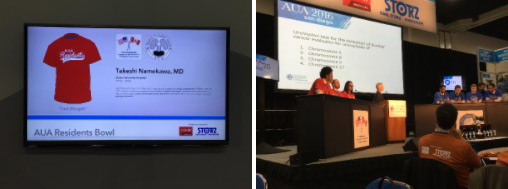
âèÍåAíÈÌffE¡ÃÉÖ·ém¯ðâ¤àÌ©çAUAÌðãpresident̼OÜÅLoè³êÜ·B
հ̪ìƵÄÍrA@\â«@\ÉÖ·éâ誽oè³êAÄÆú{ÌÖSÌá¢ð´¶Üµ½B
Northeastern teamÍ1ñíɵ½àÌ̱ÅcOȪçskµÄµÜ¢Üµ½B

(Ê^F¶©çìAcåw OHæ¶ANortheastern team)
¢Â©ú{Åà±ñÈåïªJóê½çÊ¢¾ë¤ÈÆv¢Üµ½B
ïúÉJUA/AUA resident programÌmentorÅ éAtlanta Emory University HospitalÌDr. Chad W Ritenourª[Hɵҵľ³¢Üµ½B
Dr. Ritenour ÍNJUA/AUA resident programÌmentorƵÄ[HïðJõĢéÆ̱Æŵ½B
[HïÉÍAtlantaÌresidentàQÁµAÄɨ¯éåAíȤCÌ»ó©ç¥è̱ÆÜÅbª·èãªèÆÄàyµ¢Ôðß²·±ÆªÅ«Üµ½B

(Ê^ãiF¶©çresidentÌ3lAChairmanÌDr. Martin G Sanda
Ê^ºiFcåw OHæ¶ADr. RitenourAì)
»µÄAUA annual meeting Ì÷ßèƵÄPresident ReceptionÖQÁ¢½µÜµ½B
President Receptionͻ̼ÌÊèeÌPresidentªµÒ³êép[eB[ÅܳÉ_ÌãÌ涪½³ñ¢çÁµá¢Üµ½B

(Ê^ºi¶©ç4lÚFAcademic Exchange ProgramÅQÁ³ê½Aåw@´³äèæ¶
Ê^ãiE©ç2lÚF¯¶Rûåw@R{`¾æ¶)
COwïQÁÌyµÝÌêÂÍ»nÌHÅ·B
San DiegoÍLVRÆÌ«É é½ßLVR¿ÌXgའèܵ½B
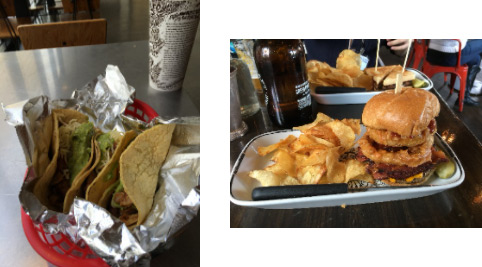
ܽAC¢É;½mɾÞ[úð©ÈªçHªÅ«éµÍCÌÇ¢¨Xà èܵ½B

NAUA Grand ReceptionÍïüªÃç³êĨèAyµÝÈCxgÌêÂÅ·B
¡NÍSea WorldÌêpðØèØÁÄÌp[eB[Å·B
éÉ©éV`ÌV[ÍålàyµßéïüªÃç³êĢܵ½B

`ÔOÒ`åAíÈT[tBin San Diego`
wïQÁÉxáªÈ¢æ¤©©çmission beach Ö

ÜÆß
AUA/JUA resident programÉQÁµAMdÈo±ðÏܹĢ½¾«Üµ½B
»ÝAÍú{ÉßèîbÀ±ÉÇíêéúXÅ·ªA¡ñÌvOž½o±ðv¢oµÂÂA¢Â©Í¢EÌäÅåAíÈwÌWÌêÆÈéæ¤ÈdªÅ«êÎÆvÁĨèÜ·B
±Ìæ¤È@ïð^¦Ä¾³Á½ú{åAíÈwï oìWÛÏõ·Açtåwåw@ãw¤@åAíÈw sìqF³öAØÝÉDinerɲµÒ¢½¾¢½MentorÌEmory University of Hosipital, Dr. Chad RitenourA»Ì¼½Ìæ¶ûɱÌêð¨ØèµÄSæè[Ó\µã°Ü·B
¶ÓFì@j
2016/3/25@sjtÜæ¶@w·\²yÑw{·\²
2016/3/25(à)çtåwwÊL`B®ÉÄw·\²yÑw{·\²ªsíêAÜ涪\²³êܵ½B
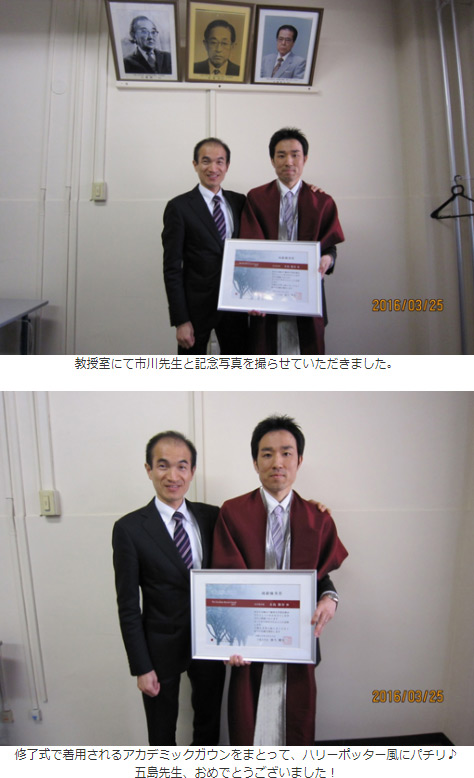
2016/1/30@æ16ñÖzÆà¤ï
FlúX¨¢bÉÈÁĨèÜ·AçtåwåAíÈãú¤C3NÚÌäºÅ·B
1/30(y)ÉåwãÈw¤t®a@g~[z[ÉÄJóê½æ16ñÖzÆà¤ïÆ¢¤AzÆàÌXyVXgÌW¤ïÉQÁµÜµ½ÌÅñ¢½µÜ·B

zÆà¤ïÍNÉ1ñJóêA»Ì¼ÌÊèzÆàÉÖ·é¤ïÅ·ªA»ÌÁ¥ÍåAíȾ¯ÅÈwlÈâûBOÈÆ¢Á½¼ÈÆà¯Ås¤±ÆÉ èÜ·B
¬KÍ̤ïÅÍ èÜ·ªAi͵íÈ¢ÌæÌÅVÌgsbNX©çzÉηém©ð[ßAåAíȾ¯ÌwïÆä×}jAbN©ÂÌL¢ÈfBXJbVªJèL°çêÄ¢½ÌªóÛIŵ½B
©ªÍz¡Ã~ãÌeXgXeñÉÖ·é¢Ì|X^[\ðµÜµ½B
QÁÒÌÙÆñǪ³öNXÌæ¶ûÅ èAãú¤CãÌæ¤ÈºÁ[ͨ»ç©ª®ç¢Åµ½ÌÅ©ÈèÑÑÁÄ¢½ÌÅ·ªAâ{æ¶ÉàFXÆtH[µÄ¢½¾«AïðyµÞ±ÆªÅ«Üµ½B
éÊãåQmãw¤Z^[³öÌäãæ¶âåwæ[ÈwZp¤Z^[ÁC³öÔÀæ¶Acåw̬âæ¶Æ¢Á½¼Èæ¶û©çlXÈAhoCX𢽾«A¡ãÌÕ°¤ÉÂȪéLÓ`ÈàÌÆÈèܵ½B
äã³öÌQmZ^[ÉÍA¡Nx©ççtåwåw@Ììæ¶à¤¯¤Åà¯wðsÁĨèÜ·B
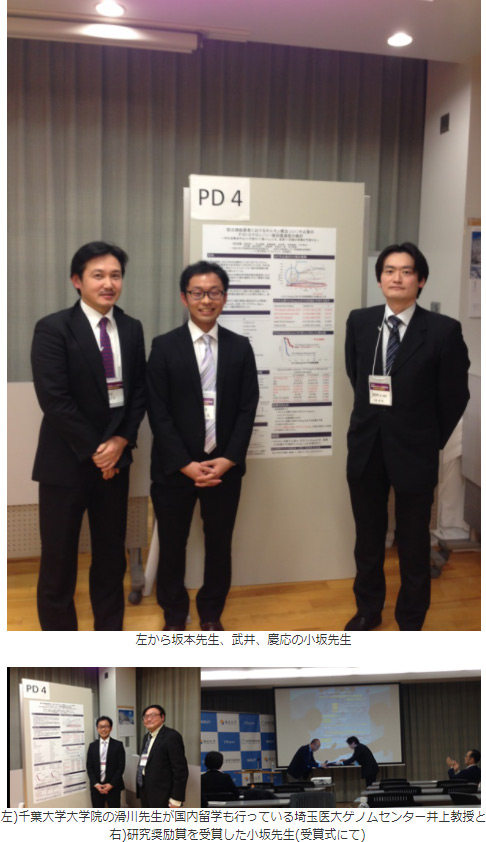
åAíÈÌÁ¥Åà ézÆàÆ¢¤ªìÍܾð¾³êĢȢ±Æà½AîbAÕ°ÆàÉ¡ãपKvȪìÅ èÜ·B
çtåÅà³çÈé¤ðißAãÃÌWÉv£µÄ¢±Æªg½Å éƶ¶Ä¨èÜ·B
¡ãÆàæ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFä@º
2015/11/17@sìæ¶@¨a¶úï
sìæ¶Öú Ì´ÓðßÄA³³â©ÅÍ èÜ·ªãÇÉĨa¶úïðJ«Üµ½B

2015/8/8`9@åóÌï(59Ìï)QÁñ
ßܵÄB½¬27Nxüǵܵ½VjAWfg1NÚ̺ŷB
88úA9úɼîÅJóê½åóÌï(59Ìï)ÉQÁ³¹Ä¢½¾¢½ÌŲñµÜ·B
åóÌïÆÍAsì³öðͶßÆ·éºa59N²ÌåAíÈåC³öÌæ¶ûÉæÁħ¿ã°çê½NJóêéwïÅA¡ñ6UñÚÌJÃÉÈèÜ·B
¡NÍ¡cÛq¶åw ØÇê³öªåÃ̽߼îÅJóêܵ½B
çtåw©çÍsì³öAâ{æ¶A¤CãÅæÜÅÈðñÁÄêÄ¢½ú¤Cã àqæ¶A»µÄ ºÌ4lÅQÁµÜµ½B
1úÚ
8úÍ16©ç©çeåwÌæ¶û©ç\ª èܵ½B
çtåw©çÍàq涪wO§BàzÃ@ɨ¯é´eXgXelÌáºÆ\ãÆÌÖA«xÉ¢Ä\µÄêܵ½B
¤CãÉàÖíç¸eåwÌæ¶ûÌ¿âÉàImÉñµÄ¢Üµ½B

\·éàqæ¶
»ÌãÍð¬ïªsíêܵ½B
sì³öÍ¡cÛq¶åwÌl¯w¶Æ¬¨ÈêÅïbðyµñŨçêܵ½B
»ÌãÍNxçtåwƯÅÛÎÇwïðJ÷éàòãÈåwÌåAíÈÌæ¶ûÆwVxɼÌèHæðH×É¢«Üµ½B
Nx̤¯JÃÉÞ¯¼åwÌãJª©ÈèÅ¢àÌÉÈèܵ½B

àòãÈåwÌæ¶ûÆùÝïãÌê
2úÚ
2úÚÍ©©ç¡cÛq¶åwåÃÌoXcA[ªJóêܵ½B
ܸͼî©çoXÅò§ÌS㪦ÖB
S㪦Í̳`¶»âYÉàwè³êÄ¢éwSãxèxªsíêÄ¢éƱëÅ èÜ·B
S㪦É
·éÆLOÙÅwSãxèxÌÀð©wB
¨o³ñÌØíÈÉê¯Á±B
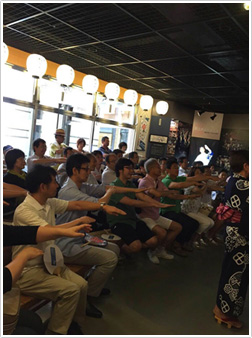
SõÅSãxèð̱
»ÌãÍÝñÈÅLOBeðµA©RUôÌÔÖB
Sãª¦É éV´©çºÌgcìÖÌòÑÝÍåÏL¼ÅAn³ÅÍjÌqªålÉÈé½ßÌx¹µÆµÄÌ©çsíêĢ黤ŷB
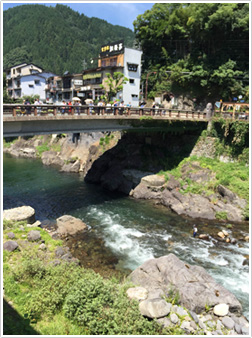
gcìÆV´
çtåwåAíÈ©©çàjÉÈé×3lª§¿ãªèܵ½B
1lÚ@â{æ¶B
eåwÜß³ÈãÅòÑñÅ¢½ÌÌÍâ{涽¾êlŵ½B
f°çµ¢òÑÝÁÕèŵ½B
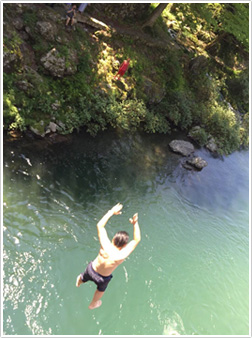
2lÚ@º
òÑñÅ©ç
·éÜÅÉ|ÄÚªJ¯çêܹñŵ½B
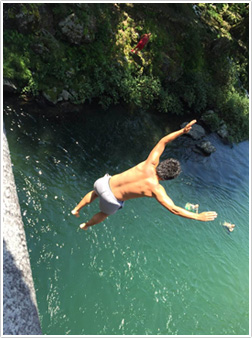
3lÚ@àqæ¶B
ÅãÉÆñ¾àqæ¶ÍAòÔ©òÎÈ¢©©ÈèÀÁ½ °òÑܵ½B
ÞÌEC és®É¼ÌÏõqÌû©çàèªí«ãªÁĢܵ½B

ú{SÁ
ÌêÂw@_
xàùµÜµ½B
â½Ä¨¢µ©Á½Å·B
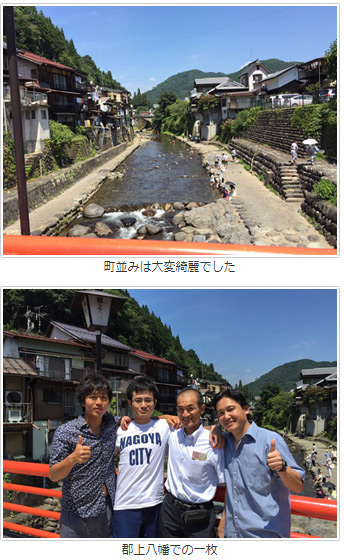
»ÌãA·ÇìS¹ÌS㪦wÜÅoXÅÚ®µAüZÜŨÀ~ñÔÌ·ð¬\µÜµ½B
¨À~ñÔÌÔ©çÍ·ÇìüÓÌL©È©RâìÅ̼ÞèAteBOðyµÞÐÆA
MÈÇð©é±ÆªÅ«åÏDëȨÌÔðß²·±ÆªÅ«Üµ½B


üZÉ
ãÍܽoXÉæèA¢EÅåÌW
°ÙwANAEgg¬ÓxÉü©¢Üµ½B
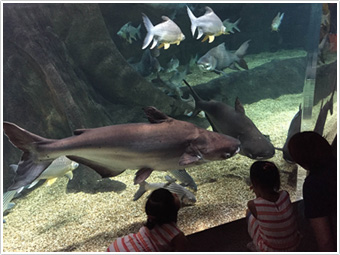
©½±ÆàÈ¢å«ÈW
ª½³ñ¢Üµ½B
±¤µÄ©©çÌ·ÍI¹µA꯽½ÉÈÁļîwÉßÁīܵ½B
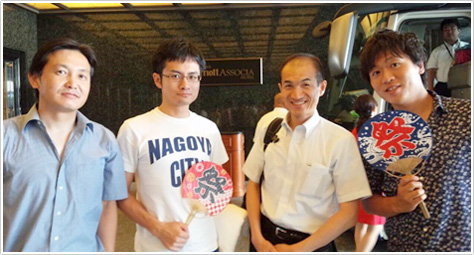
¼Ã®wÉ
µ«È4l
¡ñÌåóÌïÅÍeåwÌ涽¿ÆÌð¬ªÍ©êAܽ¼Ã®AòðiÅ«åÏDëÈ2úÔŵ½B
NÌæ7ñÍAàòãÈåwåÃÅàòÅÌJê\è³êĢܷB
¶ÓFº@³m
2015/5/15`19 AUA(ÄåAíÈwï)QÁñ
åw@¶ÌìÆ\µÜ·B
5/15-19ÉAJEj
[IYÅJóê½AUA annual meeting 2015ÉQÁµÄQèܵ½ÌŲñ¢½µÜ·B
AUAÍEAUÆÀÑåAíÈÌæÅÍÅà ÐÌ éwïÅ èA»ÌïÅ éannual meetingÍQÁÒà¢EÅåKÍÅA»Ì½ßèÌÌð¦à30öxƾíêĢܷB
¡ñAUAªJóê½j
[IYÍAJìÌ~VVbsìð]Þ¬ÅAtX¡ãÌîðc·¬ÀݪÏõnƵÄlCÅ·B
ܽWYÌËÌnƵÄàL¼Å·B
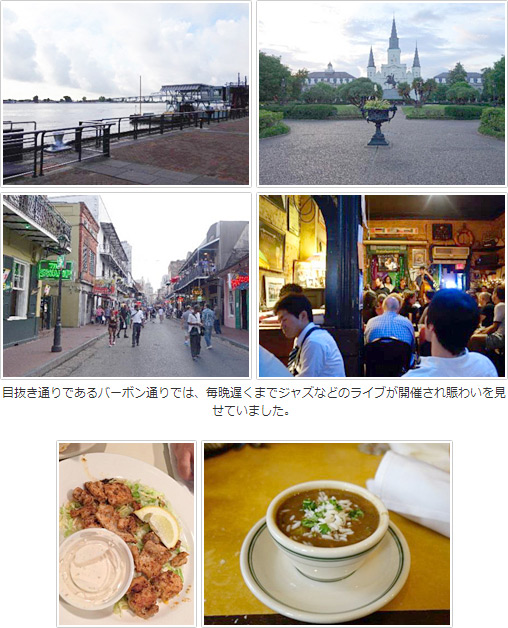
¼¨ÍPCWÆÄÎêéXpCV[È¿ÅAh¢à̪D«ÈÉÍÆÄਢµ©Á½Å·B
cæ¶ÍTÌX[vðDñÅùñŢܵ½B
¡ñAçtåw©çÍ6èªÌð³êAsì³öAâ{æ¶AÜæ¶Acæ¶(»F¡lJÐa@α)ÆìªQÁµÜµ½B

ÍúÌtÌZbVÅ\¢½µÜµ½B
tÌZbVÍ·×ÄûÅÌ\ŵ½B
ðNàAUAÅ\·é@ïÉbÜêܵ½ªA|X^[ZbVÅ Á½½ßAAUAÅÌûÍßÄŵ½B
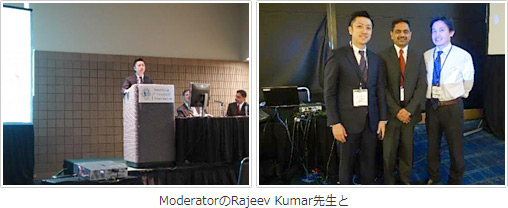
誽¢±ÆÉtA©çà¢Â©¿â𢽾«Üµ½ªAÌpêÍÅ;¢½¢ªv¤æ¤É`¦çê¸A×s«ðÀ´µÜµ½B
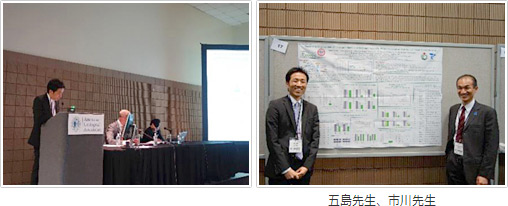
Üæ¶ÌO§BàÌîb¤Ì\ÌlqÅ·B
Üæ¶ÍÆ2wNµ©áíÈ¢ÌÅ·ªA¬¨ÈpêÅÌ°XƵ½\ÉåÏhðó¯Üµ½B

»ÝVancouverÉ é British Columbia Cancer Agency Genome Sciences CentreɯwÌ¡ºæ¶Ì²\à èܵ½B
Androgen receptor ÌN[ðtargetƵ½¤ÅA¨ïR«O§BàÉηéVK¡Ã¨æѸ@ƵÄÚ³êĢܷB
±ÌªìÅÍBritish Columbia Cancer AgencyÌMarianne Sader涪¢EÅàæ1lÒÅ èA¡ºæ¶ÍSaderæ¶ÌàÆŤð³êĢܷB
±ÌãAÍAµÄµÜÁ½½ßȺÍcæ¶ÉñµÄ¢½¾«Ü·B
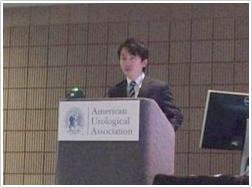
cÌ\Å·BpêÍÉå«ÈsÀðø¦ÈªçÌ\ŵ½ªAÙ¢pêÅǤɩ³ÉðI¦Üµ½B
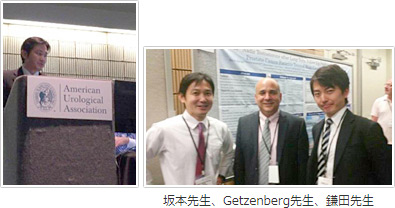
â{æ¶Ì\Å·B
³ªÌ\ÅA§ÄÂÉ
ÆÍܳɱ̱ƩƢ¤æ¤ÈA¬¨Å©Á±¢¢Xs[`ŵ½B
\ÌãÍCWAiÏõƵÄASWAMP(¼nÑ)cA[ÉsÁīܵ½B
j
[IYüÓÍC²ªáA
̫ͯ¢næƵÄmçêĢܷB
ze©çÔÉhçêÄ1ÔÅ»nÉ
B
C·Í30xA¼xàAÞ¹©¦éæ¤È³ÌA{[gÉæÁÄèo·ÆSn梪¢Ä«Üµ½B
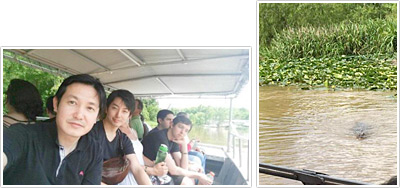
µÎç¢ÆA
Êɽâçöµ¢JQªc
»¤AAQ[^[Å·B
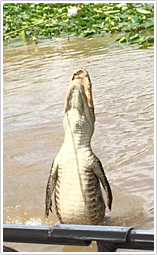
KChª¨àÞëÉ}V
}Æ\[Z[WÌ¢½_ð·µoµ½»ÌuÔAËR
Ê©çòÑoµA_Éç¢Â«Üµ½B
KcAÆå«È¹ªoĵDªhêéÙÇAAQ[^[ÍDÉÔ©Áīܵ½B
»¤µÄAQ[^[ÍêuɵÄl¨ðD¢éÆAIRƼnÌÖÁ¦Ä¢«Üµ½B
AQ[^[Ì°|Æ»±Å\ÅÌÁÜ´àYê³èAyµ¢L¯¾¯ªSÉcÁ½1úŵ½B(c)
³ÄAiÈ©È©¨b·é±ÆªÅ«È¢¼ÌåwÌæ¶ûÆHðµÈªçð¬ð[ßé±ÆªÅ«éÌàCOwïÅÌyµÝÌê¾Æv¢Ü·B

AJÌg[}XWFt@[\åwÌåAíÈÅNjJtF[ð³êÄ¢éªRåwÌJ{æ¶çÆÌ[H
(¶©çAäæ¶AJ{æ¶Aâ{æ¶A¡ºæ¶Aì)
J{æ¶Íú{ÅÍܾ]èyµÄ¢È¢AÇîáÌྡÃð½o±³êĨèñíÉ»¡[¢¨bª·¯Üµ½B

wïêßÌXgÅÌHÅ·B
¶©çAªRåwÌJ{æ¶ALåwÌàæ¶A¡ºæ¶Aì
E©çAâ{æ¶AåwÌ´æ¶AÜæ¶
ܽAéÆu[XÅͳܴÜÈÅVÌ@BªW¦³êfXg[VÌ̱ªÅ«Üµ½B
»ÌÅàj[N¾Á½Ìª~Xpi}ÆÊ^ðÆ龯Ìu[XÅ·B
»ÌCpNgÅAÌSÌv[Vàe͸OµÄµÜ¢Üµ½ªc

~Xpi}Æâ{æ¶
(SÌâ{æ¶t@ÌFl·Ýܹñ)
ÜÆß
¡ñ2ñÚÌAUAÖÌQÁðʵÄAåAíÈEÌ¢EÌghÉGê×ÉÈÁ½ÆÆàÉ©ªÌåw@Å̤Éhðó¯é±ÆªÅ«Üµ½B
10©çåwa@ÉßÁ½Î©èűÌæ¤Èf°çµ¢\Ì@ïð^¦Ä¢½¾«A{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
Å·ªAAèÌòs@ªxµ½½ßVJSó`Åæèp°¸A}ç¯[eÉê·é±ÆÆÈèܵ½B
½Ü½Ü¯¶ÖÉæµÄ¢çÁµáÁ½cåwåAíÈÌæ¶ûÉÍAµêÈ¢guÅS×¢AåϨ¢bÉÈèܵ½B
AUAÌÅãÉYêçêÈ¢v¢oªÅ«Üµ½B
¶ÓFì@j
2015/3/20`24 EAU(¢BåAíÈwï)QÁñ
ãú¤CãÌáäÅ·B
3/20-24ÉXyCE}h[hÉÄJó꽢BåAíÈwïÉQÁµÄQèܵ½B
¡ñÍw±ãÅ éâ{æ¶Æjñl·Åµ½B
Ê^ðð¦Ä²ñvµÜ·B

ú©ç¬wïêÖBsXn©çÔÅ20ªç¢Ìå«È{Ýŵ½B
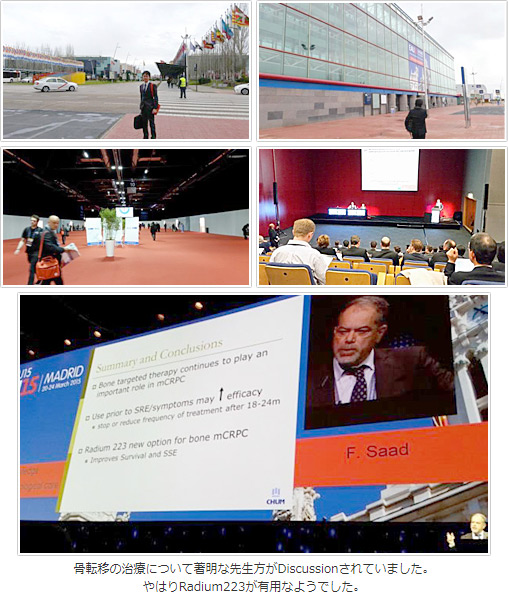
ãÃ@í[J[Ìu[Xà½oWµÄ¨èAÅV@íÉ¢Ä෱ƪoܵ½B
Úðø¢½ÌÍ360²ñ]ªoéAED¡ÃpÌESWLðpµ½u(ÕgªÇV¶ð£i·éçµ¢HÉÝÍH)APSAÌÌʪ10ªÅoé|[^u¸íÈÇŵ½B

wïúÉAâ{涪À·ÌÎZbVª èܵ½B
Poster\Æ¢ÁÄàêÊÉòRÌ|X^[ª\çêÄ¢éí¯ÅÈAÍ14èÙÇÅ·×ÄdãÅÌ\Æ¿^ª èܵ½B
SessionÌßÌ20ªÍposter viewingª èܵ½B
öÝÉA8èªRCTÆ¢¤¢Qualityŵ½B

ÔÉAN7ÉÈÆàòãÈåwª¤¯J÷éæ13ñÛAHÎÇwï/13th International Symposium on Urolithiasis (ISU2016)ÌLñà¸ÍIÉs¢Üµ½I

ISUÌptbgðzéâ{æ¶
2úÚÉÍâ{æ¶ÌO§BàÌîb¤ÉÖ·é\ª èܵ½B
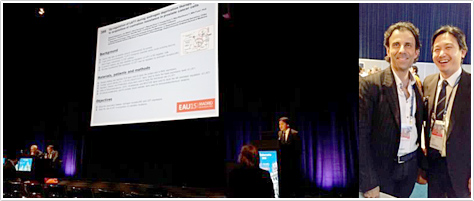
\³êéâ{æ¶(¶)B
ÈOAJi_̤CŨ¢bÉÈÁ½çµ¢ggåwÌTony Finelliæ¶(E)B
éÉÍAÅßÌCWOX^[ÌêlACMXÌRoyal Marsden HospitalÌGerhardt Attardæ¶Ì²uð·@ïª èܵ½B
¢BÅÍO§BàÉηézÃ@ƵÄLH-RHagonistPÜ©çÌgpªsíêĨèA»ÌÏ_©çÌVKòÜ(Abiraterone,Enzalutamide)ÌÝèûÉ¢Ą̈bð·±Æªoܵ½B
CRPCãAAbi©EnzaluͼûÆ௶ç¢LøƦĢܵ½B

Attardæ¶ÉAAWSÌKv«É¢Ŀâ³êéâ{æ¶B
(öÝÉALH-RHãÉÇÁ·éJ\fbNXɽ̢¢lÍAWSðs¢A«¢lÉÍAWSðsíÈ¢Æ̦ŵ½)

¶©çâ{æ¶AáäA²u³ê½Attardæ¶AF{åwÌÍìæ¶B
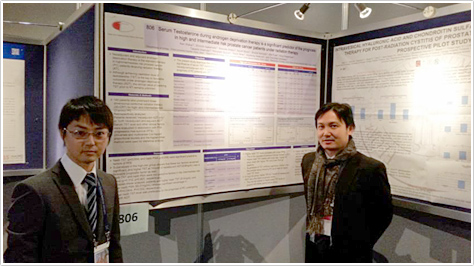
»ÌúÉÍÌAO§BàúËüÃ@ÌeXgXelÉÖ·é\ª èܵ½B
1NÔâ{æ¶É²w±¢½¾¢½èÅ·B

ÈñÆ©ßOÌ\ªIíÁÄ©çAßã©çÁ}ñÔÅQÔÙÇÌoZiÜÅ«ðεܵ½B
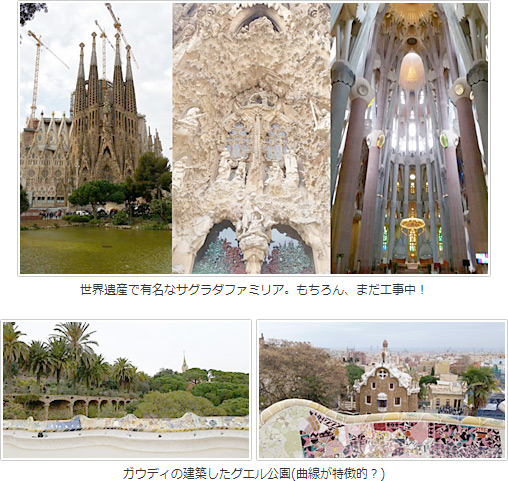
s¯íÌíÎÌÕªcésXB
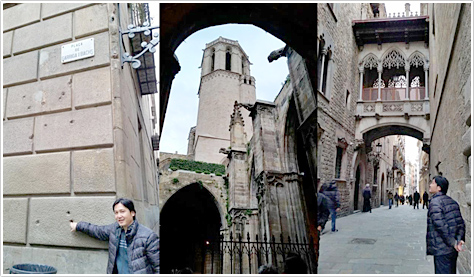
ÇÉÍA¢Ü¾ÉàíÉæéeeÌÕªcÁĢܷB
éÍ^ÇA[KEGXpj[ÌðÏÉs±Æªoܵ½B
µ©àAoZivsA}h[h!!
bVâCEiEhÌv[ðÚÉÄ«t¯Ä«Üµ½B

»Ì¼Éà\ÌÔÉXyCoðÁ½èAtRðÓܵ½èÆ}h[hÌXài·é±Æªoܵ½B
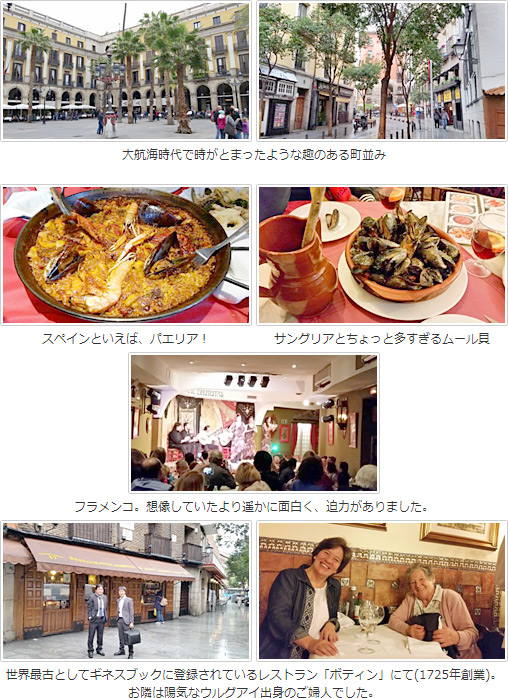
ÜÆß
ßÄåAíÈãƵÄÛwïÉQÁµA¢EÌL³ðÀ´µÜµ½B
ú{ÅÍÀ»µ¦È¢æ¤È¤â¡Ãà¢ÄÅÍÇñÇñÆißçêĨèAñíÉ×ÉÈèܵ½B
ܽAK¸µàpêªöpêÅÈ¢XÌæ¶ÌpêÍ̳ÉàÁ©³êܵ½B
ÁÉEUÌæ¶ûÍÆÁÌANZgÍ ÁÄàApêðêêÌæ¤Éµ¢¿^ÈÇð³êĨèA©ªài©çpêɵêeµÞKµð¯½¢Æ´¶Üµ½B
¡ñ±Ì\̽ßÉòRÌûXɲ͸«Üµ½B
²w±¢½¾«Üµ½æ¶ûAxðµÄ꽯úA»µÄSÌÌÄÂðµÄ¸¢½â{æ¶ÉA±ÌêðØèÄ[äç\µã°½¢Æv¢Ü·B
â{æ¶Í²©gài©çïcâ\ÈÇŨZµ¢AÌ\ðhø²w±¸«Üµ½B
¯lÌe[}Žx©\ðdËīܵ½ªA\OÈÇÉÍAú[éÜÅÅ¿í¹Ét«Áĺ³é±Æà èܵ½B
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
©gƵÄàfÃÌTçAJe²×âðÍÈÇÅa@ÅQÜèð·é±Æà½AµñÇÈÁ½úà èܵ½B
½¾A±¤µÄêNÔÌIíèÉXyCÌnÅ\ðµÄ½ðwԱƪoAæ£ÁÄ«Ä{ÉÇ©Á½Æv¢Üµ½B
ܽ¬·µÄÛwïÌêÉßÁÄé±Æªoéæ¤A¡ãà±Ì̱ðÆÉêwæ£ÁÄ¢«½¢Æl¦Ä¢Ü·B
¶ÓFáä@
QOPS/PQ/PP æ616ñú{åAíÈwïnûï QÁñ
ãú¤CãÌáäÅ·B
à¤ðṈÆÆÈÁĵܢܵ½ªA2014/12/11(Ø)ÉEäm
ÉÄJóêܵ½uú{åAíÈwïnûïvÉQÁðµÄÜ¢èܵ½ÌÅA²ñð³¹Ä¸«Ü·B
nûïÆÍAÖÌåAíÈãtªWÜèÇáñâ¤\ðs¤êÅ·B
Ìa@¾¯ÅÍÈAäXçtåÈÇßxÌa@àQÁµÄ¨èÜ·B
NÉRñJóêĨèA¡ñÅÈñÆæ616ñð¦½æ¤Å·B
(Æ;ÁÄà200NO©çâÁÄ¢½í¯ÅÍÈ¢Æv¢Ü·ª)
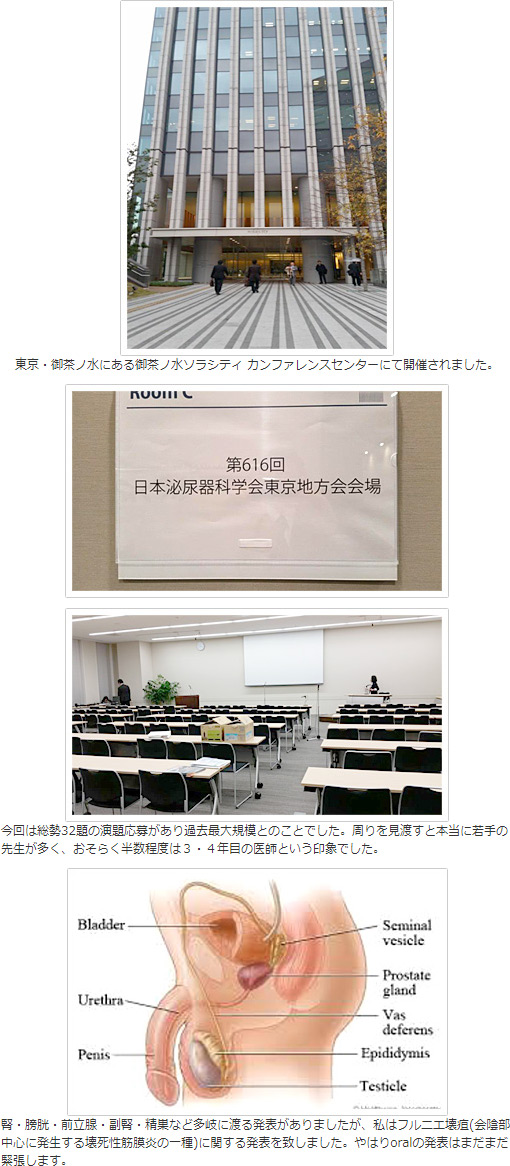

ÅãÉxXgv[e[VÜÌ\ª èA^ÇóÜ·é±Æªoܵ½B
\·éÈãÍ_ÁÄ¢±¤ÆbµÄ¢Üµ½ªAܳ©{ɸ¯éÆÍvÁĢܹñŵ½B
ÜóðàçÁ½ÌÍw¶Èŵ½B

ܳÉáèÌ\ïƾÁ½´¶ÅA¯NãÆvíêéæ¶ûª½³ñQÁ³êĢܵ½B
mè¢ÉÈé±ÆÍoܹñŵ½ªA±ê¾¯ÌáèåAíÈ㪢Äea@ŤCµÈªç¤\ðµÄ¢éÆ¢¤±ÆªåÏhÉÈèܵ½B
¡ñÍ^ÇóÜ·é±Æªoܵ½ªA¯NãÌæ¶ûÆߢAæèÇ¢\AæèÇ¢¤ªoé椸iµÄ¢«½¢Æ´¶Üµ½B
ÅãÉA±Ì\Éü¯²w±E²¾ðº³¢Üµ½²Ëæ¶ðßÆ·éw±ãÌæ¶ûA»µÄOÌ\ûKÉt«ÁÄ꽯úÌæ¶ûÉA±ÌêðØèÄ[äçð\µã°½¢Æv¢Ü·B
½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFáä@
QOPS^PP^QT@sìæ¶@¨a¶úï

sìæ¶Ì¨a¶úð¨j¢µÄAãÇÉĨa¶úïðJ«Üµ½B
sìæ¶Í²o£ÌÍK¸ãÇÖ¨yYðÁīĺ³Á½èAãÇ̨Ùq ªÒµÈéƨâÂð·µüêĺ³Á½èA×â©È¨S¢ðº³¢Ü·B
¢Âà¢ÂàãÇÖ·©È¨C¢ðº³ésìæ¶Öú Ì´ÓðßÄA¨a¶ú¨ßÅƤ²´¢Ü·I
QOPSNPPPú`Qú@uThe Best of AUA in Japan 2014vÉQÁµÄ
ßÄÌeÆÈèÜ·B{NxVüÇÌáäÆ\µÜ·B¡ãÆàæ뵨è¢\µã°Ü·B
±ÌxÍ11/1,2(yEú)ÉEiìÉÄJóêܵ½uThe Best of AUA in Japan 2014vÉQÁµÄÜ¢èܵ½ÌÅA²ñð³¹Ä¸«Ü·B
uAUAvÆÍÄåAíÈwï(American Urological Association)̪ÅAuBest of AUAvÍ»ÌwïÉıÌPNÔÅÅàÚðWß½\ÌXðAAUAÌo[Å éæ¶ûªí©èâ·ðàµÄ¾³éïÅ·B
AJ©çàAUA faculty (³õ)Ì涪¡¼¢çÁµáèAú{ÌfacultyÌæ¶ûÆÆàÉÅVÌm©âeNmW[É¢ĨbðµÄº³¢Üµ½B


AUA facultyÌæ¶BpêÌuÅ·ªA¯ÊóªÂ¢Ä¢Ä»êð·±Æàūܵ½B
æʶÍàâæ¶Ì²¿âB¬ÎÅ·B1ZbV(45ª)Å¿âª20âÈãoé±Æà èܵ½B


ÜÆß
òRÌ\ðí©èâ·à¾µÄàç¢Afloor©çàհɦµ½s¢¿âªoÄ¢½ÌÅA©·ªå«LªèÆÄàLÓ`Èïŵ½B
»ê¾¯ÅÈfacultyÌæ¶â¼åÌæ¶Æ¨bµ·éż@̨bðf¤±ÆªoAñíÉhÉÈèܵ½B
2015NÌAUAÌè÷تÁĢܷªA©gàAUAÅ\oéæ¤æ£ÁÄ¢«½¢ÆüßÄv¢Üµ½B
ÇL

Oñ¶©çàâæ¶Aâ{æ¶Acæ¶AáäB
ãñ¶©çÁ¡æ¶A`[hæ¶B
±êÍ2010/10/26ÌåAíÈÊMÉfÚ³ê½w¶©UïÌÊ^ÅAà¨CÉüèÌàÌÅ·B
SNOÉÈèÜ·ªAw¶¾Á½Rl(àâæ¶Acæ¶Aáä)ÍÝÈüǵܵ½B
S©çÍåwÌãú¤CãƵÄÆàÉdðµÄ¨èÜ·B
±ê©çàæ¶û̲w±ÌàƸiµÄQè½¢Æv¢Ü·B
æ뵨è¢vµÜ·B
¶ÓFáä@
QOPS^R^QP`QQ@The 4th Congress of Asian Pacific Prostate Society QÁñ
ßܵÄA½¬25NxüÇÌRcN²Æ\µÜ·B
»Ý®a@ÉÄãú¤Cð³¹Ä¸¢Ä¨èÜ·B
©Èèxêĵܢܵ½ªüÇ1NÚÌåwa@αÌÛÉo±³¹Ä¸¢½AwïQÁñðvµÜ·B
æ4ñAWA¾½mO§BwïÍV°åwåÃ̳, 2014N3É«êE¼ìÌÃÀÙÉÄsíê, {wæèsì³ö, â{涪QÁ³êܵ½B

ÍuValidation of active surveillance criteria for pathological insignificant prostate cancer in Japanese Men.vÆ¢¤èÅ\ð³¹Ä¸«Üµ½B
cOȪç\ÌÊ^Í èܹñª, pêÅ10ªÔ\·éÆ¢¤, È©È©o±Å«È¢Ôŵ½B
³XÙ£·é«iÈÌÅ·ª, ±Ì\ŵÍx¹ªÂ¢½ÌÅÍÆ, ¡ÆÈÁÄÍ´¶Ä¨èÜ·B
¯É¼ÌåAíÈÊMÅà©êĢܷª, COwïÅÌpêÍÌåسðÉ´µÜµ½B
1úÚÌȩ́eïïêB

«ê¯wÌtÌ, «ê¿ðúµÜµ½B
Ê^Í èܹñŵ½ª, àòåwÌÀسö²vÈƯ¶e[uÉÈèÆÄàÙ£µ½Ìðo¦Ä¢Ü·B

d®ì
ÌæyÅà èÜ·AàÕ¦åw R¼³öƨéªoܵ½B
ܽ, K^ÉàYoung Investigatorfs Award Æ¢¤Üð¸ªoܵ½B
©ªðÜß4¼óܵ, ØÌûª2lÆMåwãÃZ^[²qa@ ãCê涪O§BàÌîb¤ÉÄóܳêܵ½B
©ªÌÍÍ{ÉÍ©Å, °kƯɽ¾½¾´Óŵ½B
ÅIúÌéÉÍwïÜÌöÜ®ª·èsíêܵ½B
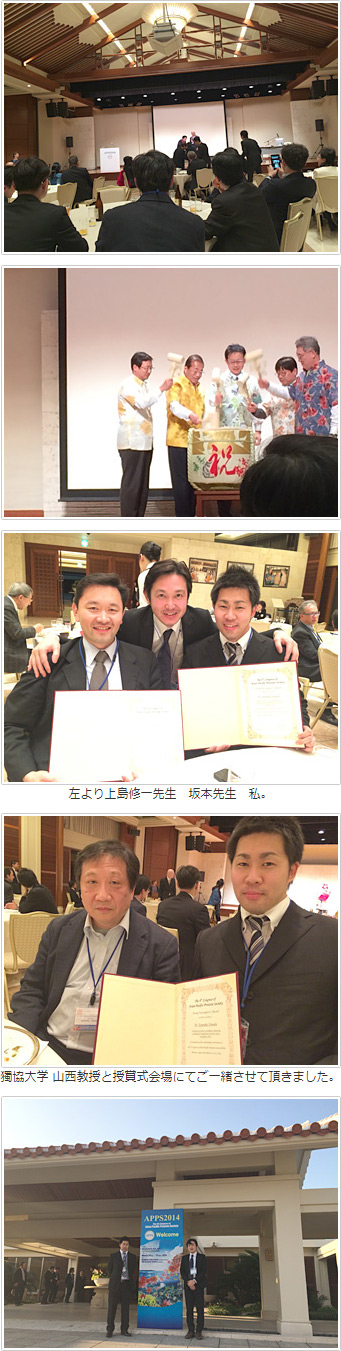
ÜÆß
2úÔÆ¢¤Z¢Ôŵ½ªAßÄÌCOwïÅÌpê\A³çÉÍÜÜŸªoAåÏMdÈo±Åµ½B
üǵķ®Ìåwa@αűÌæ¤Èo±ð³¹Ä¸ÆÍvÁĢܹñŵ½B
éÉÖAa@Öf[^ûWÉsÁ½è, îáÌÏðZt³ñÉw±µÄ¸¢ÄvZµ½èÆ, n¹Èìƪ`ÉÈèåÏãÝÉÈèܵ½B
ÅãÉÈèÜ·ª, ú̲ªDêÈ©Á½ÉàÖíç¸\¼OÜÅ}c[}w±ðµÄ¸«Üµ½â{æ¶, sì³öðnßÕ°¤Ì@ïð¸«Üµ½æ¶û, ³çÉͤZtlÉúäç\µã°Ü·B
¶ÓFRc@N²
QOPS^P^V@vXe(Åìtü¯G)Ö̪ªbZ[W
æðNbN·éÆPDF`®ÉÄ{Å«Ü·(vXe No.3æè]Ú)
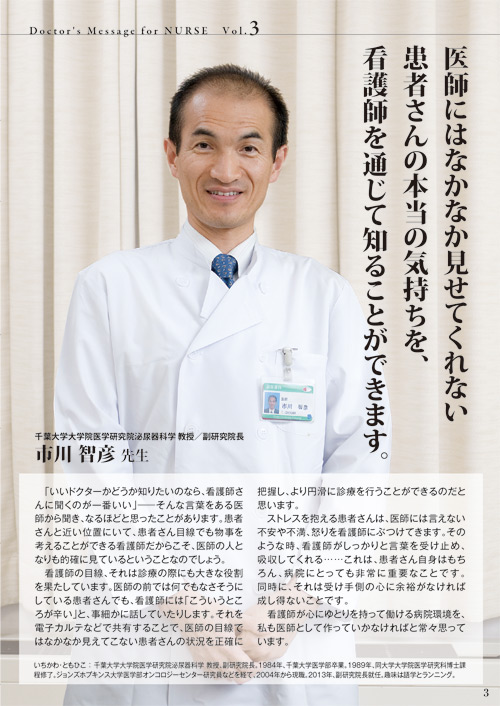
¶ÓFsì@qF
QOPRNXTú`Wú@Journal of Urologyªå÷éPeer Review SeminarÉQÁµÜµ½B
Ji_ÌoN[o[ÅSIU̼OÉJ©êAJUÌEditorÌæ¶ûª_¶ðReview·é|CgÌu`ª èA»ÌãAO[vɪ©êÄùÉs³êÄ¢é_¶ÌR¸Ì|CgAâè_ðc_µÜµ½B
¢Ee©çæ¶ûªQÁ³êܵ½B
ܽA»ÝoN[o[ÌBC Cancer AgencyɯwÌ¡ºæ¶Æ°ÉàïÁīܵ½B
oN[o[ÍAÈOAÈÌÔqæ¶AAcæ¶A¬æ¶ÈÇà¯w³êÄܵ½B
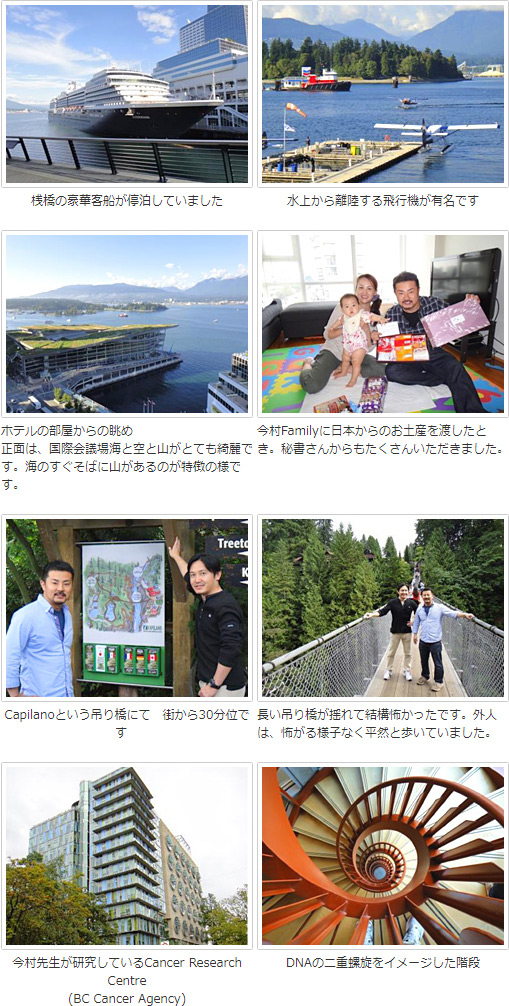


ÜÆß
oN[o[ÍAñíÉãYíÈ`¬ÅA©ÂAéoà¢ÄàSâèÈ¢ÙÇÀSÈƱëŵ½B
`Ì·®ßÉRâkJà èA~ÍWhistlerÆ¢¤L¼ÈXL[êÜÅàS©çêÔöxÆ¢¤D§nÉ èÜ·B
ú{lÌÝÈç¸A¢E©çZuBðÜßÄKêéRªæª©èܵ½B
Z~i[ÍAñúÔÉí½èJUÌEditorÌûÌLectureÌ ÆASmall Groupɪ©êÄ\Mµ½Hc_ªðí³êܵ½B
ChlâAtJlÈÇÌpê\Í̳ɽ¾³|³êܵ½B_¶¸ÇÌ|CgÈÇú Üè³íé@ïªÈ¢ÌÅAñíÉMdÈo±ÆÈèܵ½B
ܽAú{©çà½Ìæ¶ûɨé±ÆªÅ«Üµ½B
¡ºæ¶àA{ŽÌFlÉÍÜêA²Æ°ºÉñíÉ[Àµ½¯w¶ðß²µÄ¢éæ¤Åµ½B
¥ñAá¢æ¶ûࡺæ¶Ìæ¤É¯wðÚwµÄæ£Áľ³¢II
¶ÓFâ{@Mê
QOPR^T^QP@Ⱥ©ÍÜÁ½jO
æðNbN·éÆPDF`®ÉÄ{Å«Ü·(Astellas Square 2013N4-5æè]Ú)
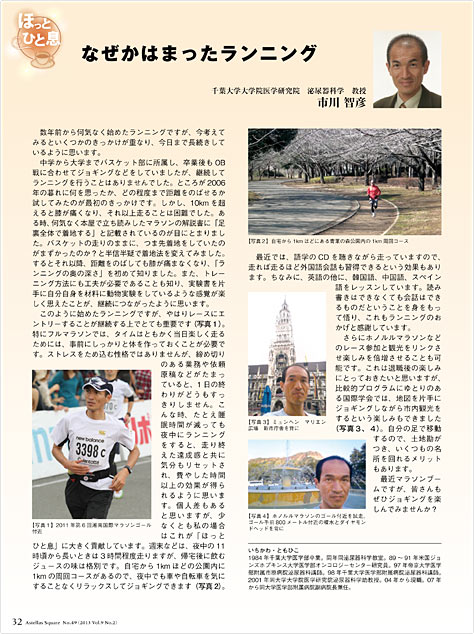
¶ÓFsì@qF
QOPQ^PP^QQ`QS@ú{åAíà¾wïQÁñ
2012N1122ú`24úÉåäÛZ^[ÅJóê½æ26ñú{åAíà¾wïïÉQÁµÄÜ¢èܵ½B
w´«AhXeÇÉηé o¾ºtEpãÌ~³òà~ÉÖ·éÕ°I¢FpOt@\Ê̳¡Ã¬ÑxÅAú{åAíà¾wïOWXgA[hðóÜ·é±ÆªÅ«Üµ½ÌŲñ\µã°Ü·B
Ìæ¤ÈáyÒª±Ìæ¤ÈÜ𢽾¯Üµ½±ÆͽÉߪÅAgÉ]é±Æɶ¶Ü·ªA¯ÉñíÉ èª½A¡ãÌãÝÆÈèܵ½B
¡ñÌ¢ªÅ«Üµ½ÌàAçtåwÌtOÈÌ`ÆAf[^Ì~ÏðµÄ¾³Á½æ¶û̶ÝA»µÄ»êçÌcåÈf[^ðûWAðÍȳÁÄ¢éàCæ¶Ì¨©°ÆSæè´Ó\µã°éæÅ·B
±Ìêð¨ØèµÜµÄA²w±¢½¾¢½æ¶ûÉúäç\µã°Ü·B
¡ãͱÌtOÈÌ`ð¥PµA³çÉòô³¹Ä¢¯éæ¤A¸iµÄÜ¢èÜ·B
MÉÈèܵ½ªA±Ìæ¤È¼_ éÜ𢽾¯Üµ½±ÆðAú{åAíà¾wï·@¼cöuæ¶Aåï·ð±ßçêܵ½kåwåAíÈräzêæ¶É[´Ó\µã°Ü·B

QOPQ^X^RO`PO^Q@SIU2012QÁñ
2012N930ú©ç104úÜÅÌúÔAªÛïcêðSÉJóê½32nd Congress of the Societe Internationale dfUrologie (SIU)ÉQÁvµÜµ½B

2011NxÈVjAWfgÅ Á½ìjæ¶(»ÝAçt§ªñZ^[åAíÈα)ªModerated PosterÅuExternal Validation of a Preoperative Prognostic Nomogram for Renal Cell Carcinoma in Two Patient PopulationsvAPodium SessionÅuExternal Validation and Comparison of Prognostic Models for Renal Cell Carcinoma Recurrence in a Japanese Populationvð\³êܵ½B
ܸúÍModerated Poster\ª èܵ½B



ïêàâïêtßÌJtFÅAú{lÌáèÌ涪½ñàScriptÃ¥µÄ¢½èããÌæ¶ÆÅ¿í¹µÄ¢ép𽩩¯Üµ½B
©ªªÓ©ðq×éą̀±ªÜµ¢Å·ªA¡ñìæ¶ÍßÄÌÛwïÅ\ªß¬éÙǧhÉ\µÄê½Æv¢Ü·B
\àeEXChðüOÉ¢µAzè³êé¿^ð½pIÉl¦AScriptð½ñàC³µûK·éB
»êçðìæ¶ÍúífÃÌTçŵÁ©èõµÄÕñ¾©ç±»A¡ñÌ¿Ì¢\ªÅ«½Ì¾ÆñíÉ𵴶ܵ½B
ÅãÉÈèܵ½ªAsìqF³öðnßäw±¸¢½æ¶ûAܽ¡ñõìæ¶ÉSIUÅÌ\Ì@ïð^¦Äº³Á½çt§ªñZ^[åAíÈEO§BZ^[· Acæ¶Éúäçð\µã°Ü·B
¶ÓFàC@FM
QOPQ^U^QV`QX@challenge in ENDOUROLOGY Report
2012N627ú`29úÉtXEpÅJóê½challenge in ENDOUROLOGY ÉQÁvµÜµ½B

ß©Á½Ìŧ¿ñÁ½GbtFÅ·ªAåϬGµÄ¢éæ¤ÅW]äÉoéÌÉÔÍ|©éÆÌŵ½B
ú{ÌXJCc[â^[Æá¢üÍÉ¢¨ª³¢ÌÅÆÄàå«©¦Üµ½B


¨âÂÉÍGXvb\Æ}h[kªèÔÌlŵ½B
Ê^ÍAú{̰̼OÌRÆÈÁ½JtFuFouquet'svÆèÔj
[ÌGXvb\Æ}h[kA
ÆÄàü¡µ©Á½Å·B
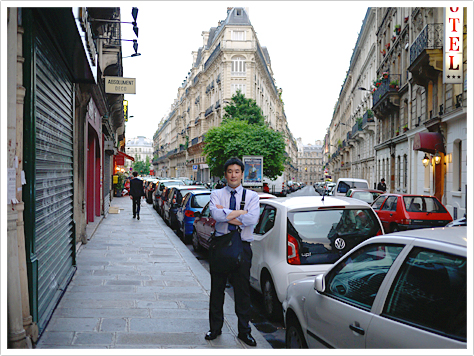
hæÌzeÌO̹ŷB
¾¡ã ̨ª»ÌÜÜZîâze»µÄJtFâæLƵÄgp³êĢܷB
»êɵÄàAHª·²¢Å·B
pÅÍAHͽèOÅoéÆ«ÍOãÉÔðÔ¯ÄÇ©µÄo黤ŷB
»Ì½ßop[;ç¯ÌÔΩèÅ·B¶»Ìá¢ð´¶Ü·B
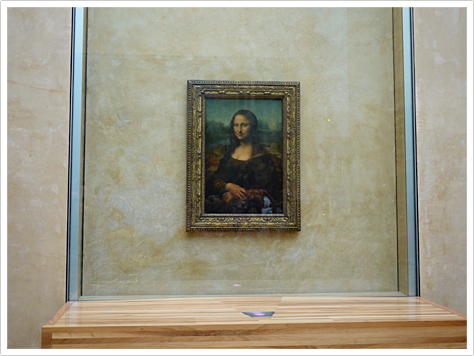
åϬñÅ¢½ÌÆAÔª Ü賩Á½ÌÅZÔÌØÝÆÈèܵ½ªA[uüpÙÉ«ð^Ñܵ½B
L¼ÈuiUÌ÷ÎÝvð©Üµ½ªAÍÁ«è©¦éƱëÜŽÇè
ÌÉåÏêJ·é®ç¢¬ñŢܵ½B
Ê^ÍôRãYíÉBê½êB
heKXŵdÉççêĢܷB
iUÍA©ªÉWÜéåQÌÏõqðÙ»ÎñÅ¢éæ¤É੦ܵ½B
ÜÆß
¡ñÌwïÅÍAçtåwåw@Hw¤ÈÜ\³ö̤ºÆ̤¯¤àeð\³¹Ä¸«Üµ½ªAVµ¢ÖÌchallengeÆ¢¤wïÌe[}ÉÒÁ½èÌ\¾Á½æ¤É´¶Üµ½B
ܽAxÌ¢\âLive surgeryð©Ä½Ìhðó¯åÏãÝÉÈèܵ½B
¶ÓFº@aF
QOPQ^U^W`X@æ24ñú{àªåOÈwïïQÁñ
2012N68ú`9úɼîÛïcêÅJóê½æ24ñú{àªåOÈwïïÉQÁvµÜµ½B
K¢ÉàAuHigh predictive accuracy of Aldosteronoma Resolution Score in Japanese patients with aldosterone-producing adenoma. (Surgery 2012)vÅú{àªåOÈwャ23Nx¤§ãÜðAu´«AhXeÇpãɨ¯ét@\áQÌ°Ý»ÉÖ·éÕ°I¢F«taVKÇÌ\ªöqÌñvÅæ24ñú{àªåOÈwïïDG|X^[Üð¸«Üµ½ÌÅäñ\µã°Ü·B
Ìæ¤ÈówáyÒª` éú{àªåOÈwï©çeÜ𸯽±ÆÍgÉ]éh_ƶ¶AüßܵÄú{àªåOÈwï· ©æ¶Aåï·ð±ßç꽡cÛq¶åwàªåOÈ â£È³öðnßäR¸¸¢½æ¶ûÉ[´Ó\µã°Ü·B
÷ÍÅͲ´¢Ü·ªA¡ãÆàú{àªåOÈwïÌXÈéW̽ßÍðsµÄ¢«½¢Æ¶¶Ü·B
àªåOÈwïÆ¢¤¾tÍAçt§àÅÍ Üè·«éõݪȢ©àmêܹñªA@bóBEbóBAtîáAûBÈÇLàªå¾³ðÎÛƵ½OÈnwïÅ·B
çtåwa@åAíÈÅÍAåAíÈêåãæ¾ãÉàªåOÈwïwè̤Cðs¦ÎuàªåEbóBOÈêåãvÌæ¾àÂ\Å·B
ïÍNÄÉJóêÜ·ªAOÈâåAíÈA¨@ôAÈÈÇî{ÌæÌÙÈéæ¶ûªàªåOÈÆ¢¤êÂÌSubspecialityð¤LµAàªåOÈfÃÌXÈéÉÝðÚwµÄc_·é½ßñíÉCª èÜ·B
¡ñÌïÍAåï·Ìâ£È³öÌf°çµ¢äÑzÉæèÆÄàZ§ÅA¾ú©çÌfÃÉ·®Éð§ÄçêéàeÉÈÁĨèܵ½B
SubspecialityÌwïÖÌQÁÍAî{ÌæªÙÈéæ¶ûÌäwEâc_ÉGêAiÍCt¯È¢±ÆðF¯Å«ÄåÏLÓ`Å éÆíÉv¢Ü·B
³ÄA¡ñÌóÜ͵ĩªêlÌÍŸÕÅ«½àÌÅÍÈA½ÌÔÌx¦ª Áı»¾Æv¢Ü·B
sìqF³öðnßäw±ð¸¢½æ¶ûAtOÈåðSíêıçê½æ¶ûAܽx¦Äê½ãyâX^btÌFlÉúäç\µã°Ü·B
±ê©ç©ªàæNÌâYðH¢×·ÌÅÍÈAãÖâ¹édªÅ«éæ¤É¤èsðÏ޶ŷB
¡ãÆàäw±AäÚ£Ìöðæ뵨è¢\µã°Ü·B


êlÅQÁµ½ÌÅBêÈ©Á½öÜ®ÌÊ^ð¡cÛq¶åwæèÁĸ«Üµ½B
åÏ·©¢äS¢ð¸ÕµA½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
QOPQ^T^PX`QS@AJåAíÈwï(American Urology Association)Report
2012N519ú`24úÜÅJóê½AUAÉQÁµÄ«Üµ½B
¡ñAAg^Æ¢¤AAJìÌssÅJóêܵ½B
ïêÌ·®»ÎÉÍACNNÆ¢¤TVÌ{ÐâARJR[Ì{ÐAÀÑÉA¹Ý³ê½¨ÙÈǪ èÜ·B
ú{©çAòs@Åй12©ç14ÔÙÇ©©éñíÉ¢êÅ·ªA¢E©çåAíÈãªWÜèÛwïªJóêܵ½B




̯wæÌ{XÅAsì³öÌFlÌNatasha³öÆ@ú{HXgÉÄ
ÜÆß
¡ñAtlantaÅAUAªJóêܵ½B
¡ñAüÇ2NÚ̪æ¶âAåw@¶ÌàCæ¶A¡ºæ¶ÈÇá¢æ¶ûà½QÁ³êܵ½B
ÖAa@©çÍAéåwçtãÃZ^[̬æ¶Acæ¶AMåwãÃZ^[²qÌéسöA_J涪QÁ³êܵ½B
çtåw©çàNÆä×ÄQÁ³êéæ¶âA誦īܵ½B
±ê©çàAåw©ç½ÌîñðMÅ«éæ¤ÉSª¯Ä¢«½¢Æv¢Ü·B
ܽAsÝÌÔAÕ°ðx¦Ä¢½¾¢½æ¶ûÉ´ÓðÌ׳¹Ä¢½¾«½¢Æ¶¶Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPQ^S^PQ@Da VinciVXeð±üµÜµ½
2012N2©çྺèpp{bg(da Vinci S)xÉæéO§BSEpðnßܵ½B
4©çÍà¾èppx@íÁZƵÄNÛ¯ÌtÎÛp®ÆÈèAÛ¯fÃƵÄsÁĢܷB
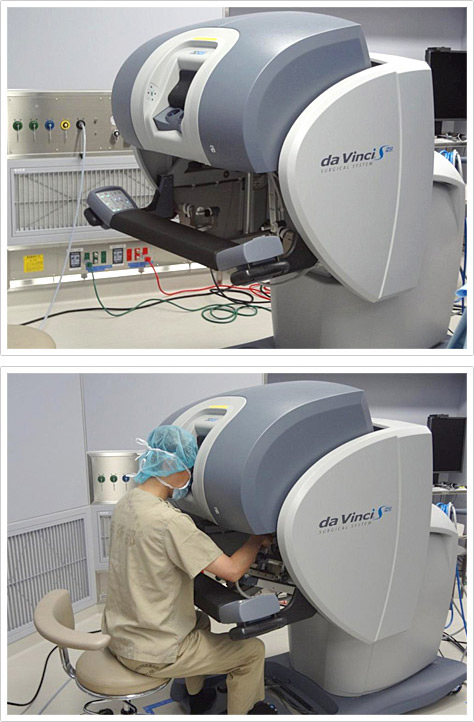
pÒpR\[(Surgeon's Console)FpÒÍR\[Ì3³æð©Èªç³ÒpJ[gÌ{bgA[Éæèt¯½eíççqðìµÄèpðs¢Ü·B

³ÒpJ[g(patient cart)F 4{Ì{bgA[(õwÇp1{ðÜß)Åèpðs¢Ü·B»Ì¼Aèª o¾èppççqð2{p¢ÄpÒÌèpðT|[gµÜ·B
QOPQ^Q^S@æ10ñçtåAí o¾vOQÁñ
¡NxüÇ¢½µÜµ½ìÅ·B
2012N24úɧ{êìsÉ éJohnson and JohnsonÌ{Åsíê½æ10ñçtåAí o¾vOÉQÁµÄ«Üµ½ÌŲñµÜ·B
¡{æ¶Aéåw¿ÎãÃZ^[ÌrØ液w±ÌàÆA o¾èpÌg[jOðsÁīܵ½B
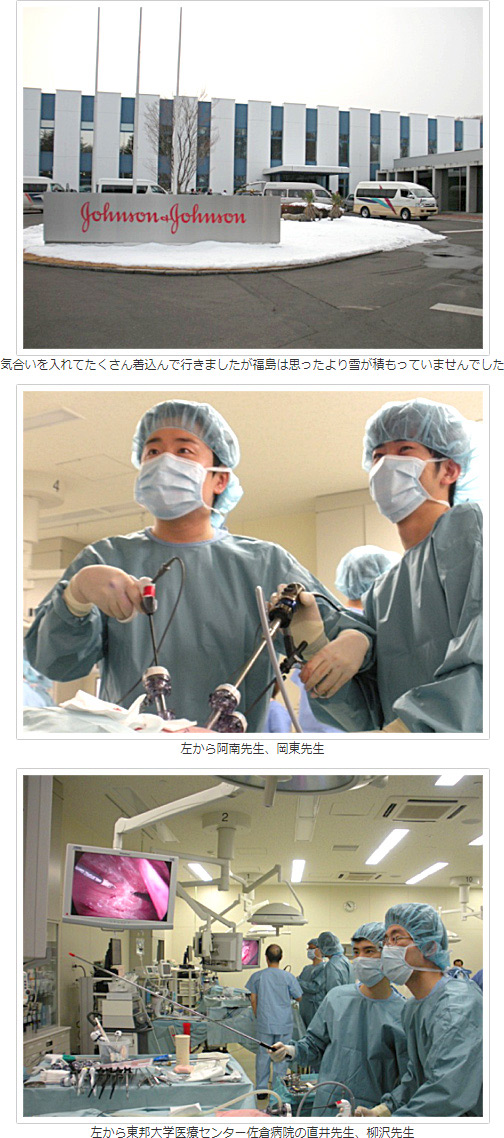
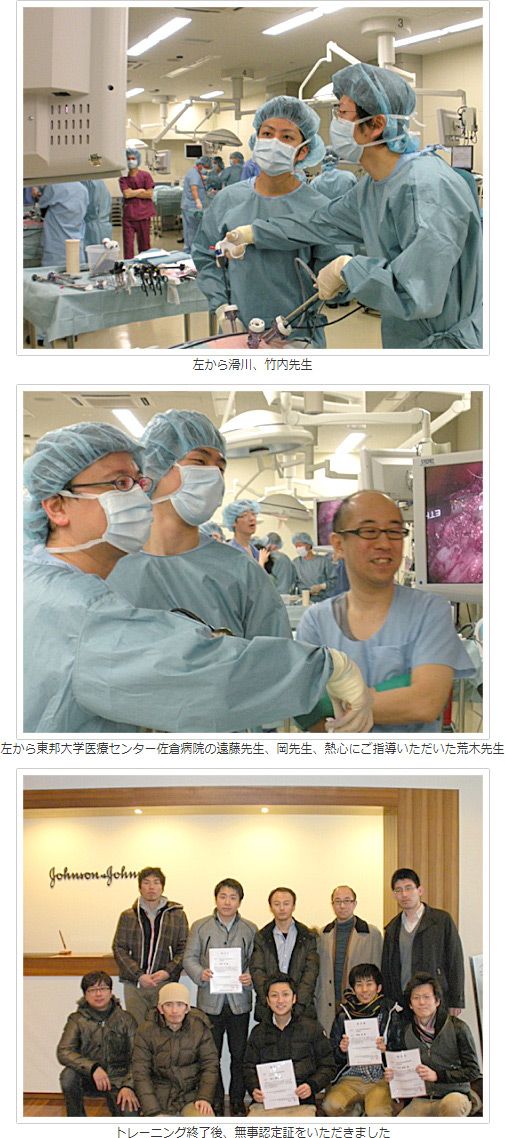
ÜÆß
ú æè o¾Ìèpɧ¿ï¢AèÍðµÄ¢½Âàèŵ½ªA¢´ÀÛÉ o¾ÌpÒƵÄççqðÂÆÈ©È©v¤æ¤ÉÍiÝܹñŵ½B
µ©µ±Ìæ¤Èf°çµ¢@ïð^¦Ä¢½¾«A¡ÜÅÈãÉèZ̤èsÉãñÅ¢«½¢ÆÓðV½ÉµÜµ½B
²w±¾³Á½æ¶ûA èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFì@j
QOPQ^P^QW@¯åï
µµ¢¦³ª±Aæ26ñçtåAíȯåïwpWïªJóêܵ½B
ïêàÅÍÕ°E¤¬ÊÌ\E¢_ªsíêܵ½ªA»ÌÔðDÁÄAæ¶ų̂Ê^ðBç¹Ä¢½¾«Üµ½B

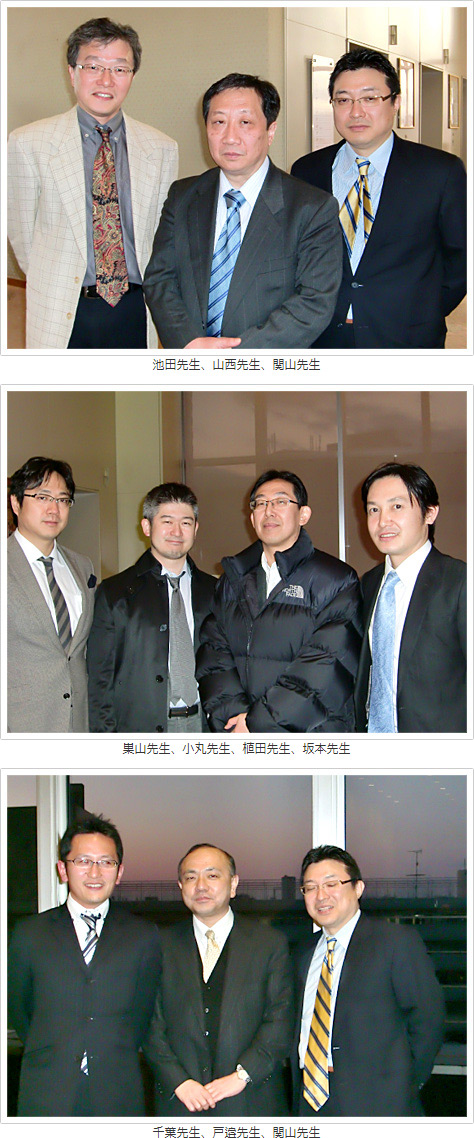

¡ñÌwp§ãÜÍz{æ¶ÆàC涪óܳêܵ½B

ìÑÌ|[YII
z{æ¶AàCæ¶A¨ßÅƤ²´¢Ü·I
Q½¾µ¢AõBeɶĺ³Á½æ¶ûA èªÆ¤²´¢Üµ½B
úïêàÅT|[gµÄ¢½¾¢½ûXÉàA±ÌêðØèÄäç\µã°Ü·B
QOPQ^P^QP@æPQñÖzÆà¤ï åw RãïÙ
ݼêÌ~éæ¤È¦¢AæPQñÖzƪñ¤ïÉåw@¶Ì¡ºæ¶ÆQÁµÄ«Üµ½B
wïꪡNÍåwàÅ èA\ÌOÉAïêÌ»ÎÌãiÉ éAsñÌÅ«é[XuÁµG¢©éªvÉsÁīܵ½B


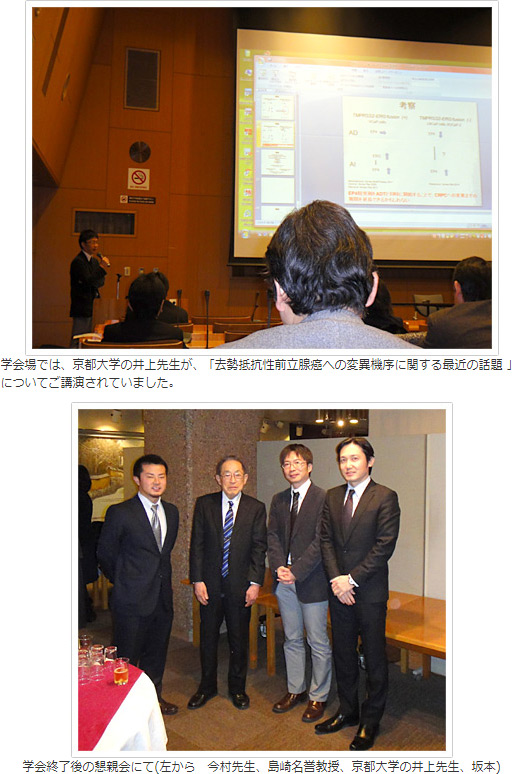
ÜÆß
¡ñAÖzÆà¤ïªåwÌwàÅJ©êܵ½B
åÈOàA½Ì{Ý©çæ¶ûªQÁ³êĢܵ½B
\ðʵÄA¡AãÍA¢ãSequenceÉ嫬êÄ¢é±ÆðÀ´µÜµ½B
¡ãA@ïðÝÄAçtåÅàAÕ°Ì©çÌâ`q»ðÍÉ¢ãSequencerðp¢½ðÍðsÈÁÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
ܽAsåwÌäãæ¶Ì²uÅÍAåw@¶A¢ãÉnéO§Bà̤ð²\ÉÈçêĢܵ½B
·Nó¯pªêéA¬êÌ é¤Ìdv«ðÀ´µÜµ½B
±ê©çAçtåÌåw@ࢢ¤ªMÅ«éæ¤ÉãñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^PP^RO@ú{åAíà¾wïÜóÜñ
±ñÉ¿ÍAºÅ·B
1130ú`122úÉsÅæ25ñú{åAíà¾wïªJóêAuSurgical navigation using three-dimensional computed tomography images fused intraoperatively with live video.vÆ¢¤èÚÅÅwïÜð¸ªÅ«Üµ½ÌÅA²ñ¢½µÜ·B
±ÌÜÍAÂlÌwÍÌÝÅóܵ½ÜÅ͵ÄÈAéåw¿ÎãÃZ^[[JKj³öAçtåwHw¤ÈÜ\Cj³öA»µÄsìqF³ö̲¦ÍÉæ踪o½Üƾ¦Ü·B
±ÌêðØèÄúäç\µã°Ü·B
e³öÍà¿ëṉ̃ÆADGÈæyûÌlÉA¢Â©ÍãyÉÜðóܳ¹Ä °çêélÈAå«È(̾¯ÅÍÈ)æyÉÈêélA¸iµÄܢ轢Æv¢Ü·B




¶ÓFº@aF
QOPP^PP^QQ@ïDG|X^[ÜóÜñ
¡NxüÇvµÜµ½ªÅ·B
T[tBÅoêµ½èàµÄ¢Ü·B
2011N1020(Ø)`22(y)Éæ76ñú{åAíÈwï瑱lÅJóêAu@ɨ¯é´«AhXeÇpãÌ~³ò~ÉÖ·éÕ°I¢-Aldosteronoma Resolution ScoreÌOØ-vÆ¢¤èÅDG|X^[Ü𢽾±ÆªÅ«Üµ½ÌÅAäñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
·NÏÝã°Ä«½Õ°f[^ª Áı»ÌóÜÅ èAæyûÉÍåϴӵĨèÜ·B
ÁÉÌ\Ìo±Ì½ßÉÆl^ðñµÄº³Á½àCæ¶ÉÍ´ÓµÄ൫êܹñB
{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
±ê©çÍ©çe[}ðßÄ\µÄ¢«½¢Æv¢Ü·I¡ãÆàæ뵨袵ܷB
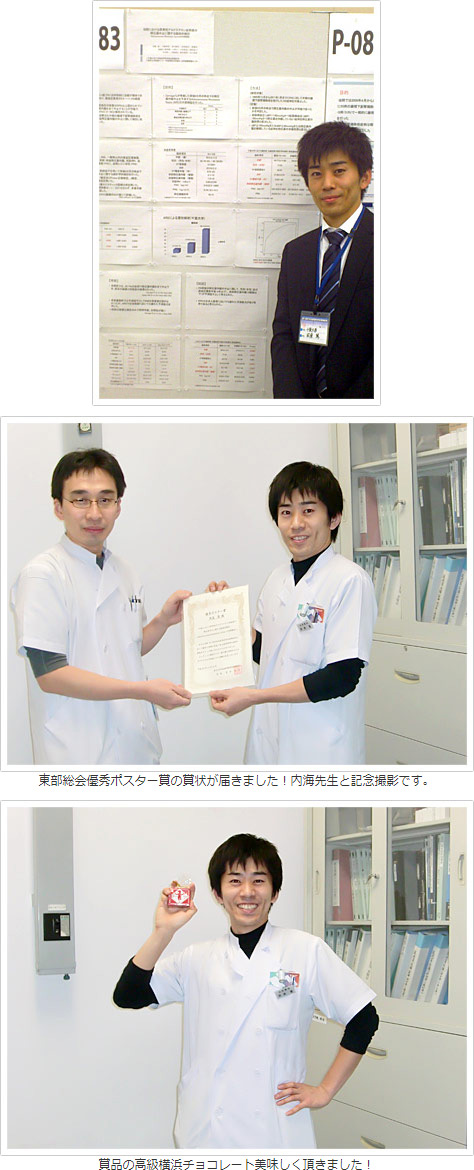
¶ÓFª@Ä
QOPP^PP^PS@University of South California a@©w
SBURªXxKXÅI¹ãAT[XxOÉ éUSCÉa@©wÉsÁīܵ½B
©wÍA»ÝA»n̳öƵÄC³êÄ¢éºæ¶É¨è¢³¹Ä¢½¾«Aåw@¶Ì¡ºæ¶Æz{æ¶Æ¤ÉAa@©wð³¹Ä¢½¾«Üµ½B
USCÌåAíÈÍA_r`ÌIyÅ¢EIÉL¼ÈInderbir@Gill涪ChairmanƵÄÝгêÄ¢é¢íäéTop InstituteÅ·B
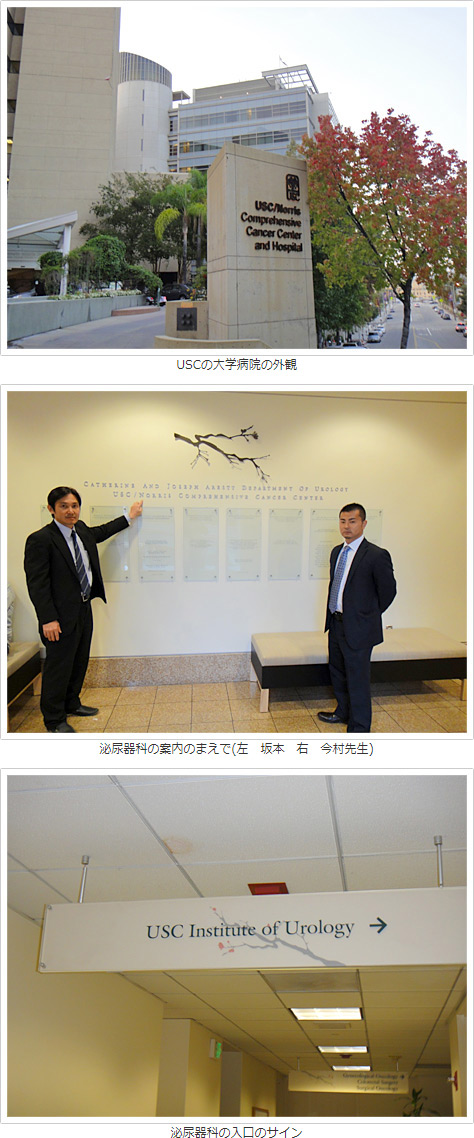

ãÇàÌi@Wfg©çX^btAéÈǽÌûXªZµ»¤É¢Ä¢Üµ½B
ãÇÅR[q[ð²yÉÈèܵ½B

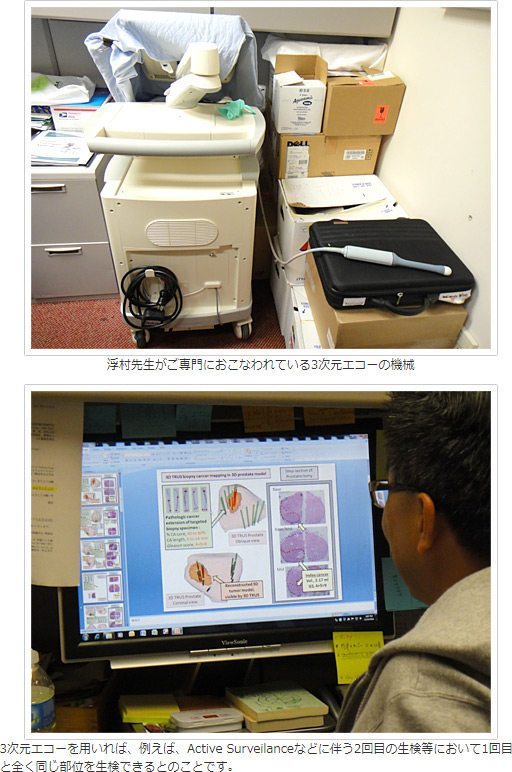

Gillæ¶ÍAcOȪçhoCÉo£ÅsÝŵ½ªAGillæ¶Ì³öºð²Äࢽ¾«Üµ½B
²Ìæ¤ÉÆÁÄàLA®©çÍALAhW[YÌX^WAª©¦éÅÌP[Vŵ½B
(¶©ç@¡ºæ¶Aºæ¶Az{æ¶)
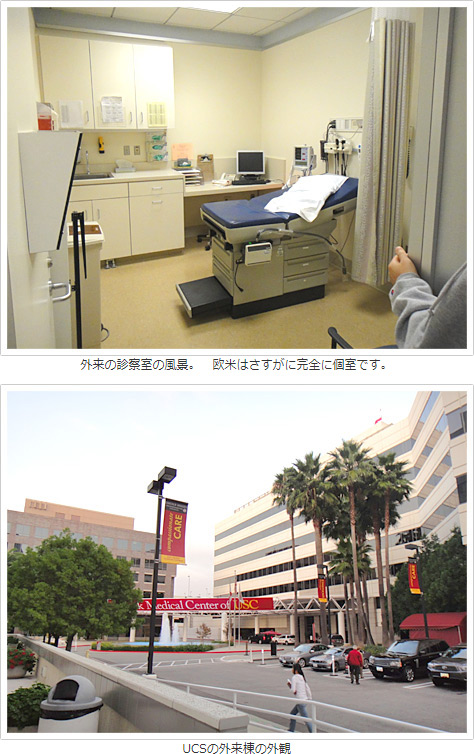

©wI¹ãA¢EÅêÔå«Èbgn[o[ÌMarina Del ReyÉ éXgÉAêÄsÁÄ¢½¾«Üµ½B
ñíÉ¿àiFàf°çµAv¢oÉ̱éêúÆÈèܵ½B
ÜÆß
±ÌxAºæ¶É¨Zµ¢¨è¢³¹Ä¢½¾«Aåw@¶Æ¤ÉUSCÌa@©wð³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ºæ¶ÍA3³GR[ÈÇðp¢½Focal@Therapyð²êåƳêĢܷB
«AFocal@Therapy̳çÈé±üÉæèA¢EIÉèpª¸éXüÉÈéÌÅÍÆ̨bðf¢Üµ½B
³Ò³ñÉÆÁÄIðª¦é㪷®»±ÜÅÄ¢éæ¤ÈóÛðó¯Üµ½B
USCÍAAJÅàgbvxÌa@Å èAWfgAtF[ÈÇÍAµ¢£ð¿²¢Ä|WVð¾Ä¢éæ¤Åµ½B
ܽAúAAUAÌè÷تÚOÅ èAºæ¶ÉàAäXÉྡྷ¢½¾¢Ä¢éAhoCÉ¢½Gillæ¶©ç ¢èÍǤÈÁÄ¢é £ÆÌÛdbª èܵ½B
âÍèA¢EDZɢÁÄàåAíÈÌiͯ¶¾Æv¢Üµ½B
a@©wÍAú{ÆÙÈé_ª½ èAêÂêªñíÉVNŵ½B
{ÉA¨Zµ¢Aºæ¶ èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^PP^PO`PP^PR@SBUR(Society for Basic Urologic Research) in Las Vegas
2011N1110ú(à)`13ú(ú)ÉLas VegasÅJóê½SBUR(Society for Basic Urologic Research)É¡ºÆz{æ¶Aâ{æ¶ÆQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
ܽA»ÌOãÉLos AngelesÉ৿ñèA»ÝUCLAɯw³êÄ¢éãæ¶Éà¨ï¢µÄ«Üµ½B

³ÄAÌSÌwïÅ·ªAlIªMÂLas VegasÌHard Rock HotelÉÄJóêܵ½B
zeàÉÍà¿ëñJWmà èARockª¬êAêuwïɽµÍCðYêĵܢ»¤Å·ªA|X^[ZbVÉÆz{涪èðoµAL¼Èæ¶ûÉRgâAhoCX𢽾±ÆªÅ«Üµ½B

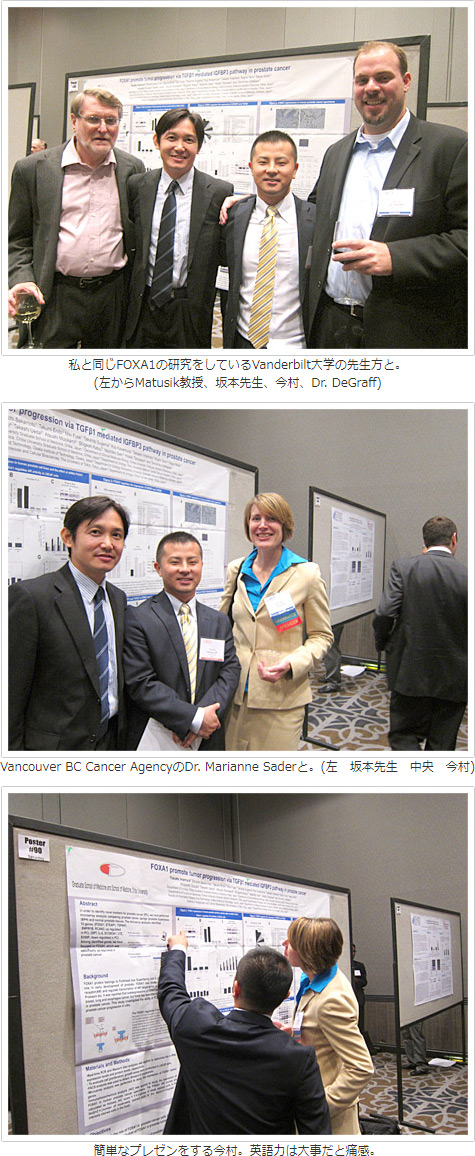

ÜÆß
SBURÅÍAUAÈÇÆÍáÁÄKͪ Üèå« èܹñªAä¼Èæ¶ûÆCyÉbªÅ«A©ªÌ¤É¢ÄRgâAhoCXðàç¦é«ª èAñíÉLÓ`ŵ½B
_¶ÌreviewerÉÈéÂ\«Ì élÉ©ÄàçÁ½ÌÍwïÉQÁµ½å«ÈÓ`ÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B
ܽA¯w̼åwÌú{lÌæ¶ûÉà¨ï¢µÄA¢ë¢ëÈb𨷫·é±ÆàÅ«AÆÄàhÉÈèܵ½B
v[ðͶßpêÍÍKvsÂÅ éÆÉ´µAܽúX¤àæ£ë¤Æv¢Üµ½B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^PP^R@æ6ñÃìÛ}\
Gg[µÄ¢½2011N3̲q©úN}\A2011N4Ì©·Ýª¤ç}\ªkÐÌe¿Å~ÉÈèAvµÔèÌt}\QÁÆÈèܵ½B
¡ñÍOÉèÝð\ªÉūĢȢÅÌQÁÆÈÁĵܵ½B
rÜÅÍärI²Å4ÔÈàÅè«êéy[XðۿȪçyµêܵ½B
ƱëªA36kmtßÅ«ªÂÁĵܢssÂ\ÆÈèܵ½B
36`39kmÜÅk10ªãÅà¢Ä¢é¤¿ÉñµÄ«½ÌÅA39km`jOðÄJµA»ÌÜÜS[ÜÅèØêܵ½B
¡ñÍ4ÔðØé±ÆªÅ«¸cOŵ½ªA40kmÈ~ÌÔÍßÅZÅ Á½±ÆÈÇAvXÉÂȪé¢Â©Ìûnà èܵ½B
PD¼O1öxÅà éöxèñÅ¢êλêÈèÌÊÍc¹éB
QDäÁèÅà·ÔA·£ÌûKªÓOÆøÊIB
RD«ªÂÁÄàÓOÆñ·éà̾B
SDäÆèÌ éy[XÅéÆAyµñÅêéB
ñÍ2012N415úÌ©·Ýª¤ç}\ÉGg[ðl¦Ä¢Ü·ªA±êçðQlÉyµõµ½¢Æv¢Ü·B

¶ÓFsì@qF
QOPP^X^PO@T[tB
7`8ÉçtååÃÌwïÈÇà èAvµÔèÉåAíÈT[tBÌo[ÅTÌÐLCÝÉsÁīܵ½B
¡ñAV½É¤Cã̪æ¶A»µÄAnæãÃAg©çAÃì³ñÆAغ³ñªQÁ³êܵ½B
ßÍAgÌ`ª¡êÂÅAââêJµÄ¢élqŵ½ªAr©çÍAÝȲqð©ñÅgɤÜæÁĢܵ½B
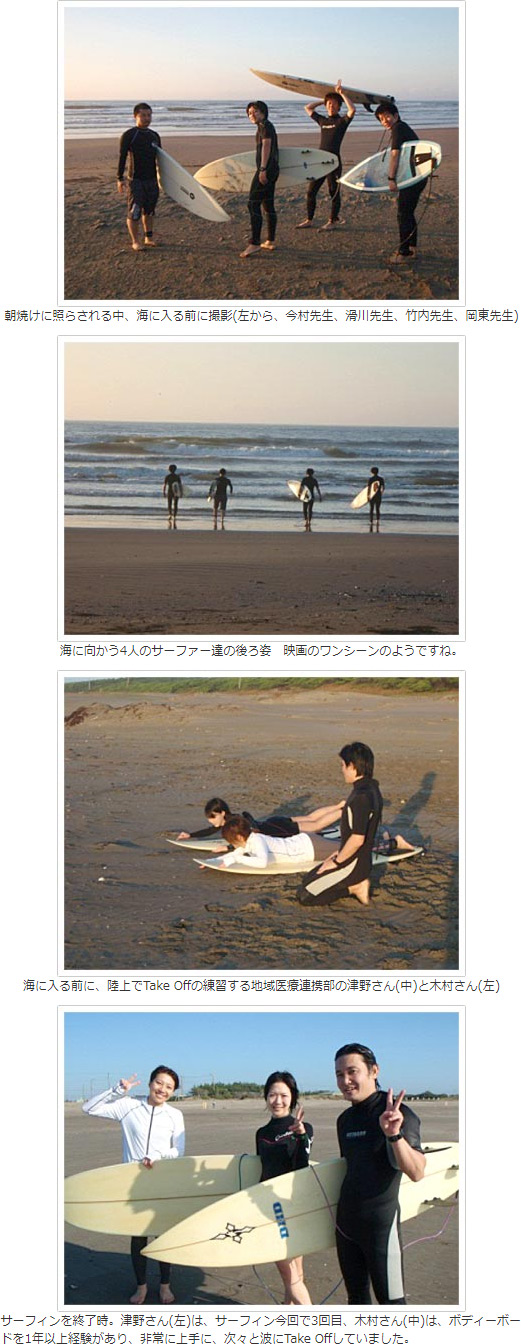
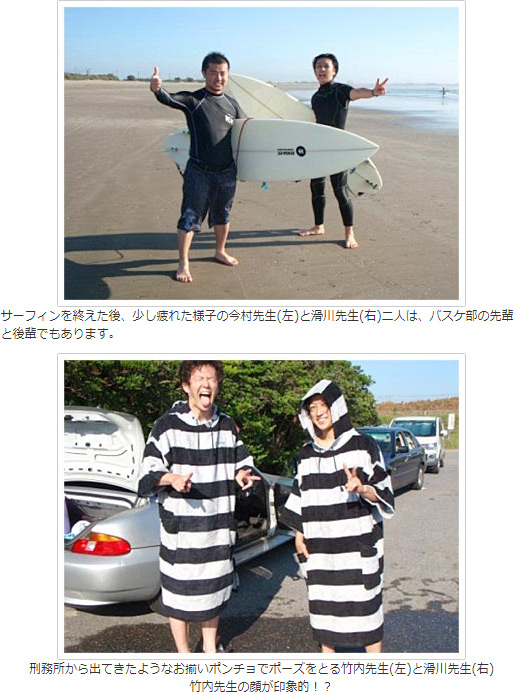
ÜÆß
¡ñA½ÌãÇÌæ¶ûAyÑAnæãÃAg©çàQÁ¢½¾«Üµ½B
ÄÌ©ÌCÉAú ÌXgX©çàðú³êéuÔŵ½B
ÅßAwïÈÇàdÈèAÈ©È©s@ïª èܹñŵ½ªAvµÔèÉWÜèAyµ¢ÐÆðß²µÜµ½B
±ê©çàAOnÆOffð¤Üg¢ª¯ÄãñÅ¢«½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^W^QV@ú{AHÎÇwï@æ21ñwpWï@Vol.3@`óÜñ`
826ú(à)E27ú(y)ÉJóê½ú{AHÎÇwï@æ21ñwpWïÉÄÈ@â{@Mê涪îbå§ãÜðóܳêܵ½B

QOPP^W^QU@ú{AHÎÇwïæ21ñwpWï@Vol 2
wïÌæ¶ûÌ\îÉÅ_ð ÄÄPick Up µÄÝܵ½B



QOPP^W^QU@ú{AHÎÇwïæ21ñwpWï
2011N826ú(à)E27ú(y)£bZÛïcêɨ¢Äú{AHÎÇwïæ21ñwpWïðJõܵ½B
ú{åkÐãɨ¯éeíCxgÌ©lÈÇà èܵ½ªAÖWÌæ¶û©çÌ·©¢²w±E²xÉæè³I¦é±ÆªÅ«Üµ½B
{wpåïÌvOâ²uàeÉ«ܵÄÍAURL: http://www.congre.co.jp/jsur2011/program.htmlÉ´^WðfÚµÄ èÜ·ÌÅA²»¡Ì éûͲº³¢B

QOPP^W^U@Urology Expert Forum in ÂX ËÔ½ÕèI
8Ì{̢ȩAÂXÉÄAOOåwÌåAíȪå²ÌUrology Expert ForumÉQÁµÜµ½B
àÆàÆAºa59N²Ì¯ú̳öÌæ¶ûªìçê½wïÅAçtåÈOÉÍAå²ÌOOåwðͶßA_ËåwAåªåwA¹}AiãÈåwA¡cÛ¯q¶åw©ç½Ìæ¶ûªQÁ³êܵ½B
¡ñAËÔ½ÕèÉí¹ÄÌJÃÆ¢¤±ÆÅA©çéÜÅwïA»µÄAÕèÌßÉ
Ö¦ÄAé`ËÔ½ÕèÉQÁ·éÆ¢¤ÆÄàg«IhÈÍ©ç¢ð²õ¢½¾«Üµ½B
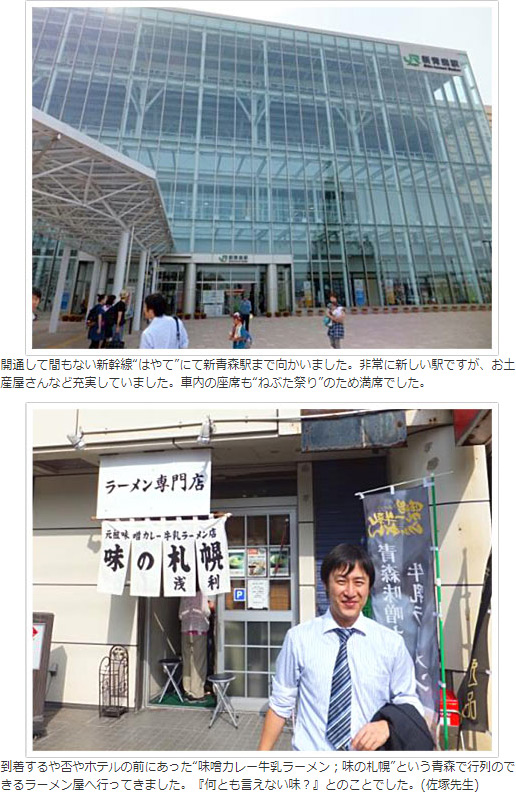
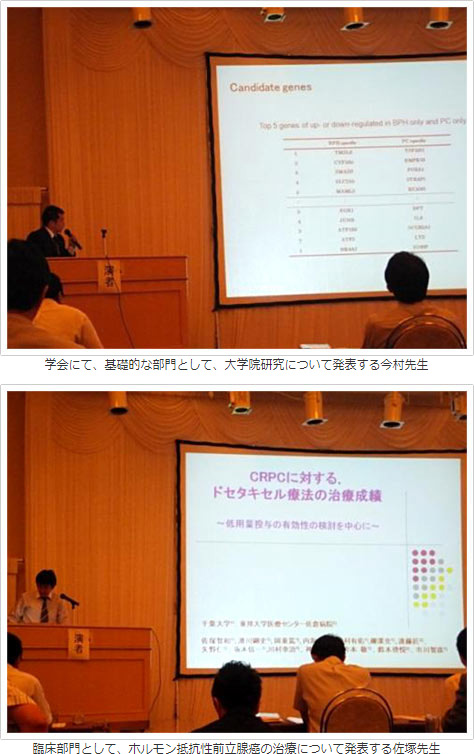

ÜÆß
ÄÌñíÉ¢GßÉAÆÄàÁµß²µâ·¢ÂXÌwïÉQÁ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
wïÅÍA½ÌáèÌæ¶ûªñíÉxÌ¢ä\ð³êĢܵ½B
\ÌÝÈç¸AOOåwÌæ¶û̲ÄàÅAÈÌãtÍAßÄgËÔ½ÕèŵËé!!hÆ¢¤MdÈo±ð³¹Ä¢½¾«Üµ½B
S©çAOOåwåAíÈÌåR@ͳöðͶßAãÇÌæ¶ûÉ´Óðq׳¹Ä¢½¾«½¶¶Ü·B
ܽA2NãÌçtåwªå²ÌÆ«Íæ£çËÎÆv¢Üµ½B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^V^QW@ï¡ð¶©µÄtbV !!@¾úà³CÉæ£ë¤!!
SÌãw¶ÌFlA¤CãÌFlA¢©ª¨ß²µÅ·©H
æ99ñú{åAíÈwïïA2011N421ú(Ø)`24ú(ú)¼Ã®ÛïcêÌÁÊéæuß´¹IåAíÈ̯\åAíÈãÌAt^[5F[Àµ½]Éà½ZÈúífÃÖÌMA`FWvÅuµ½ÛÌAC[WrfIÅ·B
³çEfÃE¤ÈÇÌƱÌÝÅÈAï¡ÌÔà«Á¿è±ÆÉæÁÄAæè[Àµ½¶ðé±ÆªÅ«évÆ¢¤A¾úðÚw·áèãtÉεÄbZ[Wðééæŵ½B
©îßÌöÅÌjOâåïÖÌQÁiAÅßÍ®OÅûK·é±Æª½¢½ßWÅÌjOÍÙÆñǵÈÈèܵ½ªAgbh~(¢íäéjO}V[)ÅÌjOª§qªÁÄ¢énX^[ÌC[WÆdÈé±Æ©ç»ÌlqðBeµ½rfIðAv[VrfIÉÜÆß½àÌÅ·B
dªRÏAåϾ!H
¢â¢âA»ñȱÆÍÈ¢A꾬¹Î·×ÄZbgB
Èéæ¤Éµ©ÈçÈ¢ÆAèØééÍÇ¢¾©±ÆB
ÉÆÁÄAjOâ[XÉQÁ·é±ÆÍASgÆàÉZbgµÄA½ÅàOü«ÉæègÞ´®ÍÉÈÁĢܷB
¸_IÉ¢çÂçÄàA÷ÌIÈÂç³Éä×êν¢µ½±ÆÍÈ¢IH
ú{̢ͳÀÌÂ\«ðéß½á¢ÍÉ©©ÁĢܷB
F³ñA·ª·ªµ¢¾ð¬µÄ¢Ü·©H
¶ÓFsì@qF
QOPP^V^QR@ú{AhW[wïæ30ñwpåïVol.2@`óÜñ`
2011N722ú(à)E23ú(y)ÉJóê½ú{AhW[wïæ30ñwpåïwïÜ@pê\åðÈâ{Mê涪óܵܵ½B

QOPP^V^QR@ú{AhW[wïæ30ñwpåï
2011N722ú(à)E23ú(y)ssZ^[ze()ɨ¢Äú{AhW[wïæ30ñwpåïðJõܵ½B
ú{åkÐãɨ¯éeíCxgÌ©lÈÇà èܵ½ªAÖWÌæ¶û©çÌ·©¢²w±E²xÉæè±ÌLO·×«æ30ñwpåïð¬÷ ÉI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
{wpåïÌvOâ²uàeÉ«ܵÄÍAURL:http://www.congre.co.jp/andrology30/É´^WðfÚµÄ èÜ·ÌÅA²»¡Ì éûͲº³¢B

QOPP^V^PT@æ12ñ@zÆà¤ï
æ12ñ@zÆà¤ïªÌlJÅJóêܵ½B
åw@¶Ì¡ºæ¶ÍAwO§BàVK}[J[̯èðÍxÆ¢¤^CgÉÄAú ©çåw@ŤµÄ¢éFOXA1Æ¢¤}CNACðÍ©ç¯èµ½`ÌðÍàeð\µÜµ½B
ÈñÆA¡ñªßÄÌîbÌwï\IIÆ¢¤±ÆÅA¡ºæ¶ÈãÉAw±³¯Ìâ{©gªÙ£Å°s«É×éHÆ¢¤\zOÌÔÉ©íêȪçwïÉQÁµÜµ½B


ÜÆß
ßÄÌ\É©©íç¸A\zÈãÉâÃÉ\ð±È·åw@¶Ì¡ºæ¶ªóÛIŵ½B
¿^ÉàAImɦĢܵ½B
¢©ÉAÌÆè±µêJIH¾Á½©æí©èܵ½B
±ê©çA¡ºæ¶àAàÌwïÍàÆæèA10ÉÍAJÌXxKXÅÌåAíÈîbwïSBURÅÌ\ªT¦Ä¢Ü·B
±ê©ç̳çÈ鬷ªñíÉyµÝÉv¢Üµ½B
aãæ¶A±ê©çà²w±æ뵨袢½µÜ·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^QU@åAíÈT[tB@Full Member
©êÅÐLCÝÉÈÌT[tBo[A¡ºæ¶(åw@¶)A|àæ¶(3NÚ)Aìæ¶(3NÚ)Aâ{(³)ÅT[tBÉsÁīܵ½B
SizeÍA¹`¨Æå«Aââµ¢RfBVÅAá±ñ¼A\zOÌnvjOÉ©íêĵܢܵ½B
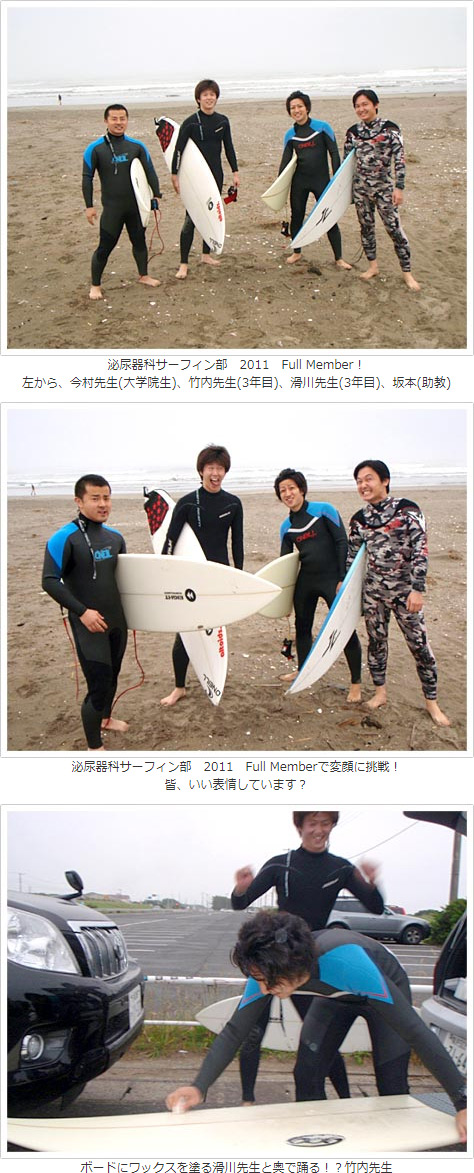

T[tBÌãA|àæ¶(E)ÍA{[hÌtBðÜèAâ{(¶)ÍA¨Å±ÉAUðÂÁĵܢܵ½B
±ê©çÍAÝȳñCðt¯Üµå¤B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^QT@ãå@àä¤
åãÅ¡±ÌïcÌúAåw@¶ã̶t(AÇÑåwãwòw³º)Å»åãåwåw@ ãwn¤È òwuÀ ¶ÌVXeòw@àäD³öðKâµÜµ½B
àäæ¶ÉÍA³ºÅÍAaûæ¶AÎcæ¶A¢gæ¶A¡ºæ¶AoOfBbV
©ç̯w¶ÌAhmedÈǽÌæ¶ûª¨¢bÉÈèܵ½B
ÌÇÑ̤ºÍA24ÔN©µç¤µÄ¢éÆ¢¤óÔÅA½¿ðÆÄàg©AÉAµµH²w±¢½¾«Üµ½B
àäæ¶ÍA¡NÌ826`27úÉ£ÅsíêéA³ºåÃÌAHÎÇwïæ21ñwpWïÉÄÁÊuuA~m_gX|[^[ƾ³FVX`AÇÆ««îáðSÉvð¨è¢³¹Ä¢½¾¢Ä¨èA²uɺ¤²¥AÆA¤¯¤Ì²kÈÇð©ËÄK⳹Ģ½¾«Üµ½B
OúI_©çAµ½Î©èÆ¢¤AñíɨZµ¢È©ÉàÖíç¸AΩçàðÜß½¤ÌbâA_¶É¢IJk³¹Ä¢½¾«A½ÌMdÈAhoCX𢽾«Üµ½B
u¤Æ^HvÆ¢¤bÉÈÁ½Æ«ÉAu¤É¨¯é^ÆÍêÊIɾíêÄ¢éæ¤ÈAà¢Ä¢ÄËR¨àðE¤æ¤ÈÞÌàÌÅÍÈ¢A¤ÌÅA©ªÅ¼àð§ÄÄÂ\«ðièñÅ¢«AÅIIÉ©RÉN±ÁÄ¢é»ÛðwæÅ´¶é±ÆªÅ«½ÉF¯·éà̾vƾíê½¾tªóÛIŵ½B
ÂäÉη驪ÌçȳðÉ´µÜµ½BBB
¡ãÆà²w±æ뵨è¢\µã°Ü·B
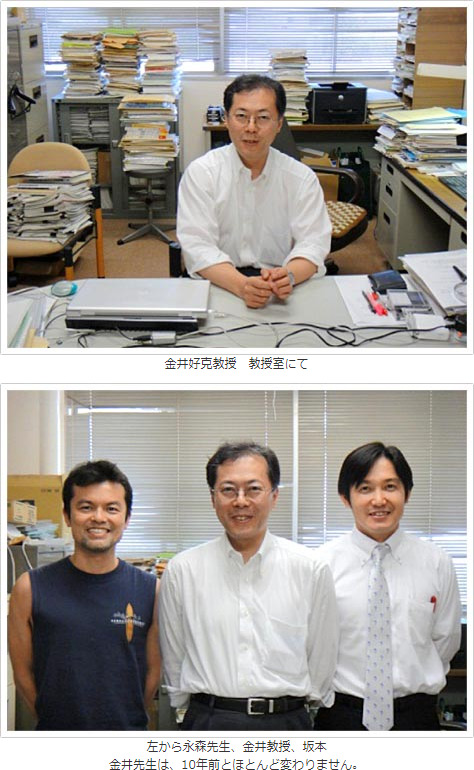
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^PW@à½ÆAHÎÌÂȪèH
çtsÈwÙÉÄAæ71ñ@`ÌÈwV|WEu`AÍlAæÌÔÏ»ÌÈwÆpvªJóêܵ½B
ÎÌ`É¢Äuð²Ë¢½¾«A¢ÂàÆââÙÈéÌæÅ·ªAÉ¡¼_³öA¼Ã®s§åwåAíÈÌæ¶ûA[Jæ¶AÎcæ¶A¡ºæ¶ç̲¦Íð¾ÄAÈñÆ©³É\ðI¦é±ÆªÅ«Üµ½B
¡ñAߥ̈wÆwÌwïÅ èASãÒÆá¤_©çc_³êÄ¢ÄAªÌhÉÈèܵ½B
wïêÅAà½Ì\¢É¢Ĥ³êÄ¢éåwÛ³{wÌcFêæ¶Ébµ©¯Ä¢½¾«AÎ\¢ÌJjYÉηé½ÌV½È_ð²ñ¢½¾«Üµ½B
cæ¶ÍAu¨[¢ARy[g[vÆ¢¤{ðoųêATVÈÇÅàæo³êÄ¢éæ¶Å·B
à½ÉÍAPDµ¸(Drop), QDñ](Rotation), RD·x(Heat)ªåØÅAñ]ÌXs[hâAÌpxª30xÅ é±ÆàåØÈæ¤Å·B
à½ÍAC^Aâ|gKÈÇ¢EÉ èA·×ÄôIÈ`óÅA¯¶à½ÍAñÂÆÈ¢»¤Å·B
_ÎÅÍA_̤ªÌàÅÍA30xÉX¢Ä¢ÄA37xÌ·xÆAKxÈ
¬ª èAà½Ì»¢ßöÆñíÉĢ黤ŷB
AHÎÅÍAV
E_ΪAÁÉà½Æ½\¢ðà¿Ü·ªA¨»çAÎÌ\¢ÌJjYÌqgÍAà½É éÌÅÍHÆv¢Üµ½B
൩µ½çttª30xHÆv¢Üµ½B
c涩çÍAV½È_ð²ñ¢½¾«A½É èªÆ¤²´¢Üµ½B
¡ãÌΤɶ©¹Ä¢¯½çÆv¢Ü·B

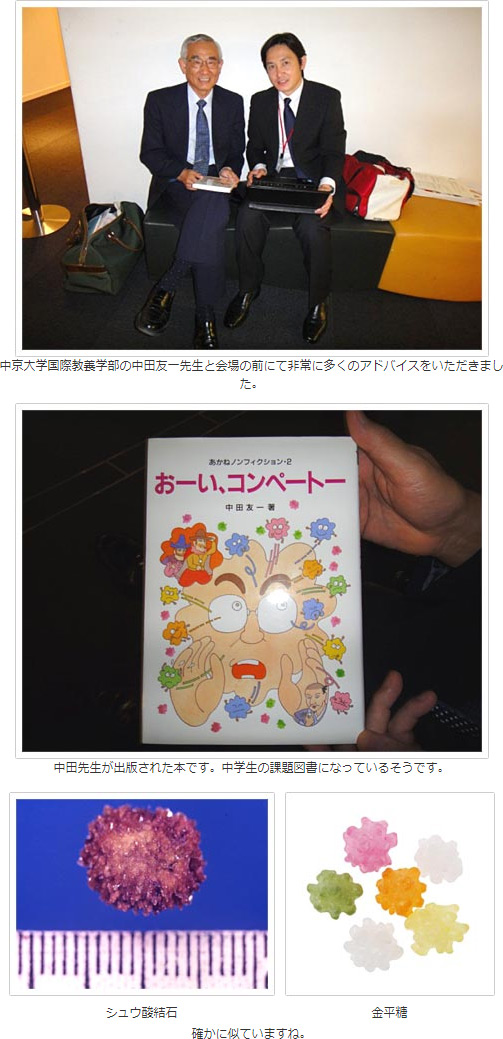
ÜÆß
¨wÆwêåÌæ¶ÆÌDiscussionÅÍAÜÁ½ÙÈéìÅÎÌJjYðÇy³êéÌÅñíÉQlÉÈèܵ½B
ܽA¡ÜÅCªt©È©Á½æ¤ÈAVµ¢pxÅÎÆ¢¤¾³ðÝé±ÆªÅ«½æ¤Év¢Ü·B
ÉÍAÊÌFieldÌwïÉQÁ·é±ÆÌÓ`ðÄF¯µÜµ½B
³ºÅÍA¡N(H23N)Ì826ú`27úÉ£bZÅæ21ñAHÎÇwïðåõܷB
äsÌ©êéæ¶ûAw¶³ñàA¥ñA²QÁæ뵨è¢\µã°Ü·B
cFêæ¶A¢ë¢ëÆ èªÆ¤²´¢Üµ½B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^PP@çtåAíÈWkï
çtåAíÈWk窱ze~}[ÅJóêܵ½B
ÍV°åwYÀa@AkÍú{ãÈåwçtka@A¼ÍÛ®a@AìÍTca@ðÜßA½Ìçt§àÌæ¶ûÉäQÁ¢½¾«AïÅÍAȲ¢_𢽾«Üµ½B
æ¶ų̂üÅA³ÉI¹·é±ÆªÅ«Üµ½B
ܽA¯å̽Ìæ¶ûÉvµÔèɨé±Æàūܵ½BÀçêĨèÜ·ªA§eïÌÊ^ðfÚ³¹Ä¢½¾«Ü·B
ñíɨZµ¢ÉàÖíç¸A²QÁA½É èªÆ¤²´¢Üµ½B

¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^PO@åAíÈ©Uï
åAíÈ©UïªçtÅsíêܵ½B
úíÕ°ÅZµ¢A¤CãÌæ¶ûÉûÍéÎéQÁ¢½¾«Üµ½B
Èåwsìa@ÌYæ¶(ãt2NÚ)ðSÉAVhÌJRa@ÌXæ¶(1NÚ)A¡lJÐa@Ìcæ¶(1NÚ)AD´ãÃZ^[Ìäæ¶(1NÚ)AXÉÍAYæ¶ÌOr[ÌãyÅà éAãw6N¶ÌàâNÆàNàì¯Â¯Äêܵ½B
¨ülÅAêïAñïƽÌæ¶ÉQÁ¢½¾«åÏ·èãªèܵ½B
åAíÈÌש¢à¾Í³Ä¨«AÈÆàAsì³öðSƵÄAAbgz[ÈãÇ̵ÍC¾¯Å઩ÁÄà禽ÌÅÍÆv¢Üµ½B
½¿àá¢æ¶ûÆGꤾ¯ÅA½ÌGlM[ðàçÁ½CªµÜµ½B
çtåÌåAíÈƵÄàA¡ãAÇñÇñá¢æ¶ûÌôÌêðñÅ«éæ¤ÉúXw͵Ģ«½¢Æv¢Ü·B
QÁ¢½¾¢½æ¶ûAw¶³ñA±ê©çàæ뵨袵ܷB
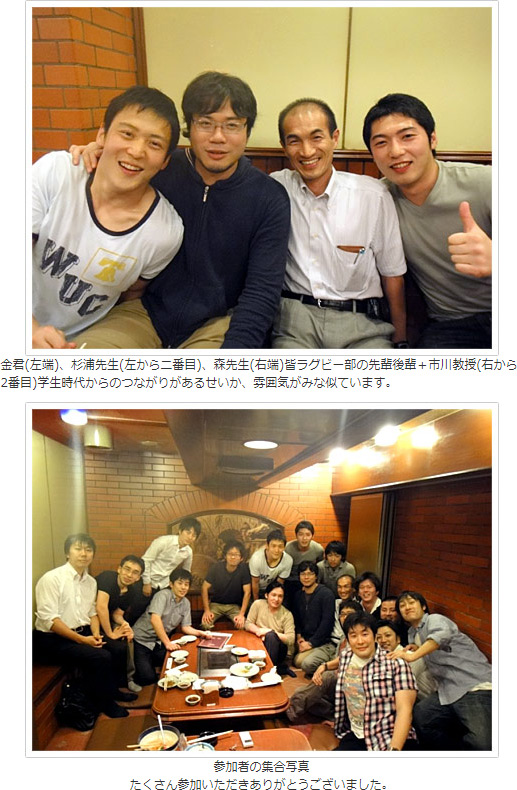
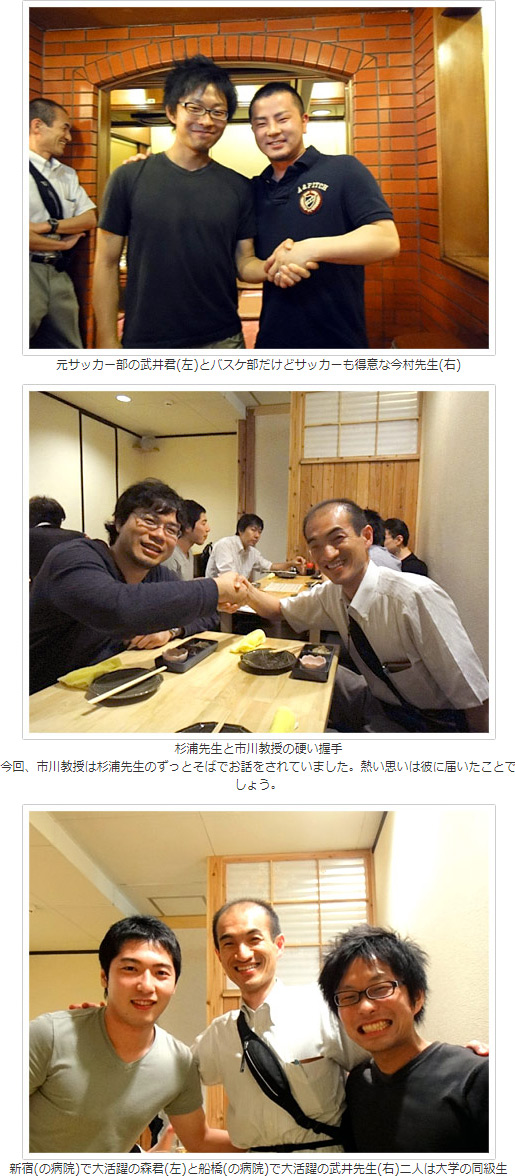
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^X@åAíÈT[tB@New Member!!@a¶
©êÅAÐLCÝÉT[tBÉsÁīܵ½BSizeÍA¹A³ÌÅÌConditionŵ½B
¡ñÍAÈÌxbhTChðñÁÄ¢éAäÏN(5N¶)ÆClinical ClerkshipÅñÁÄ¢éàâN(6N¶)ÆêÉCÉ¢Áīܵ½B
ñlÆàåwÅÍOr[ÅôµÄ¢Ü·B
àâNÍAnCÈÇÅAT[tBo±ª·ÅÉ èA¡ñêÉsÌÍ2ñÚÅ·ªAñíÉÈPÉgÉÌéÌóÛIŵ½B
êûAäÏNÍA¡ñßÄÅ·ªA10ñÈãATake Offɬ÷µÄ¢ÄAvèmêÈ¢PotentialIHð´¶Üµ½B
ãw¶àAwNÉÈéÆA×Aa@ÀKÆÅú Zµ¢Å·ªAÉÍA§²«ÆµÄAܽs«Üµå¤B

¶ÓFâ{@Mê
QOPP^U^V@AUA report 2011 Washington DC
5/19`5/24ÜÅAVgDCÉÄAAJåAíÈwï(AUA)ªJóêܵ½B
¡NÍAàC涪AAUA-JUA Exchange ProgramðóܳêQÁ³êAâ{ÍA¡NÌ10/1`2ÉJóêéBest of AUA in JapanÌÎZbVÌæÞðËÄQÁµÜµ½B
úÉSBURÆ¢¤îbÌåAíÈwïªJóêA¢EÌåAíÈÌæ̤ð[h·éæ¶ûªQÁ³êĢܵ½B
ÁÉAbèÌO§BàÌVòMDV-3100ÌJÉgíê½Charles Sawyeræ¶Ì\âAßNA̲ª·®êÈ©Á½è¼_³ö̯wæÌ{X¾Á½Coffeyæ¶É¨ï¢Å«½ÌªóÛIŵ½B
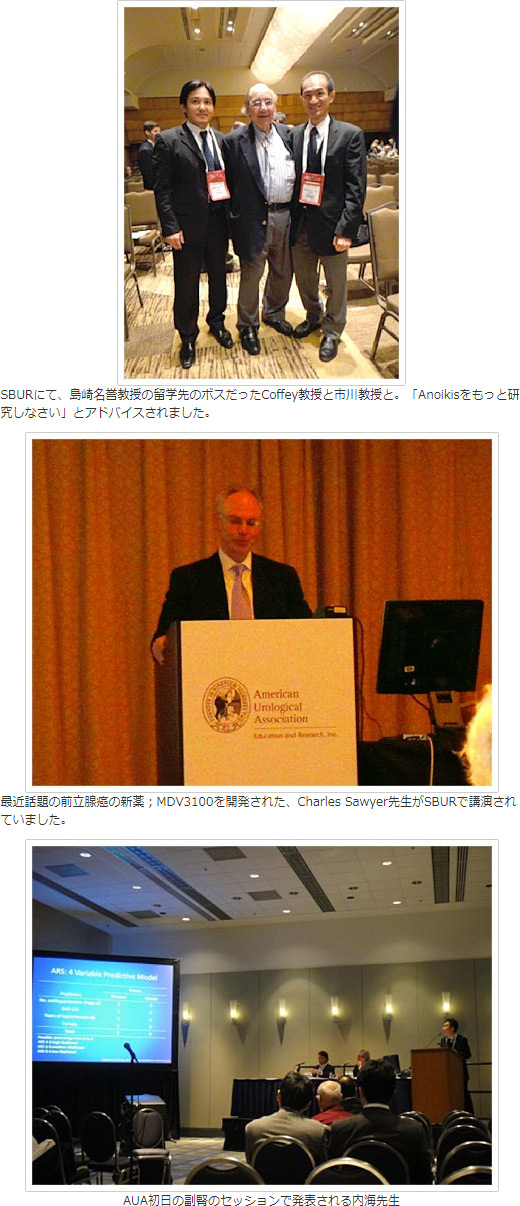

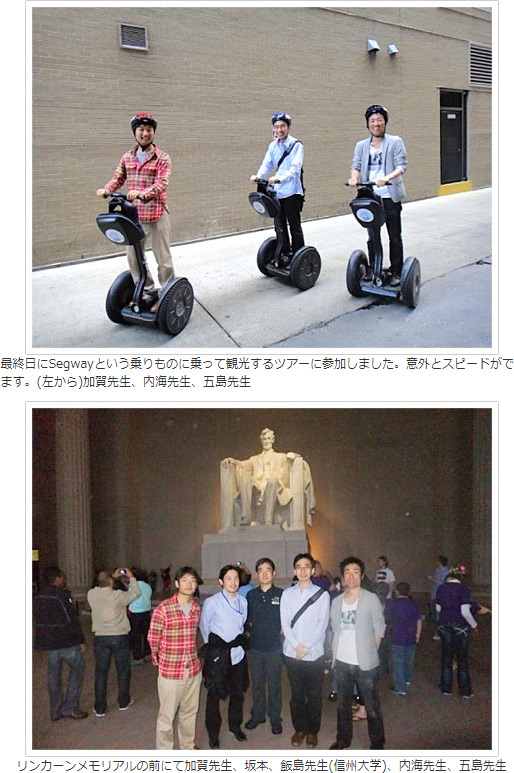
¡NÌAUAÍAxÌ¢½Ì\ÌÅàAO§BàÅÍAMartin Gleaveæ¶Ì{ɨçê½ARûåw̼{æ¶ÌMDV3100ÆClusterinjQÜ̹pÃ@ª(SUOÅóܳêĢܵ½)AÎÅÍA¼Ã®s§åw̪cæ¶Acûæ¶çÌÎ`¬Æ}Nt@[WÌÖAÉ¢ÄÌ\ÈǪóÛIŵ½B
SBURÅÍACoffeyæ¶AGetzenbergæ¶AChang æ¶ÈǽÌåAíÈðã\·éæ¶ûƨbµ·é@ïª èhÉÈèܵ½B
NÍAåw@¶Ì¡ºæ¶Az{æ¶AàCæ¶ðßA½Ìèªçtå©çàÊéæ¤Éãݽ¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^R^PO@Advancement in UrologyÉQÁµÄ
217ú`19úÜÅnCÌCLLÅAUAÆJUAÌæêñð¬vOƵÄAAdvancements in Urology 2011 an AUA/JUA SymposiumªJóêܵ½B
úÄ©çAåAíȳöAX^btÈÇv200lÙÇQÁ³êܵ½B
È©çAsì³öAìºutÆâ{ªQÁµÜµ½B
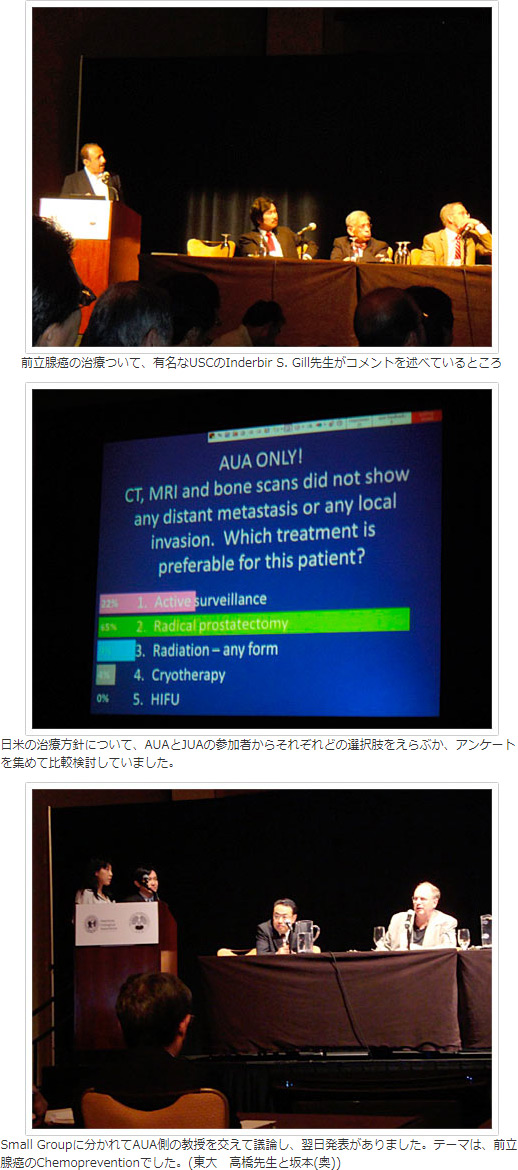

ÜÆß
¡ñAAUAÆJUA̯vOÌêÂƵÄAAdvancement in UrologyªAnCÅJóêܵ½B
ú{©çà¼Èæ¶ûªQÁ³êAAJ©çàAUSCÌInderbir S. Gillæ¶âAAUAÌSecretaryÌRobert C. Flaniganæ¶ÈǽÌL¼Èæ¶ûªQÁ³êܵ½B
ÊíÌåKÍÈÛwïÅÍA𬳹Ģ½¾@ïªÈ¢Å·ªA¡ñÌæ¤ÈärI¬³ÈïÅÍACyɨbð³¹Ä¢½¾«AñíÉhÉÈèܵ½B
±±NAúÄÌåAíÈwïÌð·vOª¦Ä¢Ü·ªA¡ãAXÉAAJÆú{Æ¢¤£ªßâÄéóÛðó¯Ü·B
çtåwåAíÈàæèÛIÈ´oð©È¯È¯êÎÆv¢Üµ½B
ñíÉZµ¢úíհƱðAsÝÌÔAx¦Ä¢½¾¢½æ¶ûÉS©ç´Óð\µã°½¢Æv¢Ü·B
¶ÓFâ{@Mê
QOPP^Q^PT@æ23ñåc´}\Ææ5ñÃìÛ}\
2008N1116úæ3ñÃìÛ}\ÅL^µ½t}\@p[\ixXg3Ô39ª(lbg)ÌXVðÚwµÄ2010N1123úÌæ23ñåc´}\Æ2011N123úæ5ñÃìÛ}\É`WµÜµ½B
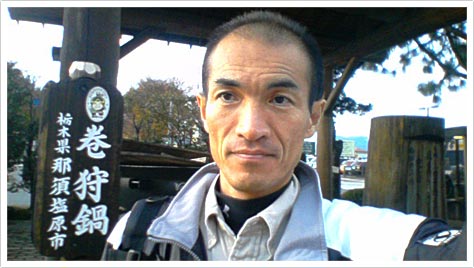
ÙÚSÌóÔÅQÁµ½åc´}\B
15kmÙÇÜÅͲqæêܵ½ªAoOÌHÌÊɸsµAXÉ Ì£èð©oB
25kmÜÅͽƩ3Ô30ªØèÌy[Xð۵Ģ½àÌÌA»êÈ~ÍêCÉXs[hàáºA30kmtßÅCªª«Èè¹Î½ÅqfB
§ÀÔ4ÔÅ̮̩ʵª§½¸A ¦È^CB
ß{´wOÅxWð¾ÁÄBeµ½Ê^Å·B

¶ÓFsì@qF
QOPP^Q^W@¨a¶úï
¨xÝÉAxܫȪç12¶ÜêÌų̂a¶úïðJõܵ½B

հɤÉÆtñ]Ìz{æ¶ÆLxÈm¯Æ¾é¢l¿ÅÝñÈðøÁ£ÁÄêéO³ñB
±ê©çÌ1Nª¨ñlÉÆÁÄf°çµ¢NÆÈèÜ·æ¤A¨Fè\µã°Ü·B
QOPP^P^QQ@¯åï
122úÉæ24ñçtåAíȯåïªJóêܵ½B
¯åÌæ¶ûªWÜèAú ÌÕ°E¤¬Êð\³êܵ½B
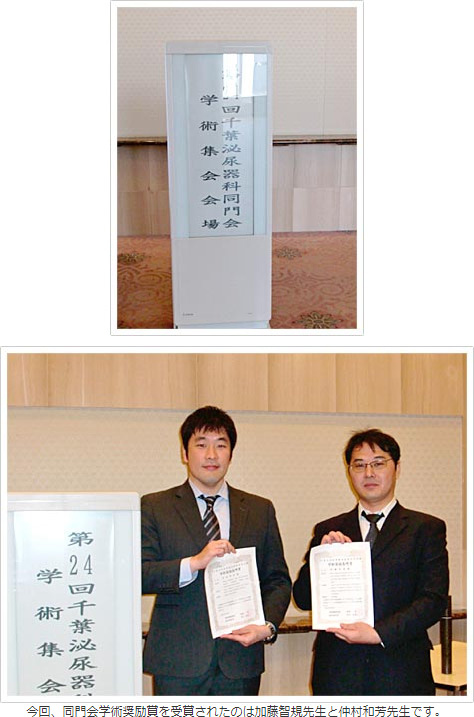
úÍQ½¾µ1úªß¬ÄµÜ¢AÈ©È©Ê^Beūܹñŵ½ªAóttßÅLb`µ½æ¶ûÅ·B

¨Zµ¢A²QÁ¢½¾«Üµ½æ¶û¨æêlŲ´¢Üµ½B
ܽAúÌïêX^btÌûðͶßA²¦Í¢½¾«Üµ½òRÌûXɱÌêð¨ØèµÄ´Ó\µã°Ü·B
èªÆ¤²´¢Üµ½B
QOPO^PQ^QW@åAíÈYNï
12{AåAíÈÌYNïªJ©êAåAíÈaEOÅìt³ñAcANüÇ\èÌcªWµÜµ½B
ܽ¨Zµ¢Aè¼_³öÉà²QÁ¢½¾«Üµ½B
cOȪç¼ÅQÁÅ«È©Á½ûà¢çÁµá¢Ü·ªAFÅêNÔðUèÔèȪçA¨¢µ¢¨¿Æ¨ðÅ·èãªèܵ½B
ܽAÙ¢åAíÈÊMÅͲ´¢Ü·ªA¨t«¢¢½¾«ÜµÄ èªÆ¤²´¢Üµ½B
NªFlÉÆÁÄf°çµ¢êNÆÈèÜ·æ¤AçtåwåAíÈw³ºõꯨFè\µã°Ü·B

QOPO^PQ^PS@ãÇÉĨa¶úï
N11Asì³ǫ̈a¶úïðJ¢Ä¢Ü·B
¨Zµ¢A¢Âà¨C¢º³é³öÖÌA³³â©È´ÓÌC¿Å·B
±ê©çÌêNªf°çµ¢êNÆÈèÜ·æ¤AÀ±èAãÇéꯨFè\µã°Ä¢Ü·B

QOPO^PP^QU@æPRñÖXg[}nre[V¤ï
çtåw¼çtLpXà¯â«ïÙÅAæPRñÖXg[}nre[V¤ïðJõܵ½B
ƾâ@BìÈÇúÌ^cSÄ𩪽¿ÌèÅs¤×åÏÅÍ èܵ½ªAåAíÈÌÅìt³ñB̦ÍàLèA³·ï¡ÉI¦éªoܵ½B
ä¦Í¢½¾«Üµ½ûXÉAú¨ç\µã°Ü·B


QOPO^PP^PT@wïo£@|bRÒ|
SIU(Societe International d'Urologie)Æ¢¤ÛwïÉQÁ³¹Ä¸«Üµ½B

¶©çºA[Jæ¶AÁêæ¶
rA@\âAHÏXÌcèªSÌwï¾Á½ÌÅ·ªAwïÅÌ×àeâ\àeÍÂlIÉ·¢Ä¾³¢B
ÆÉà©Éàóê½ÌªÈñÆubRv
F³ñAbRsÁ½±Æ èÜ·©H
»à»àbRÌ겶mŵ天H
±ñÈ@ïð¸©È¯êÎÈ©È©s@ïÍ èܹñæËB
»êÅÍAbRÅÌÊ^ð²ÐîµÜ·B
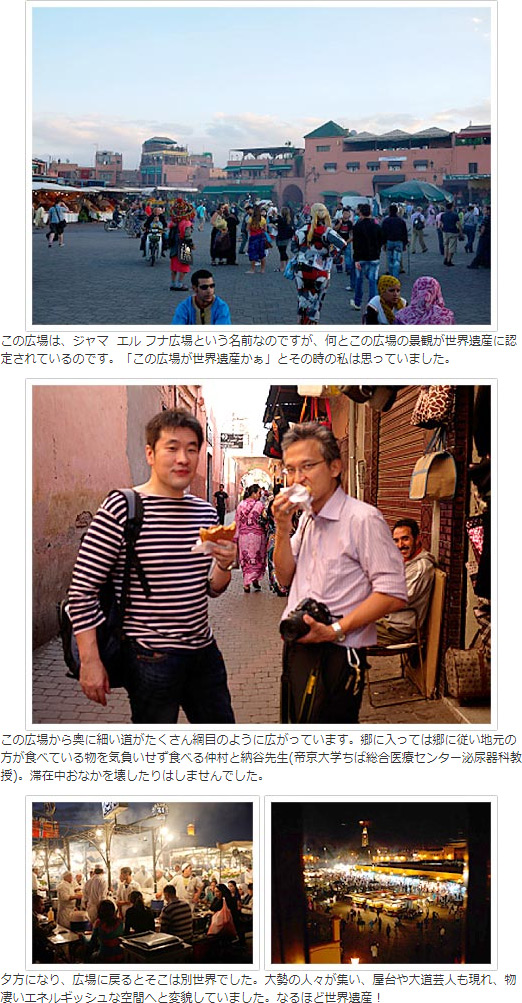
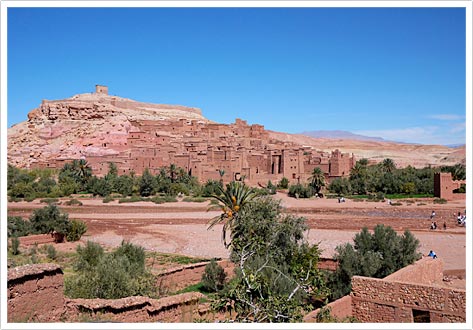
AgXR¬ðoÁĺèÄÆ1.5ÔüöxÌfRâÇ̹ð100km/hÅ3ÔöxÅ
«Üµ½B
Í\|©Á½Å·ªA[Jæ¶ÍQÄܵ½B
Áêæ¶ÍÔ¢µÄ¢Üµ½B
±±ÍA¢EâYuACgExEnbhDvB
±±ÍARÌRÉìçê½vÇÌlÈWÅ¡à3Æ°ªZñÅ¢éÌÅ·B
fæuArAÌXvuOfBG[^[vunivgvͱ±ÅBeªsíêĢܷB

bR¿ÆµÄA¶ªNXNXAEªT_Å·B
Ç¿çàÆÄਢµA¢Âà ÁÆ¢¤ÔÉ®HµÄ¢Üµ½B
»Ì¼ÉàA^WçàÆÄਢµ©Á½Å·B
ú{lÌûÉͤæ¤Év¢Ü·B
bRÅÌÛwïQÁÍ×ÉÈ龯ÅÈAåÏMdÈo±ÉÈèܵ½B
¶ÓFº@aF
ÁÊñe
SIU World Meeting on lower urinary tract dysfunction ÉQÁµÄ
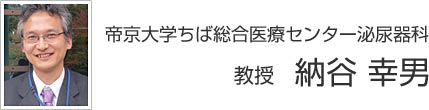
ÝȳñÍbRÉsÁ½±Æª èÜ·©H
ãLÌwïªbRÅJóêAºæ¶AÁêæ¶ÆÆàÉsÁīܵ½B
AtJA}PV
ÌånÍԢŷB
¨à¯¶ÔÅ·B
Ôƾ¦ÎîMÌÔÅ·B
lXÍÝñÈCª èAsêÍCɿĢܷB
Ô¢ånÅÆê½IWðiÁ½W
[XÍÆÄਢµ¢Å·B
CXÅ·ªA¿áñƵ½XÉs¯ÎA¨ðàùßÜ·B
tXêÆArAêªöpêÅ·ªApêàµÊ¶Ü·B
XÍ©]ÔÆ´`Å ÓêĢܷB
ÔÍ»ÌÈ©ðDÁÄÁÄ¢ÄANNVÌÅ·ªA·®ÉµêÜ·B
300kmð3Ô©¯ÄA^NV[ÅsÆAऻŷB
»Ì¬ÍA£¢Ä¢Ü·B
»±ÅH×½^WçÆbRT_ͨ¢µ©Á½Å·B
hÍ5¯Åê8000~ç¢AS[WXÅ·ªÆÄàÀ¢B
wïÌbªS èܹñªAAJf~bNÈbÍDZÅÅàÅ«Ü·B
åØȱÆÍA»nÌóCÉGêé±ÆÅ·B
wïÅ×µ½ ÆÍA§²«ªåØÅ·B
ÝȳñAêÉŽɢ¯È¢êÉ¿áñÆèðoµÄAwïÉs«Üµå¤B
QOPO^PP^V@å@Õ
çtåwãwÅå@ÕªJóêAulÌÌsvcWv ð©wµÄ«Üµ½B

¶ÓFâ{@Mê
QOPO^PO^QX@æ19ñ¬R[h[X
2007N5ÄåAíÈwïÅsíê½ñ5kmÌ[Xð«Á©¯Énß½jOB
ärIZ¢10kmÌL^ÅÍA2008N622úæ25ñx¢XCJ[h[XÅ44ª50b(lbg)ÌxXgL^ðoµÄÈA2009N628úæ26ñ¯[X45ª46bA2010N627úæ27ñ¯[X45ª8bÆàÍâL^ÌÀE©ÆvÁĢܵ½B
ƱëªA2010N1010úæ19ñ¬R[h[Xɨ¢ÄC·20xEÜVÆ¢¤DðÉàbÜêA43ª16b(lbg)Æ©ÈxXgð1ª30bàXVūܵ½(Ê^FS[ÜÅ ÆS[gtß)B
8E9ÌAR[ðT¦½Ô300kmjÌøÊÉæéàÌ©Æv¢ÂÂAܾܾNîÉts·éLÑµëª éà̾ÆäȪçÁ¢Ä¢Ü·B
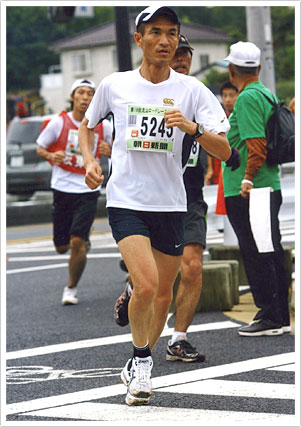
¶ÓFsì@qF
QOPO^PO^QU@©Uï
10{@ãw6N¶ðSÉåAíÈÌ©Uïðs¢Üµ½B
²Æ±Ì^Á½¾ÉàÖíç¸A½Ìw¶³ñÉQÁ¢½¾«A{É èªÆ¤²´¢Üµ½B
sì³öàÅsíê½ïcÌ ÆAì¯Â¯Äº³¢Üµ½B
ïÍA¨AlÅ巵ŵ½BܽJ÷éÌÅF³ñæëµB
^ââ¿âàÇñÇñó¯t¯Ü·B
»¡Ì éw¶³ñA¤CãÌûÍAºÐÈ[urohisho@office.chiba-u.jpÜŲAº³¢B

¶ÓFâ{@Mê
QOPO^PO^W@}\
t}\@p[\ixXg@3Ô39ª(lbg)Å®µ½[XB
¢Ü¾ÉA»ÌxXgðXVÅ«¸B
¡V[YÍL^XVðÚwµÄA2010N8©çÍÔROOûKB

¶ÓFsì@qF
QOPO^PO^P@xúÌç
X^ú@¯åÌæ¶ÆRlÅÐLCÝÖT[tBÉs«Üµ½B
T[tBÍw¶ã©ç±¯Ä¢éï¡ÌêÂÅ·B
fÃA¤ÆQ½¾µ¢úðÁĢܷªAµÅàÔÌæêéxúÍ龯OÉçtÌCÖÔðç¹Ü·B
v¢ØèÌ𮩵ÄASàÌàZbgI

¶ÓFâ{@Mê