疾患について

千葉大学大学院医学研究院
心臓血管外科学
千葉大学病院
心臓血管外科

大動脈は胸にある胸部大動脈と、おなかにある腹部大動脈に分けられます。胸部大動脈は場所により、大動脈基部、上行大動脈、弓部大動脈、下行大動脈と呼ばれます。心臓を出て、大動脈弁の周囲を支えている部分を大動脈基部といい、そこから頭側へ行く部分を上行大動脈、頭や腕へ行く3本の枝を出しながら後ろへむかって弓なりにUターンする部分を弓部大動脈といいます。そのあと、背骨の横を足側に向かっておりていく部分を下行大動脈と言います。下行大動脈から横隔膜を貫いて、おなかに入った部分を腹部大動脈といい、肝臓、胃腸、腎臓など重要な臓器に枝を出したあと、へその高さで左右に分かれます。左右に分かれた後の部分は腸骨動脈とよばれ、さらに骨盤、臀部への枝をだしたのち、足の付け根である鼠径部に達します。さらに枝分かれしながら、太もも、ひざ、足先へ向かいます。
動脈が部分的に大きくなったものを動脈瘤といいます。風船と同じで、小さいときは大きな力を加えないと、なかなか大きくなりませんが、いったん大きくなり始めると、少しの力で簡単に大きくなっていき、最終的には破裂する危険性があります。
この病気はこれまで動脈硬化が原因と考えられてきましたが、最近の研究で、一般にいわれている動脈硬化性疾患、すなわち、脳血管障害、心筋梗塞、狭心症、閉塞性動脈硬化症とは、異なる病態であると考えられるようになってきています。
動脈硬化の危険因子である喫煙、高血圧、高脂血症、などは動脈瘤形成に関係しているといわれていますが、糖尿病などは、無関係といわれています。ニコチンなどにより、動脈壁を構成している、細胞外基質を溶かす酵素の活性があがっている人がほとんどで、この酵素の働きにより動脈の壁が脆弱になり、血圧に負けて、だんだん膨らむと考えられています。大多数が喫煙歴のある高齢の男性です。
その他の原因としては、マルファン症候群やその類似疾患のように先天的に動脈壁が脆弱、外傷、ベーチェット病、高安動脈炎のような動脈壁の炎症、感染によって、動脈瘤形成が惹起 等があります。
動脈瘤のできる部位により胸部大動脈瘤、胸腹部大動脈瘤、腹部大動脈瘤と呼ばれています。また動脈瘤の形や成り立ちから、紡錘状瘤/嚢状瘤(図)、真性瘤/仮性瘤/解離性瘤(図)などと呼ばれます。
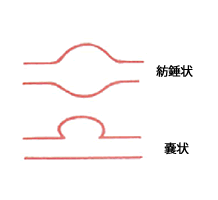
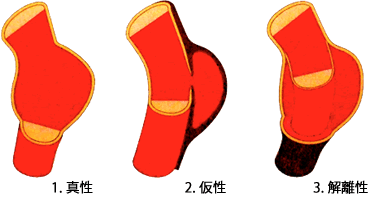
大動脈瘤は、大きさや場所によって異なりますが、症状のないことが多く、これが大動脈瘤の特徴であり、危険な点です。
胸部大動脈瘤は、健康診断などでたまたまレントゲン検査を受けたとき、大動脈が拡大しているのがわかり、初めて診断される場合が多いのですが、瘤が拡大してくると、圧迫による症状が出てくることがあります。例えば、食道が圧迫されて「ものを飲み込みにくい」、左半回神経(声帯を動かす神経)の圧迫による「かすれ声」などです。
腹部大動脈瘤の場合も症状のないことが多く、たまたま、お腹を触ってみて、脈をうつ "こぶ"に気づき、初めて診断される場合も少なくありません。
破裂する前は、無症状な場合が多いのですが、一旦、破裂すると激しい痛みを生じます。急激なショック症状になったり、突然死したりすることもまれではありません。
未破裂の腹部大動脈瘤は、径にもよりますが、一般に1年間に直径が平均2-5mm大きくなるとされていて、破裂予防のための内科的な治療としては薬を飲んで血圧を下げることになります。降圧薬の内服により動脈瘤の拡大傾向を若干遅らせることが期待できますが、一度大きくなった瘤が縮小することはなく、瘤が大きくなった場合は、外科治療を決断する必要があります。径が40mm以下の腹部大動脈瘤の破裂は稀ですが、径が 50mmを越えると破裂の可能性が出てきます。
手術適応については、施設間で様々な考え方があります。ただ、55mm以下の小径の腹部大動脈瘤に対する早期治療介入が生命予後を改善するという証拠は、2015年1月の時点で、未だ報告されていません。したがって、がんに対する治療のように、早期発見、早期治療という考え方は大動脈瘤にはあてはまりません。100%安全な治療が存在しない限り、治療に早期介入して悪いことはありませんが、良いということもありません。当院では、原則的に、50mm以下の患者様には、厳重な経過観察を勧めています。
ただ、形状が囊状(偏心性)の場合や、急速拡大を来した場合、小径であってもこの限りではなく、治療介入が必要な場合もあり、担当医の説明をよく聞く必要があります。
治療には大きく分けて2通りあり、(1)開腹して大動脈を露出し、瘤を切り開き、人工血管を直接ぬいつける人工血管置換術と、(2)足の付け根からカテーテルを挿入してステントグラフトを内挿する手術です(図)。どちらも手術の安全性は高く、予定手術では、手術死亡率は1%以下ですが、それぞれに欠点と利点があります。
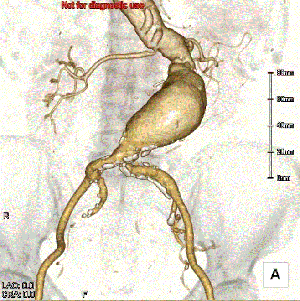

人工血管置換術は1950年台初頭から行われており、どのような形の動脈瘤であっても、直接縫って治すために確実に治療できます。しかしおなかを切るので、術後の傷のいたみはステントグラフト治療より強いため、背中に硬膜外麻酔といって鎮痛のためのチューブを入れ、鎮痛剤などで痛みを緩和します。また術後の食事の開始までに3,4日かかる(おならがでるまで)、以前におなかの手術を受けている方では癒着のために手術の難易度(危険性)が高くなる、といった欠点があります。
一方、ステントグラフト治療は、比較的歴史が浅く、1989年にロシア語で最初に報告され、1991年に英語論文で報告され、一気に世界に広まることになります。日本でも1990年台前半から自作のステントグラフト治療が開始され、2006年に企業製造のステントグラフトの認可がおり、広く全国に広がりました。ステントといわれる網枠に人工血管をぬいつけて細く折りたたんだものを、足の血管からおなかの動脈瘤の上までカテーテルで上げていき、そこで網枠を押し広げるようにステントグラフトを留置するものです。患者さんの血管に直接縫い付けるのではなく、中からおしつけて広げるだけなので、継ぎ目で血液が漏れると瘤が破裂する危険性が残ってしまいます。そのため動脈瘤のかたちや太さ、血管の曲がり具合などの面からいろいろと制約があり、ステントグラフトに適した形の動脈瘤とそうでない患者さんに分かれてしまいます。
長期的な成績も次第に明らかになっており、ステントグラフト治療に再治療が多いということが報告されてきています。ただ、再治療=開腹手術ではなく、ほとんどの症例で、再血管内治療で、克服できているということも分かってきました。
また、これまで治療結果が不確実と言われ、特に若年者には敬遠されていたステントグラフト治療ですが、開腹での手術は、厳重な長期followがされていなかったため詳細が分からなかっただけで、よく経過を調べると、腹壁瘢痕ヘルニア、開腹に伴う癒着性イレウスの発症、また性機能障害などの合併症も起こることが報告されており、また、腎動脈直下の瘤、骨盤深くに存在する内腸骨動脈瘤を、結局残さざるを得ない状態で治療が終えられている症例もあり、開腹での人工血管置換が完全に治療できているという考えは、改めなければいけなくなっています。
逆に、高齢者、抗血小板療法、抗凝固療法を長期間継続しなければいけない虚血性心疾患を有する症例、巨大な瘤の症例は、ステントグラフト治療の長期成績があまりよくないことが分かってきており、このような症例こそ、全身状態が許せば、開腹で人工血管置換手術を行った方がよいと言えます。
当院では、いずれの治療を受けた患者様も、術後も半年から1年ごとの定期的なフォローアップを行うようにしています。
術後経過は、ステントグラフト治療の場合、手術時間については一概に言えませんが、どんなに手術時間がかかっても、傷が小さく、痛みが少ないので、食事は、術当日または翌日から通常どおり摂ることができ、2−4日後には退院可能な状態になっています。開腹手術の場合は、2-3日間の絶食期間が必要ですが、7-10日間で退院できる場合がほとんどです。
胸部大動脈瘤は胸の大動脈がふくれる病気です。場所により、上行大動脈瘤、弓部大動脈瘤、下行大動脈瘤と呼ばれます。真性瘤の場合、正常の2倍以上にふくれると破裂する危険性が高くなり、治療が必要となります。どの部位でも、直径60mm以上のもの、有痛性のもの、壁の一部分が突出する形でふくれる(嚢状瘤)ものは破裂の危険性が高く、手術を行う必要があります。
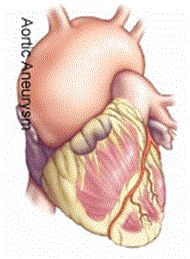
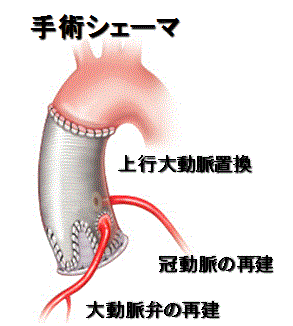
手術は、上行、弓部大動脈、胸腹部大動脈の瘤の場合は、人工血管置換術が第一選択として、行われます。開胸し、人工心肺下、上行、弓部大動脈の場合、脳分離体外循環をもちいて、人工血管で置きかえる手術をおこないます。大動脈内の血液の流れを止めた状態で、動脈硬化の進んだ大動脈を切ったり、縫ったりすることができるので、大動脈内の粥種、血栓塞栓を末梢に飛ばしにくく、ステントグラフト治療に比べて、血栓塞栓症を来しにくいと考えられます。
大動脈基部の拡張病変は、"バルサルバ洞動脈瘤"、"大動脈弁鈴拡張症"といった病名で呼ばれます。この部位が拡張していると、大動脈弁閉鎖不全(逆流)を合併していることが多く、心不全が現れることもあります。大動脈弁逆流があっても、大動脈弁の性状が良好であれば、自分の弁を温存した大動脈基部置換手術が行われ、自分の弁の性状が不良な場合は、人工弁付きの人工血管で置換します。いずれの場合も、心臓の筋肉を栄養する血管、冠動脈2本をつなげかえる必要があり、手技はやや複雑になります。
一方、下行大動脈の瘤については、頸部分枝から距離がある場合には、その治療成績、手術侵襲の低さからステントグラフト治療が、第一選択に行われます(図)。
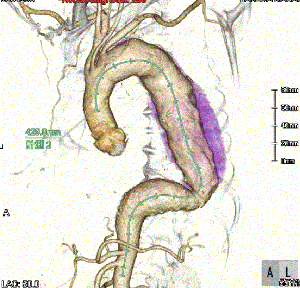

ただ、頭にいく血管を出す領域である弓部大動脈瘤であっても、高齢者、全身状態の悪い患者さんの場合、開胸せずに分枝再建を併用したステントグラフト治療を選択せざるを得ない場合もあります(図)。それぞれの治療法に、利点欠点があるので、それらをよく考慮して、治療法を選択すべきであると考えます。
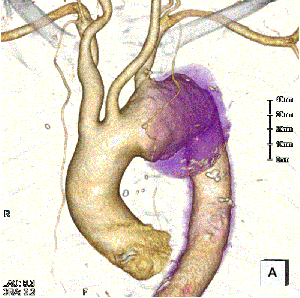
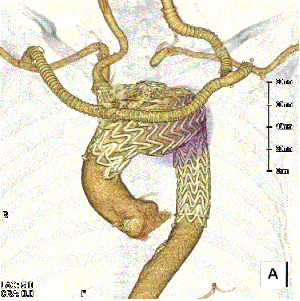
胸部と腹部領域にまたがった領域に存在する大動脈瘤を、胸腹部大動脈瘤とよび、その瘤の及ぶ範囲によって、治療内容が大きく変わってきます。多くは、腹部臓器を栄養する重要な血管を含んだ部分に瘤が発生しているため、胸のみならず、おなかもあける、大きな皮膚切開が必要になります。左肺を抑えた状態で、人工心肺を使用し、腹部血管を縫いなおし、大動脈を人工血管で置換する手術を行います。患者さんにとっての手術のストレスはやや大きくなるため、こういった手術に耐えられないと判断した症例に限って、ステントグラフト治療を併用した治療も考慮します。ただ、下行大動脈の瘤のように、ステントグラフトを内挿するだけでは治療不可能な場合が多く、腹部の重要な血管をどのようにして残し、再建するかを考えなければいけません。
動脈の壁は内膜、中膜、外膜の三層構造になっています(図)。動脈解離とは、内膜に亀裂ができて、そこから動脈の壁が裂けていく病気です。解離を起こした動脈を断面でみると2つの腔になっており、もともと血液の通り道であった真腔と、解離を起こしたあとに壁の間に血流路ができた偽腔とにわかれています。大動脈解離は突然おこる病気で、起こしてまもない状態を急性大動脈解離といいます。急性大動脈解離の発症時には、今までに経験したことのない激しい胸痛、背部痛が突然に出現します。解離に伴う血流の障害から、手足の冷感や痛み、心不全による呼吸困難、心タンポナーデによるショック、心筋梗塞による胸痛、脳梗塞による麻痺、脊髄虚血による下半身麻痺、腸管壊死による腹痛など、様々な症状を認める場合があります。大動脈解離を起こした血管壁は薄いため、径が大きくなりやすく、大動脈解離によって大動脈がふくれた状態を解離性大動脈瘤といいます。
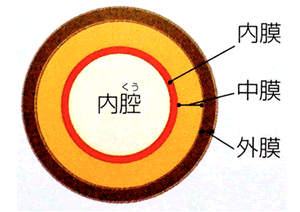
急性大動脈解離は、上行大動脈に解離があるA型、と、上行大動脈に解離がないB型 ( Stanford分類 )に分けられます(図)。
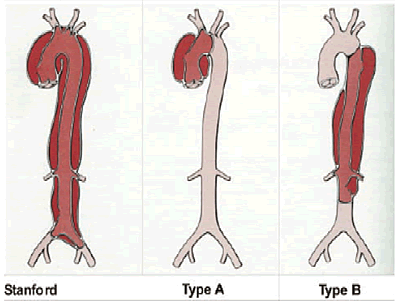
A型解離は、突然死を来たす合併症(心嚢内への破裂・出血、心筋梗塞、大動脈弁閉鎖不全症、脳梗塞など)を生じやすく、放置すれば、発症後48時間以内に50%、2週間以内に75%の高率で死亡するといわれています。そのため診断がつき次第、緊急手術の対象となります。この場合、解離の入り口の場所、進展範囲、患者さんの術前状態により術式は若干異なりますが、多くは、開胸、人工心肺下、脳分離体外循環下に、上行大動脈、弓部大動脈を人工血管に置換する手術が行われます。手術までの間に、心タンポナーデ、心筋梗塞、脳梗塞により突然死することもあり、予断を許さない状態が続きます。
B型解離は、多くの場合はすぐには手術せず、まずは血圧を下げ、解離の進展や続発する合併症が起こらないように集中治療管理が行われます(降圧安静療法)。しかし、発症時、すでに破裂、臓器血流障害等を合併している症例もあり、そのような場合は、ステントグラフトによる解離の入り口の閉鎖を行うことが、最も低侵襲で、根治性が高いといわれ、ガイドラインにも記されています。降圧安静治療の間にも、CT検査、その他で破裂、臓器障害の危険性があると判断した場合には緊急手術(原則的にステントグラフト治療)を要します。そうでなければ内服薬による血圧の調整を行いながら、リハビリを進め、ゆっくりと日常生活に復帰していきます。
ただ、最近の研究で、降圧安静治療で急性期を乗り越えても、この時期に大動脈径がすでに40mmを超えている症例は、遠隔期に、高率に手術治療を含む大動脈事故を発症することが報告されています。さらに瘤拡大を来してからの遠隔期での治療は、非常に複雑で、治療も困難を極める場合が多いため、発症間もない時期に、ステントグラフトにより解離の入り口を閉鎖すべきであると言う考えが主流になってきています。
症例や、施設の対応能力に依存するところが大きいと言えますが、当院では、適応のある症例にはこの時期に積極的に治療に介入し、安全に治療することができており、遠隔期における複雑な治療を避けることができるように取り組んでいます。
以上より、大動脈解離(解離性大動脈瘤)の患者さんの場合、A型、B型を問わず、大動脈外科手術、ステントグラフト治療の両方に習熟した心臓血管外科医が常時勤務する施設で、急性期、慢性期管理を行うのが理想的と言えます。